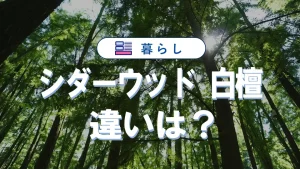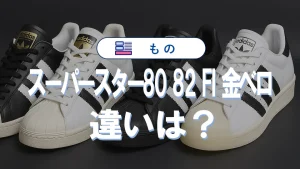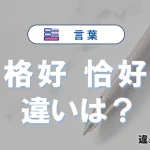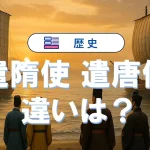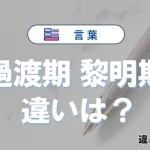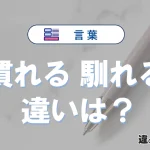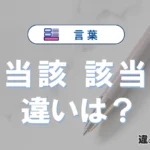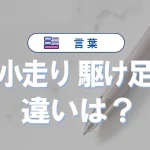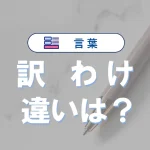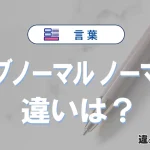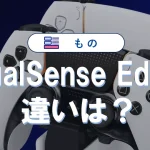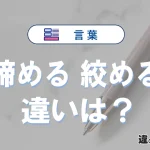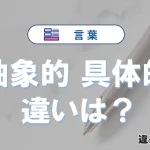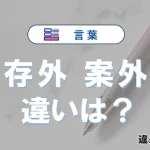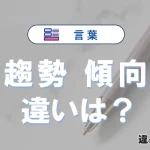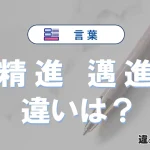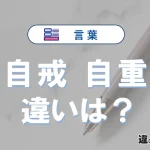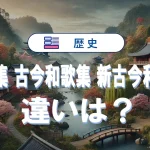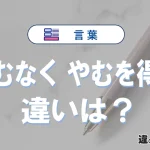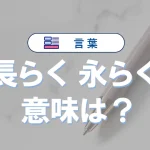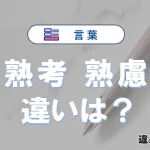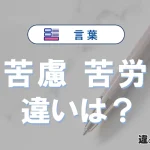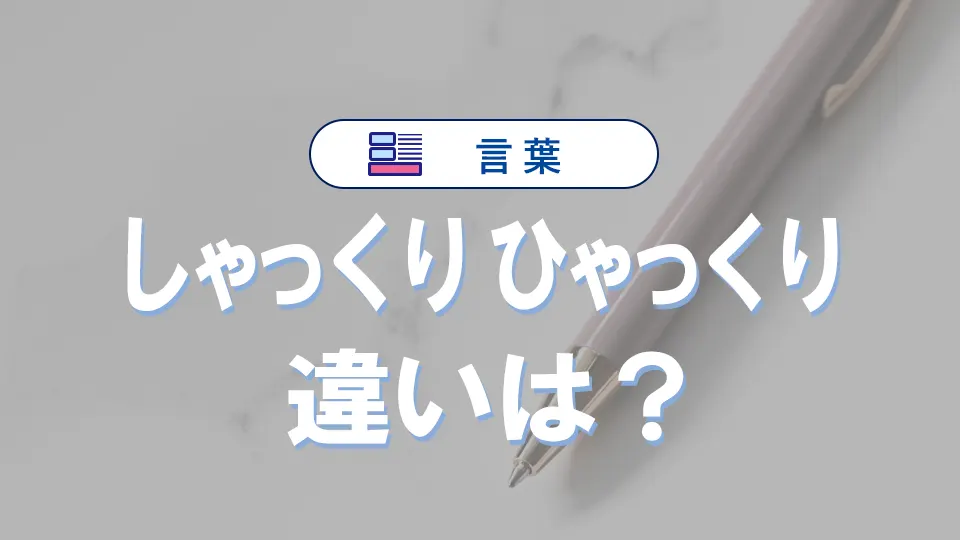
「しゃっくり」と「ひゃっくり」、どちらも日常会話でよく耳にする言葉ですが、実際には違いがあるのかと疑問に思ったことはありませんか? 結論から言うと両者は同じ現象を指しており、標準的には「しゃっくり」と表記されるのが一般的です。本記事ではその違いを言語学的・医学的な観点から詳しく解説し、赤ちゃんの場合の注意点や止め方、受診が必要なケースまで網羅的にお伝えします。
目次
しゃっくり・ひゃっくりの違いはある?(最初に結論)
多くの人が気になる「しゃっくり」と「ひゃっくり」の違いですが、結論から言えば両者は同じ現象を指す言葉です。どちらも横隔膜(おうかくまく:胸腔と腹腔を隔てる大きな呼吸筋)の不随意な痙攣(けいれん)によって生じる「ヒッ」という音を表現しています。国語辞典やNHKの放送用語集では「しゃっくり」が標準的な表記として採用されることが多く、公的文書やニュース記事ではこちらが推奨されます。一方で「ひゃっくり」は古くから口語で使われてきた異形で、日常会話や育児シーンでは依然として広く通じています。つまり意味の差はなく、正誤の問題ではありません。
医学的な正式名称は「吃逆(きつぎゃく)」
医療現場では「吃逆(きつぎゃく)」という漢字表記や、英語での singultus(シングルタス) という名称が使われます。「吃逆」とは、中国医学に由来する漢語で、現在も医学辞典や診断基準に残る正式用語です。
参考:日本大百科全書|しゃっくり
言語学的な背景:表記・発音・方言史から整理する
「しゃっくり」と「ひゃっくり」という二つの言い方は、日本語の擬音語(オノマトペ)の特性による音の揺れから生まれました。擬音語は現象を模倣するために音感を重視し、地域や家庭ごとに異なるバリエーションが生まれやすいのです。
「しゃ」と「ひゃ」の音の違い
「しゃ」は摩擦音を含む柔らかい響き、「ひゃ」は息を強く感じさせる清音で、どちらも「ヒッ」という音を模倣する自然なバリエーションです。そのため、特定の地域で「ひゃっくり」が優勢になったり、家庭内で使われ続けたりすることがあります。
辞書・標準語における扱い
国語辞典やNHKの用語集では「しゃっくり」が優先される一方、「ひゃっくり」も異形として記載されています。つまり「ひゃっくり」が誤用とされることはなく、あくまで日常の多様な表現の一つとして許容されています。
方言・世代差のニュアンス
言語調査では、年齢層や地域によって呼び方の分布に違いがあることが報告されています。若い世代はメディアの影響で「しゃっくり」に統一されやすい傾向があり、高齢層や家庭内の習慣では「ひゃっくり」が根強く残る場合があります。
医学的な基礎知識:なぜしゃっくりが起きるのか
しゃっくり(吃逆)は、横隔膜の不随意収縮により吸気の途中で声門(声帯の開閉部位)が閉じ、特徴的な「ヒッ」という音が出る現象です。横隔膜は主要な呼吸筋で、通常は自律神経系により規則的に動いていますが、迷走神経や横隔神経が一時的に過敏になったときにこの反射が生じます。
参考:MSDマニュアル|しゃっくり
一般的な誘因
早食い、炭酸飲料やアルコールの摂取、胃の急激な膨張、急激な温度変化、大笑いや驚きなどが典型的な誘因とされています。これらはいずれも胃や横隔膜、神経反射を刺激しやすい状況であり、一過性のしゃっくりが生じやすくなります。
多くは自然に治まる
ほとんどのしゃっくりは数分から数時間で自然に消失します。これは神経反射が短期間でリセットされるためであり、通常は特別な治療を必要としません。
医学的に問題となる場合
48時間以上続く「持続性しゃっくり」や、1か月以上続く「難治性しゃっくり」は、消化器疾患(逆流性食道炎・胃潰瘍)、中枢神経疾患(脳梗塞・脳腫瘍)、代謝異常(腎不全など)、薬剤性の副作用などが背景にあることがあり、医療機関での精査が必要です。
参考:時事メディカル|長引くしゃっくりに注意
日常生活での「しゃっくり/ひゃっくり」の使い分け
結論として、文章や公式な場面では「しゃっくり」を使用するのが無難です。一方、家庭や育児の場面では「ひゃっくり」も自然に用いられており、誤解や不快感を招くことはほとんどありません。
特に赤ちゃんのしゃっくりはよく見られる現象で、多くの場合は心配不要です。ただし、長時間続き授乳や呼吸に支障がある場合は小児科への相談が推奨されます。
しゃっくり・ひゃっくりに関するよくある質問
Q1:医学的に正しい呼び方はどちらですか?
→ 医学用語は「吃逆(きつぎゃく)」ですが、日常的には「しゃっくり」が標準表記です。
Q2:「ひゃっくり」は方言なのですか?
→ 明確な地域限定の方言ではなく、全国的に散在する口語的な異形です。
Q3:赤ちゃんのしゃっくりは心配ですか?
→ 機嫌がよく呼吸や哺乳に問題がなければ自然な現象です。ただし長時間続く場合や苦しそうに見える場合は小児科に相談してください。
Q4:止め方は本当に効果がありますか?
→ 息こらえや水を飲むなどで一時的に改善することはありますが、科学的に保証された方法は限られています。無理をせず、持続する場合は医療機関を受診することが重要です。
まとめ|違いは“言い方”だけ。標準は「しゃっくり」、医学は「吃逆」
本記事を通じて明らかになったのは、「しゃっくり」と「ひゃっくり」は同じ現象を指す表現であり、正誤の区別は存在しないという点です。辞書や公式文書では「しゃっくり」が優先され、医学的には「吃逆(きつぎゃく)」が正式名称です。日常会話では「ひゃっくり」も自然に使われ、意味の混乱は生じません。
また、医学的な観点からは多くのしゃっくりが一過性で自然に治まりますが、48時間以上続く場合や生活に支障をきたす場合は医療機関での相談が推奨されます。言葉の違いに迷ったときは場面に応じて使い分け、症状が気になるときは早めの対応を心がけましょう。