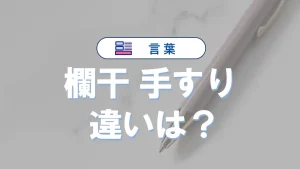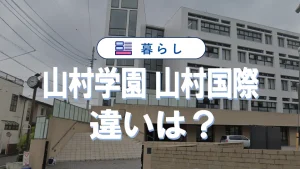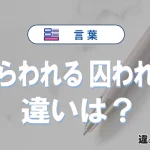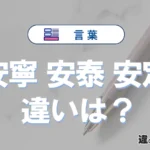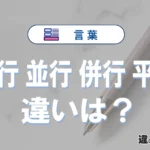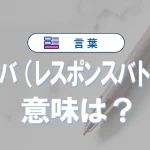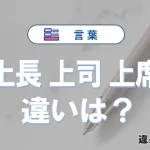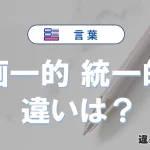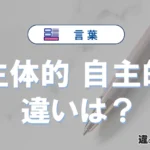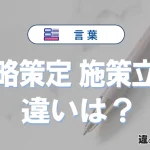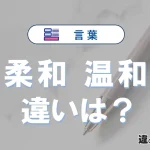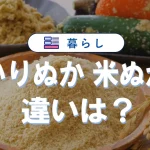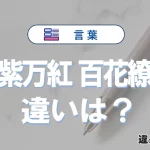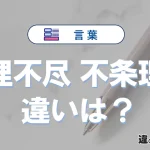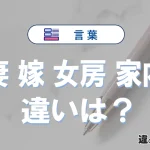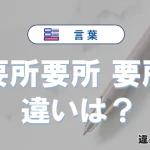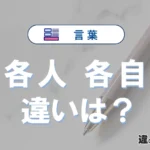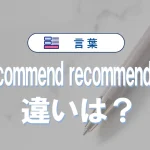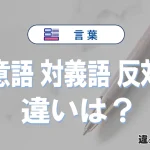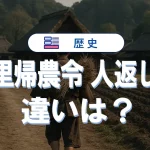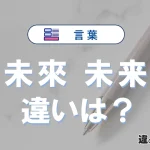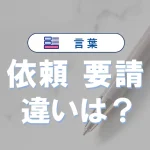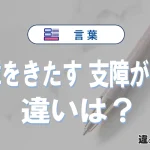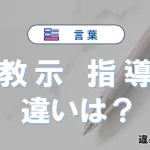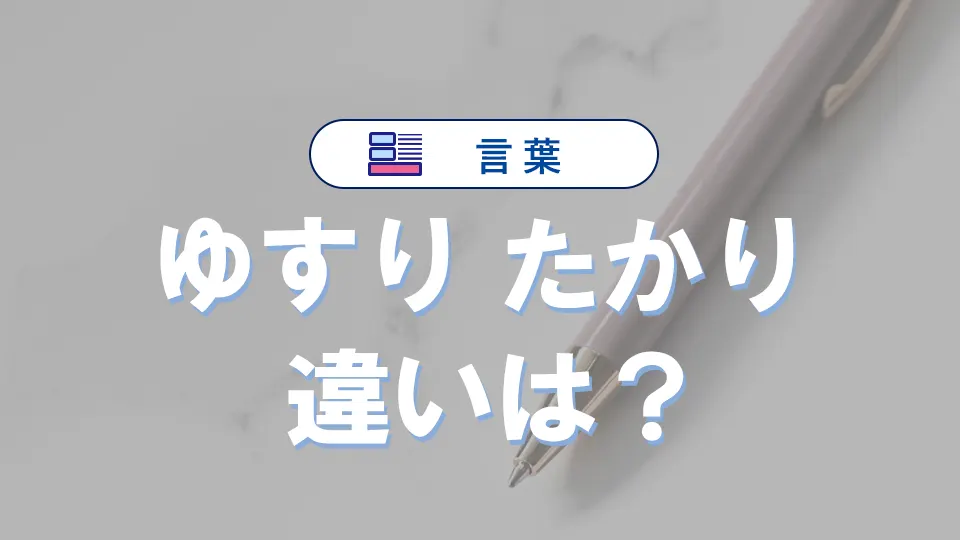
「ゆすり」と「たかり」は、いずれも「金品を無理に要求する」「むしり取るような行為」を意味する言葉ですが、ニュアンス・用法・法的評価などには違いがあります。「ゆすり」は恐喝・強請の要素を伴う威圧的な行為を指し、「たかり」はねだり・頼み込みの性質を含んだ幅広い意味合いを持つという点が主な違いです。本記事では、両語を意味・語源・使い方・英語表現など多角的に解説します。
目次
「ゆすり」と「たかり」の違いと意味
「ゆすり」とは?意味と例文
意味
「ゆすり」は、威迫や脅迫を伴って相手に金品や財物を出させようとする行為、またはそのような要求をする者を指します。国語辞典では「おどして金品を出させること」「強請(ごうせい)」などの意味が挙げられています。
「揺すり(ゆすり)」という表記も見られ、「揺する」動作が転じて「揺さぶるように圧力をかける」意味が派生したと考えられます。
使い方・注意点
- 単に「金をねだったり頼んだりする」よりも、脅し・威圧を含む強いニュアンスがあります。
- 法的には恐喝罪・強要罪に問われうる行為と重なります。
- 文語的・書き言葉にもよく現れる単語です。
例文
- あの政治家は、便宜を図らせるためにゆすりをかけた疑いがある。
- 相手の弱みを握ってゆすりを働くようなことは、許されない。
- 「支援を出さなければ暴露する」とゆすりをかけられた。
- ゆすりに屈してしまえば、後でしつこく要求される。
- 実際にゆすりが疑われ、警察の捜査対象となった。
「たかり」とは?意味と例文
意味
「たかり」は、ねだったり頼んだり、または寄生的に金品を引き出そうとする行為を指します。「脅したり泣きついたりして金品を出させる」といった意味も含むことがあります。動詞形は「たかる(集る・強請る)」で、名詞形「たかり」が導かれます。
使い方・注意点
- 日常的・口語的に「たかる」「たかりにくる」など使われることが多い。
- 社会通念上や感覚的には「図々しくねだる」「しつこく頼む」程度の意味合いを含むことがある。
- 必ずしも法的な脅迫や強要を伴うわけではありませんが、度が過ぎれば不法行為になる可能性があります。
例文
- 彼は友だちにたかりまくって、金を借り続けている。
- 親にたかってばかりいては自立できない。
- あの店員は客にたかるように、あれこれ追加を頼んでくる。
- 無理にたかろうとして相手を不快にさせた。
- たかりのように頼む姿勢では信頼を失いやすい。
「ゆすり」と「たかり」の用法の違い
両者は似た意味を持ちますが、語感・用法・法的評価などで使い分けられます。以下に主な違いを整理します。
| 項目 | ゆすり | たかり |
|---|---|---|
| 威圧・脅迫性 | 高い(暴力・脅しを含むことが多い) | 必須ではない。ねだり・頼み中心 |
| 法的評価 | 恐喝罪・強要罪に触れる可能性大 | 通常の範囲なら違法にならないが、過剰なら問題 |
| 語感・文体 | 書き言葉・フォーマルで使われやすい | 口語・日常語で使われることが多い |
| ニュアンス | 相手の弱みを利用する不当性が強調される | 図々しく頼む性質を含む |
| 使用例場面 | 政治・交渉・犯罪など重い文脈 | 家庭・友人・日常場面も多く用いられる |
たとえば、友だち間で“ちょっとおごって”という程度を「たかる」と言っても許容される場合がありますが、相手の弱みを握って「出さなければ暴露するぞ」と迫る行為は「ゆすり」と呼ぶのが適切です。
関連する犯罪としての位置づけ
「ゆすり」および「たかり」が法制度上どのように扱われるかを整理します。
恐喝罪・強要罪との関係
- 恐喝罪(刑法第246条等):相手を脅迫、暴行、脅しを以て、金品を交付させたり、財産的利益を得たりする犯罪。
- 強要罪(刑法第223条等):脅迫または暴行を用いて他人に義務のない行為をさせる(またはさせない)罪。
ゆすりは、これらの犯罪の構成要件に符合しやすい場面が多いとされます。たとえば「脅し文句を使って支払わせた」「秘密をばらすぞと圧迫した」といった状況では、ゆすり=恐喝・強要に該当する可能性があります。
一方、たかりのようなねだり・頼み込み・粘り強さだけで構成される行為は、必ずしも違法とはなりません。ただし、「同意のない金銭の回収」「過度な精神的圧迫・脅し」が介在すれば違法性が認められます。
民事責任
ゆすり・たかりのいずれの形でも、不法行為(民法第709条)として損害賠償責任を問われる可能性があります。たとえば「不法に金銭を無理に取られた」「心理的苦痛を受けた」などを理由に、被害者が損害賠償を請求するケースも考えられます。
社会的・道徳的観点
ゆすり・たかりはいずれも社会的には好ましくない行為と見なされ、倫理的批判の対象になります。特に政治・企業・公共機関では、「ゆすり・たかり体質」のレッテルを貼られることがあります。
「ゆすり」と「たかり」の語源と背景
「ゆすりたかり」の語源
「ゆすりたかり」は、古く「強請たかり」「揺すりたかり」として用いられ、両者が結びついて一語化した表現です。「ゆすり」と「たかり」はともに強請(ごうせい)という漢字を当てることがあり、この漢字表記には「強く請う」という意味が込められています。
「ゆすり」の語源としては、もともと「揺する(ゆする)」動詞から来て、「揺さぶるように圧力をかける」ことが比喩的に「脅して取り立てる意図を示す行為」に転じた、という説があります。
一方、「たかり」の語源は、動詞「たかる(集る・強請る)」に由来します。「集る(あつまる)」は群がる意味を持ち、「強請る(ねだる、請い求める)」という語形もあるようです。
たかるという言葉自体、かつては「集って寄生する」意味も含み、後に「頼み込んで金銭・物品を得ようとする」意味が派生したと考えられます。
このように、「揺すり」+「たかり」という構成が、強圧とねだりとの両面を表す合成語として形成された可能性があります。
歴史的背景と日本における事例
歴史上、役人や権力者が庶民に対して無理な要求を行うことは「ゆすりたかり」と批判される対象になってきました。特に、宿場・関所・検問を利用した強制徴収や、行列を利用した要求などが記録されています。
江戸期以降、「ゆすりたかり」は悪徳行為の象徴的言葉として文学・風刺・諺(ことわざ)などに取り上げられ、たびたび批判の対象となりました。現代でも不正請求・強引な集金・便宜要求などの事例で、この語は引き合いに出されます。
漢字の成り立ちと意味
- 揺(ゆ):振る、ゆする意を持つ漢字。「揺すり」はこの字を使うことがあります。
- 強請(ごうせい):強く請う意味を持つ漢字表記で、「ゆすり」「たかり」に用いられることがあります。
- 集(つどい・あつまる):群がる意味。「集る(たかる)」の語根として使われます。
- 請(こ」う・たのむ):請求・頼む意味を含む字。強請の「請」字は強く請う行為を示唆します。
「ゆすり」と「たかり」の比較と類語
「ゆすり」と「たかり」の類語
両語と意味が近い語・関連語を挙げ、それぞれの違いも踏まえて解説します。
- 恐喝(きょうかつ・きょうかつする/恐喝罪)
相手の弱みを利用し、暴行・脅迫などで金品を強要する行為。ゆすりと重なる領域があります。 - 強要(きょうよう・強要する/強要罪)
暴行・脅迫で義務のない行為を強制すること。ゆすり的要素を含む場合がある。 - 強請(ごうせい・強請する)
「強く請う」こと。ゆすり・たかり両方にかかわる語で、書き言葉で使われやすい。 - 脅迫(きょうはく・脅迫する/脅迫罪)
相手をおどして恐れを抱かせ、自分の意図を通そうとする行為。ゆすりの側面を持つ場合がある。 - たかる(動詞形)
たかる → たかり。群がる、頼み込む、ねだるなどを含む範囲の広い語義を持つ。
「ゆすり」や「たかり」に似た表現
日常・文章で使われる、ゆすり・たかりに近しい表現をいくつか紹介します
- ねだる:頼み込む意味。ゆすり・たかりより穏やかな語感。
- せびる:金・物をせびる、無理に要求する意味。
- むしり取る:力ずくで奪う意味が強い表現。
- 搾取(さくしゅ):支配的立場から利益を不当に取り上げる行為。
- ゆすり取る:ゆすりの特性を強めた言い回し。
- ねだり屋:たかり傾向のある人を揶揄的にいう語。
「ゆすりたかり」の英語での意味と使い方
ゆすりたかりの英語表現
ゆすり・たかりを英語に訳すとき、以下のような語が対応候補になります
- blackmail:
恐喝、ゆすり ➝ 秘密をばらすぞと脅して金銭をとる意味を含む語。 - extortion:
強制的に金品を奪う、強請するという意味で、ゆすり・ゆすりまがいの行為に対応することがある。 - racketeering:
組織的なゆすり・恐喝行為、詐欺行為などを含む犯罪行為を指す語。 - shakedown(米語):
「ゆすり」の俗語的表現。「金を出さないと困るぞ」と迫る意味を持つ。 - mooching / to mooch(口語):
「たかる」に近いニュアンスで、「ねだる」「おねだりする」意味で使われることがある(やや軽い語感)
英語圏での用法と例文(日本語訳)
| 英語例文 | 日本語訳 |
|---|---|
| He was arrested for blackmailing his business partner. | 彼はビジネスパートナーをゆすって逮捕された。 |
| The gang was involved in extortion of local shop owners. | そのギャングは地元の商店主にたかり・強請していた。 |
| They threatened a shakedown unless he paid them. | 支払わなければ困るだろうとゆすりをかけた。 |
| She always mooches snacks from her friends. | 彼女はいつも友人からお菓子をたかっている。 |
| Their operation was a form of organized racketeering. | 彼らの組織は、ゆすりたかり的な組織犯罪形態だった。 |
英語圏でも「blackmail」「extortion」「shakedown」などは犯罪的文脈で使われることが多く、日常の「たかる」的意味合いは “mooch” など軽い語で表現されることがあります。
まとめ:「ゆすり」と「たかり」の違いや意味
本記事で扱った内容の要点を改めて振り返ります
- ゆすりは、威圧・脅迫性を伴う強い要求を示す語で、恐喝・強要との結び付きが強い。
- たかりは、ねだり・頼み込み・粘り強さを含む幅広い語で、必ずしも法的強制性を伴うとは限らない。
- 「ゆすりたかり」は、両語の性質を併せ持つ合成表現として使われる。
- 類語(恐喝・強要・脅迫など)や近似語(ねだる・せびる・搾取など)を使い分けることで表現の強弱が調整できる。
- 英語では “blackmail”, “extortion”, “shakedown”, “mooch” などの語が対応語になり得るが、文脈に応じて選ぶ必要がある。