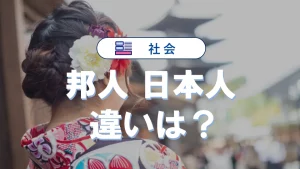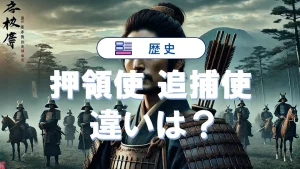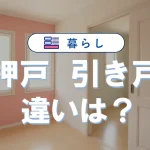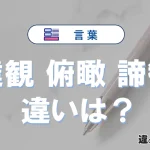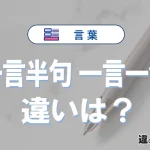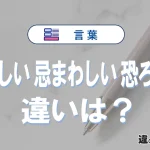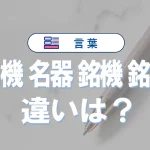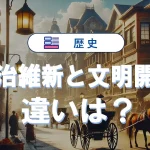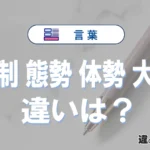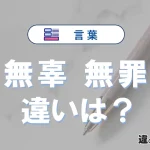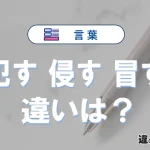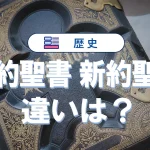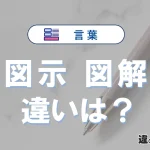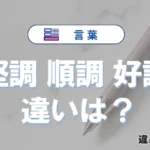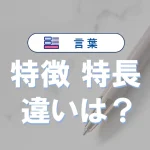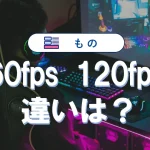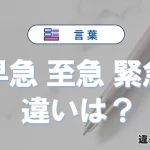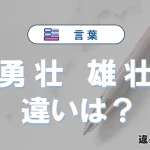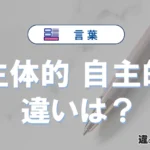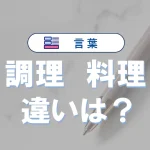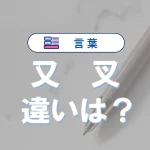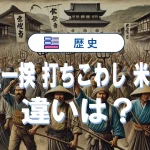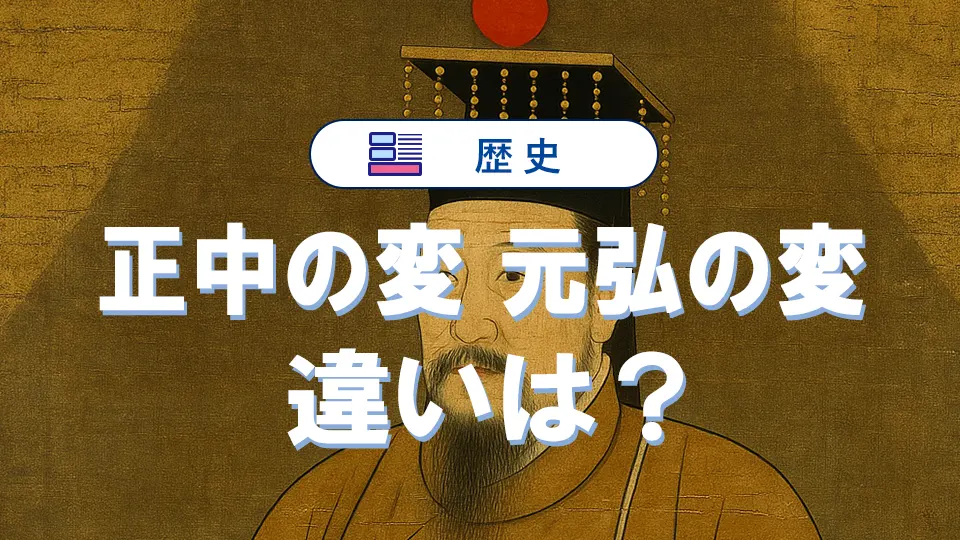
鎌倉時代末期に起こった「正中の変」と「元弘の変」は、日本史の中でも重要な転換点として知られています。しかし、「正中の変 元弘の変 いつ起きたの?」「なぜ発生したの?」「違いがよくわからない…」と感じている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、後醍醐天皇を中心とした討幕運動の流れを、正中の変と元弘の変の違いや背景をふまえながら、簡単にわかりやすく解説していきます。また、覚えやすい語呂合わせや年号の覚え方、日野資朝の役割についても整理しています。
結論として、正中の変と元弘の変は、後醍醐天皇による2段階の討幕計画であり、元弘の変をきっかけに鎌倉幕府は滅亡に至りました。
- 正中の変と元弘の変がいつ起きたか
- それぞれの事件がなぜ発生したのか
- 両事件の違いや時系列の流れ
- 年号の覚え方や語呂合わせによる記憶法
目次
「正中の変」「 元弘の変」とは何かを解説

正中の変と元弘の変はいつ起きた?
正中の変と元弘の変は、どちらも鎌倉幕府末期に起きた歴史的な事件で、天皇を中心とした討幕運動の始まりとされています。年号と西暦は以下の通りです。
| 事件名 | 年号(和暦) | 西暦 |
|---|---|---|
| 正中の変 | 正中元年(元亨4年) | 1324年 |
| 元弘の変 | 元弘元年 | 1331年 |
- 正中の変(しょうちゅうのへん) は、1324年9月に発覚した倒幕未遂事件で、実際の武力衝突は起きていません。
- 元弘の変(げんこうのへん) は、1331年から1333年にかけての広範な反幕府の戦いで、鎌倉幕府滅亡の引き金となりました。
約7年の間隔で2つの事件が発生していますが、いずれも後醍醐天皇による幕府打倒の試みであり、流れとしては連続した討幕計画と捉えることができます。
正中の変と元弘の変はなぜ起きた?

この2つの事件の背景には、政治的な不満や天皇家と幕府の対立構造がありました。発生の要因を整理すると以下の通りです。
正中の変の主な要因
- 御家人の困窮:元寇後の恩賞不足により御家人の生活は逼迫。
- 幕府の腐敗と専制:北条高時が政治に関心を持たず、側近に政治を委ねて政治が混乱。
- 朝廷の不満:幕府が天皇の即位や継承にも口出ししていたため、朝廷側に強い反発があった。
元弘の変の主な要因
- 正中の変の失敗をふまえた再挑戦:後醍醐天皇は武士層だけでなく、寺社勢力などにも協力を求め、計画を広げた。
- 朝廷主導の政治復活への強い意志:天皇親政の実現を目指す後醍醐天皇が、幕府体制そのものを否定しようとしていた。
両事件は、単なる反乱ではなく、当時の天皇権力と幕府体制の衝突が顕在化した政治闘争でもありました。
正中の変と元弘の変の簡単な時系列
この項目では、2つの事件の流れをコンパクトに理解できるよう、簡単な時系列表にまとめます。
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 1318年 | 後醍醐天皇が即位(大覚寺統) |
| 1321年 | 院政を停止し、天皇親政を開始 |
| 1324年 | 【正中の変】倒幕計画が発覚。武力行使はなし。日野資朝が流罪。 |
| 1331年 | 【元弘の変】再び討幕計画。吉田定房の密告により発覚。 |
| 1331年 | 後醍醐天皇、笠置山で挙兵するも敗北。隠岐へ流される。 |
| 1333年 | 足利尊氏が六波羅探題を攻撃。新田義貞が鎌倉攻めで幕府崩壊。 |
このように、正中の変は未遂に終わったのに対し、元弘の変は実際に戦が起こり、最終的に幕府崩壊へとつながった大事件でした。
後醍醐天皇の討幕への執念とは

後醍醐天皇の討幕への姿勢は、並々ならぬ執念を感じさせます。彼は単に一度の失敗で終わらず、何度も策を変えながら倒幕を追い求めました。
後醍醐天皇の行動例
- 親政開始で政治改革に着手し、記録所の復活や徳政令的施策を実施。
- 正中の変の失敗後も、仏教勢力(東大寺・興福寺)に接近して支援を依頼。
- 息子の護良親王を宗教界トップ(天台座主)に据え、軍事力の確保を画策。
- 隠岐に流されても諦めず、脱出後に倒幕の綸旨(命令)を発し、全国に支持を求めた。
このように、後醍醐天皇の行動は一貫しており、王政復古の理想実現を目指して、全精力を倒幕に注いだことがわかります。
日野資朝の役割と処遇について
日野資朝(ひのすけとも)は、後醍醐天皇の側近として倒幕計画の中心にいた人物です。学識に優れた公家でありながら、討幕という危険な計画に関与したことで、後世にもその名を残しました。
日野資朝の主な役割
- 宮廷内での討幕思想の推進役。
- 正中の変では俊基らとともに倒幕を企て、宴会を装って謀議を行う。
- 幕府に密告され鎌倉に送られ、結果として佐渡島へ流罪。
処遇の変化
- 正中の変では「疑わしきは罰せず」の姿勢から死罪を免れる。
- しかし元弘の変後には、天皇との再関係が問われ、最終的に処刑される。
このように、資朝は政治的な知識人であると同時に、命がけで理想を貫こうとした人物でした。彼の運命は、後醍醐天皇の討幕運動がいかに過酷であったかを物語っています。
「正中の変」「元弘の変」の違いと覚え方

正中の変と元弘の変の違いをわかりやすく
正中の変と元弘の変はどちらも後醍醐天皇による討幕計画ですが、発生時期や規模、結果に明確な違いがあります。
| 項目 | 正中の変(1324年) | 元弘の変(1331~1333年) |
|---|---|---|
| 規模 | 密談レベルの未遂事件 | 全国規模の武力衝突 |
| 発覚経路 | 内部の密告(土岐頼員) | 側近による密告(吉田定房) |
| 後醍醐天皇の対応 | 幕府に釈明し、処分は回避 | 女装して脱出、笠置山で挙兵 |
| 結果 | 計画失敗 → 流罪者あり | 武力衝突 → 幕府崩壊につながる |
| 死傷者・処罰 | 流罪・謹慎(死者なし) | 天皇流罪、関係者は死罪または戦死 |
簡単に言えば、「正中の変」は討幕の“火種”、一方「元弘の変」は“引き金”として機能し、最終的な鎌倉幕府の崩壊に直結した事件です。
正中の変・元弘の変の語呂合わせで覚える
年号を覚えるのにぴったりなのが語呂合わせです。リズムが良くて印象に残りやすいフレーズをいくつかご紹介します。
正中の変(1324年)の語呂合わせ
- 「秘密にしてよ(1324)正中の変」
- 「討幕の秘密、知る(1324)正中の変」
- 「父さん強い(1324)正中の変」
元弘の変(1331年)の語呂合わせ
- 「父さん災難(1331)元弘の変」
- 「父さん再度計画(1331)元弘の変」
- 「天皇一味、災難(1331)元弘の変」
これらを繰り返し口に出したり、書いて覚えたりすることで、数字と出来事を結びつけやすくなります。
元弘の変後に起きた鎌倉幕府の崩壊

元弘の変は単なる反乱では終わらず、鎌倉幕府そのものを滅ぼす結果を招きました。その流れは以下の通りです。
崩壊までのポイント
- 足利高氏(後の足利尊氏)が寝返り
→ 京都の六波羅探題を攻め落とし、幕府の西の拠点を喪失。 - 後醍醐天皇が隠岐から脱出し、再び綸旨を発布
→ 各地で討幕運動が活性化。 - 新田義貞が鎌倉へ進軍
→ 天然の要害・鎌倉を破り、幕府本体を制圧。
1333年5月、幕府の中心人物である北条高時が自害。ここに、1185年から続いた鎌倉幕府は約150年の歴史に幕を下ろします。
覚え方で混乱しやすいポイントと注意点
正中の変と元弘の変は、名前も内容も似ているため、特に以下の点で混乱しやすくなります。
よくある混乱ポイント
- 年号の違い(1324と1331)が覚えづらい
- 日野資朝・日野俊基など人物名が似ていて混同しやすい
- 元弘の乱=元弘の変? という呼称の違い
- 「変」と「乱」の違いに戸惑う(実際には明確な区別はない)
対策のヒント
- 「1回目=密告で失敗(正中)」「2回目=戦で本格化(元弘)」と段階で覚える
- 年号は語呂合わせ+数字を繰り返す
- 主要人物は役割を「天皇の側近」「実行者」などでグループ分けして整理
正中の変・元弘の変を簡単に復習する方法

短時間で内容を振り返るには、以下のステップで学習するのが効率的です。
ステップ1:年号を覚える
- 語呂合わせで「1324:正中」「1331:元弘」
ステップ2:主な登場人物と立場を整理
- 後醍醐天皇:討幕の中心人物
- 日野資朝・俊基:側近として計画を支援
- 足利高氏・新田義貞:幕府滅亡に関わった武士
ステップ3:流れを図や表にまとめる
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 1324 | 正中の変(失敗) |
| 1331 | 元弘の変(挙兵) |
| 1333 | 鎌倉幕府崩壊 |
ビジュアルで把握することで、頭に入りやすくなります。
受験やテスト対策に役立つ理解のコツ
歴史の流れをしっかり理解しておくことで、記憶に残りやすくなります。単語暗記だけでなく、関連づけて学ぶのがポイントです。
テスト対策のコツ
- 比較で覚える:「正中=未遂」「元弘=実行と成功」
- 人物でつなげる:「後醍醐天皇→護良親王→楠木正成→足利尊氏→幕府滅亡」
- 背景を知る:元寇・永仁の徳政令など、幕府の弱体化もセットで押さえる
また、頻出問題としては以下のようなパターンが多く見られます。
- 「正中の変で処罰された人物は?」
- 「元弘の変で鎌倉幕府を裏切った有力御家人は誰か?」
単純な年号ではなく「人物と出来事の関係性」を理解しておくと、高得点につながります。
正中の変と元弘の変を理解するために|要点まとめ
- 正中の変は1324年に発覚した未遂の倒幕事件
- 元弘の変は1331年に始まり、鎌倉幕府滅亡へつながった
- 両事件とも後醍醐天皇が主導した討幕計画である
- 正中の変では武力衝突はなく、計画段階で失敗した
- 元弘の変では実際に挙兵が行われ、全国的な戦闘が起きた
- 幕府の腐敗や御家人の困窮が討幕の背景にあった
- 正中の変では日野資朝が佐渡に流され、死罪はなかった
- 元弘の変では日野資朝が処刑され、後醍醐天皇も流罪になった
- 後醍醐天皇は隠岐に流された後も脱出し、綸旨を発した
- 足利高氏や新田義貞の寝返りが幕府崩壊の決定打となった
- 正中の変は討幕運動の火種として歴史的意義がある
- 元弘の変は結果的に建武の新政を導いた転機である
- 年号は語呂合わせ「秘密にしてよ(1324)」「父さん災難(1331)」で覚えやすい
- 両事件は「変」と「乱」の使い分けに注意が必要
- 正中と元弘の違いを比較表で整理すると記憶しやすい