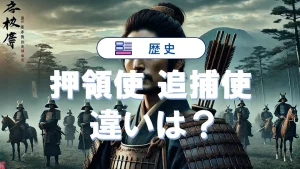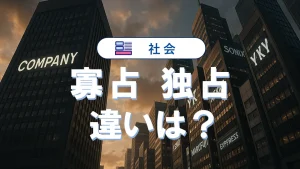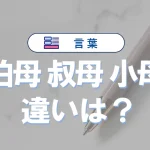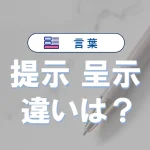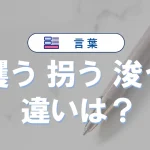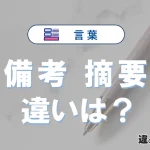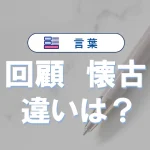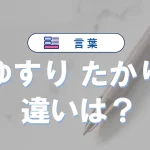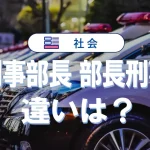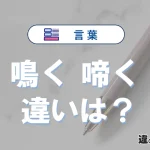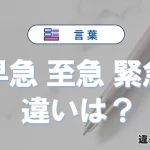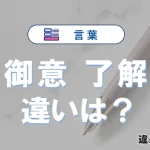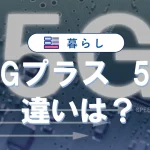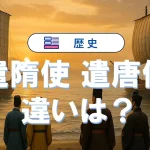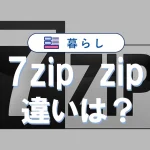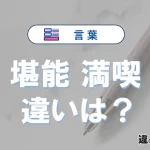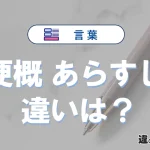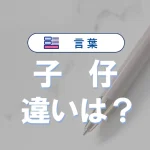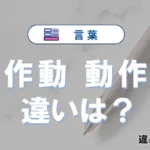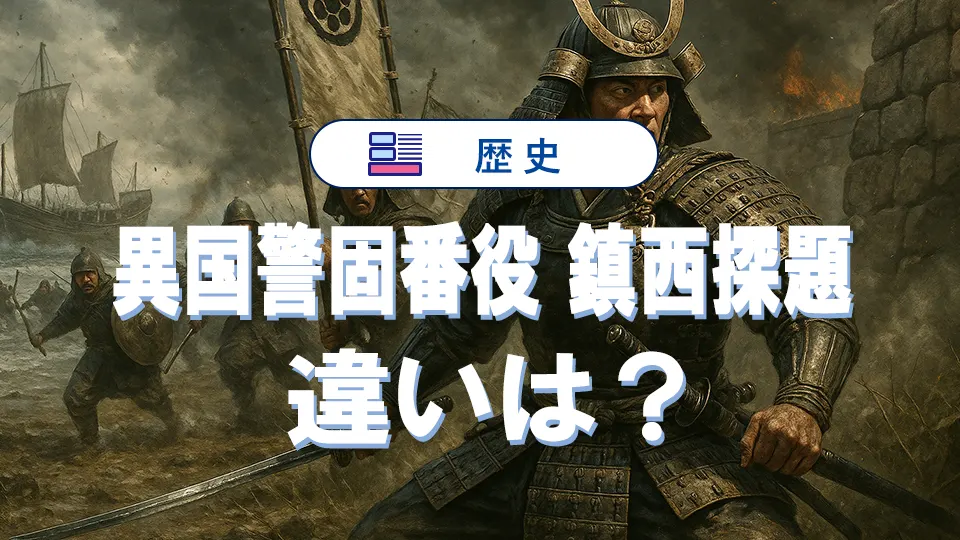
この記事では、「異国警固番役と鎮西探題の違い」について簡単にわかりやすく解説しています。
鎌倉時代、日本は「元寇(げんこう)」として知られるモンゴル帝国からの二度の襲来に直面しました。
この未曾有の危機に対応するため、鎌倉幕府は二つの重要な制度を設けたんです。
それが「異国警固番役」と「鎮西探題」です。
この記事では、この二つの制度の違いをできるだけわかりやすく解説していきますね。
結論から先にお伝えすると、「異国警固番役」は九州の海岸線を守るための常設的な警備システムだったのに対し、「鎮西探題」は九州全体を統治・指揮するための総合的な行政・軍事機関でした。
この基本的な違いを理解することで、文永の役(1274年)や弘安の役(1281年)といった蒙古襲来に対して、日本がどのように対応したのかがより深く見えてくるはずです。
これから、異国警固番役の強化過程や長門警固番役の設置、沿岸部に築かれた石塁(石築地)など、鎌倉幕府が講じたさまざまな防衛対策についても詳しく見ていきながら、この激動の時代の流れを一緒に整理していきましょう!
- 異国警固番役と鎮西探題の違いをわかりやすく理解できる
- 異国警固番役と鎮西探題が作られた背景と目的を知ることができる
- 文永の役や弘安の役など蒙古襲来に対する防衛策を把握できる
- 石塁(石築地)や長門警固番役など防衛強化策の具体例を学べる
目次
異国警固番役・鎮西探題とは何か簡単に解説

異国警固番役を簡単に解説(何のために・いつ・誰が)

「異国警固番役(いこくけいごばんやく)」という言葉、聞いたことはありますか?
これは、モンゴル襲来に備えて鎌倉幕府が設けた防衛制度のことです。
1271年に九州の御家人たちに対して、大友氏の指揮下で筑前や肥前の要所を警備するよう命じたのが始まりとされています。
その後、1274年に「文永の役」で実際に元軍の襲撃を受けたことから、翌1275年にさらに強化されました。
文永の役では元軍が九州北部に上陸して日本に大きな脅威をもたらしました。
この経験から、鎌倉幕府は防衛体制を本格的に整備する必要性を痛感したのです。
そこで、非御家人にも勤番を拡大したり、長門警固番役を設置したり、石塁(石築地)を構築したりするなど、さまざまな対策を講じました。
異国警固番役の特徴は、九州地方の御家人たちが交代制で沿岸地域の警備にあたる仕組みを作ったことです。
一時的な対応ではなく、常設的に防衛を続ける体制を構築した点が画期的でした。
異国警固番役のポイントを簡単にまとめると:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作られた時期 | 1271年(文永8年)、1275年に強化 |
| 作った人物・組織 | 鎌倉幕府(執権:大友氏) |
| 目的 | 元軍襲来に備え、九州沿岸部を警備するため |
| 特徴 | 九州の御家人(及び非御家人)による交代制の沿岸警備 |
このように、異国警固番役は日本を外敵から守るための本格的な軍事対策だったのです。そして、これが後の九州防衛策にも大きな影響を与えることになりました。
鎮西探題を簡単に解説(何のために・いつ・誰が)

次に、「鎮西探題(ちんぜいたんだい)」についてお話しましょう。
これは、九州地方を統括し、軍事・行政・司法を担当するために鎌倉幕府が設置した役職です。
元軍の襲来によって浮き彫りになった九州統治の課題に対応するため、より強力な支配機構が求められたことが設置の背景にありました。
鎮西探題が設置されたのは1293年(永仁元年)です。
これは文永の役(1274年)と弘安の役(1281年)の二度にわたる元軍襲来の後のことでした。
つまり、元寇後の防衛と九州統治のための制度だったんですね。
鎎倉幕府によって初代鎮西探題に任命されたのは北条兼時でした。
彼は九州の御家人たちを直接指揮し、幕府の命令を現地に浸透させる役割を担いました。
特に、蒙古襲来の後に広がった土地問題の調整や、異国警固番役の統括など、多岐にわたる任務を負っていました。
鎮西探題の要点をまとめると:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作られた時期 | 1293年(永仁元年) |
| 作った人物・組織 | 鎌倉幕府(初代:北条兼時) |
| 目的 | 九州統治の強化と軍事防衛の再編 |
| 拠点 | 筑前国(現在の福岡県福岡市周辺) |
鎮西探題は、単なる防衛担当ではなく司法権を持ち、現地での幕府権力の代行者として広範な権限を持っていた点が大きな特徴です。その後の九州における幕府支配の基盤となった重要な制度だったと言えるでしょう。
異国警固番役と鎮西探題の違いをわかりやすく

「異国警固番役と鎮西探題って何が違うの?」と思われる方も多いのではないでしょうか。
どちらも元軍による侵攻に備えるために設置された制度ですが、目的や役割にははっきりとした違いがあります。
この違いを理解することで、鎌倉時代後期の防衛体制がより明確に見えてきますよ。
まず、異国警固番役は「防衛専門」の仕組みでした。
1275年に強化され、九州北部沿岸を警備するため、御家人たちが交代で警備を行う役目を担いました。
簡単に言えば、「現場を守る兵士たちの制度」と考えるとわかりやすいですね。
一方、鎮西探題は「統治と防衛の司令塔」という役割でした。
設置は異国警固番役よりも遅く、1293年です。
鎮西探題には、九州地方の軍事指揮だけでなく、土地問題の調停や御家人たちの統率、裁判権など広い権限が与えられていました。
単なる防衛だけでなく、行政・司法を含めた総合的な支配機関だったのです。
異国警固番役と鎮西探題の違いをまとめると:
| 項目 | 異国警固番役の強化 | 鎮西探題 |
|---|---|---|
| 設置時期 | 1275年(建治元年) | 1293年(永仁元年) |
| 主な役割 | 九州沿岸の警備 | 九州地方の軍事・行政・司法の統括 |
| 設置のきっかけ | 文永の役(1274年)後の防衛強化 | 元寇後の土地問題や統治体制の必要性 |
| 管轄範囲 | 九州北部沿岸 | 九州全域 |
このように、異国警固番役と鎮西探題は目的も規模も大きく異なる制度だったのです。
異国警固番役ができた理由

「なぜ異国警固番役が必要だったのか?」この疑問にお答えしましょう。
異国警固番役が設けられた理由は、元軍の襲撃が予想されていたためです。
当時の日本には恒常的な沿岸防衛体制が整っていませんでした。
そして、1274年に起こった元軍の襲撃(文永の役)での大きな危機感により、鎌倉幕府は防衛体制の抜本的な強化に着手します。
異国警固番役はその一環として、九州沿岸を常時守備する体制を作るために強化されたのです。
異国警固番役の主な特徴は、九州に所領を持つ御家人たちに警備を義務付けたことです。
しかも、これは単なる臨時措置ではなく、半永久的な任務とされました。
交代で番役に就く方式を採用し、いつ襲来があってもすぐに対応できる体制を目指しました。
異国警固番役創設の要因を整理すると:
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 脅威 | 元軍による日本侵攻 |
| 当時の状況 | 沿岸防衛体制が不十分だった |
| 創設の狙い | 常設の沿岸警備を整備するため |
このように、異国警固番役は日本を守るための「恒常的な防衛ライン」を築くために作られた制度だったのです。
鎮西探題ができた理由

では、鎮西探題はなぜ設置されたのでしょうか?
鎮西探題が設置された背景には、元軍襲来後の九州支配の混乱があります。
文永の役、弘安の役と続いた元寇の後、九州では御家人たちの土地争いが激化しました。
また、異国警固番役のような防衛制度だけでは、広範な地域統治には限界があったのです。
このため、鎌倉幕府は単なる防衛だけでなく、行政・司法・軍事を一体的に管理する新たな機関として鎮西探題を設置しました。
1293年、初代鎮西探題に北条兼時が任命され、九州に派遣されました。
鎮西探題には、次のような複数の役割が課せられていました:
- 九州全域の軍事指揮
- 土地問題や争いの調停
- 異国警固番役の監督
- 幕府命令の伝達と執行
つまり、鎮西探題は九州における幕府の出先政権とも言える存在でした。
鎮西探題ができた理由を整理すると:
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 元寇後の状況 | 九州御家人の対立、土地問題の深刻化 |
| 異国警固番役の限界 | 防衛には対応できても、統治までは不十分 |
| 設置の狙い | 九州支配の強化と安定 |
| 指導者 | 北条兼時 |
このように考えると、鎮西探題の設置は「単なる防衛強化」ではなく、九州全域を安定させるために必要不可欠だったとわかります。
異国警固番役と鎮西探題の歴史をたどる

最初の蒙古襲来(元寇):文永の役

1274年、元(モンゴル帝国)と高麗の連合軍が日本に襲来した事件が「文永の役」です。
これは、日本にとって初めての大規模な外国からの軍事侵攻でした。
元軍は約900艘の軍船に乗り、兵力はおよそ2~3万人規模とされています。
彼らは九州北部の博多湾に上陸し、日本側は御家人を中心とした軍勢でこれを迎え撃ちました。
この戦いで、元軍は組織的な集団戦法や火薬兵器(てつはう)を駆使し、日本側を圧倒しましたが、夜間に撤退し、最終的に暴風雨により大損害を被って引き揚げました。
文永の役は日本にとって大きな衝撃でした。
これにより、鎌倉幕府は沿岸防備の重要性を痛感し、防衛体制の整備に乗り出すことになります。
このときの経験が、後の異国警固番役や石塁構築といった対策へとつながっていきました。
異国警固番役の強化とその背景

文永の役後、日本は元軍の再来に備える必要に迫られました。
そこで鎌倉幕府が進めたのが「異国警固番役」の強化です。
元々の異国警固番役は1271年に開始され、九州沿岸を御家人たちが交代で守る仕組みでした。
しかし、文永の役の教訓から、防衛体制の脆弱さが明らかになったため、次第に内容が強化されていきます。
例えば、警備範囲の拡大、警備の常駐化、石塁の築造などが加わりました。
また、異国警固番役には、単なる兵力の動員だけでなく、武器や兵糧の備蓄、連絡体制の整備といった役割も求められるようになります。
特に、博多湾沿岸では常に即応できる体制が構築されていきました。
このような背景には、再度の蒙古襲来が現実的な脅威となっていたこと、そして九州地方の重要性が増していたことがありました。
長門警固番役の設置について

異国警固番役の一環として、特に重要な役割を担ったのが「長門警固番役」です。
長門国(現在の山口県西部)は、博多湾と並んで元軍の上陸が予想される重要拠点と見なされていました。
そのため、鎌倉幕府は1276年頃、長門にも警固番役を設置し、警備体制を強化しました。
長門警固番役では、地元の御家人に加え、本州側からも御家人が派遣され、交代制で沿岸警備に当たりました。
特に、関門海峡を押さえることが目的とされ、万が一九州だけで食い止められなかった場合の「第二防衛線」として機能することが期待されていたのです。
まとめると、長門警固番役は単なる九州防衛の補完ではなく、日本本土防衛の要所を担った重要な施策だったといえるでしょう。
石塁(石築地)の構築と防衛策

元軍の再襲来に備え、鎌倉幕府が実施した対策の中でも特に注目されるのが、「石塁(石築地)」の構築です。
石塁とは、博多湾沿岸に築かれた長大な防塁で、1276年から1280年頃にかけて建設が進められました。
長さは約20kmにも及び、高さは平均2m、幅も2m前後だったと伝えられています。
この石塁は、元軍の上陸を防ぎ、攻撃を食い止めることを目的としていました。
建設には、九州に所領を持つ御家人たちが動員され、各自担当区間を分担して築造が行われました。
また、石塁の後方には軍勢を待機させ、敵が上陸を試みた場合には即座に反撃できる体制が整えられました。
このように、石塁は単なる防壁ではなく、総合的な防衛システムの中核を成していたのです。
今でも福岡市周辺には、当時の石塁の遺構が確認されています。
二度目の蒙古襲来(元寇):弘安の役

1281年、元軍は再び日本侵攻を試みました。
これが「弘安の役」と呼ばれる二度目の元寇です。
今回は、元と南宋を征服した後の中国本土からの大軍(江南軍)と、高麗軍からなる連合軍が組織され、前回を大きく上回る規模、兵力は合計14万人とも言われます。
この連合軍は東路軍と江南軍に分かれ、それぞれ別ルートから日本を目指しました。
日本側は、石塁の構築や異国警固番役の強化によって万全の体制を整えていました。
その結果、博多湾に押し寄せた元軍を防ぎ、局地戦で優位に立つことに成功します。
さらに、長期化する戦いの中で台風が発生し、多くの元軍船が沈没しました。
この自然災害が決定打となり、元軍は大損害を受け、侵攻を断念しました。
弘安の役は、日本が侵略から自国を守った歴史的な勝利として語り継がれています。
同時に、これをきっかけに日本国内の政治・社会にも大きな影響を及ぼしました。
御家人の疲弊と鎌倉幕府の衰退

元寇後、最も深刻な問題となったのが、御家人たちの経済的疲弊です。
異国警固番役の継続、軍備の負担、石塁の維持管理など、多大な負担を背負った御家人たちは、次第に生活基盤を失っていきました。
御家人の困窮を受けて、鎌倉幕府は「徳政令(とくせいれい)」と呼ばれる債務帳消しの政策を発令しました。
しかし、この政策は一時的な救済にとどまり、根本的な解決にはなりませんでした。
むしろ、貸し手である商人や寺社勢力との対立を招き、社会不安を増す結果となります。
この御家人層の不満と疲弊は、やがて幕府の支配力低下へとつながります。
最終的に、14世紀前半に後醍醐天皇による倒幕運動(元弘の乱)が起こり、鎌倉幕府は1333年に滅亡へと追い込まれました。
まとめると、元寇は単なる外敵の撃退にとどまらず、その後の日本史に深い爪痕を残した出来事だったのです。
いかがでしたか?異国警固番役と鎮西探題の違いや成り立ちについて理解が深まったでしょうか。
モンゴル帝国の侵攻という国家的危機に対して、日本がどのように防衛体制を構築していったのか、その歴史的な流れがわかりやすくなったかと思います。
異国警固番役・鎮西探題の役割と歴史|要点まとめ
- 異国警固番役は1271年に鎌倉幕府が設置した防衛制度
- 文永の役を受け1275年に異国警固番役を本格強化
- 九州北部の御家人たちが交代で沿岸警備を担当
- 異国警固番役は非御家人にも勤番が拡大された
- 長門警固番役は九州以外にも防衛体制を広げた施策
- 石塁(石築地)は博多湾沿岸に築かれた防衛施設
- 石塁は約20kmにわたる長大な石の防塁であった
- 鎮西探題は1293年に九州支配を強化するために設置
- 鎮西探題の初代担当者は北条兼時であった
- 鎮西探題は軍事・行政・司法の権限を持った
- 文永の役では元軍の奇襲に日本側は苦戦した
- 弘安の役では石塁と防衛体制が効果を発揮した
- 台風による自然災害が元軍を壊滅させた
- 元寇後、御家人たちは経済的に疲弊していった
- 徳政令は御家人救済のため発布されたが効果は限定的だった