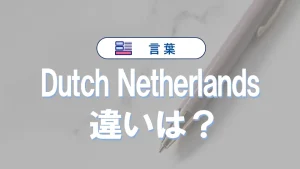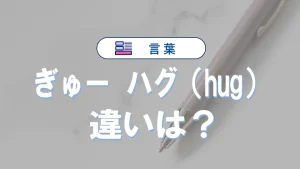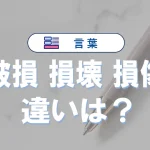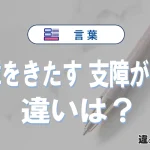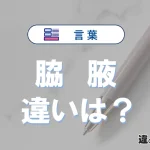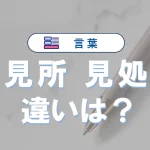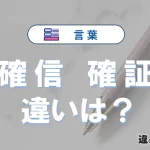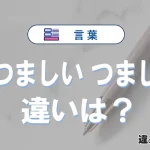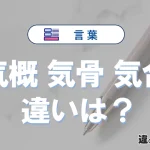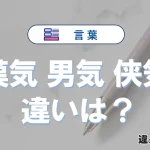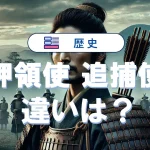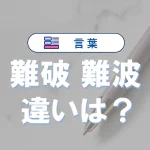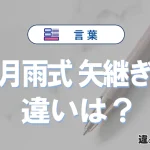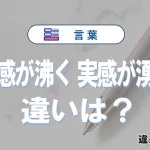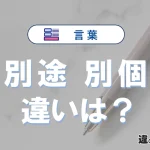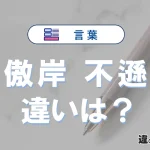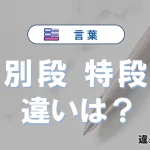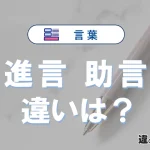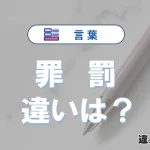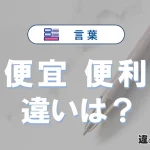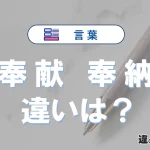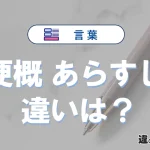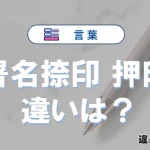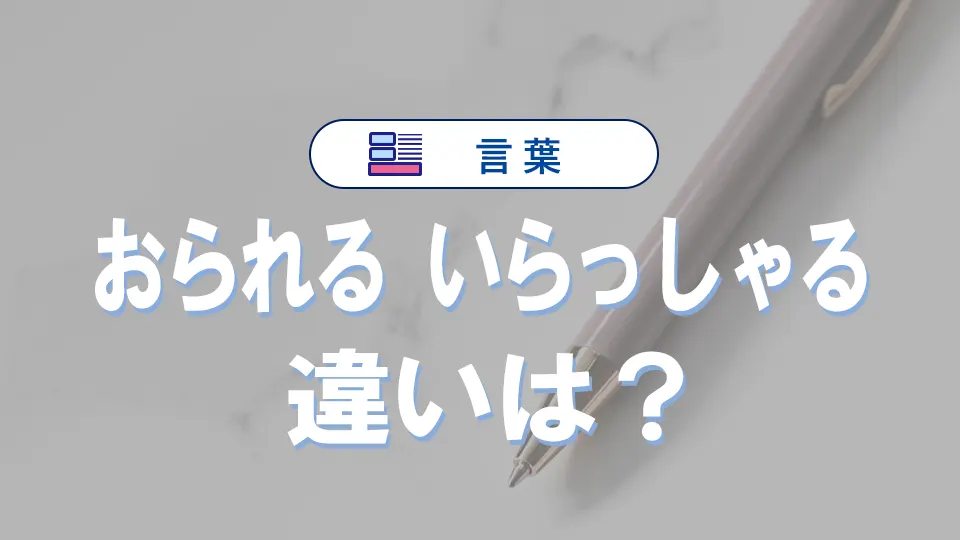
敬語を正しく使おうとすればするほど、「おられる」と「いらっしゃる」の使い分けに迷った経験はありませんか?
どちらも「いる」の尊敬語にあたりますが、実はニュアンスや使用シーンには違いがあります。文化庁の『敬語の指針』でも、尊敬語の誤用は相手に違和感を与える可能性があると指摘されています(文化庁:敬語の指針)。
ここでは、国立国語研究所や言語学者の研究、新聞記事の事例も交えながら、「おられる」と「いらっしゃる」の違いを丁寧に整理していきましょう。
目次
「おられる」と「いらっしゃる」の違いとは?
「おられる」は動詞「おる」に尊敬を表す「お」が付いた形で、もともとは方言的な使用が強い言葉です。『日本語学』(明治書院)の論文でも、関西方言における「おる」の尊敬表現が日常的に用いられていることが指摘されています。
一方、「いらっしゃる」は全国的に使われる標準的な尊敬語で、文化庁の国語世論調査(令和3年度調査)でも「いる」の尊敬語として最も認識度が高い表現です。NHK放送文化研究所の調査でも「公式な放送では『いらっしゃる』を優先的に用いる」との基準が示されています。
「おられる」と「いらっしゃる」の比較表
| 項目 | おられる | いらっしゃる |
|---|---|---|
| 敬語の種類 | 尊敬語(「おる」+「お」) | 尊敬語(「行く・来る・いる」の尊敬語) |
| 使用シーン | 日常会話・親しい間柄・関西地方で自然 | ビジネス・公的文書・公式なスピーチ |
| 印象 | やや口語的・親しみやすい | 標準的・より丁寧で無難 |
| 誤用リスク | 方言的に聞こえる場合あり | 二重敬語に注意(例:「いらっしゃられる」) |
| 言い換え例 | 席におられる → 席にいる | 席にいらっしゃる → 席にご在席です |
| 専門機関の評価 | 地域差が強い(国立国語研究所調査) | 全国的に標準的(文化庁・NHK基準) |
「おられる」と「いらっしゃる」の使い分け方
たとえば、学校で「先生は研究室におられますよ」と言っても失礼ではなく、自然な表現として受け止められます。しかし、就職面接やビジネス文書では「先生は研究室にいらっしゃいます」と表現したほうが確実です。
読売新聞(2021年5月特集記事)でも「ビジネスでの敬語誤用は印象を損ねる可能性がある」と指摘されており、特に「おられる」を多用すると「くだけた印象を与えやすい」と報じています。
よくある誤用とその修正方法
よくあるのが「二重敬語」です。「社長はいらっしゃられる」という表現は一見丁寧に見えますが、実際には不自然です。「いらっしゃる」自体が尊敬語なので「られる」を重ねる必要はありません。文化庁の敬語指針でも「重複した敬語は避けるべき」と記載されています。
また、朝日新聞デジタル(2020年9月記事)では「おられる」を全国放送で多用するアナウンサーへの違和感が紹介されており、「おられる」は必ずしも万人に受け入れられる表現ではないとされています。
言い換え表現について
敬語は一つに固定せず、状況に応じて表現を切り替えるのが理想です。「お見えになる」「お越しになる」などの表現は相手の動作に焦点を当てる場合に便利です。
国語学者の金田一春彦氏も著書『敬語』(岩波新書)の中で「一つの敬語にこだわらず、場面や相手に応じて表現を選ぶ柔軟さが大切」と述べています。
実践で役立つ例文(5つ)
- 課長はただいま会議室にいらっしゃいます。(公式な場で最も安全な表現)
- 先生は研究室におられますので、こちらへどうぞ。(日常的・親しみを込めた場面)
- 部長は外出中で、社内にはお見えになりません。(フォーマルな言い換え)
- ご担当者様は席にいらっしゃいますでしょうか。(電話対応でよく使う)
- 本日は多くの来賓の皆様にお越しいただき、誠にありがとうございます。(公式スピーチや挨拶)
「おられる」「いらっしゃる」に関するよくある質問
どちらがより丁寧ですか?
一般的には「いらっしゃる」の方が丁寧で、全国的に通用する表現です。
「先生がおられる」は失礼ですか?
失礼ではありませんが、フォーマルな場では「先生がいらっしゃる」とした方が安心です。
就職面接や公式文書ではどちらを使うべき?
文化庁の指針や新聞社の敬語マニュアルでも「いらっしゃる」を推奨しています。面接や公的文書では必ずこちらを使うのが無難です。
【まとめ】「おられる」と「いらっしゃる」の違いを理解して正しく使おう
「おられる」と「いらっしゃる」は、いずれも尊敬語でありながら使用シーンや受け取られ方に違いがあります。「おられる」は親しみを込めた日常的な表現、「いらっしゃる」はフォーマルで全国的に認められた表現です。
文化庁の『敬語の指針』、国立国語研究所の調査、新聞記事や学者の解説を見ても「いらっしゃる」が公的な場面で推奨されていることは明らかです。
今日から少しずつ実践して、相手に好印象を与える敬語表現を身につけていきましょう。