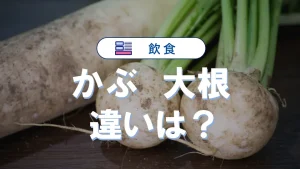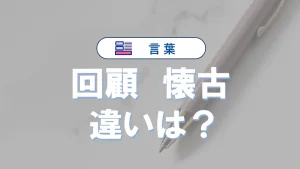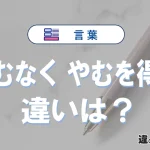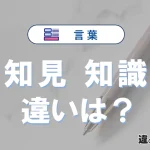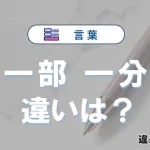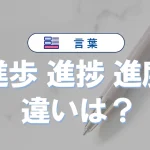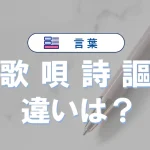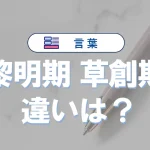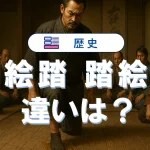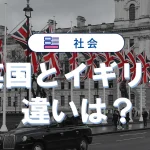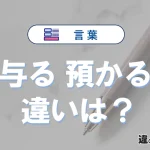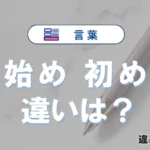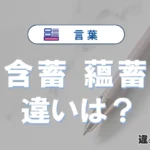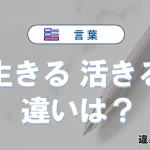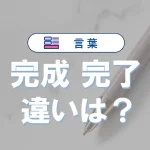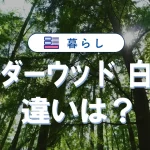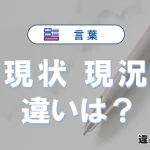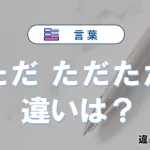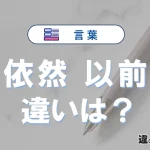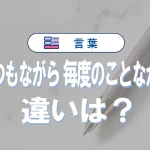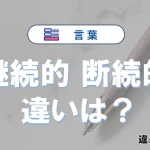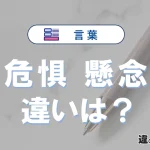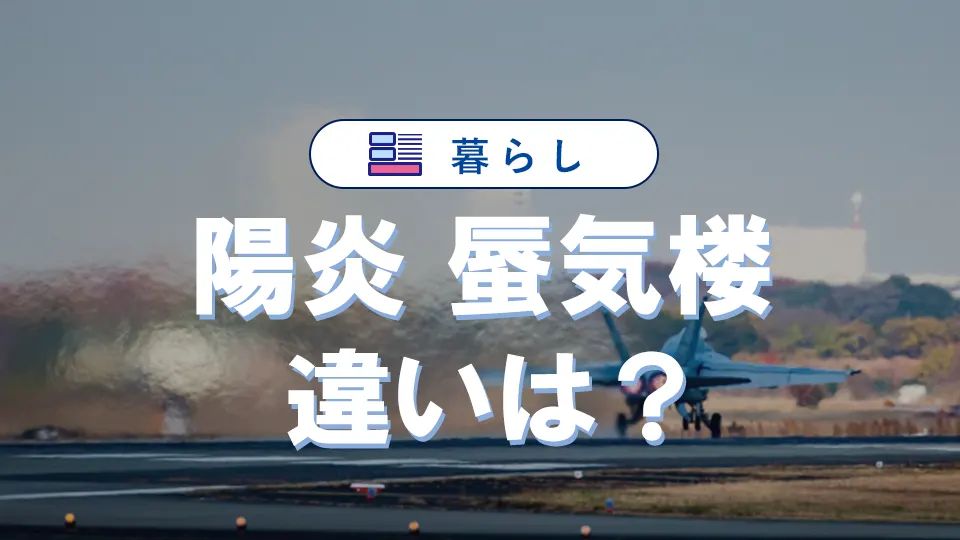
私たちが夏の強い日差しの下で道路や砂漠を眺めるとき、「ゆらゆらと景色が揺れて見える陽炎」や「存在しない水面や建物が現れる蜃気楼」を目にすることがあります。どちらも光の屈折によって生じる自然現象ですが、その仕組みや観察される状況、文化的背景は異なります。本記事では、気象学・物理学・文化史的な観点から「陽炎」と「蜃気楼」の違いを詳しく解説します。
目次
陽炎と蜃気楼の違いを理解しよう
陽炎とは?その現象の仕組みを解説
陽炎(かげろう)は、地面近くの空気が加熱されて屈折率が変化することで起きる現象です。例えば真夏のアスファルト道路や砂地では、太陽からの強烈な日射で地面が熱せられ、その直上の空気の温度が急激に上昇します。この高温の空気は密度が低く、周囲の空気と異なる屈折率を持つため、光が揺らめくように屈折します。結果として、遠方の景色が揺れ動いて見えるのです。
- 特徴:揺らぎ・歪みが中心で、像そのものは現れない
- 身近な例:夏の道路、砂漠、炎の上など

この現象は英語で heat haze や heat shimmer と呼ばれ、光学的には「大気の屈折率揺らぎによる像の変形」に分類されます(国立天文台)。
蜃気楼の概要と特徴を知る
蜃気楼(しんきろう)は、遠方に存在しない風景や物体が見える現象です。光が大きく屈折することで、実像や虚像が別の位置に現れるのが特徴です。蜃気楼には大きく2種類あります。
- 下位蜃気楼(inferior mirage):地表付近が高温で、その上が冷たい場合に生じます。道路に「水たまり」があるように見える「逃げ水」現象が代表例です。
- 上位蜃気楼(superior mirage):寒冷地や海上で、下層が冷たく上層が暖かい場合に発生します。船や建物が空中に浮かんで見える現象が典型です。

蜃気楼の最も有名な観測地のひとつが富山湾で、「春の蜃気楼」として知られています(富山観光ナビ|蜃気楼(蜃気楼展望地点)。
陽炎と蜃気楼の違いを明確にする
| 現象 | 原因 | 見え方 | 英語表現 |
|---|---|---|---|
| 陽炎 | 微細な空気の温度差による光の揺らぎ | 景色が揺れる・歪む | heat haze, heat shimmer |
| 蜃気楼 | 強い温度勾配による大きな光の屈折 | 実在しない像や逆さ像が現れる | mirage |
つまり、陽炎は「揺らぎの現象」、蜃気楼は「像が現れる現象」という違いがあります。
陽炎と蜃気楼の違いと発生条件

気象と温度の影響について
陽炎は晴天・乾燥・強い日射といった条件が重なると発生します。地表面が高温になりやすい夏場が最も典型的です。一方、蜃気楼は気温の逆転層(inversion layer)が条件となり、寒冷な地域や海上でも頻繁に見られます。
光の屈折とその仕組み
光は「屈折率の異なる媒質」を通過すると進行方向を変えます。大気の屈折率は温度に依存して変化するため、温度勾配が大きい場合には光が曲げられ、観測者の眼に虚像や揺らぎとして届きます(Born & Wolf, Principles of Optics, 1999).
夏の特定の条件下での両者の発生
- 陽炎:真夏の道路・砂漠・炎の上などで日常的に観察可能
- 蜃気楼:春先の富山湾、アラスカや北欧などの寒冷地、砂漠地帯で発生
両者は「同じ光学現象に基づくが、温度差のスケールと光の屈折の度合いが異なる」とまとめられます。
陽炎と蜃気楼の違いと観察体験

砂漠や道路の景色と陽炎の関係
砂漠や舗装道路では「地面から熱気が立ち上る」ように見えますが、これは実際には光の揺らぎです。映画や小説でも「砂漠を歩く旅人が陽炎に惑わされる」描写がしばしば登場します。
蜃気楼の写真と美しい景観
富山湾の蜃気楼は、船が宙に浮かんだように見える現象で有名です。写真資料でも幻想的に記録され、観光資源ともなっています。
逃げ水との関連性について
「道路に水があるように見えるが、近づくと消える」現象は典型的な下位蜃気楼です。これを俗に「逃げ水」と呼び、日本の古典文学や俳句でも詠まれています。
陽炎と蜃気楼の違いと恐怖神秘
蜃気楼にまつわる怖い話
古代中国では、蜃気楼は「蜃(大蛤の妖怪)が吐き出す気が作り出す幻」と信じられていました。そのため「蜃気楼」という漢字表記が生まれました。
陽炎の幻想的な側面
陽炎は「儚く揺らめく」様子から、日本文学では無常観や命の儚さの象徴として詠まれます。『枕草子』や俳句にも頻繁に登場します。
日本における文化的な意味合い
- 陽炎:夏の季語として俳句に詠まれる
- 蜃気楼:神秘的現象として伝説や民話に登場
文化的背景を踏まえると、両者は単なる自然現象にとどまらず、人間の想像力をかき立てる存在といえます。
陽炎と蜃気楼の違いと英語表現
陽炎の英語と海外での認知
陽炎は heat haze や heat shimmer と表現され、特に砂漠や戦場の描写で使われます。軍事映画などでは、望遠レンズ越しの景色が揺らめく描写として描かれます。
蜃気楼の英語とその用例
蜃気楼は mirage と訳され、「幻影」や「実在しないもの」という比喩的な意味でも広く使われます。例:The promise of wealth turned out to be a mirage.(富の約束は幻想に過ぎなかった)。
両者の英語表現の違いと使い方
- 陽炎:揺らめき → heat haze
- 蜃気楼:幻像 → mirage
英語圏では、mirage の方が文学的表現や日常会話に登場する頻度が高いといえます。
まとめ|陽炎と蜃気楼の違いと今後の学び
陽炎と蜃気楼の理解を深めるために
陽炎は「揺らぎ」、蜃気楼は「幻像」という本質的な違いがあります。両者を正しく理解することで、日常の自然現象をより豊かに楽しむことができます。
関連情報や文献の紹介
新しい発見に繋がる視点
陽炎や蜃気楼は、単なる「不思議な現象」ではなく、大気の構造や光の物理を反映する自然の鏡です。これらをきっかけに光学や気象学を学ぶことは、日常を科学的に見る視点を育み、新しい発見につながるでしょう。