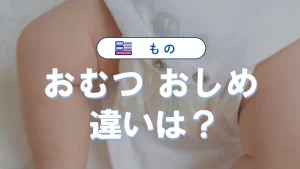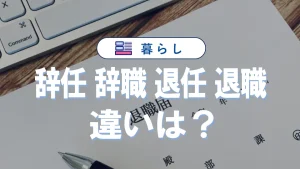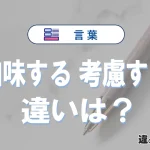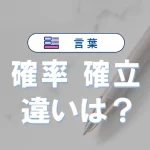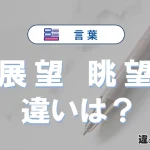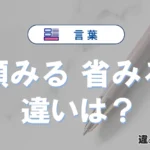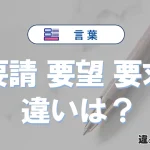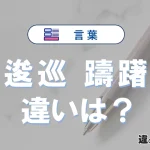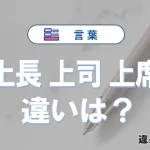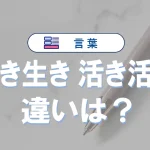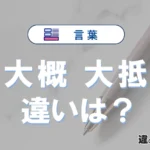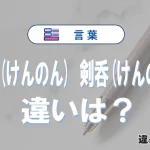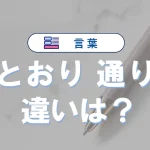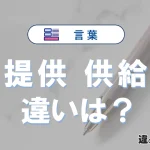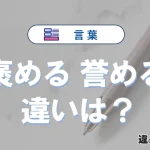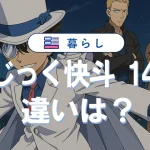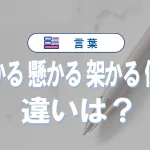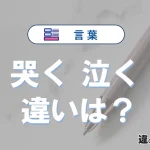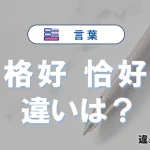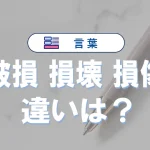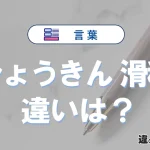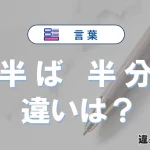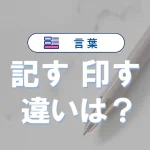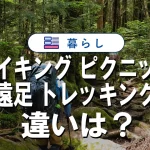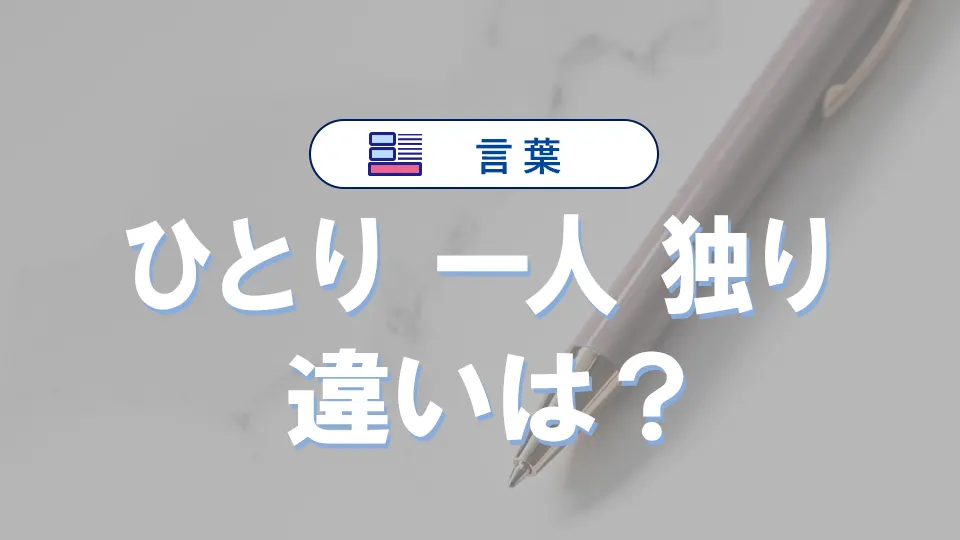
日常の中でよく使う「ひとり」「一人」「独り」という言葉。どれも同じ「ひとり」と読むのに、書き方によって意味やニュアンスが異なります。 「ひとりで旅行に行った」「一人で作業した」「独りで泣いた」――どれも文法的には正しいものの、受ける印象や伝わる感情は微妙に違います。 この記事では、日本語表記の微細な違いに注目し、「ひとり」「一人」「独り」の意味・使い分け・例文・語源までを丁寧に解説します。 文法の視点だけでなく、文化的背景や心理的なニュアンスにも踏み込み、より自然で深みのある日本語表現を身につけましょう。
目次
「ひとり」「一人」「独り」の違いと意味は?
「ひとり」の表記と用法
ひらがなで表記される「ひとり」は、最も柔らかく親しみやすい印象を与えます。 漢字の「一人」や「独り」に比べると、視覚的にも感情的にも穏やかで、口語的・感覚的な文章に適しています。 特に会話文・エッセイ・詩などで自然なリズムや語感を重視する場合、「ひとり」は理想的な選択肢です。
また、「ひとり」は文脈によって、単なる人数の意味にも、孤独のニュアンスにもなり得ます。 これは日本語特有の曖昧さと温かみを兼ね備えた表記であり、「人と人との距離感」を優しく表現できる点に特徴があります。 たとえば、「ひとりの時間が好き」という表現は、「孤独を楽しむ」というポジティブな意味合いを帯びます。
一方で、「ひとりだけ取り残された」という場合は、寂しさや孤立感を含むこともあります。 つまり、「ひとり」は文脈次第で“温かさ”にも“寂しさ”にも変化する多面的な表記なのです。
「一人」の定義と用法
「一人」は、最も中立的かつ標準的な表記です。主に「人数が1であること」を示す客観的な語として使われます。 たとえば、「参加者は一人です」「一人だけ遅刻した」というように、感情ではなく事実を淡々と伝える文脈に適しています。
公的文書、ビジネス文書、学術論文などでは、「ひとり」や「独り」ではなく、基本的に「一人」が選ばれます。 これは、漢数字による数詞表現が公式文書において読みやすく、統一性を保ちやすいからです。
また、「一人前」「一人称」「一人暮らし」などの複合語も、この「一人」を基礎にしています。 このような言葉では、「1名」や「単独」という数量的・構造的意味が前面に出ます。
国語辞典によると、「一人」は「人数を数える語であり、単に一名であること」と定義されます。 したがって、「感情を伴わない“ひとり”」を表すのに最も適した表記が「一人」なのです。
「独り」の意味と用法
「独り」は、「独」という字が示す通り、「他と離れている」「孤独である」「自立している」といった意味を含みます。 これは、感情・哲学・文学の文脈で多用される表記であり、読み手に強い印象を与えます。
「独り」は物理的な孤立だけでなく、精神的な孤高をも表すことがあります。 「独りで生きる」「独り言」「独り立ち」「独り占め」などの熟語では、自立・単独行動・孤独が強調されます。
特に文学作品では、「独り」は象徴的に使われ、「寂しさ」「強さ」「自由」「孤高」といった対照的な概念を表現するのに適しています。 これは英語でいえば “alone” と “solitude” の中間的な位置づけに近いニュアンスです。
学術的には、「独り」は孤立状態の心理描写や文学的比喩として使われることが多く、 日本語教育研究でも「孤独・独立を表す語」として解説されています。
それぞれの表記の違いと使用場面
3つの「ひとり」の使い分けを、意味・印象・使用場面の観点から整理すると次のようになります。
| 表記 | 意味・役割 | 語感 | 使用場面 |
|---|---|---|---|
| ひとり | 柔らかく自然な表現。人数や孤独の両義を含む。 | 親しみ・やさしさ・口語的 | 会話・エッセイ・日常表現 |
| 一人 | 客観的に「1名」を表す。最も中立的。 | 無機質・標準的 | 公文書・ビジネス文書 |
| 独り | 孤独・自立・独立を強調する。 | 感情的・文学的 | 詩・小説・心情表現 |
つまり、「ひとり」は感覚的、「一人」は事実的、「独り」は心理的と言い換えることができます。
「ひとり」「一人」「独り」の使い分け
公用文における使い分け
公用文や報告書など、正式な場では「一人」または「1人」が推奨されます。 特に人数・統計・数値データを扱う場合は「1人」が好まれ、文章的な部分では「一人」を用います。
例:「欠席者は一人」「職員1人あたりの費用」「1人暮らし世帯が増加している」など。
文部科学省の公用文ガイドラインでも、原則として「人数を数える場合は漢数字、一連の数字が並ぶ場合は算用数字を用いる」とされています。 「独り」は公的文書では避けられ、感情表現が不要なときは「一人」が基本です。
日常会話での違い
日常会話では、感情や語感によって使い分けられます。 友人同士の会話やブログでは「ひとり」が自然で、感情表現や詩的ニュアンスを出したい場合は「独り」が使われます。
| 状況 | 自然な表記 | ニュアンス |
|---|---|---|
| 気軽な発言 | ひとりでカフェに行った | 軽い・柔らかい |
| 客観的説明 | 一人が遅れてきた | 事実的 |
| 感情表現 | 独りで泣いた | 寂しさ・重み |
| 自立の強調 | 独り立ちする | 強さ・誇り |
孤独感と応援の言葉の使い方
「独り」は孤独を強調し、「ひとり」は優しさを伝えます。 たとえば、「あなたは独りじゃない」は強い励ましの言葉であり、「ひとりじゃないよ」は柔らかく包み込む響きを持ちます。
孤独感の描写においても、「独りぼっち」は切なさ、「ひとり時間」は心地よさを表します。 このわずかな表記差が、読者の感情に大きな違いを与えるのです。
「ひとり」「一人」「独り」の例文
「ひとり」を使った具体例
- 今日はひとりで美術館へ行った。
- たまにはひとりでゆっくり過ごしたい。
- 彼女はひとりで笑っていた。
- ひとりで食べるご飯も悪くない。
- 夜風に吹かれながらひとり散歩した。
「一人」の使い方と例文
- 参加者は一人だけでした。
- 一人当たりの料金は500円です。
- 彼は一人で全てを終わらせた。
- この部屋には一人しかいません。
- 一人前の料理を追加で注文した。
「独り」の意味を活かした例文
- 独りで泣く夜は長い。
- 彼は独りきりで旅に出た。
- 誰にも頼らず独り立ちする。
- 独り言のように呟いた。
- 独りで過ごす時間が好きだ。
「ひとり」「一人」「独り」の表記のルール
1人と横書きの使い方
「1人」は算用数字を使う表記で、数値的正確さを求める場合に用いられます。 ニュース記事や統計資料などでは「1人」「2人」と統一することで可読性が高まります。
ただし、感情や心理を表す文章では数字表記が冷たく感じられるため、「一人」や「ひとり」が選ばれる傾向があります。
1人1人との使い分け
「1人一人」「一人一人」「一人ひとり」などの表記にはわずかな違いがあります。
- 公的文書やビジネス文章:一人一人(統一感と正式感)
- 読みやすさと柔らかさの両立:一人ひとり
- 親しみを優先する文章:ひとりひとり
文化庁の『公用文作成の手引』でも、用語統一を重視する立場から「一人一人」を標準としています。 ただし、詩的・感情的な文章では「ひとりひとり」も許容されています。
一人一人の正しい表記法
意味的な違いはほぼありませんが、読みやすさと印象で選ぶことが大切です。 文書全体で統一されていれば、どの表記を採用しても問題はありません。
「ひとり」「一人」「独り」の語源と文化的背景
日本語における「ひとり」のもつ意味
「ひとり」は古語の「ひ」「たり」から生まれたとされます。 「ひ」は“ひとつ”“一”の意味を持ち、「たり」は助数詞の語尾。 つまり、「ひとり」は「ひ(1つの)+たり(人)」=「1人の人」という古い数え方が語源です。
日本語の中で「ひとり」は、数的意味と感情的意味の両方を持つ稀有な語であり、 この曖昧さこそが日本語の美しさを象徴しています。
言葉の進化と現代の使われ方
現代では、「ひとり〇〇」という言葉が数多く生まれています。 「ひとり旅」「ひとり飲み」「ひとりカラオケ」「ひとり焼肉」など、 “孤独を恐れず楽しむ生き方”としての「ひとり」がポジティブに使われるようになりました。
一方で、「独り」は孤立や悲しみを象徴する言葉として文学作品や心理描写に多く登場します。 この二面性が、日本語における“ひとり”文化の奥深さを物語っています。
「一人は好きだけど独りは嫌い」という言葉の響き
この言葉が示すように、「一人」は“状態”であり、「独り」は“感情”です。 「一人で過ごす時間」は自分を取り戻すための静寂ですが、「独りになること」は孤立を意味します。 つまり、「一人」と「独り」の差は、“自分が選んだひとりかどうか”という主体性の違いにあるのです。
まとめ:「ひとり」「一人」「独り」の違いと意味
使用シーンに応じた使い分けの重要性
・客観的な人数 → 「一人」「1人」
・柔らかく日常的 → 「ひとり」
・孤独・自立・文学的 → 「独り」
このように、同じ読みでも「誰に」「何を」「どんな感情で」伝えたいかによって使う表記を変えることで、 日本語表現は一層豊かになります。
これからの言葉の使い方のトレンド
現代では「ひとり」をポジティブに捉える風潮が広まり、「独り」を文学的・内省的に使うケースが増えています。 SNS時代の今だからこそ、「ひとりでいること」=「自由で自分らしい生き方」という新しい価値観が定着しつつあります。
言葉は時代とともに変化します。 「ひとり」「一人」「独り」――この3つの“ひとり”を意識的に使い分けることが、 豊かな表現力と感情の深さを身につける第一歩となるでしょう。