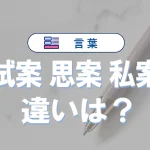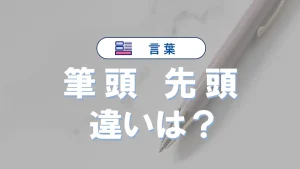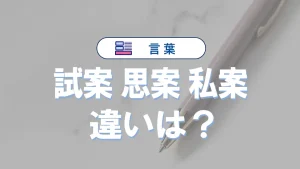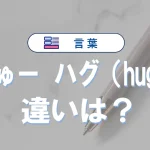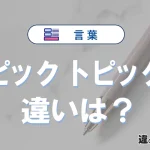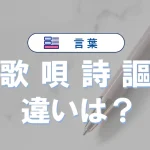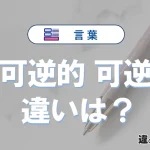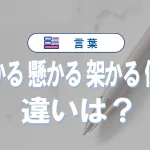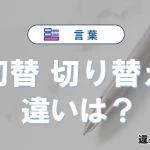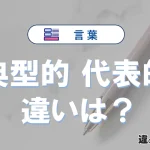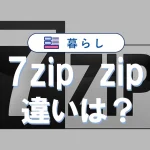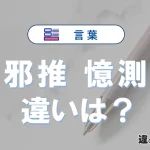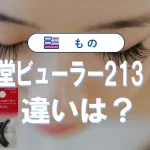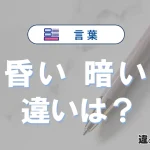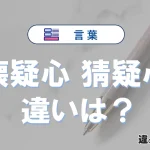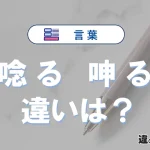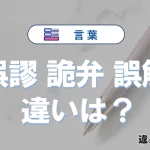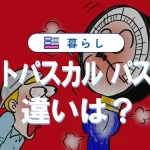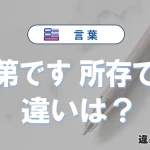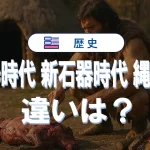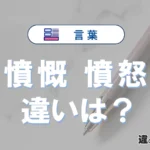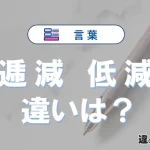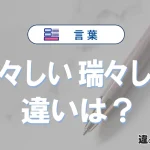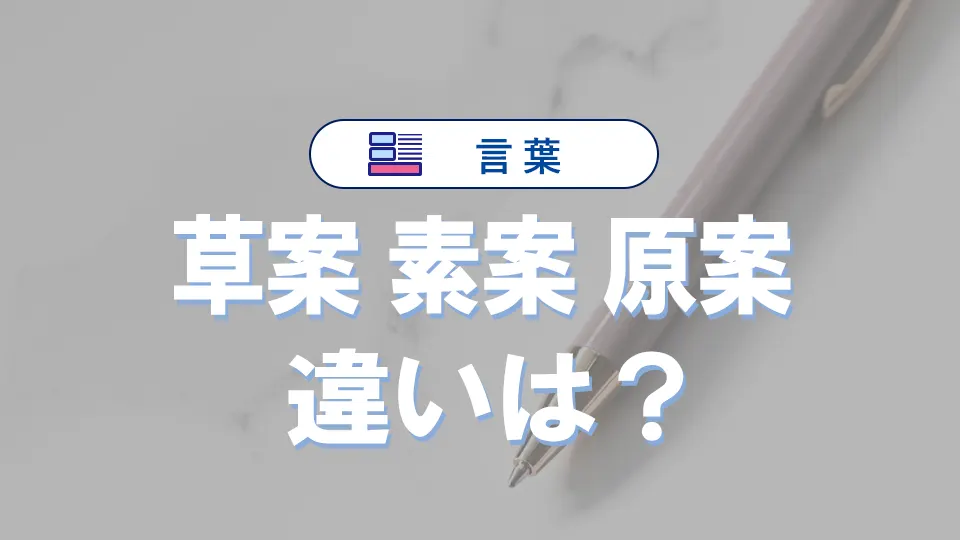
「草案・素案・原案」の3語は、議論・企画・文書作成の過程でしばしば混同されがちですが、それぞれニュアンス・使われる場面・性質が異なります。本記事では、それらの違いを明確に整理し、使い分けをマスターできるように、意味・用例・比較表・応用までを網羅します。
結論を先に言えば:
- 素案:まだおおまかな構想段階。細部は未確定・方向性を示す案
- 草案:文書・企画の“たたき台”的案。ある程度内容を盛り込んだ初稿
- 原案:承認・議論用にほぼ固まった案。最終調整を待つ案
本稿を読めば、「この場面ではどの語を使うべきか」が迷わなくなります。
目次
草案・素案・原案の基本理解
草案とは?その意味と役割
「草案(そうあん)」とは、最終的な文書や計画を作成する前の “たたき台” としての案を指します。文書・政策・規約・契約書といった体裁あるものを作るとき、最初に構成や主な内容を仮に盛り込む文書です。
語源的には、「草」は「本格化する前・粗略な段階」の意を含むもので、「草案」は「本格化前の案」を意味します。
役割・特徴:
- 決定前に関係者の意見を集め、修正・調整を行うための素材
- 内容確定度は中程度:方向性は定まるが、細部は未確定
- 複数案を重ねて議論を進める過程で使われる
- 「草案を練る」「草案を提出する」「草案を修正する」といった用法が一般的
たとえば、法案や条例、契約書、企画書、方針文書など、文書化・形のあるものを作る場面で多用されます。
素案の定義と利用シーン
「素案(そあん)」は、草案の以前の段階、つまり「大枠の案」「構想段階の案」を指します。語の「素」には「根本・原初」「基礎となるもの」という意味があり、そこから派生して、「正式な案を作るための元になる構想」の意味になることが多いです。
特徴:
- 構想・アイデアの段階 → 詳細が定まっていない
- 複数の方向性を並べて比較する段階で使われやすい
- まだ正式文書化するレベルではない
- 利用される場面としては、企画立案、プロジェクト構想、政策立案の初期段階など
たとえば「都市再開発の素案」「新規事業の素案を検討する」「政策の素案を公表する」といった使い方が挙げられます。
原案とは?草案との違いを解説
「原案(げんあん)」は、草案と同じく“案”の一種ですが、「議論・承認用にかなり固まった案」「再確認・最終調整を待つ案」というニュアンスがあります。つまり、最終段階に近い案が「原案」として扱われるケースも多いです。
特徴:
- 草案より少し完成度が上の案
- 議案・承認にかけられる前段階
- 文書だけでなく、設計案・デザイン案・企画案など幅広く使われる
- 「原案を提示する」「原案として審議にかける」「原案が採択される」といった表現が一般的
また、草案が文章の下書きとして特に使われる傾向が強いのに対し、原案は文書以外(設計・デザイン・設定等)にも用いられる柔軟さがあります。
草案・素案・原案の違い
草案と素案の違い
| 観点 | 素案 | 草案 |
|---|---|---|
| 段階 | 構想・方向性レベル | 具体的な案(初稿) |
| 内容の確定度 | 低い | 中程度 |
| 用途 | 比較・アイデア出し | 議論・修正・調整 |
| 形式 | 非公式/雑案 | 文書形式化しやすい案 |
| 使用例 | 素案を複数比較する | 草案を基に修正を重ねる |
素案はアイデアの種まき、複数案を併存させて方向性を模索する段階。一方、草案はその中から形を整え始めた案で、関係者の意見を反映しながら肉付けしていく役割を担います。
草案と原案の比較
| 観点 | 草案 | 原案 |
|---|---|---|
| 段階 | 中間案 | 最終確認前 |
| 内容の確定度 | 中程度 | 高い(ほぼ固められた案) |
| 用途 | 改訂・議論・加筆 | 承認・採択を待つ |
| 修正量 | 比較的自由 | 修正は限定的 |
| 使用例 | 草案を関係者に回す | 原案を審議にかける |
草案はまだ大きな修正余地を残しますが、原案になると修正範囲は限定的になり、方向性がかなり確定したものとして扱われます。
素案と原案の使い方の違い
素案と原案は、両者は段階や目的がかなり離れていますが、対比すると次のようになります:
- 素案 → 原案へ昇華:まず素案段階で複数のアイデア・方向性を洗い出し、その中から絞り込み → 草案化 → 複数修正 → 最終的に原案とする流れ
- 使い分けの感覚:
・素案:まだ未定要素が多いため「仮案・検討案」的意味合い
・原案:承認前提で最終案を示す「これで進めよう」という意思表示
つまり、組織で企画を進める場合、序盤段階で「素案を検討する」、中盤で「草案を示して修正を重ねる」、終盤で「原案を提出して決裁を得る」というフェーズ分けが自然です。
試案・仮案との違い
試案とは?
「試案(しあん)」は、「まず試みとして出す案」「仮に作った案」という意味で使われます。試行錯誤段階の案、あるいは仮に作った案というニュアンスがあります。
特に「この方向で行けるかどうかを試す案」「アイデア実現可能性を確かめるための案」として使われることが多く、正式案になるか否かは未定です。
仮案とは?
「仮案(かりあん)」は、案としての形はあるが、確定ではない仮の案という意味です。暫定的・仮置き的な意味を強く帯びます。
たとえば「仮案を示した上で意見を募る」「仮案として公開する」といった使われ方をします。最終案ではないが、議論スタートの基点となる案です。
使い分けを整理
これらを含めて、段階感を整理すると次のようなイメージになります
素案 → 試案/仮案 → 草案 → 原案 → 最終案(成案など)
- 素案:構想・方向性の段階
- 試案/仮案:草案に近づけるための試作案
- 草案:実質的な案の初稿
- 原案:ほぼ最終化された案、承認待ち
- 最終案(成案など):確定した案
使い分けのポイントは、「確定度」「修正余地」「公開/審議前かどうか」の3点を意識することです。
草案の実例と使い方
草案の具体例文
- 来月の展示会案内文の 草案 を作成しましたので、ご確認ください。
- 規約改正の 草案 を一度共有しますので、フィードバックをお願いします。
- 契約書の 草案 を送付しました。修正箇所があればご連絡ください。
- 新商品発表用のプレゼン資料の 草案 を今日中に完成させておきます。
- 企画書の 草案 を基に、支店と意見交換をして内容を固めたいと思います。
契約書における草案の役割
契約書の世界では、草案はしばしば「たたき台」として相手とやり取りをする前段階として使われます。具体的には:
- 初期条件・条文案を草案として提示
- 相手側が修正・追加を提案
- 相互に交渉・調整を重ね、最終版へ近づける
- 修正履歴・コメント機能などで変更点を明示
- 最終的に双方合意を得て、正式な契約書化
草案段階で法務チェックやリスク検討を行うことが重要で、この段階を疎かにすると後で不利な条文が入るリスクもあります。また、自社側で草案を出すメリットは、初期提案権を持てること。すなわち、自社に有利な条文を初めから盛り込んで交渉を始められる点です。
文章作成における草案のメリット
文書・記事執筆・レポートなどで草案を使う際の利点を挙げます:
- 内容構成の見直しがしやすい
- 関係者(社内・チーム)で段階的に意見を反映できる
- 全体像を先に確認でき、抜け漏れを防止
- 心理的には「完璧でなくてよい案」を出すことで着手ハードルを下げる
- 複数案を比較しながら改善できる
特に、チームで文章を共同編集する際には、草案段階で方向性を合意しておくことで後の混乱を防ぎやすくなります。
草案・素案・原案の類義語や対義語
草案的言い換えと類語
草案の類義語・言い換え表現には以下のものがあります:
- 初案
- 下書き
- 仮案
- 試案
- ドラフト(英語 "draft" の和製語)
これらはいずれも「確定前の案」であるニュアンスを含みます。ただし、「初案」「仮案」は草案よりも未確定度が強い表現になることがあります。
草案に関する対義語
草案の対義語には主に以下のようなものがあります:
- 成案(せいあん):完成した案
- 最終案/確定案:最終決定された案
- 正式版/本案:公式化された案
たとえば、草案から修正を重ねて最終案が確定したら、「この草案を最終案として確定する」と表現できます。
よくある質問
Q1. 草案・素案・原案は絶対にこの順番で使わなければならない?
いいえ、必ずしもその通りでなく、プロセスや用途によって順序が前後したり、素案を省略して草案から入ることもあります。重要なのは「案の確定度」と「修正余地」の感覚をもって使い分けることです。
Q2. 「案」という語だけではダメか?なぜ草案・原案などを使う?
「案」だけではその案の性質(どの段階の案か)が伝わりにくいため、草案・原案などの修飾語を加えることで「未確定」「議論用」「承認待ち」といったニュアンスを明確にできます。
Q3. 英語ではどう表現すればいいか?
- 草案 → draft, rough draft
- 素案 → conceptual draft, preliminary draft
- 原案 → proposed draft, original proposal
英語でも “draft” を基本に修飾語を加える形式が多く、ニュアンスを加える言葉が後につきます。
まとめ「草案・素案・原案」の違い、意味、使い方
本稿では、草案・素案・原案という3つの語を、段階性・確定度・用途という観点から整理しました:
- 素案:まだ方向性を示す段階。複数案を比較検討
- 草案:具体的な構成を盛り込んだ初稿。修正しながら議論を進める
- 原案:承認・採択を待つ、かなり固まった案
さらに、「試案」「仮案」などの近似語の整理、草案を使った実例、類義語・対義語も含め、現場で使い分けられるよう深掘りました。
この知識を持っておくと、「この場面ではどの語を使えば適切か」「どの段階で案を出せばいいか」が明確になるため、文書作成・企画提案・契約交渉などあらゆるビジネスシーンで役立てられるでしょう。