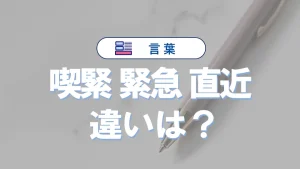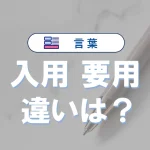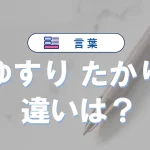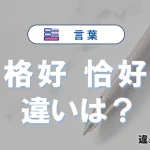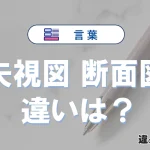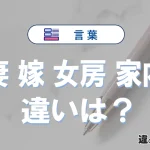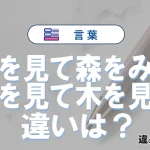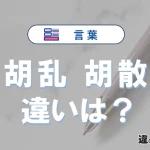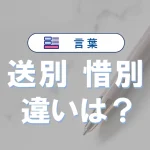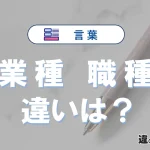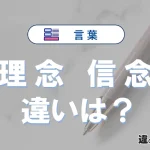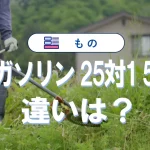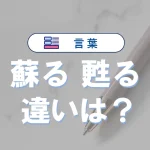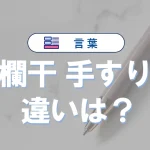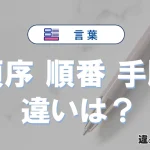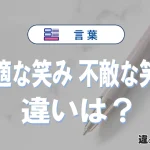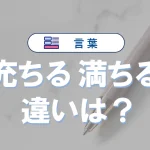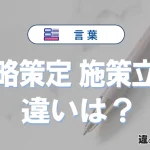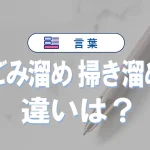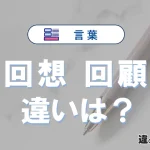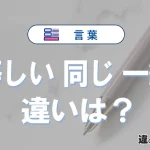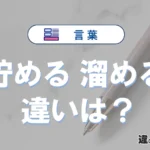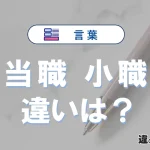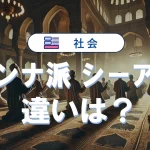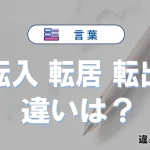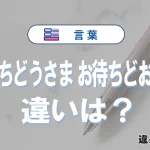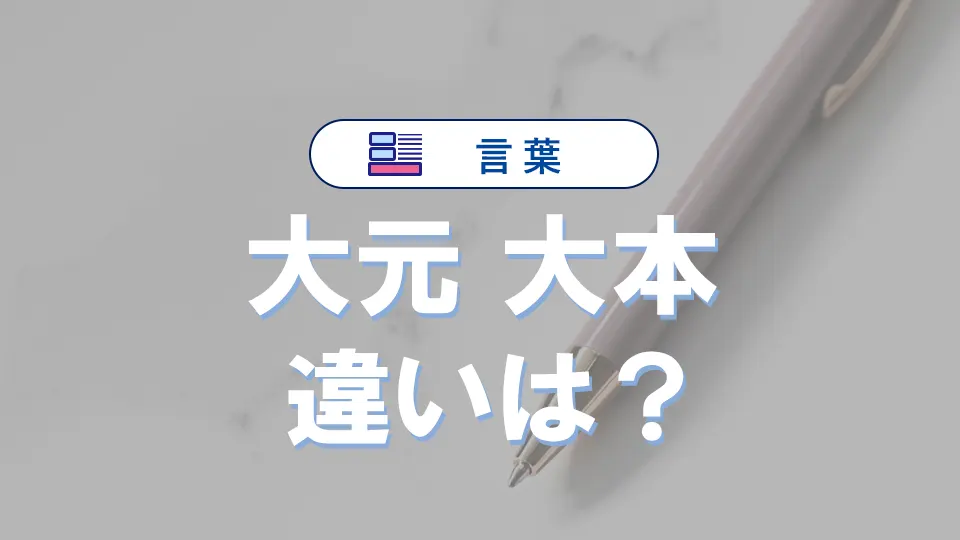
「大元」「大本」という言葉は、どちらも「おおもと」と読み、物事の根源や基礎を示す語として用いられます。しかし、実際には「大元/大本」の意味・語源・使い方・類義語・対義語・言い換えなどには微妙なニュアンスの違いがあります。「大元・大本 違い 意味 語源 類義語 対義語 言い換え 使い方 例文」というキーワードで探している方にとって、どちらを使えば適切か迷う場面も多いでしょう。本記事では、「大元」と「大本」を徹底的に比較・整理し、その意味や語源、類義語・対義語、言い換え、英語表現、そして具体的な使い方・例文を詳しくご紹介します。
この記事を読んでわかること
- 「大元」と「大本」の意味や語源の違い
- 両者の使い分けのコツと英語表現の違い
- 「大元」「大本」の類義語・対義語・言い換え表現
- 実際に使える例文と使い方・間違いやすいポイント
大元と大本の違い
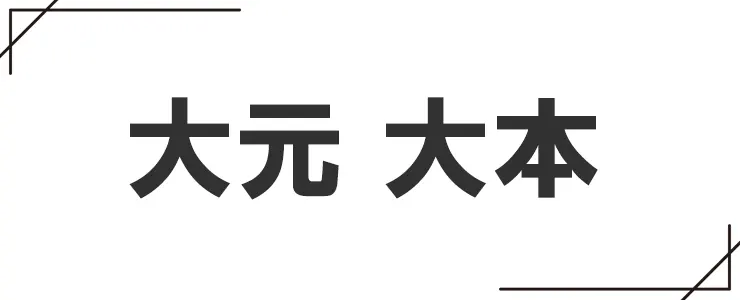
結論:大元と大本の意味の違い
まず、結論から申し上げると、「大元」は「物事の“始まり”や“出発点”・“起点”」を強く意識した表現、「大本」は「物事の“根幹”や“基盤”・“本質”」を意識した表現と言えます。
例えば、「このシステムの大元(=発端)を確認する」なら「大元」が適していて、「この制度の大本(=根本の仕組み)を理解する」なら「大本」が自然です。もちろん、両者が重なって使われる場面もありますが、ニュアンスとして「始まり」か「基盤か」がポイントになります。
大元と大本の使い分けの違い
使い分けの観点として、以下のポイントが挙げられます:
- 起点・発端か基盤・根幹か: 「大元」は「そもそも始まったところ」「原因・起点」に焦点。「大本」は「そこから展開される枠組み・土台」「核となるもの」に焦点。
- 使用頻度・語感: 実際には「大本」の方がやや汎用的・抽象的に使われる傾向があり、「大元」は「原因を掘る」「起こりを探る」場面で使うというブログ等の指摘があります。
- 文脈との相性: ・「トラブルの大元(=発生源)を突き止める」→大元
・「企業の成長には大本(=基盤・方針)がしっかりしていることが重要だ」→大本
ただし注意点として、辞典的には「大元」「大本」が完全に区別されず、同じ意味で使われるケースも多く、「厳密な違いはない」とする見解もあります。
大元と大本の英語表現の違い
英語で表現する場合、「大元」「大本」ともに “root”, “origin”, “basis”, “foundation”, “core” などが該当します。例えば、「大元に戻る」は “return to the root/origin”、「大本に立ち返る」は “go back to the foundation” のように訳せます。
しかし英語訳で使い分けるなら
- 大元 → “origin”, “source”, “starting point”
- 大本 → “foundation”, “basis”, “core principle”
このように分けて考えておくと、英語で同様のニュアンスを出しやすくなります。
大元の意味

大元とは何か?
「大元(おおもと)」とは、文字どおり「大(大きい)+元(もと・起こり)」という構造をもち、物事の起点や出発点、原因となるところ、あるいは根本となるものを指します。
国語辞典においても「物事の根本・起こりを示す」語であると説明されています。
大元はどんな時に使用する?
具体的には以下のような場面で使われます。
- 出来事やトラブルの出発点・原因を示す:例「その問題の大元を探る」
- アイデア・構想が生まれた最初の段階:例「この企画の大元となった発想は…」
- 物事が派生した根源・起源:例「この文化の大元は〇〇にある」
このように、「最初に起きた/発生した/始まった」という時間的・因果的な側面で使われることが多いです。
大元の語源は?
「大元」という語の構成を整理すると、「大」は「おおい・おおきい」「偉大な」という意味を含み、「元」は「もと」「起こり・原点」を意味します。つまり「大きなもと」「主要な起点」を意味する語義構造です。
古くから「物事が生じるところ」「根元」「起源」という意味で用いられてきたと考えられ、語彙的にも「元(もと)」を含む多くの語(例:「元来」「元凶」「元祖」)と同様の語源的背景があります。
大元の類義語と対義語は?
「大元」の類義語・対義語を整理すると、以下のようになります。
| 類義語 | 意味・例 |
|---|---|
| 根本 | 物事の根底。例:「根本原因」 |
| 原点 | 物事の出発点。例:「原点に戻る」 |
| 起源 | 物事が始まった源。例:「文化の起源」 |
| 起点 | 動きや展開の始まり。例:「出発の起点」 |
| 対義語 | 意味・例 |
|---|---|
| 末端 | 物事の終わり・先端。例:「組織の末端」 |
| 派生 | 元から派生したもの。例:「派生的な現象」 |
| 派生先 | 元から分かれ出た先。例:「派生先の課題」 |
また、「言い換え可能なフレーズ」としては、「根本的な起点」「発端」「源」「出発点」などがあります。
大本の意味
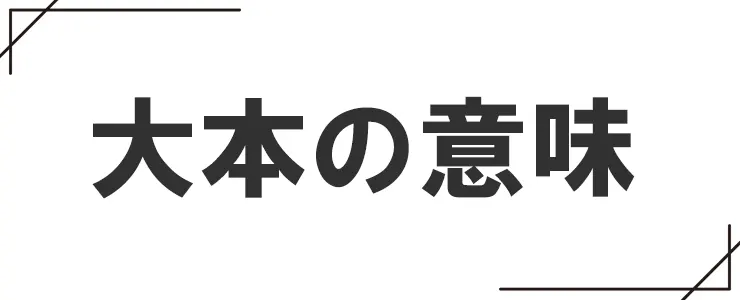
大本とは何か?
「大本(おおもと)」とは、「物事の最も基本となるもの」「根本・基盤・核心」を意味する語です。辞典でも、「物事の根本になるもの。根元・根源。」と記載があります。
語感としては、「大元」と同様に「おおもと」と読むことができますが、意味的には前述のとおり「起点」よりさらに「そこから続く仕組み・本体/基礎構造」に視点があると言えます。
大本はどんな時に使用する?
以下のような場面で使われることが多いです。
- 組織・制度・構造など、物事の根幹・基盤を示す:例「会社の成長には理念が大本だ」
- 物事の本質・方針・主軸を表す:例「理論の大本を理解する」
- 哲学・思想的な枠組み・土台を語る時:例「文明の大本に位置する価値観」
このように、「物事が成り立つ/維持されるための基盤=大本」というニュアンスで使われることが多いです。
大本の語源は?
「大本」は「大(大きい・重要な)+本(もと・根本)」という構造です。「本」は「根・もと」「主要な」「中心の」という意味を持ち、「大本」で「最も重要な根本」という意味合いが生まれます。
古典的には、「大本」という語は江戸時代に「大形の書籍(大本判の本)」を指す意味もあったようですが、現代語としては「根本・基盤」の意味で定着しています。
大本の類義語と対義語は?
「大本」の類義語・対義語を整理すると、以下の通りです。
| 類義語 | 意味・例 |
|---|---|
| 基盤 | 物事を支える基礎。例:「学問の基盤」 |
| 根幹 | 物事の中心・肝心な部分。例:「組織の根幹」 |
| 本質 | 物事の核心的な性質。例:「議論の本質を見る」 |
| 基礎 | 土台となる部分。例:「基礎知識を学ぶ」 |
| 対義語 | 意味・例 |
|---|---|
| 枝葉 | 本質から派生した細部・部分。例:「枝葉にこだわる」 |
| 表層 | 物事の表面的な部分。例:「表層的な理解」 |
| 末端 | 物事の末尾・末節。例:「組織の末端まで」 |
言い換え可能なフレーズとしては、「根本」「基盤」「土台」「核心」などが挙げられます。
大元の正しい使い方・例文
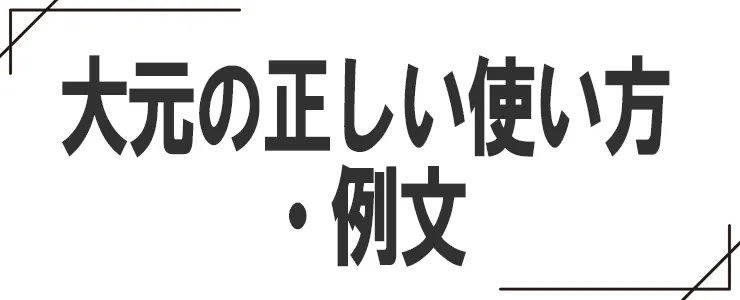
大元の例文
「大元」を使った例文を5つ挙げます
- 「トラブルの大元を突き止めたことで、対策が明確になった。」
- 「この企画の大元にあるアイデアは、学生の発想を活かすことだった。」
- 「文化の大元を探ることで、歴史的背景が見えてきた。」
- 「経営改善には、まず問題の大元を確認する必要がある。」
- 「その戦略の大元となった考え方は、シンプルで分かりやすかった。」
大元の言い換え可能なフレーズ
「大元」を言い換えられる表現として、以下があります
- 「根本的起点」
- 「発端」
- 「源(みなもと)」
- 「出発点」
- 「原点」
大元の正しい使い方のポイント
「大元」を正しく使うためのポイント
- 「何が一番最初にあったか/原因・起点は何か」という意識を持つ。
- 文脈として「出発」「始まり」「起点」「原因」などを伴う語と好相性。
- 「大元となっている」「大元から派生する」など、派生・展開という因果的な流れを示す。
- ただし、「大本」のように「基盤・根幹」の意味で使うと、語感として少しズレを感じることがあるため注意。
大元の間違いやすい表現
よくある誤用・注意点
- 「この制度の大元を見直す」という表現で「基盤・根幹」ではなく「起点・発端」であるべき場面→「大本」を使ったほうが自然な場合あり。
- 「大元に立ち返る」という文脈で「基盤に戻る」という意味合いなら、「大本に立ち返る」の方がニュアンス合致。
- 「大元がしっかりしている」という言い方で「基盤がしっかりしている」という意味を込めたいなら、「大本がしっかりしている」がより適切。
大本の正しい使い方・例文
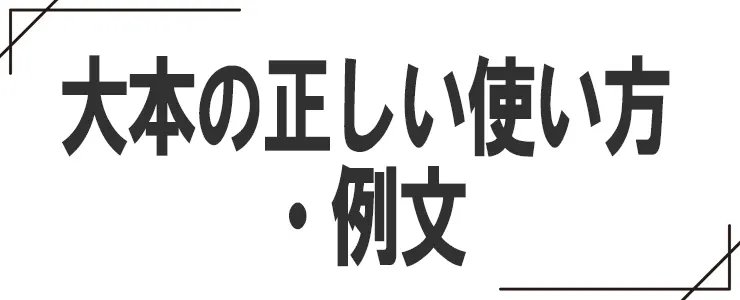
大本の例文
「大本」を使った例文を5つ挙げます
- 「組織運営の大本にあるのは、『人を尊重する』という理念だ。」
- 「この研究の大本となる仮説をしっかり整理しておこう。」
- 「社会の仕組みの大本を理解しなければ、変革は難しい。」
- 「企業の成功には、商品の質だけでなく販売体制が大本から整っている必要がある。」
- 「学問の大本に立ち返って、基礎を再確認した。」
大本の言い換え可能なフレーズ
「大本」を言い換えられる表現として、以下があります
- 「根本」
- 「基盤」
- 「土台」
- 「核心」
- 「本質」
大本の正しい使い方のポイント
「大本」を正しく使うためのポイント
- 「物事が成り立つ基礎・仕組み・構造・方針・理念」などに関して用いる。
- 「大本を押さえる」「大本を理解する」「大本から考える」などの表現が適切。
- 「基盤がしっかりしている」「根幹にある価値観」など、深層的・抽象的なニュアンスを持たせる。
- 「起点・発端」という時間的・因果的ニュアンスだけを表したい場合は、「大元」の方がふさわしい場合あり。
大本の間違いやすい表現
よくある誤用・注意点
- 「このテーマの大本を突き止める」という表現で「起点・原因を探る」という意味を込めたいなら、「大元」を使ったほうが語感的に適している。
- 「大本から派生した」という言い方で「起点から生じた」という意味を強くしたいなら、「大元から派生した」が自然。
- 「大本が動いた」という文脈で「発端・始まり」が動いたという意味なら、「大元が動いた」が語義的には合うが、実用的には「大本に動きがあった」のような「基盤の変化」を語る方が一般的。
まとめ:大元と大本の違いと意味・使い方の例文
以上まとめると、「大元」と「大本」はどちらも「おおもと」と読み、物事の根本・基礎を指す言葉です。しかし、用途・語感・ニュアンスには次のような違いがあります:
| 語句 | ニュアンス | 主な使いどころ |
|---|---|---|
| 大元 | 物事の始まり・出発点・原因など時間的・因果的ニュアンス | 「問題の大元を探る」「企画の大元となった発想」など |
| 大本 | 物事の基盤・根幹・土台など構造的・抽象的ニュアンス | 「制度の大本を理解する」「企業の大本となる理念」など |
ただし、実際には辞典等でも「大元」「大本」の違いを厳密には区別せず、「どちらも根本・起源を示す言葉」と解されているため、文脈や語感を意識して使い分けることが重要です。
使い方としては、先に「起点・発端」を示したいなら「大元」、次に「基盤・根幹」を示したいなら「大本」を軸に考えると、表現がより自然になります。また、英語訳を意識するなら「origin」「source」対「foundation」「basis」の使い分けを意識すると、英語の文章構成にも役立ちます。
最後に、例文や言い換え表現を参考に、文章や会話で「大元」「大本」を使い分けてみてください。語源や類義語・対義語を知ることで、使い方の幅も広がります。