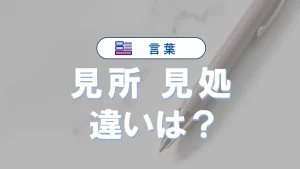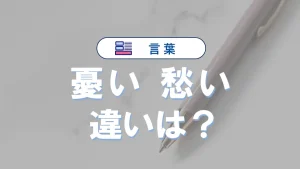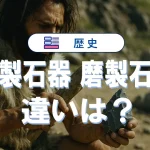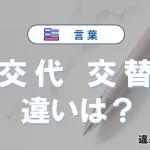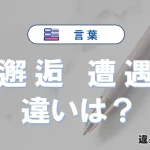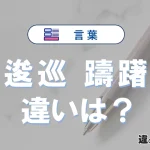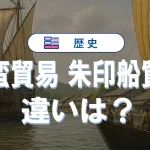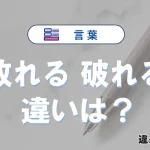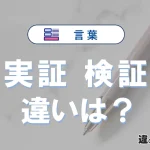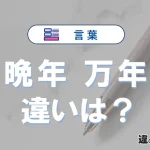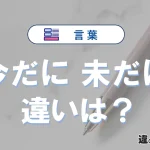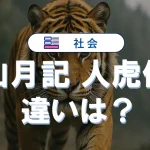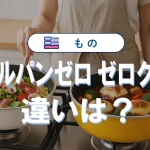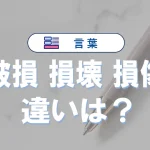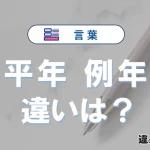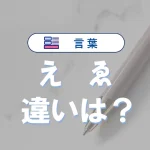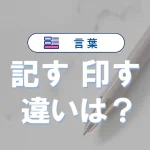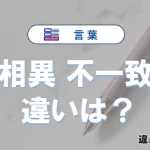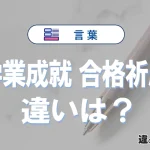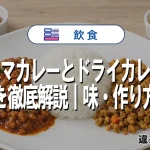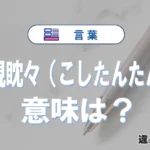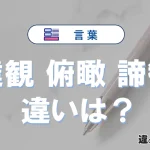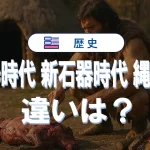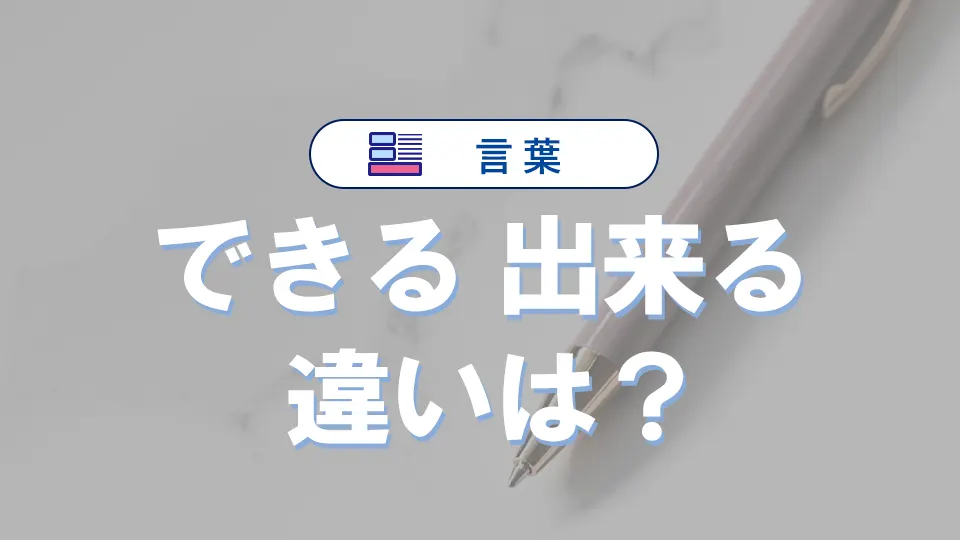
「できる」と「出来る」は、日本語を使う上で非常に頻出する言葉です。しかし、履歴書やビジネス文書などで「出来ます」「できます」のどちらを書くべきか迷う場面もあります。また、意味として「可能である」「能力がある」「完成・成立する」といったニュアンスが含まれるため、「できる」と「出来る」の記述・使い分けが重要になります。本記事では「できる」と「出来る」の違いや意味、語源、類義語・対義語、言い換え、使い方・例文までを丁寧に解説します。また、語源や類義語・対義語を知ることで、より正確に言葉を選ぶことができます。
この記事を読んでわかること
- 「できる」と「出来る」の意味と違い
- それぞれの語源・使い方・類義語・対義語
- 「できる」の正しい使い方と例文・言い換え・注意点
- 「出来る」の正しい使い方と例文・言い換え・注意点
できると出来るの違い
結論:できると出来るの意味の違い
まず結論として、「できる」と「出来る」の意味そのものには基本的に差はありません。「可能である」「能力がある」「完成・成立する」といった意味で用いられます。
しかし、「表記」と「文脈・品詞」によって適切な表記が異なります。
例えば、動詞用法の「〜ができる」「英語ができる」といった場合はひらがなで「できる」が推奨されます。
また、「出来事」「出来栄え」などの名詞的・複合語的な用法では「出来」が漢字で用いられることが一般的です。
ですので、意味では同一でも、書き方・表記のルール・ニュアンスによって「できる」か「出来る」かを選ぶ必要があります。
できると出来るの使い分けの違い
使い分けのポイントを整理しておきましょう。
| 場面/品詞 | 推奨表記 | 解説 |
|---|---|---|
| 動詞/副詞的用法(〜ができる/〜できます) | ひらがな「できる」 | 読みやすさ・公用文のルールから。 |
| 名詞用法(出来/“出来”+複合語) | 漢字「出来」/「出来る」も可 | 例:「出来事」「出来上がり」「上出来」など。 |
| 公式文書・履歴書・公文書など | ひらがな「できる」が無難 | 「記者ハンドブック」など公文書作成指針でもそのようにされています。 |
ちなみに、「出来る」をあえて使う文脈としては、格調を高めたい文体、小説的な表現、あるいは「出来上がる」「出来高」「出来栄え」のような既成の言い回しとして定着している表現などです。
つまり、日常的で読みやすくしたい文書では「できる」と書くのが基本で、漢字を使うのは意味の区別や文体の演出がある場合ということになります。
できると出来るの英語表現の違い
英語で「できる/出来る」のニュアンスを表すとき、文脈によって訳し分けが必要です。“can / be able to / possible / complete / be made”などが対応します。
例えば
- 「英語ができる」→ “can speak English” or “is able to speak English”
- 「橋ができる」→ “a bridge is completed / is built” or “a bridge is made”
- 「この仕事ができる」→ “able to do this job”
つまり、英語訳では日本語の「できる/出来る」の表記差はそのまま反映されず、意味・文脈に応じて訳語を選択することが重要です。
表記差があるからといって英語が変わるわけではありませんが、日本語での表記をきちんとすることで、日本語文の伝わりやすさも向上します。
できるの意味
できるとは?意味や定義
「できる」は、主として以下のような意味・定義を持っています。
辞書的には「〜する能力がある」「〜することが可能である」「〜が成立・完成する」などです。
- ある動作・行為を行う能力・力量がある:例「英語ができる」
- ある事柄・物事が可能・成立する:「一人でできる」「準備ができる」
- 何かが生じる・作られる・完成する:「家ができる」「作品ができた」)
このように「できる」は、動詞として多用途に使われる言葉です。
そして、現代の文書作成の指針として、動詞用法ではひらがなで「できる」と表記するのが一般的とされています。
できるはどんな時に使用する?
「できる」が使われる典型的なシチュエーションを挙げると次の通りです
- 自分や他者がある能力・スキルを持っていると表現したいとき:「彼女はピアノができる」
- ある仕事・作業・行為が可能であると伝えたいとき:「この機械で5分でできる」
- 何かが完成・成立・生じるとき:「駅前に新しい店ができる」
- 条件・可能性を表すとき:「時間があれば、明日でもできる」
このような場面で「できる」を使うことで、読み手に“その行為や可能性・成立”があるという情報を的確に伝えることができます。
できるの語源は?
「できる」の語源については、旧 日本語のカ変動詞「でく(出来)」や「出来る(でくる)」から派生したという説があります。
具体的には、「出来(でく)」が「出来る(でくる)」と連体形化・活用化し、さらに時代を経て「できる」という読み・表記に定着してきたという歴史があります。
この語源を知ることで、「出来る/できる」の漢字・ひらがなの使い分けが、単なる表記上の問題ではなく、言語の歴史的背景も含んでいることが理解できます。
できるの類義語と対義語は?
「できる」に近い意味を持つ語(類義語)と、逆の意味を持つ語(対義語)を整理します。
- 〈類義語〉可能だ、行える、〜ができる、〜が可能だ、達成できる
- 〈対義語〉できない、不可能だ、無理だ、不能だ
例えば、「彼は英語ができる」という文なら、言い換えとして「彼は英語を話すことが可能だ」「彼は英語を話す力がある」といった表現が可能です。
そして「彼は英語ができない」と書けば対義語の用法になります。
出来るの意味
出来るとは何か?
「出来る」は「できる」とほぼ同じ意味を持つ言葉ですが、表記(漢字/ひらがな)や品詞・文脈によって使い分けられます。
多くの場合、「出来る」は「出来(名詞)」「出来+上がる/出来合い」などの複合語として使われることが多いです。
つまり、「出来る」を単独で動詞として使うこともありますが、文章・文体・媒体の表記方針によってはひらがな「できる」が推奨されます。
出来るを使うシチュエーションは?
「出来る」を使う典型的な場面は次のとおりです
- 「出来事」「出来上がり」「上出来」といった名詞・複合語に含まれる場合:「素晴らしい出来だった」
- 古風・格調高い文体や、小説・文学作品・演説などで「出来る」をあえて漢字表記として使いたいとき
- 「〜が出来る/〜を出来る」といった書き言葉的な体裁を意識したいとき(ただし、動詞用法ではひらがな推奨)
ただし、一般的なビジネス文書・Web記事では「できる」と書く方が読みやすく、表記の迷いが少ないと言われています。
出来るの言葉の由来は?
「出来る」の由来は先述の「出来(でく)」+「る(動詞化)」という構造にあります。
「出来(でく)」自体は「成り立つ/生じる」という意味を持っており、「出来る(でくる)」を経て現代語の「出来る/できる」へと発展していきました。
この由来を踏まえると、「出来る」が漢字で書かれることがあるのは、「出来(成果・完成)」「出来上がる」といった“成立・生成”を強調する名詞的ニュアンスを含む場合に適している、という理解につながります。
出来るの類語・同義語や対義語
「出来る」に関しても、類語・対義語を整理してみます。
※意味的には「できる」と同じ語彙域です。
- 〈類語/同義語〉成し得る、可能だ、達成できる、実現できる
- 〈対義語〉遂げられない、達成できない、不可能だ、未完成だ
例えば、「成果が出来る(=できる)」という文なら「成果が成し得る」と言い換えられます。
一方で「成果が出来ない(=できない)」なら「成果が達成できない」「成果が未完成だ」といった表現が可能です。
できるの正しい使い方を詳しく
できるの例文5選
以下に「できる」を使った例文を5つ挙げます
- 私は英語を話すことができる。
- このソフトを使えば、5分で作業ができる。
- 彼女は何でも迅速にできる人だ。
- 新しいビルが来年完成して、すぐに利用ができるようになる。
- 時間さえあれば、もっと良い結果ができると思う。
できるの言い換え可能なフレーズ
「できる」を言い換えると、次のような表現が使えます
- 可能だ → 「参加が可能だ」
- 〜できる/〜できません → 「〜することが可能だ/〜することができない」
- 能力・技能がある → 「〜ができる力がある」「〜が得意だ」
- 成立・完成する → 「〜が成立する」「〜が完成する」
できるの正しい使い方のポイント
「できる」を使う際に押さえておきたいポイントは以下です
- 動詞として使う場合はひらがな「できる」が推奨される。
- 文書・Web記事・ビジネス文書では読みやすさを優先し、「できる」で統一する方が無難。
- 「〜できるだけ」「〜できる限り」といった定型表現もひらがな表記が一般的です。
- 言い換え例や文脈を考えて、「できる」が本当に適切か、「〜が可能だ」「〜が得意だ」など別の言い回しが良いか検討する。
できるの間違いやすい表現
「できる」を用いる際、特に注意したい言い回し・間違いやすい表現をいくつか挙げます
- 「彼は英語が出来るが数学はダメだ」→ この文では「出来る」でも意味は通じますが、文書・Web用途なら「できる」に統一する方が読みやすい。
- 「出来るだけ早くお願いします」→ 定型表現として「できるだけ早くお願いします」が推奨。表記の混在に注意。
- 「このソフトは誰でも出来る」→ 上記のような、動詞用法で漢字を使うと読みにくさ・違和感を生む可能性があります。
- 「作品の出来」が「作品のでき」としてひらがな書きされるケース→名詞用法・複合語用法では漢字「出来」が一般的。
出来るを正しく使うために
出来るの例文5選
「出来る」を使った例文を5つ挙げます
- この建物は来年完成して、すぐに利用が出来るようになります。
- そのプロジェクトは上手く進めば、好成績が出来るでしょう。(※この用法では「できる」でも可)
- 商品の出来が思ったより良かったので、販売を開始しました。(※“出来”は名詞)
- 長年の研究の末、遂に新方式が出来るに至った。(やや文語調)
- 出来るだけ早くお願いします。(定型句では、どちらの表記でも見られますが、古風に演出するなら"出来るだけ早くお願いします")
出来るを言い換えてみると
「出来る/出来」。「出来る」を言い換えると次のような表現が考えられます
- 〜が成立する/〜が完成する → 「それが成立した」「それが完成した」
- 〜を達成できる → 「〜を達成し得る」「〜を成し得る」
- 〜が可能だ → 「〜が可能だ」「〜が実現可能だ」
例えば「新制度が出来る」は「新制度が実現可能だ」や「新制度が成立する」と言い換えられます。
出来るを正しく使う方法
「出来る」を使う際に意識したいこと
- 文体・媒体(記事・ビジネス文書・文学作品)に応じて、漢字表記「出来る」が適切かを判断する。
- 名詞「出来」や複合語「出来事」「出来栄え」などの場合は漢字「出来」を用いると意味が明確になる。
- 動詞用法であっても、あえて漢字「出来る」を使いたいなら、文体的にその選択が読者にとって分かりやすいか検討する。多くの場合「できる」に統一する方が安全です。
- 文章全体で表記を統一することで、読みやすさ・信頼性ともに向上します。例えば、「できる」「出来る」が混在すると読みづらくなるため、どちらにするか最初に決めておくのが望ましいです。
出来るの間違った使い方
以下のような用法は、表記的に注意が必要です
- 「この仕事が出来る」→ 動詞用法なので「できる」の方が一般的。
- 「時間が出来ると…」→「時間ができる」というひらがな表記が読みやすい。
- 「作品のでき」→名詞的用法なら「作品の出来」が適切です。
- 「出来るだけ」を漢字・ひらがな混在で使う→文章内で一貫していないと違和感を与える。
まとめ:できると出来るの違いと意味・使い方の例文
本記事では、「できる」「出来る」の違い・意味・語源・類義語・対義語・言い換え・使い方・例文について、幅広く解説してきました。
以下、ポイントを改めて整理します
- 意味としては「できる」と「出来る」は同じく「可能である」「能力がある」「完成・成立する」などを含んでいます。
- 表記・使い分けのポイントとして、動詞・副詞用法ではひらがな「できる」が基本で、名詞・複合語・文体演出では漢字「出来」あるいは「出来る」が用いられます。
- 語源的には「出来(でく)」+動詞化「出来る(でくる)」という流れがあり、それが現在「できる/出来る」として残っています。
- 類義語として「可能だ」「行える」「能力がある」など、対義語として「できない」「不可能だ」「無理だ」などが挙げられます。
- 「できる」の正しい使い方では、文脈・媒体・読みやすさを考えてひらがな表記を優先し、例文・言い換え・ポイント・注意点を押さえることが重要です。
- 「出来る」を使う際には、名詞用法・複合語用法・文体的意図を確認して、漢字表記であるべきかどうかを判断すべきです。
どちらの表記を使うか迷ったときは、文章全体のトーン・目的・媒体を基準に、「できる」で統一するか、「出来る/出来」を意図して使うかを決めるとよいでしょう。表記が揃っていて読みやすい文章こそ、読者にとって親切です。
ぜひ、この解説を参考にして、「できる」「出来る」を正確に、そして効果的に使いこなしてみてください。