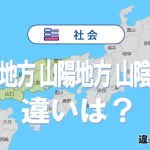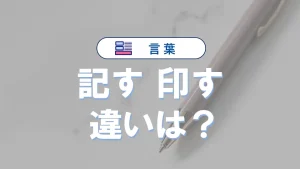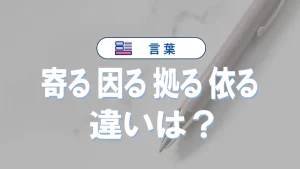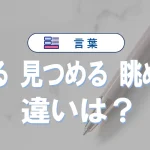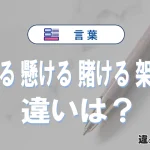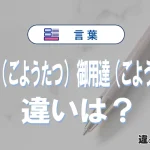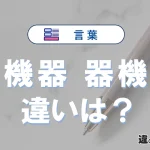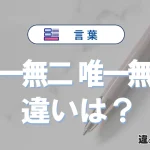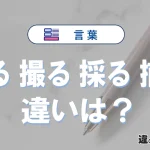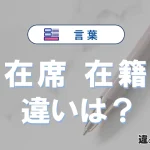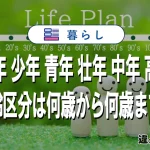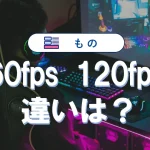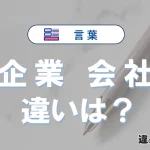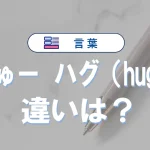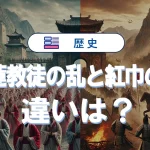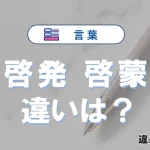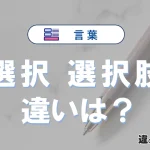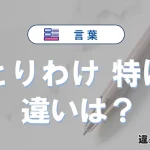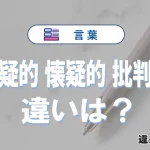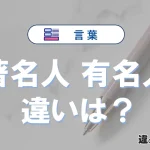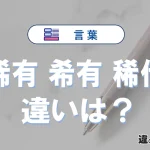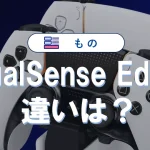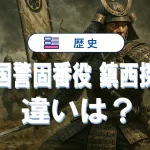「九州地方」「北九州」「南九州」は、よく耳にする地域名ですが、その区分や範囲、名称の意味・由来、さらに成り立ちの歴史や地域の特徴まで正確に説明できる人は多くありません。特に「北九州」と「南九州」の使い分けは文脈によって微妙に異なり、気象・行政・観光などの分野で定義がずれることがあります。本記事では、「九州地方」「北九州」「南九州」の区分範囲の違いや特徴を徹底解説します。
- 「九州地方」がどこを指すか(範囲・区分)と名称の由来・歴史的背景
- 「北九州」「南九州」の一般的な範囲・意味・由来・歴史・地域的特徴
- 北九州と南九州の地理・気候・経済産業の違い
- こうした区分がなぜ成立したのか、専門的に整理した背景
九州地方ってどこの地域?

九州地方とは(福岡・大分・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島)7県で構成
一般的な説明では、九州地方は本州の西方に位置する九州島を中心に、福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島の7県で構成されるとされます。学校地理や観光でもこの整理が広く使われます。ただし、機関によっては沖縄県を九州ブロックに含める分類もあり(国土地理院の都道府県一覧では「九州地方」に沖縄を掲示)、文脈で広狭があります。本稿では以降、便宜上「九州7県(沖縄を除く)」として論じます。
- 九州地方=7県が基本だが、分類の流儀により沖縄を含める場合もある
九州地方の名前の由来
「九州」の語は、古代の令制国における九つの国(筑前・筑後・豊前・豊後・肥前・肥後・日向・薩摩・大隅)に由来します。現在は7県ですが、歴史的呼称が地域名として残りました。観光公式サイトなどでも、名称由来が「旧国名の九国」にあることをわかりやすく解説しています。
- 九「九」は旧国名の数(九国)に由来し、現在の県数とは一致しない
九州地方の歴史
九州は古代から海上交通の要衝で、アジア大陸に最も近い位置関係を背景に、交易・外交・防衛・文化受容の前線として機能してきました。中世・近世を通じても、大宰府や港湾都市、火山・温泉・島嶼などの自然条件を土台に独自の文化・産業が発達します。明治維新期には薩摩や肥後などが近代国家形成に大きな役割を果たし、戦後は北部を中心に工業化・南部を中心に農畜産・観光などの地域的強みが強化されました。これらは後述の「北九州」「南九州」の分節にもつながります。
- 海の玄関口としての歴史が長く、近代以降は北部の工業・南部の農畜産で性格が分化
北九州を詳しく

北九州とは九州の北側(福岡・大分・佐賀・長崎・熊本)5県で構成
本記事では、実務・観光・メディアでよく見られる使い方に沿って、「北九州」=福岡・佐賀・長崎・熊本・大分の5県を指す通称として解説します。ただしこの語は行政上の正式区分ではありません。気象分野では気象庁が「九州北部地方(山口県を含む)」という実務的区分を用いており、福岡・佐賀・長崎・熊本・大分に山口県を加えた範囲で情報を発表します。つまり、用途によって範囲が変わりうる語である点に注意が必要です。
- 本稿の便宜定義:北九州=九州の北側5県
- 気象庁の実務区分では「九州北部地方(山口県を含む)」が用いられる
北九州の名前の由来
語源は素直に「九州の北側」という地理的説明で、南九州との対比語です。鉄道・観光商品・メディア原稿などでも「北九州エリア」「南九州エリア」といった便宜的呼称が広く用いられます。なお、北九州市(福岡県)という自治体名と北九州(地域)は別物なので混同に注意してください。
- 「北九州」は便宜的な広域呼称で、自治体名の「北九州市」とは別概念
北九州の歴史
北九州は古代から本州と九州を結ぶ海陸交通の結節点でした。近代化期には筑豊炭田・八幡製鉄所に象徴される重化学工業、港湾・鉄道網の整備が進み、工業・流通の拠点としての性格が濃くなります。現在も福岡都市圏・北九州都市圏・長崎・熊本・大分といった中核都市が連なり、九州経済の牽引役を担います。※地域史の骨格は教科書的記述、気象庁区分は前掲の一次情報に準拠。
- 古来の交通拠点性に、近代以降の重工業・流通が重なり「都市・工業」的性格が強い
北九州の特徴
地形は九州北岸の海岸線と内陸の盆地・平野が組み合わさり、都市化の進んだ地域が広がります。気候は日本海や対馬海峡の影響を受けつつも温暖で、冬季に寒気の影響が及ぶ場面もあります。産業は製造業・物流・サービスの比重が大きく、九州のゲートウェイとして航空・新幹線・高速道路・港湾が高密度に集積します。
- 都市化・交通結節・製造・流通の厚みが地域を特徴づける
南九州を詳しく

南九州とは九州の南側(宮崎・鹿児島)2県で構成
本記事では、「南九州」=宮崎県・鹿児島県の2県を指す用法を採用します。農林水産省の地域資料でも、南九州一帯の自然・産業特性が同質性を持つ地域として詳述されています。一方、気象庁の運用では「九州南部(宮崎・鹿児島の本土・種子島・屋久島)」と「奄美地方」を合わせて「九州南部・奄美地方」と表現するなど、ここでも実務上の区分が存在します。
- 本稿の便宜定義:南九州=宮崎+鹿児島
- 気象庁では「九州南部」と「奄美地方」を並記し、運用上区分する
南九州の名前の由来
語源は「九州の南側」という地理的説明です。観光・農政・物流などの分野で、宮崎・鹿児島をひとまとめに扱う実務上の便宜が高く、名称が定着してきました。
- 地理的方位に基づく便宜的広域名で、政策・観光でも頻用
南九州の歴史
古代の日向・薩摩・大隅に連なる地域で、海・火山・島嶼という自然条件と、薩摩藩を中心とする政治的・軍事的伝統が重なります。幕末~明治維新期には、薩摩の人材とネットワークが国家形成に大きく関与しました。以降、交通の近代化とともに農畜産・林業・水産・観光が発達して現在の産業構造の骨格が形づくられます。
- 日向・薩摩・大隅の歴史が下地、近代以降は農畜産・観光が基幹に
南九州の特徴
最大のキーワードは火山・温暖・多雨です。鹿児島県・宮崎県にはシラス(火山灰)台地が広く分布し、土壌・水文条件が農業や土地利用に独特の影響を与えます。気候は概して温暖で日照に恵まれる一方、台風・多雨の影響を強く受ける地域でもあります。農林水産省の地域解説は、シラス台地の分布、降水量や気温の傾向など、南九州の自然条件を具体的に示しています。
- シラス台地・温暖多雨・台風の影響—自然条件が産業と生活様式を規定
北九州と南九州の違い
地理的特徴の違い
北九州は本州に近接し、海峡・湾岸・平野が組み合わさった交通の結節性の高い地形が広がります。南九州は火山地形と台地・海岸線・島嶼が目立ち、内陸は起伏に富みます。こうした地形差が、都市の立地や産業集積の仕方に長期的な影響を与えてきました。
| 観点 | 北九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分) | 南九州(宮崎・鹿児島) |
|---|---|---|
| 地形 | 海峡・港湾・平野が点在、都市化が進む | 火山・台地・島嶼が卓越、起伏と海岸線が複雑 |
| 広域位置 | 本州(山口県)に近接し、陸海空の結節 | 九州南部~南東部、太平洋・東シナ海・離島が近い |
- 北は「結節・平野・港湾」、南は「火山・台地・島嶼」がキーワード
気候の違い
北九州は冬季に寒気や日本海側の影響を受けやすい一方で、南九州は年間を通じて温暖・多雨の傾向が強く、台風の通路にも当たりやすい地域です。気象庁の区分(九州北部地方/九州南部・奄美地方)も、運用上の気候特性の違いを反映したものです。
- 北=寒気影響が相対的に強い/南=温暖・多雨・台風リスク
経済産業の違い
北九州は製造業・流通・サービスに厚みがあり、九州のハブとして国内外からの人流・物流を集めます。南九州は農畜産・食品・観光の比重が高く、シラス台地や温暖な気候を生かした園芸・畜産が発達しています。両者は補完関係にあり、九州全体の多様性と強靭さを支えています。
- 北=都市・工業・流通中心/南=農畜産・食品・観光中心(相互補完)
よくある質問
「北九州」と「北九州市」は同じですか?
違います。北九州は広域の通称(本稿では九州北側5県の総称)で、北九州市は福岡県の政令指定都市(門司・小倉など旧5市が合併)です。文脈で判別しましょう。
「山陰地方」と「山陽地方」はどこ?九州とどう関係しますか?
両者は中国山地を境に分ける本州西部(中国地方)の地理区分です。一般に山陰は鳥取・島根(+山口北部を含める場合あり)、山陽は岡山・広島(+山口南部を含める場合あり)を指します。気象庁の予報区でも「山陰」「山陽」が使われます。九州とは別地方ですが、関門海峡で接する山口県南部(山陽側)は、気象業務上「九州北部地方」に含めて扱われることがあるため、実務では九州と密接に結びつきます。
まとめ:九州地方・北九州・南九州の違いや特徴
本稿では、九州地方の範囲・名称の由来・歴史的背景と、北九州・南九州の違い(地理・気候・産業)を、一次情報に基づいて整理しました。気象・観光・行政など用途に応じて区分が揺れうる点を押さえておけば、表現の精度は格段に上がります。併せて「山陰」「山陽」という中国地方の地理区分を理解しておくと、九州と本州西部の関係性(とくに山口県と九州北部の結びつき)が立体的に見えてきます。
- 九州=基本7県(文脈により沖縄を含む広義もあり)
- 北九州=便宜的に九州北側5県/南九州=宮崎・鹿児島が中心
- 自然条件:北は結節・都市、南は火山・温暖多雨・農畜産
- 山陰・山陽は中国地方の区分で、山口南部は実務上「九州北部地方」に含まれることがある