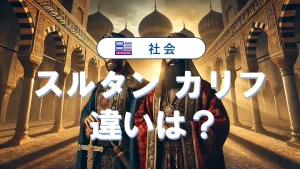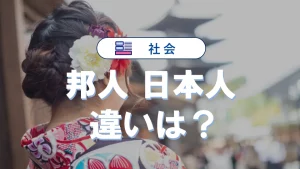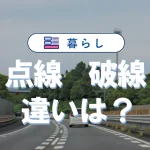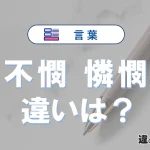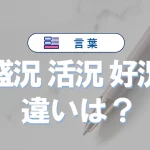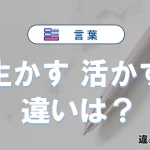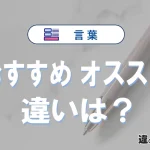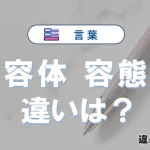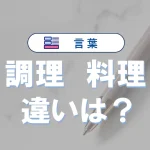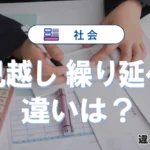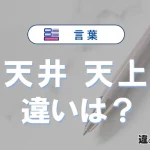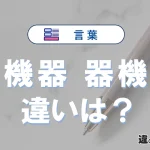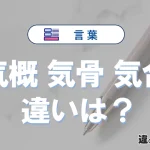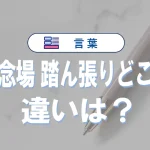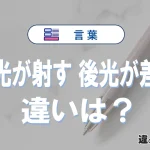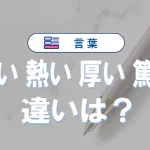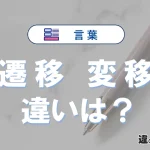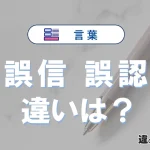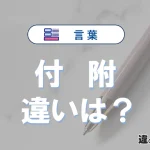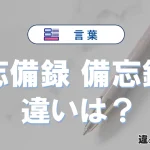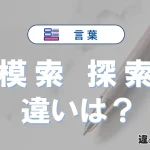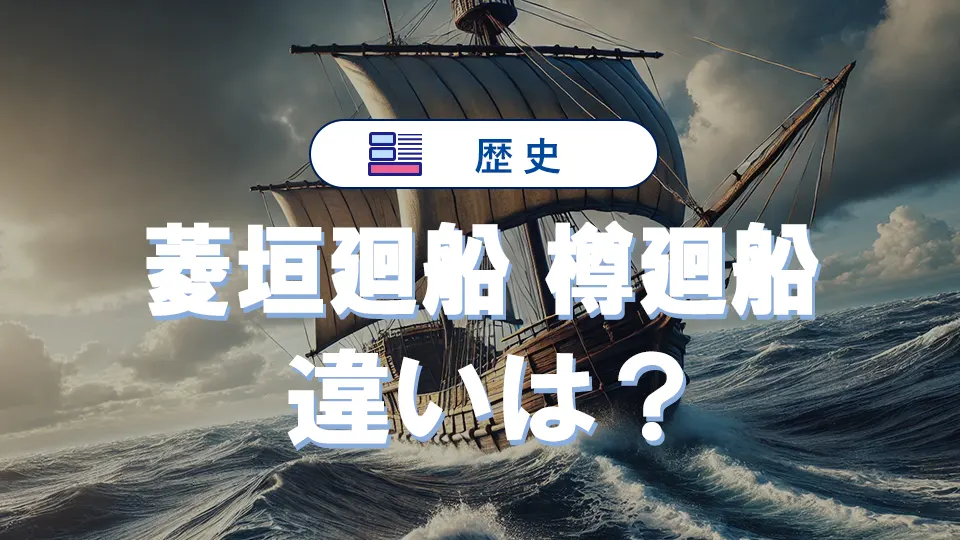
江戸時代に登場した「菱垣廻船(ひがきかいせん)」と「樽廻船(たるかいせん)」は、いずれも物流を支える重要な輸送船でした。しかし、構造や目的、運んだものに明確な違いがあります。検索で「菱垣廻船と樽廻船の違い」や「菱垣廻船とは」「樽廻船とは」といった言葉が使われることからも、多くの方が混同しやすいテーマであることがわかります。
また、「中学生でもわかるように説明してほしい」というニーズも見られます。さらに、「北前船」や「東廻り航路・西廻り航路との違い」といった関連知識も押さえておくことで、より深い理解につながります。
そこでこの記事では、菱垣廻船と樽廻船の違いは何か?をわかりやすく整理します。
結論としては、「運ぶ物の違い・構造の違い・スピードの違い」が主なポイントです。菱垣廻船は乾物などをゆっくり運ぶための船、樽廻船はお酒などをすばやく届けるための船として、それぞれの役割を果たしていたのです。
- 菱垣廻船と樽廻船の役割や運んだものの違い
- 船の構造や航行速度の違い
- 北前船との関係や航路の違い
- 江戸時代の物流と航海ルートの全体像
目次
菱垣廻船と樽廻船の違いをわかりやすく解説

菱垣廻船とは?
菱垣廻船(ひがきかいせん)は、江戸時代に活躍した大型の輸送船で、主に「江戸(現在の東京)」と「大坂(現在の大阪)」の間を結ぶ航路を行き来していました。
この船の最大の特徴は、船体の両側に木製の柵のような「菱形模様の垣(かき)」が設けられていたことです。この見た目から「菱垣」と名づけられました。見た目だけでなく、波よけや積荷の保護という実用的な役割もありました。
また、以下のような特徴があります。
- 主に「乾物」や「紙類」「布」「味噌」など、湿気に弱い荷物を運んだ
- 航行ルートは江戸と大阪を往復し「南海路」を利用していた
- 天候に左右されやすく、運行速度は樽廻船に比べて遅いこともあった
商人たちにとっては、経済活動を支える重要な輸送手段の一つでした。
樽廻船とは?

樽廻船(たるかいせん)は、江戸時代に発達した輸送用の帆船で、特に「酒の樽」を大量に運ぶ目的で活用されていました。名前のとおり、「樽=酒樽」をメインに輸送していたことが由来です。
この船の特徴は、船の構造が酒樽を効率よく積めるように設計されていた点にあります。波の影響を受けにくい形状や、安定性の高い構造になっており、スピード面でも優れていました。
主なポイントは以下のとおりです。
- 主に「日本酒」などの液体物を大量に運搬
- 航行ルートは江戸と大阪を往復し「南海路」を利用していた
- 菱垣廻船よりも速度が速く、定時性が高かった
- 商人からの信頼も厚く、運賃も安めに設定されていた
酒の消費が多かった江戸では、この樽廻船の存在が非常に重要でした。
菱垣廻船と樽廻船の読み方
それぞれの船の読み方は、少し難しい漢字が使われているため、読み間違いが多い言葉です。正しい読み方は次のとおりです。
| 船の名称 | 正しい読み方 |
|---|---|
| 菱垣廻船 | ひがきかいせん |
| 樽廻船 | たるかいせん |
「廻船(かいせん)」という言葉は、「回る船」と書きますが、「ぐるぐる回る」という意味ではありません。江戸時代においては、「定期的に往復する商用の船」を指しており、今でいうところの「定期貨物船」に近い存在でした。
菱垣廻船と樽廻船の違いを中学生向けにわかりやすく簡単に説明

中学生でもわかるように、菱垣廻船と樽廻船の違いを簡単にまとめます。
まず、どちらも江戸時代の船で、物を運ぶために使われていました。ただし、運んでいたものやスピード、船の作りに違いがあります。
- 菱垣廻船は、乾物や紙など「水に弱いもの」を運んでいた船。柵のような囲いが特徴です。
- 樽廻船は、「お酒の樽」を運ぶための船で、より早く、たくさん運べるように工夫されていました。
つまり、
- 運ぶもの → 菱垣:乾物など / 樽廻:酒
- スピード → 菱垣:遅め / 樽廻:速め
- 船の形 → 菱垣:囲いあり / 樽廻:安定性重視
このように、目的や作りの違いで、それぞれの船は役割を分けて活躍していたのです。
菱垣廻船と樽廻船の特徴を比較表にまとめると
以下に、両者の特徴を見やすく比較できる表を用意しました。
| 比較項目 | 菱垣廻船(ひがきかいせん) | 樽廻船(たるかいせん) |
|---|---|---|
| 主な輸送品 | 乾物・油・紙・布などの雑貨 | 主に日本酒、米・酢・醤油・砂糖 |
| 航行ルート | 南海路(江戸~大阪間往復) | 南海路(江戸~大阪間往復) |
| 船の構造 | 弁才船(大型木造帆走商船)を使用 船体に菱形の垣(囲い)あり | 弁才船(大型木造帆走商船)を使用 船庫が深く酒樽を積みやすい安定性重視 |
| 積載量 | 最大2000石 | 最大2000石 |
| 航行 | 年間最大8往復程度 | 年間最大10往復程度 |
| 速さ | 比較的遅い | 比較的速い |
| 運用開始時期 | 江戸時代(1619年運用開始) | 江戸時代(1730年運用開始) |
| 主な目的 | 庶民の生活物資の大量輸送 | 日本酒の鮮度維持輸送 |
このように、どちらも江戸時代の経済を支える大切な船でしたが、19世紀には菱垣廻船が解散となり樽廻船が主流となりました。
菱垣廻船と樽廻船の違いを他の船と比較

菱垣廻船と北前船の違いとは
菱垣廻船と北前船は、どちらも江戸時代に活躍した輸送船ですが、その運航ルートや役割には明確な違いがあります。
以下にその違いをまとめます。
| 比較項目 | 菱垣廻船 | 北前船 |
|---|---|---|
| 主な航路 | 大坂~江戸(南海路) | 蝦夷地(北海道)~大坂 |
| 主な目的 | 江戸と大坂間の物資輸送 | 全国各地との交易・物流 |
| 積み荷の種類 | 乾物、紙、布など | 海産物、昆布、干物、雑貨など |
| 船の所有者 | 大坂の船主が多い | 越前・北陸・関西などの商人が多い |
| 船の運用形態 | 比較的定期的な航行 | 季節ごとの長距離航海 |
菱垣廻船が大坂〜江戸間の「都市間定期便」として機能していたのに対し、北前船は北海道を含む広域を結ぶ「全国規模の交易船」として活躍していました。航路の距離や目的地の多様性から、北前船の方が広域な経済圏を築いていた点が特徴です。
菱垣廻船 樽廻船 北前船との関係
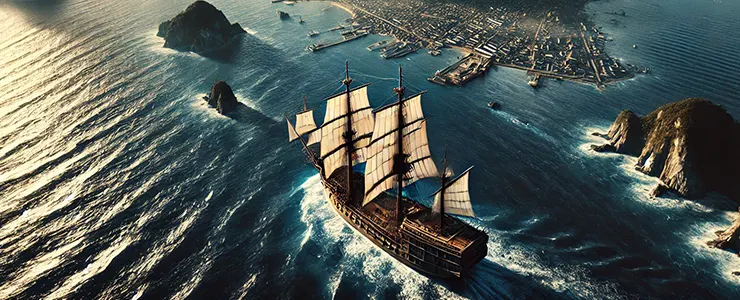
この3種の船はすべて江戸時代に登場した輸送船ですが、それぞれに異なる役割があり、互いを補完するような関係にありました。
具体的には次のようになります。
- 菱垣廻船:乾物や雑貨を江戸へ運ぶ船。主に定期的に江戸と大坂を往復。
- 樽廻船:酒樽を中心に運ぶ高速輸送船。効率重視で設計され、酒屋との取引が多かった。
- 北前船:蝦夷地(北海道)など遠方からの物資を西日本へ運ぶ広域交易船。航海距離が長い。
これらの船は、江戸という消費都市を支える物流網の一部として機能していました。特に北前船が北海道や東北の物産を西日本に運び、大坂で仕分け・再積載された荷が、菱垣廻船や樽廻船によって江戸に届けられるという流れが成立していたのです。
つまり、
- 北前船 → 地方から大坂へ
- 菱垣・樽廻船 → 大坂から江戸へ
このように、それぞれの役割と航路が異なることで、全国規模の物流ネットワークが実現していました。
東廻り航路と西廻り航路の違い
東廻り航路と西廻り航路は、江戸と大坂を結ぶ2つの主要な海上輸送ルートです。航路の選択は季節や天候、運搬する船の種類によって変わりました。
| 比較項目 | 南海路 | 東廻り航路 | 西廻り航路 |
|---|---|---|---|
| 主なルート | 大阪⇄江戸の往復 | 蝦夷地や東北の酒田→本州の東側を廻って→江戸 | 蝦夷地や東北の酒田→本州の西側を廻って→大坂 |
| 利用されやすい季節 | 通年 | 主に夏場 | 通年 |
| 航行距離 | 短め | 長め | 短め |
| 天候の影響 | 比較的安定 | 荒天に弱く運航困難な場合が多い | 比較的安定 |
| 運航 | 菱垣廻船、樽廻船 | 北前船 | 北前船 |
東廻り航路は、日本海側を通るため冬場の荒天に弱く、夏場に利用されることが多かったです。一方、西廻り航路は瀬戸内海を通るため波が穏やかで、安全性が高く安定した運航が可能でした。
そのため、次第に西廻り航路の利用が主流となっていきました。
菱垣廻船と樽廻船は何を運ぶための船か

菱垣廻船と樽廻船は、いずれも江戸時代の物流に欠かせない輸送船ですが、運んでいた物は異なります。以下に、代表的な積み荷を整理します。
■ 菱垣廻船の主な積み荷
- 乾物(昆布、干し椎茸、するめ等)
- 和紙や反物
- 漬物・味噌などの保存食品
- 雑貨類(鉄製品、木製品など)
■ 樽廻船の主な積み荷
- 酒(清酒が中心)
- 醤油や酢などの液体調味料(場合により)
- 木桶に詰めた食品(例:味噌、漬物)
特に樽廻船は、液体を安全に運べるように船体構造が工夫されており、酒造業との結びつきが強い船でした。江戸での日本酒消費量が増加するにつれ、樽廻船の重要性も高まりました。
菱垣廻船と樽廻船はどっちが早い?

運航スピードで比較すると、樽廻船の方が菱垣廻船よりも速かったとされています。
その理由には次のような要素があります。
- 船体の構造:樽廻船は樽を積載するため船倉が深く安定性とスピードを両立。菱垣廻船は荷物の保護重視で重め。
- 積み荷の特性:樽廻船の主な積荷である酒は、時間管理が求められる商品だったため、運送にも迅速性が求められた。
- 運航の仕組み:樽廻船は定期運航に加えて、商取引に合わせて臨時運行も行われた。
こうした点から、急ぎの荷物には樽廻船が好まれたのです。ただし、天候や海の状況によっては大きく左右されるため、必ずしも常に速かったとは言い切れません。
菱垣廻船と樽廻船の違い|Q&A
Q1. 樽廻船は別名何といいますか?
樽廻船は別名「酒廻船」とも呼ばれています。日本酒などの液体物を運ぶために使われた船で、その用途に由来します。
Q2. 菱垣廻船とはどういう意味ですか?
菱垣廻船は、船の側面に菱形模様の柵(垣)を備えていたことに由来する名前で、乾物や雑貨を運んだ輸送船です。
Q3. 江戸時代の3つの航路は?
江戸時代の3つの航路は「南海路」「東廻り航路」「西廻り航路」で、それぞれの海域に適した輸送が行われていました。
Q4. 蝦夷地の物産を運ぶ廻船は?
蝦夷地の物産を運ぶ廻船は北前船で、昆布や干物などの海産物を日本海経由で大坂に運び、各地に流通させていました。
Q5. 二十四組問屋とは?
二十四組問屋とは、大坂と江戸間の商品輸送を独占していた24の問屋仲間の総称で、物資ごとの流通や取引を管理していた商人組織です。
菱垣廻船と樽廻船の違いを整理|要点まとめ
- 菱垣廻船は乾物や雑貨など水に弱い品を運んでいた
- 樽廻船は主に日本酒を大量に運ぶために使われた
- 菱垣廻船の船体には菱形の垣があり積荷を保護していた
- 樽廻船は安定性を重視した構造で波の影響を受けにくい
- 菱垣廻船は速度が遅めで定期運航が中心だった
- 樽廻船は比較的高速で定時性に優れていた
- 両船とも南海路を通って江戸と大坂を往復していた
- 菱垣廻船の運用開始は1619年頃と早期から活躍していた
- 樽廻船は1730年頃に登場し次第に主流となっていった
- 菱垣廻船の構造は弁才船で大型の帆船だった
- 樽廻船も弁才船を使用しつつ、樽を効率よく積める設計だった
- 樽廻船は運賃が比較的安く商人に好まれていた
- 菱垣廻船は庶民の日用品輸送を担っていた
- 樽廻船は酒屋との結びつきが強く、江戸の酒需要を支えた
- 最終的に樽廻船が主流となり、菱垣廻船は衰退していった