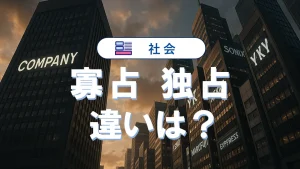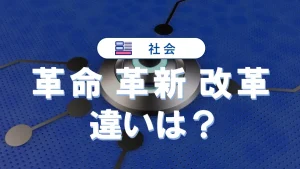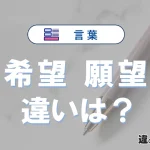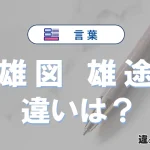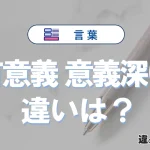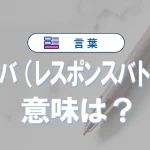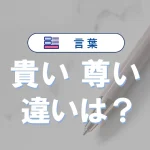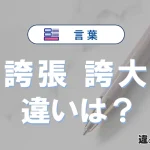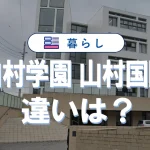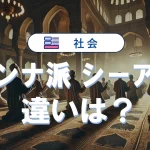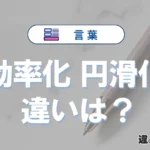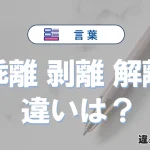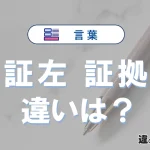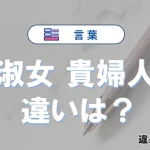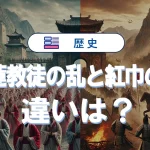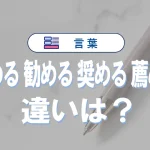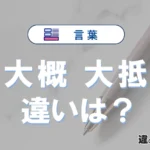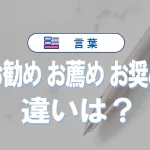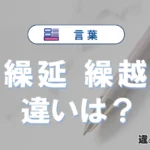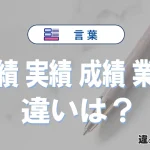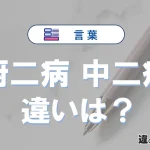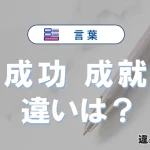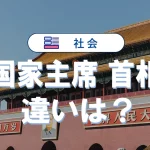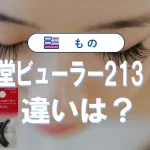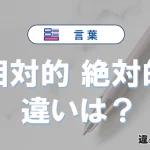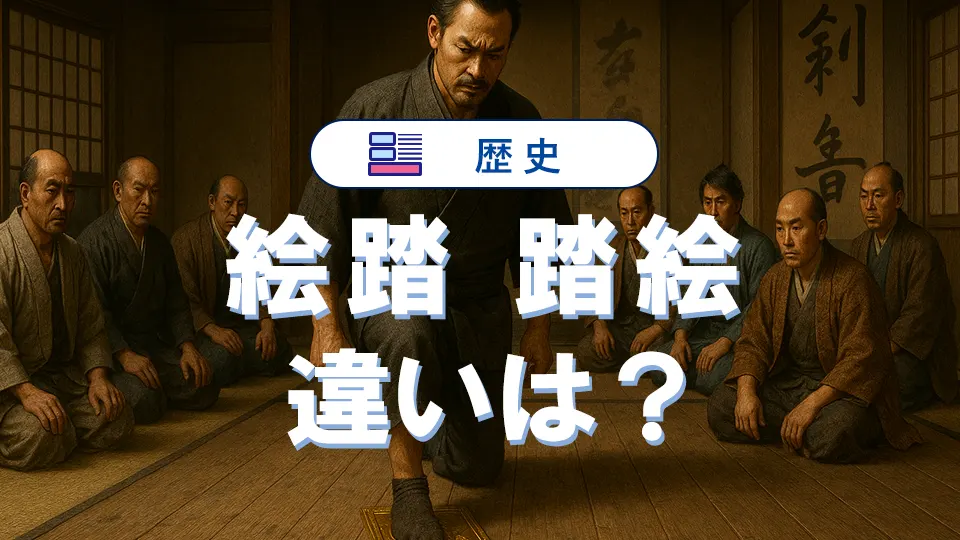
江戸時代の歴史に登場する「絵踏(えふみ)」と「踏み絵(ふみえ)」。似たような言葉ですが、実はまったく違う意味を持っています。「絵踏 踏絵 違い」と検索したあなたも、「どっちが踏む行為で、どっちが踏むモノなの?」と混乱していませんか?
この記事では、「踏み絵や絵踏みはいつから始まったのか」「踏み絵と絵踏みは教科書ではどう教えているのか」「絵踏みを踏まなかったらどうなるのか」など、気になる疑問を歴史と現代の両方から解説します。
結論として、「絵踏」とはキリスト教徒を見つけ出すために幕府が行った行為であり、「踏み絵」はそのときに使われた道具(キリストやマリアの像)を指します。つまり、絵踏が制度や方法、踏み絵が対象物なのです。
たとえば、「絵踏の目的」がキリスト教の信者を摘発することだったとすれば、その手段として使われたのが「踏み絵」であり、「絵踏みは誰が何のために行ったか」を知ることは、幕府の支配体制を読み解くヒントにもなります。
さらに「踏み絵を踏めなかった人はどうなったか」や「絵踏みに効果は本当にあったのか」「絵踏みはなぜ続けられたのか」など、教科書では知ることのできない背景にも迫っていきます。
- 絵踏と踏絵が指すものの違い
- 絵踏みの歴史的な始まりと背景
- 教科書での用語の使い分け
- 踏み絵を拒否した人の扱われ方
目次
絵踏と踏み絵(踏絵)の違いを歴史から解説

- 絵踏の目的とは何だったのか
- 絵踏みはいつから始まったのか
- 絵踏みは誰が何のために行ったのか
- キリスト教で踏み絵を使った理由とは
- 踏み絵(踏絵)と絵踏みの効果はあったのか
絵踏の目的とは何だったのか
絵踏の最大の目的は、「キリスト教の信者を見つけ出すこと」です。江戸幕府は、キリスト教を国の秩序を乱す恐れがある宗教と見なしていたため、厳しく取り締まる必要がありました。
なぜ踏ませるのか、と思うかもしれませんが、信者にとってキリストやマリアの像を踏むというのは、とても重い意味を持ちます。信仰を裏切る行為だからです。だからこそ、幕府はそれをあえて「信者かどうか見極めるテスト」として使ったわけです。
ただし、これは単なる宗教対策だけでは終わりません。江戸時代の後半になると、絵踏はすべての領民に対して行われるようになり、キリスト教だけでなく「住民管理」の一環としても使われるようになりました。
つまり、絵踏はもともとは宗教弾圧の手段でしたが、後には「幕府に逆らう考えを持っていないか確認するツール」に変化していったのです。
絵踏みはいつから始まったのか
絵踏みが始まったのは、1629年(寛永6年)です。この時代は徳川家光が将軍だったころで、ちょうどキリスト教への取り締まりが強まっていた時期と重なります。
それ以前からキリスト教に対して不信感はありましたが、この年に「踏ませる」という行為が正式に制度として導入されたことで、本格的な弾圧が始まりました。
当初は長崎を中心に行われ、キリスト教の信者が多かった九州地方で特に徹底されました。やがて九州以外の地域にも広がり、必要に応じて各地で絵踏みが行われるようになります。
ちなみに、絵踏みが廃止されたのは1858年(安政5年)です。これは日米修好通商条約が結ばれ、キリスト教に対する政策が見直されたことが関係しています。おおよそ230年もの長い期間、制度として続けられたことになります。
絵踏みは誰が何のために行ったのか
絵踏みを行ったのは、主に江戸幕府とそれに従う各藩の役人たちです。特にキリスト教徒の多かった長崎では、長崎奉行所が中心となって制度を管理していました。
この行為はただの検査ではなく、幕府にとっては「秩序を守る手段」でした。信者が増えすぎると、外国勢力とのつながりが強くなって、政治的に不安定になると考えられていたからです。
さらに、次のような背景もあります。
| 実施者 | 目的 | 補足情報 |
|---|---|---|
| 長崎奉行所 | 信者の摘発と住民管理 | 真鍮製の踏み絵を貸し出していた |
| 諸藩の役人 | 幕府の命令に従うため | 長崎以外でも実施例あり |
| 幕府中枢 | 国家統制・宗教政策 | キリシタンが政治的脅威になると懸念していた |
つまり、絵踏みは単なる宗教チェックではなく、国家権力が民衆を管理するための仕組みの一部だったのです。
キリスト教で踏み絵を使った理由とは
キリスト教の教義において、イエス・キリストや聖母マリアは非常に大切な存在です。そのため、その肖像を踏むという行為は、信仰そのものを否定するような意味合いを持ちます。
この「精神的な重み」を利用したのが踏み絵です。幕府は、絵を見ただけでは信者かどうかわかりませんが、「踏めるかどうか」で内面を暴こうとしたのです。
ただし、ここには複雑な問題もあります。キリスト教は本来、偶像崇拝を禁じています。つまり、像を神そのものとは見なしていないわけです。信仰心が強ければ、むしろ踏んでも問題ないという理屈も成り立ちます。
それでも実際には、多くの信者が苦しみ、踏むことを拒んで処罰されました。このように、教義と現実がうまくかみ合わなかった点も、踏み絵が議論を呼ぶ理由の一つです。
踏み絵(踏絵)と絵踏みの効果はあったのか
最初のころは、絵踏みはある程度効果がありました。実際に、それを拒んだ人が信者として摘発されるケースも多くありましたから。
ただし、時間がたつにつれて、効果は薄れていきます。なぜなら、信者たちが「心の中で信じていればいい」と割り切るようになったからです。つまり、表面上は踏んで見せて、内心では信仰を続ける「隠れキリシタン」が増えていったのです。
こうして、絵踏みは次第に形だけの儀式のようになり、「信仰を試す方法」としての意味は失われていきました。
一方で、幕府にとっては効果がなくても「秩序を守るアピール」にもなったため、制度として長く残ったとも言えます。だからこそ、実質的な成果が少なくなっても、幕末まで絵踏みは続いたのです。
いずれにしても、踏み絵の効果には限界があったというのが実情です。信仰心は、形だけでは測れないということかもしれません。
絵踏と踏み絵(踏絵)の違いを教科書で見る

- 踏み絵(踏絵)と絵踏みは教科書でどう書かれる?
- 踏み絵(踏絵)と絵踏みの違いはいつから混同?
- 踏み絵(踏絵)を踏めなかったらどうなった?
- 絵踏みがなぜ続けられたのか
- 現代で見る絵踏と踏み絵(踏絵)の違いの意味
踏み絵(踏絵)と絵踏みは教科書でどう書かれる?
現在の教科書では、「踏み絵」と「絵踏み」は明確に区別されています。昔の教科書では、絵を踏む行為も「踏み絵」と呼んでいましたが、近年では歴史的な用語の正確さを重視して、言葉の使い分けが見直されました。
実際、小中学校の社会科教科書では次のように記述されています。
| 用語 | 意味 | 教科書での扱い |
|---|---|---|
| 踏み絵(ふみえ) | 踏ませるためのキリストやマリアの像 | 物体としての名称 |
| 絵踏み(えぶみ・えふみ) | それを踏ませる行為 | 行為・制度としての表現 |
つまり、「踏む行為」が「絵踏み」、「使われる物」が「踏み絵」というのが今の基準です。
この変更によって、大人世代が覚えていた「踏み絵」という言葉は、今の子どもたちにとっては“部分的にしか正しくない”ものになります。教科書を読んでいて「違う表現だ」と感じたら、それは用語の整理が進んだからだと考えてよいでしょう。
踏み絵(踏絵)と絵踏みの違いはいつから混同?
もともと「踏み絵」と「絵踏み」は別々の意味を持っていましたが、この区別が曖昧になっていったのは江戸時代後期からだと考えられています。
長く続く中で、庶民のあいだでは「踏む=踏み絵をやること」と理解され、「踏み絵」が行為を指す言葉として使われるようになっていきました。記録を見ても、後年になるにつれて両方の言葉が混ざって使われる傾向が見られます。
そして、明治以降になると「絵踏み」という語自体があまり使われなくなり、「踏み絵」という言葉だけが一人歩きするようになります。その流れを受けて、戦後の教育現場では混同されたまま「踏み絵=踏む行為」として扱われていました。
教科書で区別されるようになったのは、2000年代に入ってから。言葉の意味をより正確に伝える必要があると判断された結果です。だから、大人が子どもに「絵踏みって何?」と聞かれて戸惑うのは、ある意味当然とも言えます。
踏み絵(踏絵)を踏めなかったらどうなった?
もし踏み絵を拒否したら、江戸時代では「キリシタン」として処罰の対象になりました。信仰を理由に踏まない=キリスト教徒であると見なされたからです。
処罰の内容は時期や地域によって異なりますが、以下のような段階を踏んで行われることが多かったとされています。
| 行動 | 想定される結果 |
|---|---|
| 踏み絵を拒否 | キリシタンと認定される |
| 言い訳や弁解 | 拷問による取り調べ |
| 改宗の意思を示さない | 投獄または死刑 |
特に踏めなかった人に対しては、「棄教するか、処刑されるか」の選択を迫るケースが目立ちます。また、踏んだ場合でも「気持ちがこもっていない」と言われ、さらに疑われることもありました。
ただし、幕府側としても「できるだけ棄教させたい」という方針だったため、実際には多くの人が拷問や説得の末に改宗を選びました。それでも信仰を貫いた人々がいたからこそ、歴史の中に「隠れキリシタン」の存在が残っているのです。
絵踏みがなぜ続けられたのか
絵踏みは、単にキリスト教徒を見つけるだけの行為ではありませんでした。次第に「政治的な意味」や「社会的な儀式」としての側面が強まっていきます。
江戸時代の中期以降、表立ってキリシタンを信仰している人はほとんど見られなくなりました。それでも絵踏みは年中行事のように続けられ、特に長崎では正月行事の一つになっていたほどです。
では、なぜそのような状態でもやめなかったのでしょうか?
それは、絵踏みによって「幕府の統治が行き届いている」ということを可視化できたからです。言い換えると、踏ませること自体に支配の証明としての意味があったのです。
いわば、絵踏みは「宗教弾圧の道具」から「体制維持の象徴」へと変化していったと言えるでしょう。そこに信者がいるかどうかは、もはや本質ではなかったのかもしれません。
現代で見る絵踏と踏み絵(踏絵)の違いの意味
現代では「絵踏」と「踏み絵」の違いを知ることは、単に歴史用語を正しく使う以上の意味を持ちます。それは、私たちが言葉の背景にある価値観や時代の空気をどう捉えるか、という問題にもつながるからです。
たとえば、「踏み絵」は今では比喩表現としても使われています。あるグループや組織の中で、「本当に味方なのかを試す場面」のことを踏み絵にたとえることがあります。政治の世界や企業の人事でも、こうした試される瞬間は意外と身近です。
その中で、絵踏という制度がどう使われ、どんな心理的圧力を与えたのかを知ることは、今の社会でも大切な学びになります。
また、現存する踏絵の実物を見れば、当時の信仰や文化の緊張関係がよく伝わってきます。東京国立博物館などに保存されているこれらの資料は、単なる美術品ではなく、歴史を物語る証拠でもあります。
このように考えると、「言葉の違い」を意識することが、歴史への理解を深める第一歩になるのではないでしょうか。
絵踏と踏み絵(踏絵)の違いをわかりやすく|要点まとめ
- 絵踏はキリスト教徒を発見するための踏ませる行為
- 踏み絵(踏絵)は絵踏で使用されたキリストやマリアの像や板などの物
- 絵踏は1629年に制度として正式に始まった
- 踏み絵(踏絵)を踏めない者はキリスト教徒と見なされ処罰された
- 幕府や奉行所、藩の役人が主導して絵踏を実施した
- 踏み絵(踏絵)を使うことは信者に信仰の放棄を強要する手段だった
- 本来キリスト教では偶像崇拝が禁じられていた
- 初期の絵踏には一定の摘発効果があった
- 絵踏は次第に形骸化し、信仰心の判別手段としての効果は薄れた
- 長崎では絵踏が正月行事として年中行事化された
- 教科書では現在「絵踏=行為」「踏絵=道具」と明確に区別される
- 江戸後期から明治にかけて絵踏と踏み絵(踏絵)の語が混同され始めた
- 拒否した者は拷問や処刑の対象になりうる厳しい制度だった
- 幕府にとって絵踏は民衆支配の象徴としても機能していた
- 現代では比喩的に「踏み絵」が忠誠や立場を試す行為として使われている