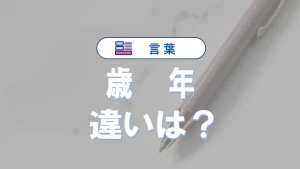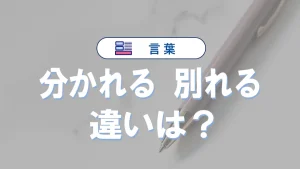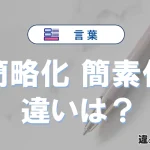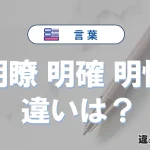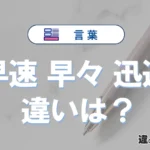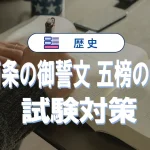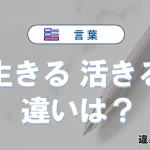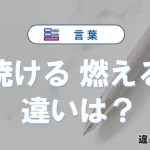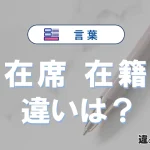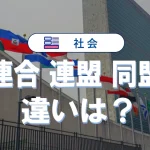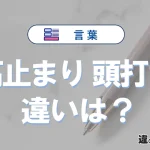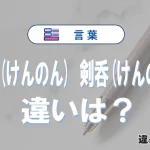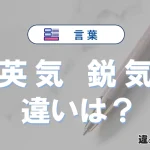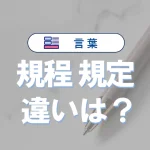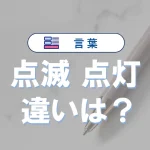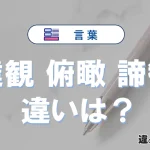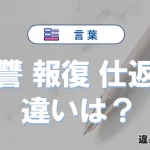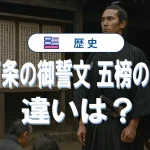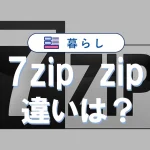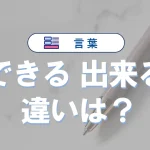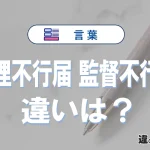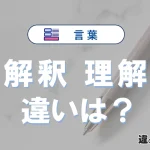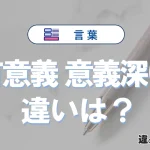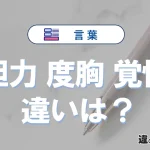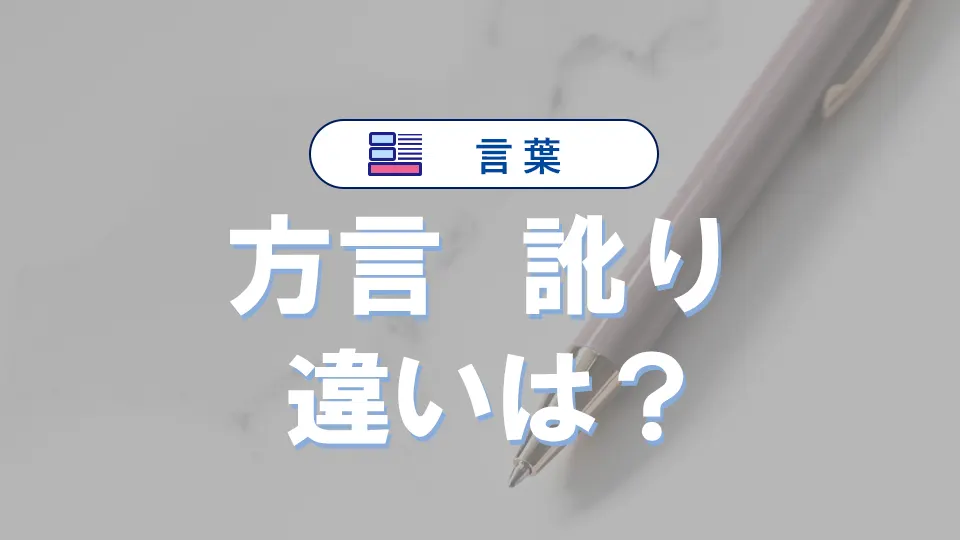
日本語を学ぶうえでしばしば混同されやすいのが「方言」と「訛り」です。日常会話の中でも「この人は方言が強いね」「訛りが残っているね」といった表現を耳にすることがありますが、両者の意味は微妙に異なります。本記事では、言語学的な観点と具体的な事例を踏まえながら、方言と訛りの違いを徹底的に解説していきます。
目次
方言と訛りの違い:基本概念
方言とは?その定義と意味
方言とは、ある地域や社会集団で用いられる独自の言語変種を指します。これは単に発音だけでなく、語彙、文法、表現の仕方にまで及びます。例えば「自転車」を東京では「じてんしゃ」と呼ぶのに対し、鹿児島では「けっちゃ」と呼ぶ場合があります。このように、同じ意味を持つ言葉であっても、地域によって全く異なる表現が存在するのが方言の特徴です。言語学の分野では、方言は「地域方言」「社会方言」などに分類され、研究対象として重要な位置を占めています(参考:国立国語研究所)。
訛りとは?違いと特徴の解説
訛りは、主に発音やイントネーションに関する差異を表す用語です。語彙や文法は標準語とほぼ同じでも、イントネーションの上がり下がりや母音の発音に違いが生じると「訛りがある」と感じられます。例えば、東北地方では「雨」という語を「ア↑メ」と高く発音することが多い一方、東京では「アメ↓」と低く始まります。この微妙な違いが、聞き手に地域性を感じさせる大きな要素となります。
方言と訛りの違いを理解する
両者の違いを整理すると、方言は語彙や文法、発音などを含む総合的な言語体系の変種であり、訛りはその中でも特に「音声的特徴」に焦点を当てた概念といえます。つまり、訛りは方言の一部として存在すると考えるのが正確です。
| 項目 | 方言 | 訛り |
|---|---|---|
| 対象 | 語彙・文法・発音を含む | 主に発音・イントネーション |
| 例 | 「自転車」→「けっちゃ」(鹿児島) | 「雨」のイントネーションが東北と東京で異なる |
| 言語学的分類 | 地域方言・社会方言など | 音声学的特徴の一部 |
方言の種類一覧(47都道府県)
日本の方言は大きく「東日本方言」「西日本方言」「九州方言」「北海道方言」などに区分されます。その内部でもさらに細かく分かれており、47都道府県それぞれに独自の表現があります。例えば青森の津軽弁は「わいは(私は)」のように強烈な特徴を持ち、沖縄では「ハイサイ(こんにちは)」など、標準語から大きく異なる独自の言語体系が存在します。これらは単なる言葉の違いを超え、地域の文化や歴史と深く結びついています。
日本の方言と訛りの違い:具体例
関西弁の特徴と魅力
関西弁は、独特のリズムと語尾のイントネーションが特徴です。「なんでやねん」といったツッコミ表現は全国的に知られており、漫才やコメディ文化と強く結びついています。また「めっちゃ」「ほんま」など、感情を強調する語彙が多いのも特徴です。言語学的には「アクセント核」が東京式と異なり、関西弁は高低アクセントが逆転する傾向があります(参考:国立国語研究所 方言研究)。
北海道弁とその文化的背景
北海道弁は、比較的新しい地域に形成された方言です。明治期の開拓によって本州各地からの移住者が集まり、その影響を受けながら独自の言葉が生まれました。「なまら(とても)」「したっけ(それじゃあ)」はその代表例です。北海道弁には東北方言の影響が強く残っており、柔らかく親しみやすい響きを持つのが特徴です。
関東弁の特徴と訛りについて
関東地方は標準語の基盤となった地域ですが、内部には多様な言葉があります。江戸っ子気質を反映した「べらんめえ口調」や、茨城弁の「〜だっぺ」など、微妙な言語差があります。訛りに関しては、東京弁の抑揚が全国標準となったため意識されにくいですが、他地域の人からすれば関東弁にも特有のイントネーションが存在します。
地域ごとの訛りの違いを探る
東北の柔らかくゆったりしたイントネーション、関西のテンポの速いリズム、九州の低音で力強い語調など、日本各地には多様な訛りが存在します。これらは人間のコミュニケーションを豊かにし、地域の個性を形成する重要な要素となっています。
方言と訛りの言語的意味と違い
方言と標準語の関係
標準語は、明治時代に教育と行政のために東京方言を基盤に定められた「共通語」です。一方、方言はその地域で自然に使われてきた言葉です。したがって、標準語と方言は対立するものではなく、状況によって使い分けられる補完的な存在です。
訛りとアクセントの違い
アクセントは、音の高低や強弱を示す言語現象です。訛りは、その地域特有のアクセント傾向や発音の癖を含む、より広い意味合いを持ちます。つまり「アクセント」は音声学的な要素の一部であり、「訛り」はそれを含む包括的な概念と言えます。
言語としての方言の役割
方言は単なる言葉の違いではなく、地域の歴史や文化を反映する「文化資産」です。例えば、漁業が盛んな地域では海に関する語彙が豊富であり、農村地域では農業に関連する方言が多く存在します。これらは地域社会の営みと切り離すことができません。
世界の方言と訛りの違いを比較
アメリカ英語 vs イギリス英語
英語における方言と訛りの違いも、日本語と比較するうえで興味深い事例です。アメリカ英語とイギリス英語は、語彙の違い(例:アメリカ「elevator」 vs イギリス「lift」)や発音の違い(例:「schedule」の発音)などが顕著です。お互いに理解可能ではありますが、文化的背景が異なるため、しばしば相互に「訛っている」と感じられることがあります(参考:Cambridge University Press)。
他言語における方言の存在
中国語は「方言多様性」の代表例で、北京語、広東語、上海語などは語彙・発音が大きく異なり、相互理解が困難な場合もあります。ドイツ語やスペイン語も地域によって語彙や発音に違いがあり、国境を越えても共通語と方言が共存しています。
日本語に見る方言の面白い事例
例えば「ありがとう」という言葉は、沖縄では「にふぇーでーびる」、鹿児島では「ありがとさげもした」と表現されます。同じ日本語でも、地域によってここまで大きな違いがあるのは興味深い現象です。
方言と訛りの違いと影響
文化としての方言と訛りの重要性
方言や訛りは単なるコミュニケーション手段ではなく、その地域の文化や歴史を象徴する存在です。例えば、祭りの掛け声や民謡には独自の言葉やリズムが込められています。
方言がもたらすアイデンティティ
人々が自分の故郷を思い出すとき、その土地の方言は強いアイデンティティを喚起します。方言は「郷土愛」を育むと同時に、地域間の交流を豊かにする要素となります。
方言教育の必要性と活用
学校や地域社会で方言を積極的に学ぶ試みも増えています。これは単なる言葉の保存ではなく、地域文化を後世に伝えるための重要な取り組みです。
方言と訛りの違いを学ぶためのリソース
オンライン英会話と方言教育
オンライン英会話ではアメリカ英語やイギリス英語など、異なる方言を学ぶ機会があります。同じように日本語の方言教材も存在し、全国各地の表現を体験できます。
参考になる方言アプリとサイト
方言をまとめた辞書アプリや、地域別の方言マップを提供するサイトが多数あります。動画コンテンツや音声教材も、リアルなイントネーションを理解するのに役立ちます。
方言を学ぶための無料教材の紹介
自治体が公開している方言辞典や、大学が研究成果をオープンアクセスで提供しているケースもあります。YouTubeなどで公開されている地域別会話動画も実践的な教材として役立ちます。
方言・訛りに関するよくある質問(FAQ)
方言と訛りの違いは何か?
方言は言語体系全体に及ぶ地域変種であり、訛りはその中でも音声的な特徴に焦点を当てたものです。
方言を学ぶ方法は?
地域の人との会話、専門書やアプリ、音声教材の活用が効果的です。
訛りを改善するためには?
朗読練習や発音矯正トレーニングが有効ですが、無理に直す必要はなく、個性や文化として尊重する姿勢も大切です。
結論:方言と訛りの違いをまとめると
方言と訛りの理解がもたらす価値
両者を理解することは、日本語の多様性を知るうえで不可欠であり、地域文化の深い理解へとつながります。
方言を尊重し、楽しむことの重要性
異なる言葉の響きを楽しむ姿勢が、人と人との交流を豊かにし、相互理解を深めます。
日本の多様性を認識するために
方言と訛りは、日本の文化的・言語的多様性を象徴する存在です。その違いを学び、尊重することは、日本社会をより理解する第一歩となるでしょう。