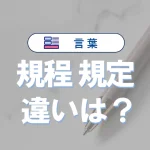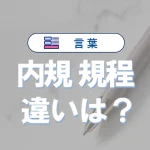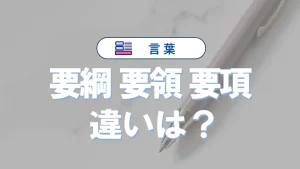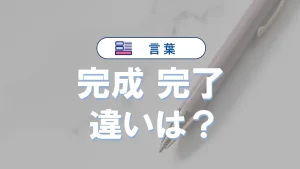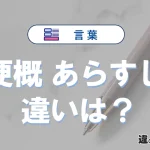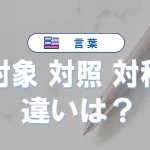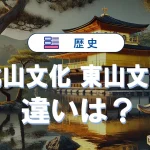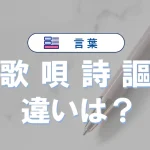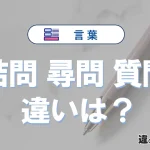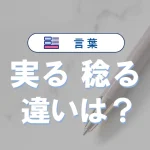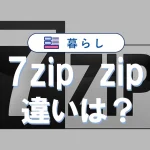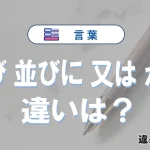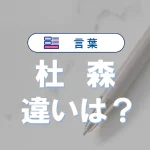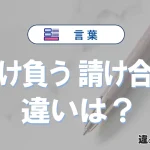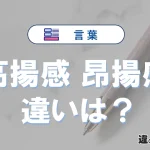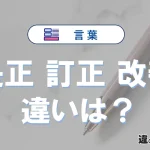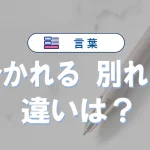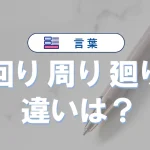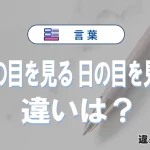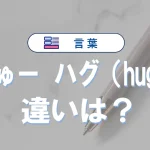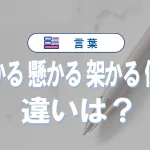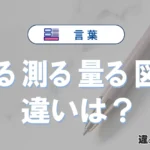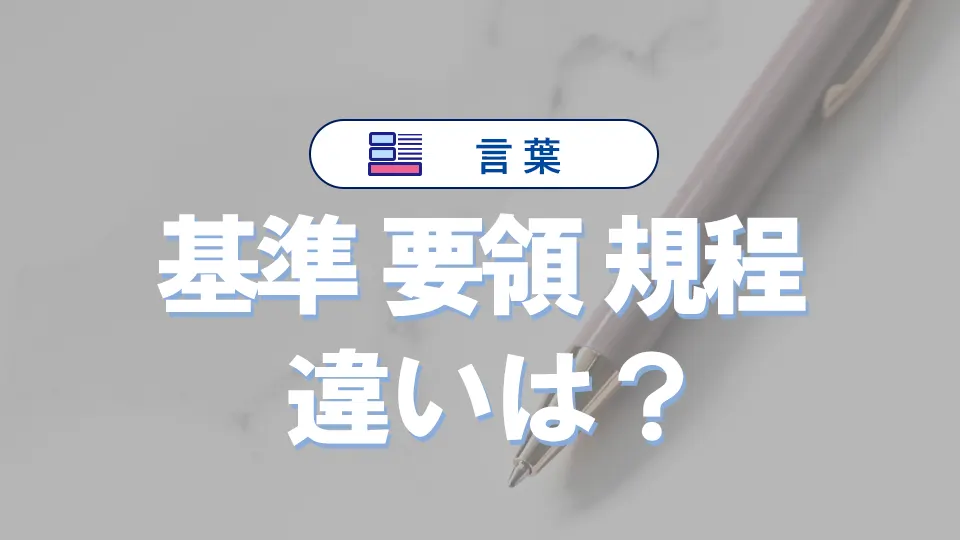
「基準」「要領」「規程」といった言葉は、ビジネス文書や日常会話、組織のルール作りなどで頻繁に使われますが、それぞれの「違い」「意味」「語源」「類義語」「対義語」「言い換え」「使い方」を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。この記事では、「基準 要領 規程」それぞれの用法を例文を交え深堀解説しています。これらを明確に把握することで、文章作成・報告書・プレゼン・社内ルール整備などにおいて、より正確で説得力ある表現が可能となります。
この記事を読んでわかること
- 「基準」「要領」「規程」それぞれの意味と語源
- 三つの言葉の使い分けの「違い」
- 「基準」「要領」「規程」の英語表現とその違い
- 各言葉の言い換え・類義語・対義語・例文(使用頻度の高いもの)
目次
基準と要領と規程の違い
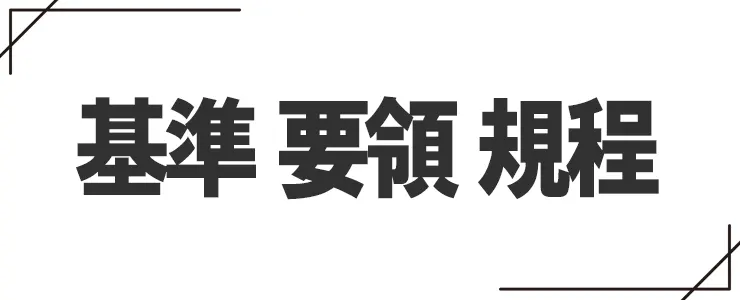
結論:基準と要領と規程の意味の違い
まず結論から言うと、これら三つの言葉の意味の違いをざっと整理すると次のようになります。
基準:物事を判断・比較・評価するための「ものさし」や「よりどころ」「標準」。
要領:物事をうまく処理するための「コツ」「手順」「要点」。
規程:組織や制度の中で定められた一連の条項・決まり・ルールの「集合体」や「文書」的な枠。
このように、基準は「判断・評価の土台」、要領は「実際に行う際の手順・コツ」、規程は「ルール(文書・体系)としてのまとまり」であるという違いがあります。
基準と要領と規程の使い分けの違い
使い分ける際のポイントとして、次のような観点があります。
- 「このプロジェクトの成功判断の基準を決める」→ 判断・評価のためのものさし
- 「この資料作成の要領を押さえる」→ 手順やコツを示す
- 「就業規程を改定する」→ 規程=組織のルール体系・文書
以下のように表で整理するとわかりやすいです。
| 言葉 | 何を指すか | 使用される場面の例 |
|---|---|---|
| 基準 | 評価・比較のものさし・標準 | 品質基準、安全基準、評価基準など |
| 要領 | 物事をうまく進めるためのコツ・手順・要点 | 仕事の要領を掴む、資料作成の要領など |
| 規程 | 複数の規定をまとめたルールブック・体系的文書 | 就業規程、給与規程、服務規程など |
つまり、「基準」「要領」「規程」はニュアンス・用途が重なりそうですが、実際には使う場面も意味も異なります。
基準と要領と規程の英語表現の違い
それぞれの英語表現も押さえておきましょう。
- 基準 → standard, criterion(複数形:criteria)
- 要領 → 英語では “knack”, “method”, “way”, “procedure” など文脈により異なります。
- 規程 → regulation, rule, procedure など。特に組織文書的意味では “internal regulations” がよく使われます。
英語表現を知ることで、国際的なビジネス文書や英語論文作成時にも適切なワードを選びやすくなります。
基準の意味
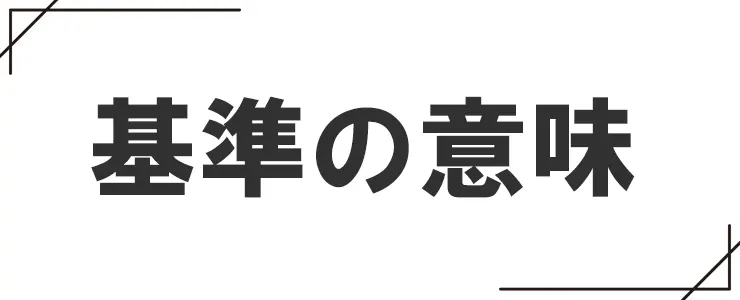
基準とは何か?
「基準」とは、「物事の基礎となるよりどころ」「満たさねばならない一定の要件」「比較・判断・評価のためのものさし」を意味します。たとえば「作品評価の基準」「設置基準」など、多くの場面で使われます。英語では criterion(単数)/criteria(複数)という語も「判断基準」の意味で使われています。
基準はどんな時に使用する?
基準は、次のような場面で使われます。
- 製品やサービスの品質を評価する際:「この製品は安全基準を満たしている」
- 採用・選考の際の条件:「採用基準をクリアしているかどうか」
- 社内・外部の比較をするとき:「この企画は他社と比較した基準がある」
- 手続き・制度の枠組みを示すとき:「審査基準」「適用基準」など
つまり、「何をもって良しとするか」「どこを切り取って判断するか」を提示する際に用いられます。
基準の語源は?
「基準」の「基」は「土台・もと」、そして「準」は「ならす・ならび・平らにする」といった意味を持ち、合わせて「ものごとの基礎をならして、一定の水準を作る」という意味合いが出ています。英語の criterion の語源としては、古代ギリシャ語 kriterion(判決の方法)に由来し、krino(判断する/裁く)という語根との関係があります。また、語源として「分ける/判断する(*krei-)」という印欧祖語が関連しているという説もあります。
基準の類義語と対義語は?
類義語
- 標準(ひょうじゅん)
- 規準(きじゅん)※ただし「基準」と「規準」の違いもあります。
- スタンダード(standard)
- 指標(しひょう)
対義語
- 例外(れいがい)
- 非基準(ひきじゅん)※あまり用いられませんが、基準から外れる状況という意味合いで
- 変則(へんそく)
要領の意味
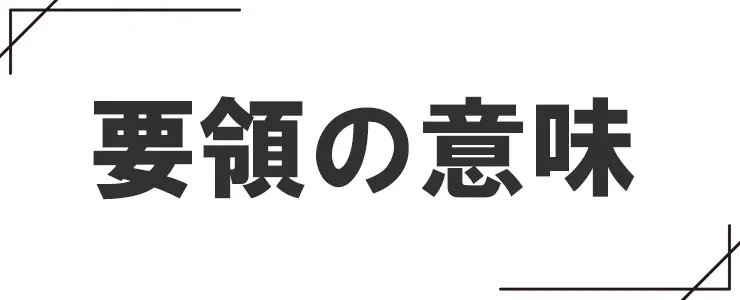
要領とは何か?
「要領」とは、「物事の要点」「物事をうまく処理する手順・コツ」を意味します。語源的には、「要(かなめ・大切なところ)」+「領(くび・えり・うなじ)」という字義から、「物事の中心・肝となる部分をつかむ」という意味合いが派生したとされています。
要領はどんな時に使用する?
要領は次のような状況で使われます。
- 仕事を早く・効率的に進めるための方法を示す:「作業の要領をつかむ」
- 会議・資料・説明などで「肝心なところを把握する」際:「説明の要領を得る」
- 何かを成し遂げるためのコツ・手順を指す:「作業の要領を教える」
- 部分効率・全体効率の観点から:「要領が悪い/良い」
要領の語源は?
「要領」の語源としては、「要(腰)」と「領(襟/うなじ)」の字義が原点です。もともと衣服を扱う際に「腰・襟(要・領)」を掴むことが重要であったことが比喩的に転じて、「物事の肝(要点)を掴む」という意味になったといわれています。また、「要点を得る=要領を得る」という言い回しもこの語源説を裏付けています。
要領の類義語と対義語は?
類義語
- 要点(ようてん)
- コツ
- 手際(てぎわ)
- 技(わざ)
- 手順(てじゅん)
対義語
- 会得できない(かいとくできない)
- 不要領(ふようりょう)※「要領を得ず」のように使われることがあります。
- 無手際(むてぎわ)
規程の意味
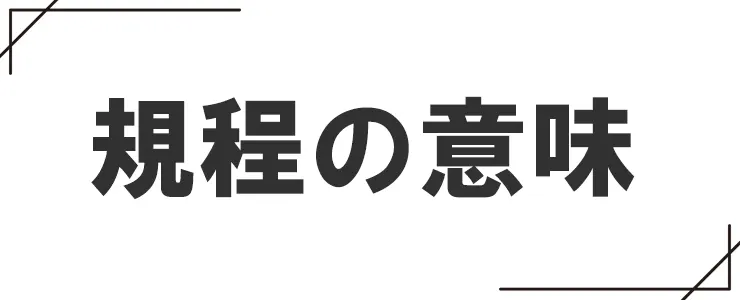
規程とは何か?
「規程」とは、「決まり・さだめ」「一定の目的のために定められた一連の条項」を意味します。特に官公庁や企業で、内部組織・事務取扱を定めたものを指すことが多いです。つまり、「規程=ルールブック」「規定の集合体」という観点があります。
規程はどんな時に使用する?
規程は次のような場面で用いられます。
- 組織の行動・手続きを文書化する際:「就業規程」「給与規程」など
- 内部統制や手続き・職務分掌を明文化するとき
- 法令や方針に基づき、社内向け・官庁向けに作成される一連の条項を整理するとき
使用例として、「この会社の賃金規程を見直す」「図書貸し出し規程に従う」などがあります。
規程の語源は?
語源的な詳細は一般にはあまり語られていませんが、字義として「規(きまり・のり)」「程(ほど・手続き・定められた順序)」という漢字の意味が合わさり、「一定の手続きや範囲を定めたきまり」というニュアンスが生まれています。国語辞典上では、「決まり」「さだめ」「一定の目的のために定めた一連の条項」を指すとあります。
規程の類義語と対義語は?
類義語
- 規則(きそく)
- 規約(きやく)
- 規定(きてい)※ここで「規定」との違いが重要です。
- 手続き(てつづき)
- システム(system)
対義語
- 非公式(ひこうしき)な慣習
- 暫定(ざんてい)的なルール
- 無規程(むきてい)状態
また、「規定」と「規程」の違いを知ることも重要です。
基準の正しい使い方・例文
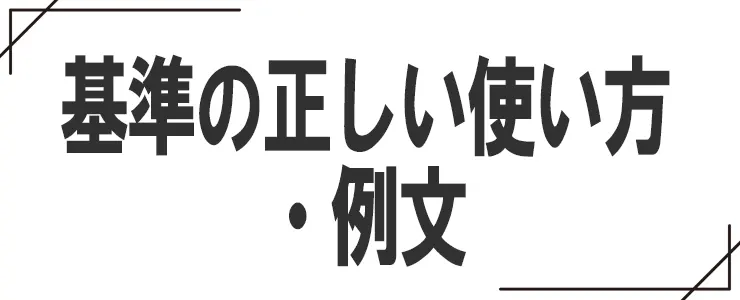
基準の例文
使用頻度の高い「基準」の例文
- この製品は安全基準を満たしています。
- 採用基準として、コミュニケーション能力を重視しています。
- 予算編成の基準が明確になっていないと、社内混乱が起こります。
- 環境保護の観点から、新たな排出量基準が導入されました。
- このレポートは国際的な評価基準に照らして作成されています。
基準の言い換え可能なフレーズ
「基準」を言い換えられるフレーズ
- 判定のものさし
- 評価の尺度
- 判断の基盤
- 標準値
- 目安/目途
基準の正しい使い方のポイント
- 「基準」は「何をもって正しい/許容/良いとするか」という判断・評価の枠組みを示します。
- 「基準」を決める際には、「測定可能」「明確」「比較可能」であることが望ましいです。
- 曖昧な「基準」は混乱を招くため、例えば「明確な数値」「期限」「定量的指標」などを併記することが有効です。
- 「基準を満たす」「基準を設ける」「基準を守る」といった言い回しで使われることが多いです。
基準の間違いやすい表現
- 「基準を決める」と言った後に内容が曖昧では意味が薄くなります。
- 「基準」であるにもかかわらず「ルール」「手順」と混同して使ってしまうケースがあります。
- 「基準値」という表現を使う際、「基準値が超えた/下回った」といった定量的な評価とセットにする方が適切です。
- 英語の “standard”/“criterion” の違いを無視して、「criterion=標準」とだけ訳してしまうと誤訳の原因になります。
要領の正しい使い方・例文
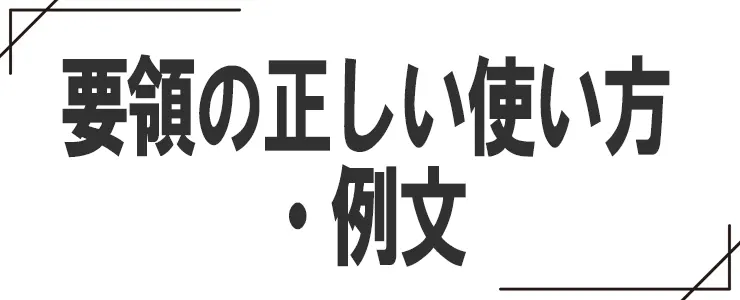
要領の例文
「要領」を使った使用頻度の高い例文
- 会議では詳細を逐一説明するより、要領を押さえて話した方が効果的だ。
- 新人でも、作業の要領を掴めばスムーズに進められる。
- この資料作成の要領を事前に共有しておこう。
4.説明が長すぎて要領を得ないまま終わってしまった。 - 経験を重ねることで、仕事の要領が良くなる。
要領の言い換え可能なフレーズ
「要領」は次のように言い換えることができます
- コツ
- 手際(てぎわ)
- 要点を抑える方法
- 手順のポイント
- 効率的な進め方
要領の正しい使い方のポイント
- 「要領」は「手順・方法・ポイント」を指し、特に効率的・効果的に進める際に使われることが多いです。
- 「要領を得る」「要領をつかむ」「要領が悪い/いい」などの表現が定着しています。
- 単に「手順」だけでなく、「コツ・ポイント」を強調したいときに「要領」を用いると適切です。
- 「要領」を使う際は、「何をどうすれば効率的なのか」「要点は何か」を意識した文脈で使うと説得力が増します。
要領の間違いやすい表現
- 「要領よくやる」という表現は、「効率的に」「スマートに」という意味合いで使われることがありますが、場合によっては「手抜き」に近く聞こえる恐れもあるので注意が必要です。
- 「要領を得ない」という言い回しは、「肝心なポイントがつかめない/要点が整理できていない」というマイナスの意味なので、ポジティブな場面で使うと誤解を招くことがあります。
- 「要領=規則・決まり」という使い方をしてしまうと、意味がずれてしまいます。「要領」はルールそのものではありません。
規程の正しい使い方・例文
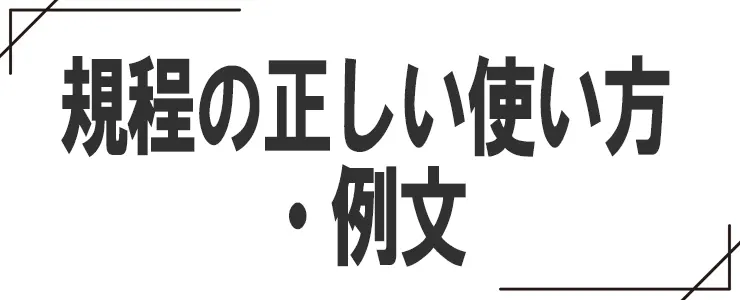
規程の例文
「規程」を使った例文
- 当社の「就業規程」を改定し、テレワーク対応を明記しました。
- 図書館の「貸出規程」に従って本を借りました。
- 社内の「服務規程」には遅刻・早退の手続きが記載されています。
- この制度については、別途「手当規程」を参照してください。
- 政府機関の「安全管理規程」を遵守することが義務付けられています。
規程の言い換え可能なフレーズ
「規程」は次のように言い換えられる場合があります
- 内部規則(ないぶきそく)
- 制度規則(せいどきそく)
- ルールブック
- 手続き体系(てつづきたいけい)
- 規則集(きそくしゅう)
規程の正しい使い方のポイント
- 「規程」は「規定」の集合体であるため、文書名や体系として用いられることが多く、「第○条の規程」ではなく「第○条の規定」と表現するのが適切です。
- 社内・官庁などの“複数の条項・章立て”を含む文章・制度を指す際に「規程」を用いましょう。
- 「規程を定める/改定する/遵守する」などの表現で使われることが多いです。
- 単一の条文や具体的な項目を指す場合は「規定」を用いるように区別することで、文章の精度が高まります。
規程の間違いやすい表現
- 「第○項の規程」という使い方は誤りで、「第○項の規定」が正しい表現です。
- 「規程=手順・方法」と単純に捉えてしまい、文書体系としての意味を理解せず使ってしまうことがあります。
- 「規程」という言葉自体が重く感じられるため、軽いルールやマニュアルに対して使うと過剰な印象を与える可能性があります。
まとめ:基準と要領と規程の違いと意味・使い方の例文
この記事では、「基準」「要領」「規程」という三つの言葉を、意味・語源・類義語・対義語・言い換え・使い方・例文といった観点から整理しました。
ポイントをもう一度振り返ると
- 基準:評価・比較のための「ものさし・標準」。使う際には「どこをもって正しい/許容/良いとするか」を明確にすることが重要です。
- 要領:物事をスムーズに進めるための「コツ・手順・要点」。実践的な場面で使う言葉です。
- 規程:複数の条項を体系化した「ルールブック・文書体系」。企業・官庁などの制度設計に関わる場面で用いられます。
それぞれの言葉を正しく使い分けることで、ビジネス文書・報告書・マニュアル・説明資料などの表現力が高まります。例えば、「このプロジェクトの成功基準を明確にし、作業の要領を共有し、規程に則った手続きを整備する」といった文章は、三つの言葉を適切に用いた好例です。
ぜひこの記事を参考にして、「基準」「要領」「規程」をより効果的に使いこなしていただければと思います。
参考文献・引用