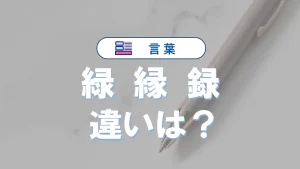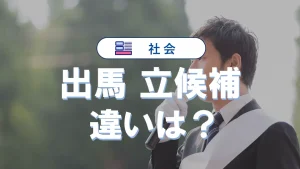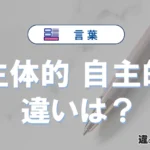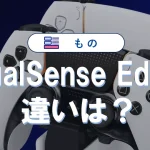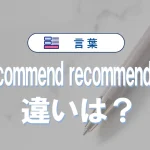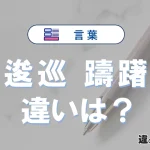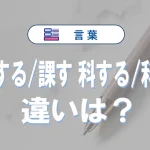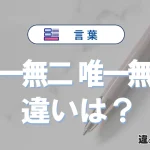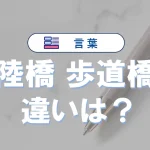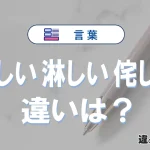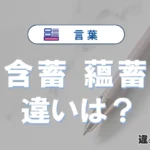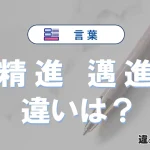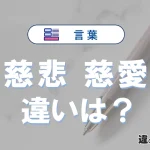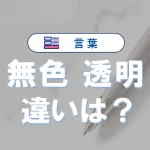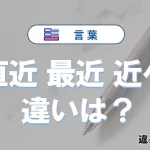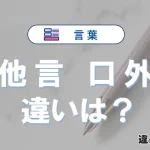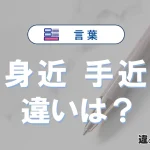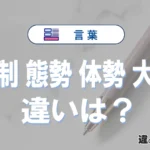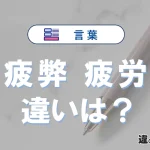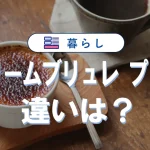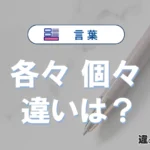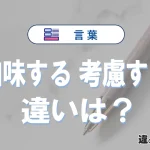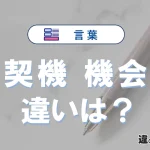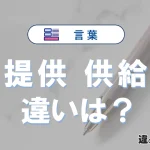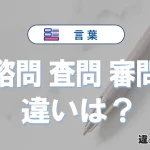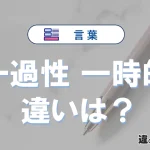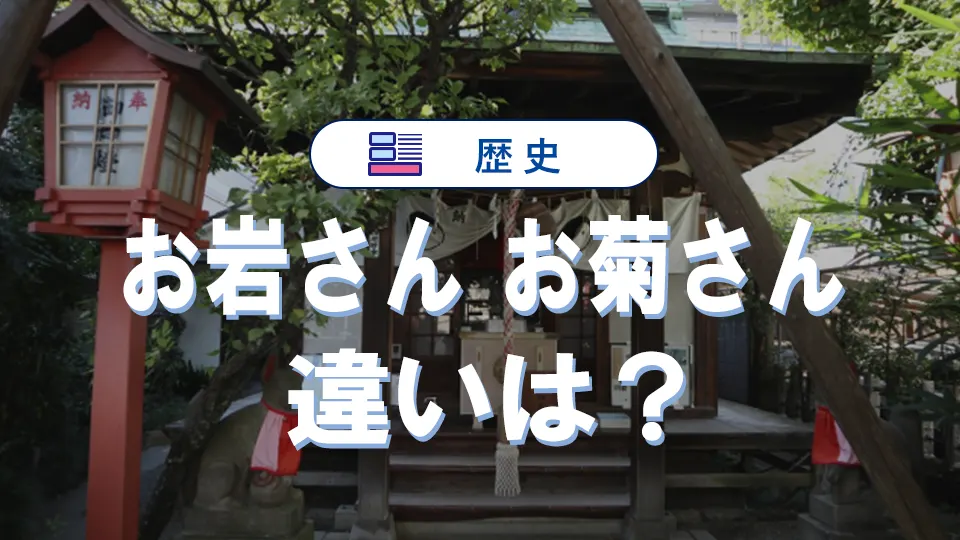
日本の怪談には、時代を超えて語り継がれる女性幽霊が多く登場します。その中でも、最も有名で、かつ文化的にも深く根を下ろしているのが「お岩さん」と「お菊さん」です。両者は「恨みの女」として共通のイメージを持ちながらも、背景や動機、物語の展開には明確な違いがあります。本記事では、四谷怪談と番町皿屋敷を中心に、二人の女性の怨念と悲劇の構造、そしてその社会的・心理的意味を詳しく掘り下げていきます。
目次
お岩さんとお菊さんの比較|四谷怪談と番町皿屋敷の舞台

四谷怪談と番町皿屋敷の概要
「四谷怪談(よつやかいだん)」は、江戸後期の人気歌舞伎作家・鶴屋南北による怪談劇『東海道四谷怪談』(1825年初演)に登場する作品です。夫に裏切られ、毒を盛られ、醜い姿となった妻・お岩が幽霊となって復讐するという、情念と因果の物語。四谷という江戸の都市社会を舞台に、人間の欲望と裏切り、女性の悲哀が生々しく描かれます。
一方、「番町皿屋敷(ばんちょうさらやしき)」は、江戸初期から口伝として広まった民話で、奉公人のお菊が家宝の皿を割ったと疑われ、無実ながらも残酷に殺されて井戸へ投げ込まれる物語です。以後、井戸から「一枚、二枚、三枚…」と皿を数える声が夜な夜な聞こえるという伝承が広まりました。この物語は、封建社会における身分の理不尽さと、忠義の報われなさを象徴しています。
| 項目 | 四谷怪談 | 番町皿屋敷 |
|---|---|---|
| 作者 | 鶴屋南北(1825年) | 民間伝承(江戸初期) |
| 主人公 | お岩 | お菊 |
| 舞台 | 四谷(江戸) | 番町(江戸) |
| テーマ | 裏切りと復讐 | 無実の罪と悲劇 |
お岩さんの物語のあらすじ
お岩は、かつては貞淑で夫想いの女性でした。夫・伊右衛門は、上昇志向と欲望に駆られ、別の女性と結婚して地位を得ようと企てます。そこで、奸計によりお岩に毒を盛り、顔が醜く崩れ落ちるような苦しみを与えたのです。
お岩はその裏切りを悟り、哀しみと怒りの果てに命を落とします。しかし死後、怨念と化した彼女は、伊右衛門の前に現れ、精神を蝕み、ついには破滅へと導くのです。お岩の怨霊は、裏切られた愛と絶望の象徴であり、単なる恐怖の存在ではなく、悲劇的な情愛の化身として描かれています。
代表的なセリフ例:
- 「ああ、恨めしや……」
- 「なぜ、私を裏切ったのです……」
- 「この顔を見ても、まだ言い逃れできるか」
- 「私の命を踏みにじった報いを……」
- 「あなたを地獄まで追っていきます……」
お菊さんの話のあらすじ
お菊は青山家に仕える忠実な奉公人でした。家宝の皿が一枚足りないという騒動が起こり、主は激怒。実際にはお菊の仕業ではなかったものの、主は怒りの矛先を彼女に向け、惨殺し井戸へと投げ込んでしまいます。その後、井戸から「一枚、二枚、三枚…」と皿を数える幽霊の声が響くようになります。
この物語では、理不尽な権力への抗い、そして無念の魂が静かに訴える“正義なき社会への警鐘”が込められています。お菊の怨霊は、決して復讐のためではなく、失われた真実を求めて現れる悲劇的な存在です。
代表的な描写の例:
- 「一枚、二枚、三枚……」
- 「お皿が……ない……」
- 「どうして、私を……」
- 「井戸の底が冷たい……」
- 「十枚目が、ない……!」
二人の女性の実話に隠された背景
お岩の物語は、実在する「お岩稲荷田宮神社(東京都新宿区)」の伝承に基づいているとされます。ここには、江戸時代から“お岩の霊を鎮めるための祠”があり、今でも俳優や映画関係者が作品の成功祈願に訪れます。
一方、お菊の伝承は、姫路城や播州地方にも残り、「お菊井戸」として現存しています。井戸を覗くと怪異が起きるとされ、観光名所としても知られています。地域ごとに細部は異なりますが、どの伝承も「忠義・純真・無念」という女性像を核にしています。
参照リンク:
田宮稲荷神社跡 四谷怪談の旧地
播州皿屋敷 姫路のお菊井戸
お岩さんとお菊さんの違い

人物背景と性格の違い
| 項目 | お岩さん | お菊さん |
|---|---|---|
| 身分 | 武家の妻 | 奉公人 |
| 性格 | 献身的で忍耐強いが激情的 | 誠実で純粋、義理堅い |
| 象徴する感情 | 裏切りへの怒りと怨念 | 無実への悲しみと無念 |
お岩は、社会的には一定の地位を持ちながらも、男性中心社会の中で「愛よりも野心」を優先された犠牲者です。一方のお菊は、身分の低さゆえに理不尽な罰を受け、声を上げることすら許されない悲劇の象徴です。お岩は怒りの化身として能動的に動き、お菊は悲しみの連鎖に囚われた受動的存在として描かれています。
恨みの原因とその行動
お岩の恨みの根源は「裏切り」。愛した相手から命を奪われたことに対する激情が、復讐という形で爆発します。対してお菊の恨みは「無実の罪」という不条理。彼女の怨霊は復讐ではなく、正義を求める魂の嘆きとも言えます。
ストーリーの展開と結末の違い
| 要素 | お岩さん | お菊さん |
|---|---|---|
| 行動 | 裏切り者への復讐を遂げる | 哀しみを繰り返し訴える |
| 結末 | 怨霊の勝利と人間の破滅 | 悲劇の永続と祟りの鎮魂 |
お岩の物語は、復讐を果たすことで物語が完結する“カタルシスのある恐怖”であるのに対し、お菊の物語は、永遠に終わらない悲しみの連鎖を描く“静的な恐怖”です。この違いは、江戸庶民の間で「能動的恐怖」と「受動的恐怖」として心理的に作用しました。
舞台設定の相違点
お岩が登場する四谷怪談は、武士社会の矛盾や腐敗を象徴しており、権力と人間の欲望を暴く社会批判性を持ちます。一方、番町皿屋敷の舞台は奉公人の世界であり、封建的な上下関係の理不尽さを描いています。つまり、お岩は「社会的悲劇」、お菊は「庶民的悲劇」を代表する存在なのです。
四谷怪談と番町皿屋敷の伝説

お岩さんの登場と幽霊の描写
お岩の幽霊は、顔が崩れた恐ろしい姿で描かれ、提灯や鏡、障子など日常の中に不意に現れる点に特徴があります。これは、観客の心理に“自分の生活空間にも怨霊が潜む”という恐怖を植え付ける演出です。歌舞伎では早替えや照明効果によって、お岩の変貌が一瞬で起こる場面が有名です。
お菊さんの存在と井戸の重要性
お菊の象徴である「井戸」は、民俗学的に“現世と冥界の境界”を意味します。お菊は井戸に沈められることで現世から隔絶され、魂が帰る場所としての「井戸」が霊的象徴へと昇華しました。井戸の底から皿を数える声は、彼女が「真実を数え直す行為」であり、赦されぬ世界への訴えでもあります。
実在の事件と伝説の関係
両作品とも江戸期の事件や噂がもとになっているといわれています。お菊井戸は姫路城に現存し、実際に「皿を数える声が聞こえた」という記録が残されています。人々は恐れながらも、どこかで彼女の無念を慰めたいという感情を抱き続けてきました。それが今も伝承を生かしている理由でしょう。
お岩さんとお菊さんの現代への影響

今日の文化における妖怪・幽霊の考察
現代のホラー文化において、お岩とお菊の影響は絶大です。「リング」の貞子や「呪怨」の伽椰子といった女性幽霊像の原型は、彼女たちの怨念構造を継承しています。理不尽な死、報われぬ愛、そして沈黙の中に潜む怒り――それらは時代を越えた“女性の叫び”として現代にも通じるのです。
舞台や映画に登場する形での再解釈
20世紀以降、多くの演出家や監督がこれらの物語を現代的に再解釈してきました。蜷川幸雄の舞台演出では女性の心理を内面化し、中田秀夫監督の作品では「静かな怨念」として描かれます。お岩とお菊は、単なる怪談の登場人物ではなく、女性の苦悩と社会的抑圧を象徴する文学的存在へと昇華しました。
まとめと考察|なぜこの物語が語り継がれるのか
四谷怪談と番町皿屋敷の重要性とその魅力
両作品の本質は恐怖ではなく、「人間の情念の深さ」にあります。お岩は裏切りに対する怒りを、お菊は理不尽に対する悲しみを象徴します。この二人の物語は、時代を越えて人々の心に響く“感情の原型”であり、だからこそ何百年経っても語り継がれているのです。
読者に伝えたいメッセージと感情の系列
お岩とお菊の物語が私たちに教えるのは、愛と裏切り、正義と報い、生と死の境界といった普遍的テーマです。彼女たちは恐怖の象徴であると同時に、人間の感情の極限を映し出す鏡でもあります。だからこそ、二人の物語は、幽霊の姿を借りて“人間らしさ”を描き続けているのです。