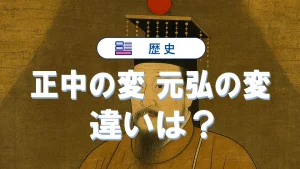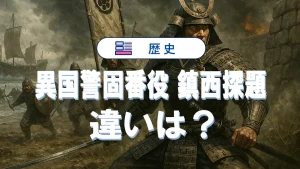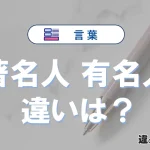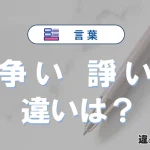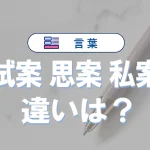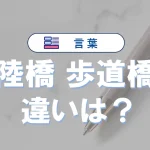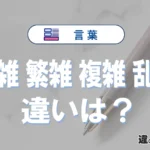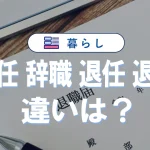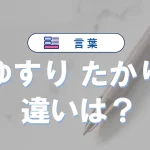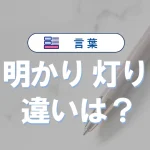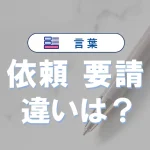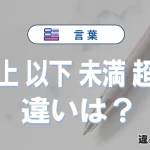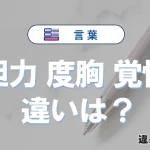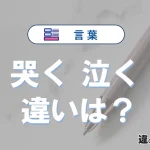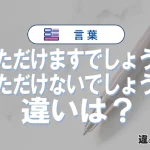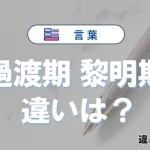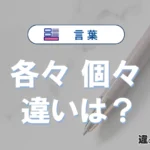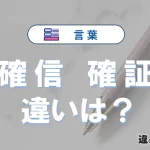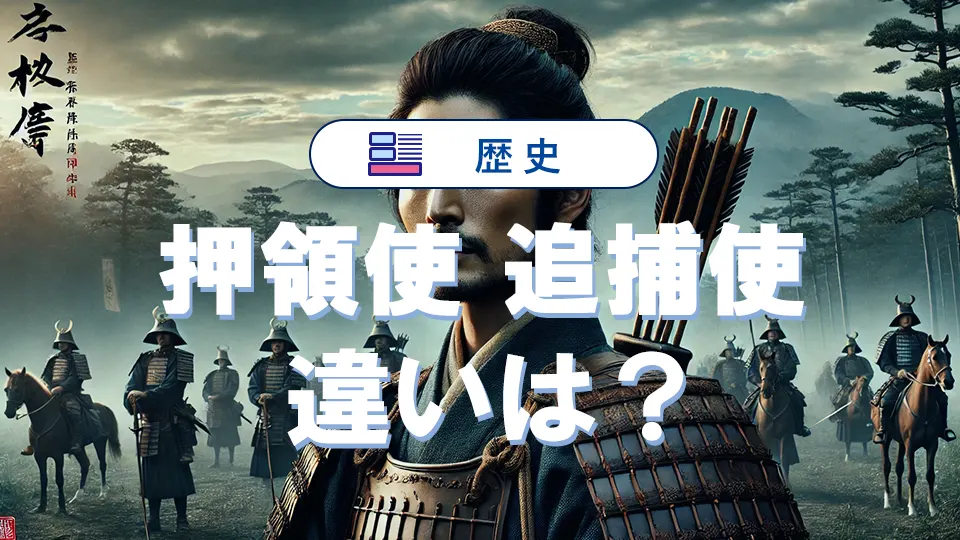
平安時代の日本史を学んでいると、「押領使(おうりょうし)」や「追捕使(ついぶし)」といった耳慣れない役職名が出てきて混乱する方も多いのではないでしょうか。特に、「押領使と追捕使の違い」はテストに出るポイントにもなりやすく、しっかりと理解しておきたいところです。
この記事では、「押領使とは?」「追捕使とは?」という基本から、なぜ誕生したのか、いつ誰が設置したのかまでを網羅的に、そしてわかりやすく解説していきます。
結論から言えば、押領使と追捕使はどちらも治安維持や軍事を担う官職ですが、それぞれ誕生した時期や活動範囲、職務内容が異なっているのです。
- 押領使と追捕使の具体的な違い
- 押領使とは何か、追捕使とは何かの基礎知識
- 押領使と追捕使が設置された歴史的背景や理由
- 武士や守護との関係を含めた制度の変遷
目次
押領使と追捕使の違いを簡単に解説

押領使と追捕使の違いとは?
押領使と追捕使は、どちらも平安時代に設けられた令外官で、軍事や治安維持を担当する官職です。名前も職務も似ていますが、いくつか明確な違いがあります。
まず押さえておきたいのは、それぞれの役割と活動地域です。
- 押領使は主に東日本で活動し、地方の治安維持を担当する役職でした。
- 追捕使は西日本や瀬戸内海を中心に、海賊や反乱の鎮圧などを目的として設置されました。
さらに、職務の性質にも違いがあります。
| 比較項目 | 押領使 | 追捕使 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 地方の治安維持 | 海賊や反乱の鎮圧 |
| 活動範囲 | 東国中心 | 西国・瀬戸内海中心 |
| 職務の性質 | 指揮官型(戦闘にはあまり参加しない) | 現場型(戦闘にも関与) |
| 常設の開始時期 | 平将門の乱以降 | 承平・天慶の乱以降 |
このように、似ているようでいて、押領使は「治安管理のリーダー」、追捕使は「治安問題への即応部隊」といった位置づけに整理できます。
押領使とは?わかりやすく解説

押領使(おうりょうし)は、平安時代初期に設置された官職で、地方の治安維持を主な任務としていました。初期の記録では、延暦14年(795年)に登場しています。
役割の特徴を簡潔にまとめると以下の通りです。
- 兵を率いるが、初期は戦闘には関与しない
- 主に東日本の治安維持を担当
- 常設化されたのは平将門の乱(935~940年)以降
- 武芸に優れた国司や郡司、後には豪族が任命された
また、押領使は指揮官としての役割が強く、実際の戦闘では部下の兵士に指示を出す立場でした。のちにその役割は、現地の有力豪族に移り、私的な武力を背景に地域を支配するようになります。
地方の警察官のような役職ですが、やがてその力が強まり、武士階級の源流となっていきました。
追捕使とは?わかりやすく解説

追捕使(ついぶし)は、平安時代中期の932年(承平2年)に登場した令外官です。設置の目的は、当時深刻化していた海賊被害や反乱への対応でした。
押領使と異なる点を中心に、追捕使の特徴を整理します。
- 主に瀬戸内海や西日本の治安維持が目的
- 海賊や反乱への対応が主な任務
- 現場に出て、実際の戦闘にも関与
- 代表的な追捕使に小野好古(藤原純友の乱の鎮圧者)
- 平安末期には惣追捕使へと発展し、鎌倉時代には守護に変化
追捕使は当初、臨時の任命でしたが、藤原純友の乱(939~941年)を機に常設されるようになります。地方の有力者が任命され、現場で武力を行使する立場となったことで、地域の軍事力を支える存在となりました。
このように、追捕使は「動ける実動部隊」として、押領使よりも即応性の高い職務が求められていたといえます。
押領使と追捕使はなぜ誕生したのか

押領使と追捕使が生まれた背景には、律令制の崩壊と治安の悪化があります。
平安時代中期には、律令制度による中央集権体制が機能しなくなり、地方での反乱や盗賊行為が頻発するようになりました。とくに以下のような要因が重なっています。
- 徴兵制の衰退と軍事力の低下(健児の制も機能不全に)
- 地方豪族の台頭により私的武力が増加
- 中央政府の支配力が及ばない地域で治安が不安定に
このような事態に対応するため、朝廷は柔軟な対応ができる「令外官」を設け、地方に軍事・治安権限を与える必要が出てきました。押領使と追捕使はその代表的な例です。
つまり、もともとは中央からの支配強化が目的でしたが、最終的には地方豪族に軍事力を任せる結果となり、武士の成長を促す土台ともなったのです。
押領使と追捕使はいつ誰がつくったのか

押領使と追捕使は、どちらも律令制の不備を補うために設置された令外官ですが、それぞれ誕生の時期や人物に違いがあります。
- 押領使:795年(延暦14年)に初登場
- 桓武天皇の時代、地方軍の再編に伴い設置されたと考えられています。
- 当初は防人の移送を担うなど、限定的な役割でした。
- 追捕使:932年(承平2年)に初設置
- 摂政・藤原忠平の時代に、南海道で頻発していた海賊対策のため設けられました。
- 追捕海賊使として始まり、のちに全国に広がります。
特定の一人の人物が「発案者」として名を残しているわけではありませんが、制度設計には当時の政権中枢であった藤原氏の影響が強かったとされています。
また、両官職が制度化されていくきっかけとなったのは、以下の大規模な反乱です。
- 平将門の乱(935~940年):押領使・藤原秀郷が活躍
- 藤原純友の乱(939~941年):追捕使・小野好古らが対応
これらの反乱は、押領使・追捕使の常設化を進める転機となり、平安時代の地方支配体制の変化を象徴する出来事でした。
押領使と追捕使が果たした歴史的役割

押領使と追捕使と藤原秀郷の関係
藤原秀郷(ふじわらのひでさと)は、押領使として知られる人物の中でも特に有名で、平将門の乱を鎮圧した功績により、その名を歴史に刻みました。彼の存在は、押領使の役割や意義を理解する上で非常に重要です。
まず、秀郷は下野国(現在の栃木県)を拠点とする地方豪族であり、平安時代中期に起きた「平将門の乱(935~940年)」で朝廷側の主力として活躍しました。
このときの状況は以下の通りです。
- 平将門は関東で独立政権を樹立しようとした反乱軍の首領
- 朝廷は地方の有力武士に対応を任せた
- 押領使として任命された藤原秀郷が出陣し、将門を討伐
押領使は元々、兵を指揮するだけの存在でしたが、この戦いをきっかけに実戦に関与する存在として認識されるようになります。
また、秀郷は「藤原北家」の出身でありながら地方で武力を行使したという点で、貴族から武士へと移行する過程を象徴する存在でもあります。彼の活躍によって押領使の役割が強調され、後の武士階級の礎となる動きが加速していきました。
押領使と追捕使の共通点と違い

押領使と追捕使は、どちらも平安時代に登場した令外官(律令に定められていない特別官職)であり、治安維持や軍事対応を目的として設置されました。この点で両者にはいくつかの共通点がありますが、それぞれの性格にははっきりとした違いもあります。
【共通点】
- どちらも朝廷の命令により設置された特別官職
- 平安時代中期の治安悪化に対応するために設けられた
- 当初は臨時の役職だったが、後に常設化された
- 地方の国司や豪族などが任命されることが多かった
【主な違い】
| 比較項目 | 押領使 | 追捕使 |
|---|---|---|
| 設置時期 | 795年ごろ | 932年 |
| 活動地域 | 東国中心 | 西国や瀬戸内海中心 |
| 主な任務 | 地方の治安維持 | 海賊や反乱の鎮圧 |
| 戦闘関与 | 指揮中心、戦闘には不参加 | 現場参加もあり |
このように、押領使は「地域密着型の警察官」、追捕使は「機動力を持つ特別部隊」のような存在だったといえるでしょう。
押領使と追捕使のその後と守護への変化

押領使と追捕使は、いずれも平安時代の地方統治を支える重要な官職でしたが、時代の流れとともにその役割も変化し、やがて「守護」へと統合されていきました。
以下がその変化の流れです。
- 常設化と権限拡大
両官職とも、平将門の乱や藤原純友の乱を契機に常設化され、軍事・治安の中核を担うようになります。 - 惣追捕使(そうついぶし)への発展
特に追捕使は、国全体を統括する形で惣追捕使という役職へと変化し、より広域な治安維持に関与するようになりました。 - 守護の誕生
1185年、源頼朝が「日本国惣追捕使」に任命されたことを契機に、惣追捕使の制度が全国へと波及。このとき新たに設けられた「守護」は、事実上、押領使や追捕使の任務を引き継ぐ形となります。 - 守護・地頭の制度化
鎌倉幕府により、守護・地頭が制度化され、武士が地域統治を担う時代が本格的に始まりました。
このように、押領使・追捕使の制度は武士政権の出発点ともいえる「守護」のルーツに深く関わっています。
押領使と追捕使が武士の起源となった理由

押領使と追捕使が、のちの武士へとつながる起源とされる理由は、いくつかの歴史的背景と構造に基づいています。
当時の社会情勢では、以下のような事情がありました。
- 中央の徴兵制度が機能しなくなり、軍事力が地方に分散
- 地方豪族が自ら武装し、自衛のための武士団を形成
- 朝廷は地方の治安維持を押領使・追捕使に依存
このような状況の中、押領使や追捕使に任命された豪族たちは、次第に実戦経験を積んだ「現地の武力担当者」となり、名実ともに武士としての地位を確立していきました。
特に注目すべき点は以下の通りです。
- 彼らは朝廷からの正式な任命を受けており、武力行使に正当性があった
- 自分の領地を守るための軍事力を持ち、戦乱時には中央からも頼られる存在だった
- 戦いの中で功績を挙げた者は、さらなる地位や土地を得て勢力を拡大した
こうして、押領使・追捕使の制度は結果的に武士の社会的正統性を育む舞台となったのです。
押領使と追捕使の登場と平安時代の背景

押領使と追捕使が登場した背景には、平安時代の政治・軍事制度の変化が大きく関わっています。
この時代の主な特徴として、次のような問題が浮かび上がっていました。
- 律令制の形骸化
中央集権体制が次第に機能しなくなり、地方行政に空白が生まれるようになります。 - 徴兵制度の廃止と健児制の不全
従来の兵制である「健児制」も運用が困難となり、軍事力の担い手が不足しました。 - 地方豪族の台頭
荘園の増加や税制の混乱により、地元の有力者が実質的な支配者として力を持ち始めます。
このような社会構造の中、朝廷は新たな治安維持・軍事担当官として押領使(795年頃)や追捕使(932年)を登用しました。
当初は臨時の役職でしたが、各地で反乱や海賊被害が頻発するようになると、常に置かれるようになり、結果として地域支配の実務者=武士層へと発展していきます。
平安時代後期には、これらの流れがまとまり、最終的に武家政権である鎌倉幕府が誕生する土台となりました。押領使・追捕使は、まさにその前夜を象徴する存在といえます。
押領使と追捕使の特徴と歴史|要点まとめ
- 押領使は795年頃に東日本で治安維持を目的に設置された
- 追捕使は932年に西日本や瀬戸内海の海賊対策として設置された
- 押領使は初期、兵を指揮するが戦闘には参加しない指揮官型
- 追捕使は現場に出て実際の戦闘にも加わる実動型官職
- 両者ともに朝廷から任命された令外官である
- 平将門の乱で押領使の藤原秀郷が反乱を鎮圧した
- 藤原純友の乱では追捕使の小野好古が活躍した
- どちらも当初は臨時の官職であったが乱を機に常設化された
- 押領使は東国中心、追捕使は西国中心に配置された
- 押領使は地方の警察的な役割を担った
- 追捕使は反乱・海賊を鎮圧する軍事的役割を担った
- 時代が下ると追捕使は惣追捕使となり国全体を統括するようになった
- 源頼朝が日本国惣追捕使となり、守護制度につながっていった
- 押領使・追捕使の存在が武士の社会的正当性の基盤となった
- 平安時代の律令制の衰退と治安悪化が設置の背景にある