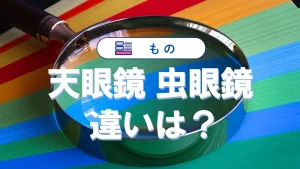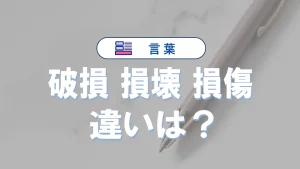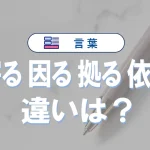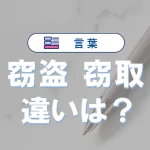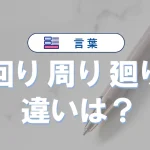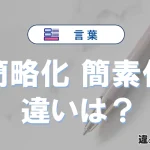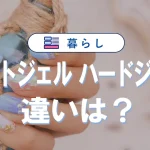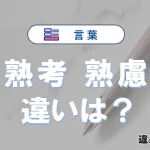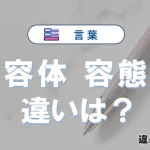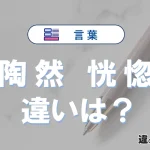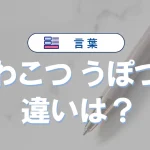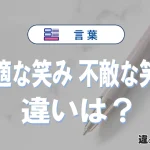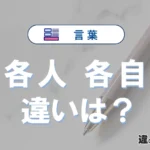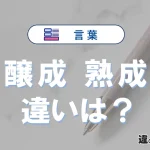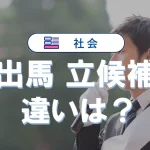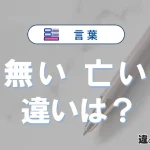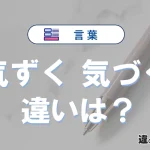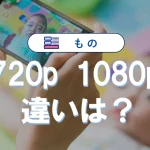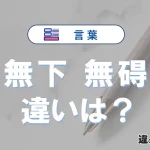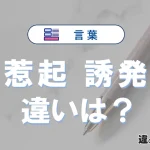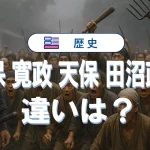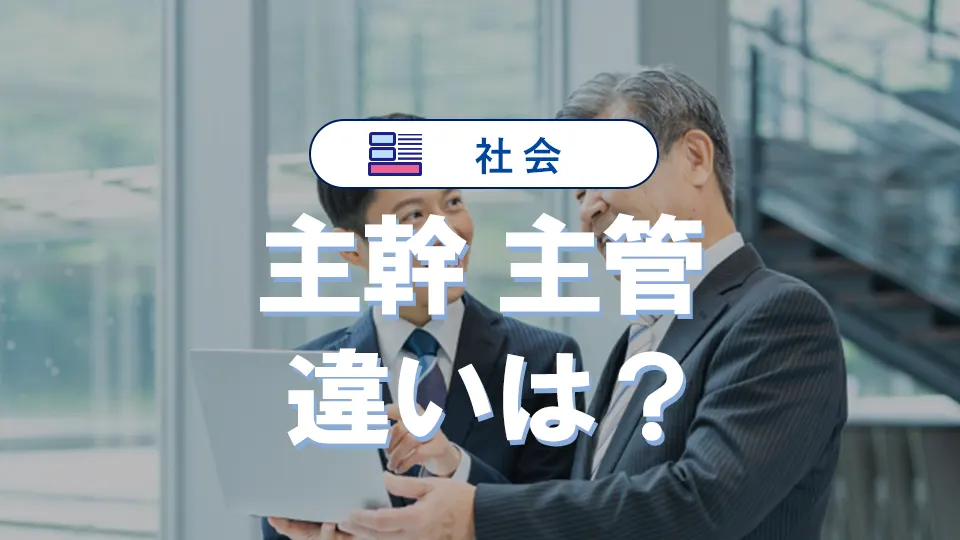
企業や行政で「主管(しゅかん)」という言葉を見かけることもあれば、「主幹(しゅかん)」という肩書を聞くこともあります。漢字は似ていますが、意味や使い方、役割には明確な違いがあります。本記事では、「主管」と「主幹」の違いを結論から先に示すと以下のようになります。
主管=ある物事を主導的に管理・管轄する立場・部署。主幹=その物事・組織の中心となって取りまとめる立場・役職。
以下では、意味・使い分け・実務例・役職体系・業界差などを段階的に深掘りしていきます。
目次
「主管」と「主幹」の基本的な意味
「主管」の意味は?
「主管(しゅかん)」は、次のように定義されます。
・「ある物事を主となって管轄・管理すること。また、その人・役」
・「労働行政を主管する」のように、ある範囲の責任を持って所管・管理する意義で使われることが多い
つまり、「主管」は、ある業務や分野を“主として管理・統括する責任”を表す言葉であり、必ずしも役職名とは限りません。「どの部門が主管か」「誰が主管か」という使われ方をすることが一般的です。
例文
1. 当イベントの主管部署は経営企画部です。
2. この業務は人事部が主管しています。
3. 会議の運営を主管者が調整する。
4. 新制度の実施を企画担当が主管して進める。
5. 予算執行に関しては財務部が主管部門とされる。
「主幹」の意味は?
「主幹(しゅかん)」は、主に役職名として使われることが多く、以下のような意味・役割を含む語です:
- 物事を構成する中心となる人、中心的な業務をまとめる役割を持つ人を指す
- 行政・自治体などで中間管理職的立場で、組織や部門の“まとめ役”を担うことが多い
- 民間企業においても役職名として採用されることがあり、課長補佐や課長に準ずる場合がある
「主」が付くことから、「主導」「主役」的な意味合いを含み、構成・運営の中心人物というニュアンスが強いです。
例文
1. 総務部主幹として業務を統括する。
2. 企画課には主幹職が置かれている。
3. このプロジェクトには経験豊かな主幹がアサインされた。
4. 主幹は、部下の進捗確認と方針決定を担う。
5. 科学技術部門の主幹は、技術方針をまとめる。
「主管」と「主幹」の違いとは?
「主管」と「主幹」は、語義・用途・立ち位置で違いがあります。以下に主な違いを整理します。
| 観点 | 主管 | 主幹 |
|---|---|---|
| 意味・語義 | 管理・管轄を主導的に担当すること/その担当 | 組織・業務の中心となってまとめる人・役職 |
| 用途 | 部署や担当分野に使われやすい(“主管部署”など) | 役職名として使われることが多い |
| 立ち位置 | 所管・監督的な立場 | 中間管理職または中核的な実務者 |
| 決定権 | 管理・管轄として調整・統制 | 実務・運営をまとめ決定を下すことも含む |
| 汎用性 | 業務・プロジェクトなど広く使える | 組織内の役職等限られた文脈で使われやすい |
要するに、「主管」は“管理・管轄”の概念寄り、「主幹」は“中心的な推進・統括”の意を携える語です。実務では重なって使われる場面もありますが、意識的に使い分けることで文意を明瞭にできます。
「主管」と「主幹」を使い分ける理由
役職としての「主管」と「主幹」
組織(特に自治体や公務部門)では、「主管」が役職名として使われるより、「主幹」が役職名として用いられることが一般的です。これは「主管」は概念的/部署名的な性質を持つためです。
ただし、例外もあります。特定組織では「主管課長」「主管幹事」などといった名称が使われることがあり、用語慣行は組織ごとに異なります。
自治体の資料では、主幹は「課長補佐級・スタッフ職」などの扱いとなることが多く、主査・主任と並ぶ中核的なポジションとして位置付けられていることが多いです 。
一方、主管を肩書に用いるケースは少ないですが、事業や分掌を「主管する」という修飾語として使われることが多いです。
業務上の主管部署と所管部署の違い
「主管部署」と「所管部署」という表現も混同しやすいですが、ここには意味の微妙な違いがあります。
- 主管部署:ある業務・事業などを主に管理・統括・主導する立場にある部署
- 所管部署:その業務を所管(取り扱い責任を有する)する部署
つまり、主管部署は“主導的立場”を含意することが多く、所管部署は“担当する責任”というニュアンスがやや穏やかです。
職場での役割と責任の違い
職場において、「主管」「主幹」の肩書や役割が付くケースでは、以下のような差異が生じることがあります。
- 主管の立場では「調整・管理・監督」の比重が強くなることが多い
- 主幹の立場では、調整・管理に加えて「方針立案」「実務決定」「推進責任」が強くなる
- 主幹は部下指導・育成・現場フォローなど、実行面での責任が重い
- 主管は複数部門にまたがる調整や責任範囲の明確化に関与することがある
「主管」と「主幹」の職種における実務
主管の担当業務とは?
「主管」が担当する業務は、主に以下のようなものがあります。
- 業務範囲の調整:複数部門にまたがる業務の境界調整
- 統括・監督:進捗確認・品質チェック・方針調整
- 責任窓口:関連部署や外部との交渉・対応
- 指示・指導:下位部署への指示・助言
- リスク管理・対応:問題発生時の対応と解決策の主導
たとえば、「情報セキュリティ主管部門」は、社内各部門のセキュリティ対策を統括・管理する役割を果たします。
主幹の主な業務内容
主幹が担う実務的な業務は、次のような内容が典型です。
- 方針決定・実行:部門戦略・計画立案とその遂行
- 調整・統括:所属グループや複数セクションの調整
- 部下マネジメント:進捗管理・評価・指導育成
- 決裁権限:ある程度の決裁処理、承認事項の執行
- 報告対応:上位への報告、説明、折衝
例えば、自治体の主幹職では、複数課にまたがる調整や事業予算管理、担当職員の配置・育成などが業務に含まれることがあります。
自治体土木部門の職名例資料では、主幹(課長補佐・補佐級)職が班長管理・業務割り振り・グループ編成調整などを行う例が記載されています。
「主管」、「主幹」の役職とは
地方公務員における「主管」と「主幹」の役割
地方自治体では、主幹は広く採用されている役職名であり、階級・待遇・役割は自治体ごとに異なりますが、一般的な傾向は以下の通りです。
- 係長級・課長補佐級の“スタッフ職”にあたることが多い
- 課長・部長といったライン職の補佐・統括を担う立場となることが多い
- 自治体によっては、主幹=課長級扱い、あるいは主幹制度を設けず別称を使うところもある
- 若年層で主幹に就くケースもあれば、年齢や経験を問うルールを設けている自治体もある
一方、「主管」が自治体で役職名として使われることは少なく、むしろ部署の責任範囲を示す言葉として使われることが多いです。
たとえば、ある自治体で「福祉主管課」という名称を使うことで、「福祉分野の主管部署」という意味合いを持たせるケースがあります。
企業における「主管部門」と「主幹部門」の違い
企業組織でも、「主管部門」「主管部署」「主幹職」といった用語が用いられることがあります。実態は企業により大きく異なりますが、一般的な違いは以下のようになります。
- 主管部門:あるテーマ・テーマ横断分野(例:リスク管理部、情報セキュリティ主管部など)が主管部門として、他部署を指導・統括
- 主幹職:部門内の中核ポジション、課長補佐クラスや部門副責任者として機能
- 主管部門は“業務横断”性が強いことが多いが、主幹部門(という表現を使うなら)は“組織内部の統括”が中心
企業では役職名を自由に設計できるため、「主幹」「主管」を役職名に使うかどうかは企業文化によります。従って、求人票や組織図をよく見て意味合いを読み取る必要があります。
歴史的背景や業界による違い
「主管」「主幹」という言葉には、以下のような歴史的および業界的な背景があります。
- 「幹(かん)」という字は「中心となる木の幹」「物事の中核」を意味し、役職名に使われると“中核性”を暗示する語感があります
- 行政・自治体の伝統的な制度では、「主事→主任→主査→主幹→主務…」といった階層構成が使われることがあった(ただし自治体により順序や呼称は異なる)
- 業界(たとえば教育現場、行政、医療)の中では「主幹教諭」「主幹事務長」など、専門分野での「主幹」肩書が使われる例があります
- また、一部組織では「主管(中国語読み zhǔguǎn)」の影響を受けて導入された用語使いも見られ、意味の揺らぎを生じることがあります
結論: 「主管」と「主幹」の違い|意味や使い方・役職をわかりやすく
最後に、まとめとして「主管」と「主幹」の違いを整理し、使い分けや理解を確実にできるようにします。
- 主管 は「管轄・管理・統括」の意味を中心とした語であり、部署名や担当分野を示す語として使われやすい
- 主幹 は「中心的なまとめ役・統括者」を意味し、役職名として用いられることが多い
- 実務場面では、主管は調整・管理系、主幹は実務決定・統括責任的な立場として使われる傾向にある
- 自治体・行政機関では、主幹が中間管理職ポジションとして定着しており、主管は役職としては稀である
- 企業や業界によって、これらの語の採用状況や意味合いにはばらつきがあるため、組織ごとの慣行を確認することが重要