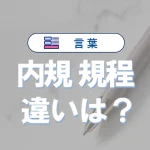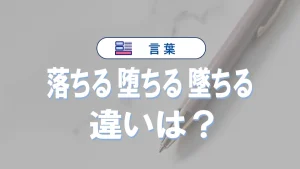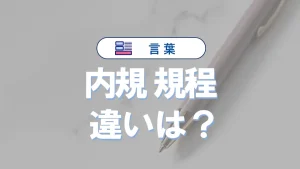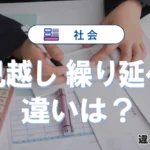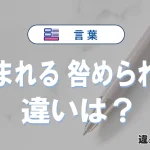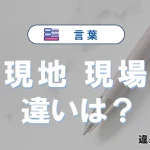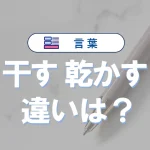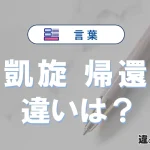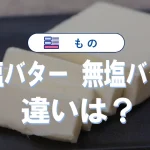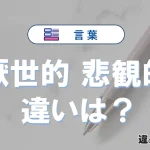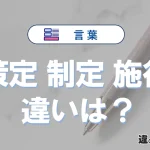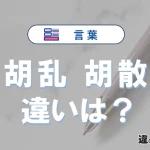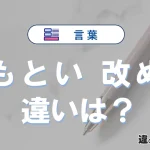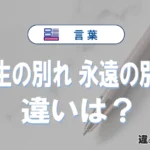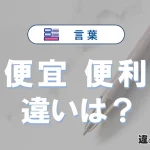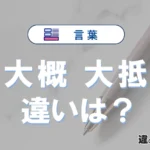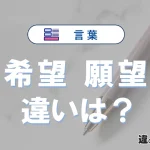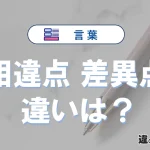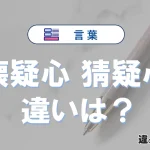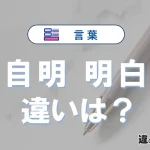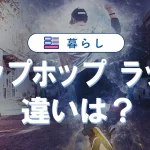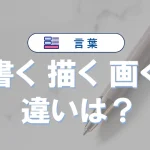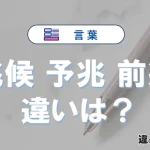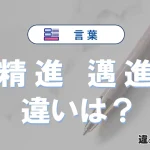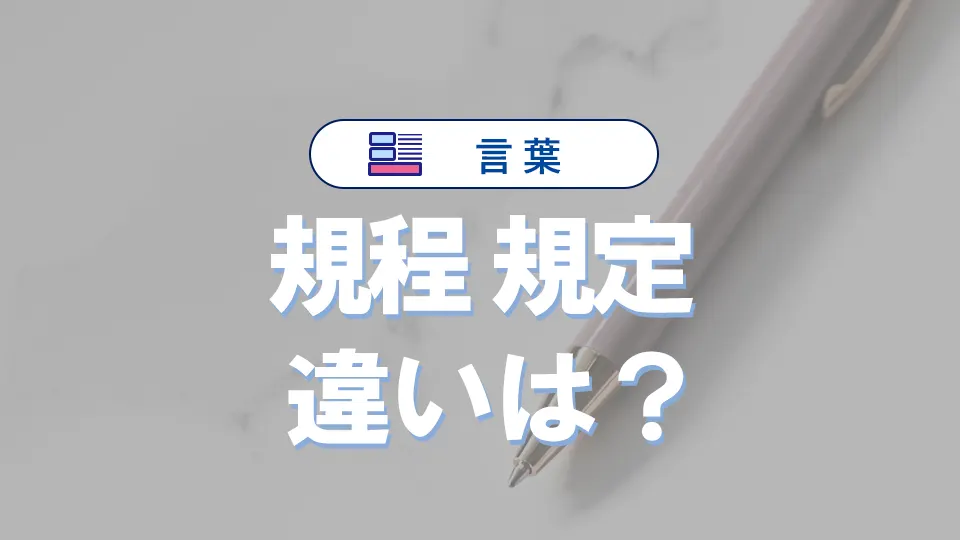
「規程」と「規定」という言葉は、読み方も同じ「きてい」であり、漢字も似ているため、ビジネス文書や法務文書、社内ルールにおいて混同されることが少なくありません。しかしながら、実はこの2つには明確な意味の違いがあり、正しく使い分けることで、文章の信頼性や専門性が向上します。この記事では「規程」と「規定」の違い・意味・語源・類義語・対義語・言い換え・英語表現などを、実際の使い方や例文を交えて詳しく深掘りして解説します。
この記事を読んでわかること
- 「規程」と「規定」の意味と語源の違い
- 「規程」と「規定」の使い分けポイント
- それぞれの言い換え・類義語・対義語の整理
- 実務で使える例文と誤用しやすい表現のチェック
規程と規定の違い
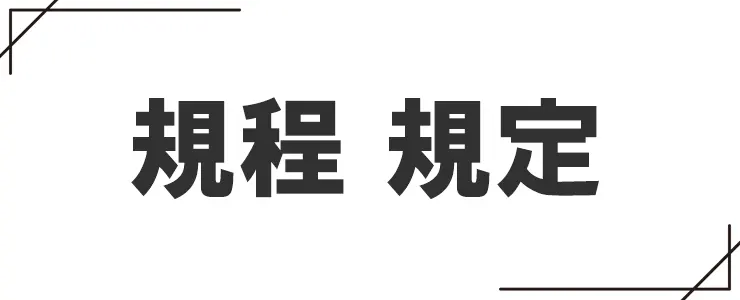
結論:規程と規定の意味の違い
まず端的に結論を述べると、「規程」はある目的のために定められた一連の条項(=条文などの複数)をまとまったものとして指します。一方、「規定」はその条項のうち「個別の一つ一つの定め・条文・内容」を指します。
具体的には、例えば「就業規則」という文書があったとすると、その中に「役職手当を支給する旨を定める第○条」があれば、この「第○条」の定めを「規定」と言い、その「就業規則」全体や「賃金規程」など一定のテーマに沿ってまとめられた文書群を「規程」と呼ぶというイメージです。
規程と規定の使い分けの違い
使い分けのポイントを押さえると、誤用を防ぎやすくなります。主なチェックポイントを以下にまとめます。
- 「規定」は動詞「規定する」が使えることが多い:例「第○条で規定する」など。
- 「規程」は基本的に動詞形「規程する」は用いず、名詞として「○○規程」という文書名・名称として使われることが多い。
- 「第○条の規定」という形式が一般的に正しい表現で、「第○条の規程」という表現は誤用とされるケースが多い。
- 文書のタイトルや総体を示す場合=「規程」、条文・定めの個別部分を示す場合=「規定」。
つまり、書類として「○○規程(例:旅費規程、服務規程)」という名称が付くことが多く、その中の「●項目はこう定める」という形の文章を「規定」と呼ぶのが正しいというわけです。
規程と規定の英語表現の違い
英語で「規程」「規定」を表現する場合、文脈に応じて使い分けることが重要です。以下をご参照ください。
| 日本語 | 英語表現 | ニュアンス・備考 |
|---|---|---|
| 規程 | regulations, rules, code, policy | 一連の条項・文書全体を示す |
| 規定 | provision(s), clause(s), stipulation(s) | 個別の条文・定めを示す |
例えば「旅費規程」は “Travel Expense Regulations”、「第5条の規定」は “provision of Article 5” のように訳されることが多いです。英語でも「規程=multiple clauses collected」、 「規定=single clause or provision」という区別感が出ています。文書を英訳・国際調整する際には、この違いを意識することで誤訳を防げます。
規程の意味
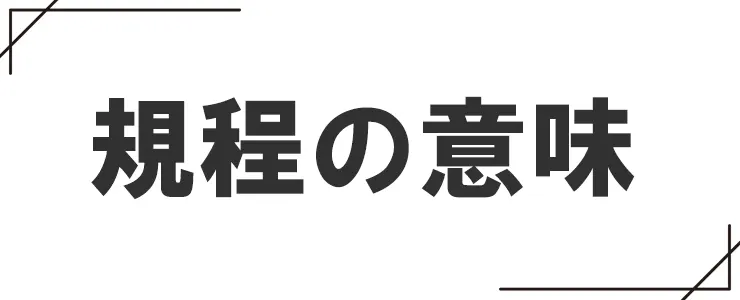
規程とは何か?
「規程(きてい)」とは、先述の通り「一定の目的のために定められた一連の条項の総体をいう」ものを指します。
つまり、例えば「社員の服務・勤務・福利厚生などを定めた文書群」を「服務規程」「就業規程」「安全衛生規程」といったように呼び、その文書全体を「規程」とみなすのです。
規程はどんな時に使用する?
実務上、「規程」は以下のような場面で使われることが多いです。
- 企業・組織が「仕組み」や「体系」を定めるための文書名として使用:例「旅費規程」「職務権限規程」など。
- 社内における「この文書を守れ」という全体的ルールを示すもの:例えば社内手続きや運営方針をまとめる。
- 「規程を定める」というよりも「規程を制定する」「規程を設ける」という表現になることが多い。実務で「規程する」という動詞は誤用とされるケースがあります。
規程の語源は?
語源的には、「規(く)=規(きまり)」「程(ほど・ていど)=基準・段階」を組み合わせた言葉と考えられ、もともとは「決まりの程度・尺度を定めるもの」という意味合いが背景にあります。
法令用語辞典にも、「一定の目的のために定められた一連の条項の総体」という定義が記載されており、語義として「まとめられた体系であること」が強調されています。
規程の類義語と対義語は?
類義語・対義語を整理しておくことで、言い換えや文書作成時のバリエーションが増えます。
| 語 | 類義語 | 対義語 |
|---|---|---|
| 規程 | 社内ルール、体系規則、ポリシー(policy) | 規定(個別条文) |
たとえば「組織運営規程」という言い方を「組織運営ポリシー」と言い換えることも可能です。ただし、ニュアンスとして「ポリシー」がもう少し概念的・抽象的になるため、厳密な「規程」の意味を求める場面ではそのまま「規程」を使うのが無難です。
規定の意味
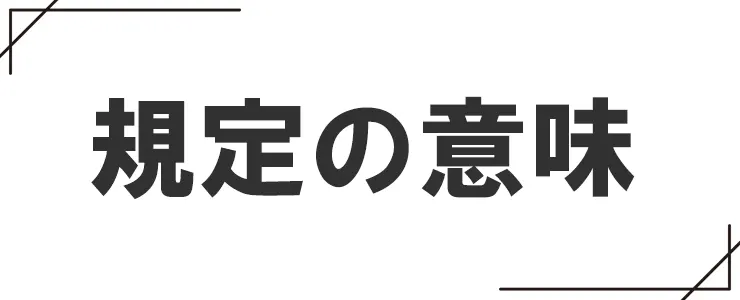
規定とは何か?
「規定(きてい)」とは、「物事を一定の形に定めること、またその定めた内容。法令の個々の条文。」という意味があります。
つまり、「第○条の規定」「この規定により」というように、「何らかの定め・条項・内容」を指す言葉として用いられます。
規定はどんな時に使用する?
実務上、「規定」は以下のような場面で使われることが多いです。
- 法令・社内規程・契約書の中の「第○条」「項」「号」といった個別の条文を示す:例「第5条の規定に従う」「本規定に基づく支給」など。
- 「規定する」という動詞を伴って、「○○を規定する」という表現で使われることが多い。
- 文章中で「この規定」「当該規定」「各規定」という形で細かな決まりや定めを指す。
規定の語源は?
語源的には、「規(きまり)+定(さだめ)」という組み合わせで、「事柄を定める/定められたもの」という意味が強いとされます。法令・条文の文脈で使われてきたため、「個別の定め」であるというニュアンスが定着しています。
規定の類義語と対義語は?
こちらも整理しておきましょう。
| 語 | 類義語 | 対義語 |
|---|---|---|
| 規定 | 条項、条文、定め、規則(rule) | 規程(規定の集合) |
言い換えとして「当該条項」「本条文」「この定め」なども使えます。ただし、表現があいまいになると「規程」と「規定」の区別がつかなくなるため、どちらを指しているかを意識しておくことが重要です。
規程の正しい使い方・例文
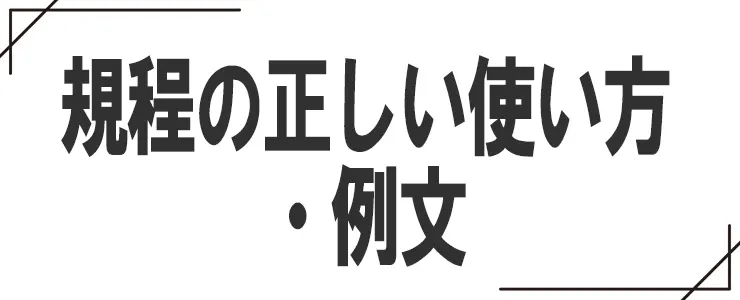
規程の例文
「規程」を使った頻度の高い例文
- 「当社の人事考課規程に基づき、査定を実施します。」
- 「安全衛生管理規程を改定し、新たな手順を全社員に周知しました。」
- 「旅費規程に定める宿泊費の上限額を確認してください。」
- 「職務権限規程を制定し、各部署の責任範囲を明確にしました。」
- 「情報セキュリティ規程に則って、社内データの取扱いを徹底します。」
規程の言い換え可能なフレーズ
「規程」の言い換えとして使えるフレーズ
- 制度(制度規程)/仕組み
- ルール集/体系ルール
- 社内ポリシー(company policy)
- 文書化された内部ルール
ただし、「制度」や「ポリシー」は「規程」という語が持つ「条文の集まり」や「制度的体系」というニュアンスとは若干異なるため、完全な言い換えではない点に留意してください。
規程の正しい使い方のポイント
使い方のポイント
- 文書名や体系を示す場合には「○○規程」という形で用いる。例:「就業規程」。
- その文書の中の個別条項を示す場合には「規定」を用いる。例:「第3条の規定」。
- 「規程する」という動詞は避け、「制定する/設ける/改定する」などを使う。
- 社内文書作成や法務文書作成時には、用語のブレを防ぐため、「規程」「規定」の定義を明確にしておくと安心です。
規程の間違いやすい表現
よく見られる誤用例
- 「第○条の規程」という表現(正しくは「第○条の規定」)。
- 「○○を規程する」という動詞表現(一般的には誤用) 。「○○を規定する」「○○を定める」が適切。
- 文書名として「給与規定」としているが、内容が条項の集合を指している場合は「給与規程」とすべきという指摘。
規定の正しい使い方・例文
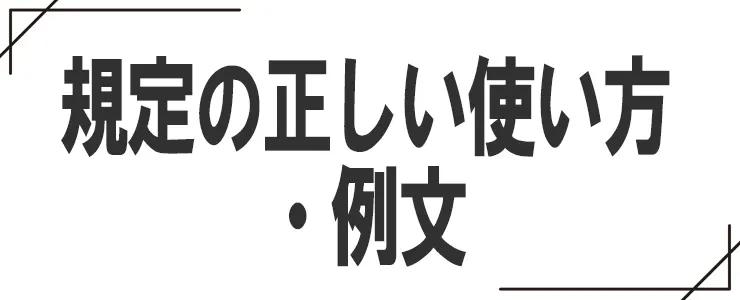
規定の例文
「規定」を使った頻度の高い例文
- 「この就業規則第5条の規定に基づき、休日出勤手当を支給します。」
- 「会議資料の提出期限は本規定によって定められています。」
- 「社内ポリシー第3項の規定では、在宅勤務を認める条件を明記しています。」
- 「契約書の第10条第2号の規定に違反した場合、罰則が適用されます。」
- 「報酬の支払いは当該規定に従うものとします。」
規定の言い換え可能なフレーズ
「規定」の言い換えとして使えるフレーズ
- 条項/条文
- 定め/規則
- 項目/規則文
- ステートメント(statement in a contract)
例えば「この条項」「当該条文」「本定め」なども「規定」の意味合いで使われることがあります。
規定の正しい使い方のポイント
使い方のポイント
- 個別の条文・定めを指す場合には「規定」を使う。例:「第2条の規定」。
- 「規定する」という動詞を正しく用いる。例:「手続きについて規定する」。
- 文書全体を指す場面では「規程」を使うことが多いため、切り替えを意識する。例えば「安全衛生規程」という名称の中の「第4条の規定」というように使い分ける。
規定の間違いやすい表現
誤用されがちな表現
- 「この規定を規程と呼ぶ」というような用法(混同を助長する)
- 「規程する」という動詞表現(誤用)
- 書類名として「○○規定」としているが、実態として条項の集合である場合、「○○規程」がより適切。例えば「旅費規定」→「旅費規程」など。
まとめ:規程と規定の違いと意味・使い方の例文
本記事では、「規程」と「規定」の違いを、意味・語源・英語表現・使い分け・例文という観点から詳しく解説しました。
改めて要点を整理します
- 「規程」=一連の条項・文書全体を指す。名称として「○○規程」が多い。
- 「規定」=個別の条文・定めを指す。「第○条の規定」「〜を規定する」の形で使われる。
- 英語では “regulations / rules / code” が「規程」、 “provisions / clauses / stipulations” が「規定」に相当するニュアンスを持つ。
- その使い分けを意識することで、文書作成・法務チェック・社内ルール策定の際に誤用を防げ、信頼性の高い文章になります。
ぜひ、日常のビジネス文書・契約書・社内規程作成・校閲の際には「規程」と「規定」の使い分けに気を配り、適切な言葉遣いを心がけてください。
参考文献・引用