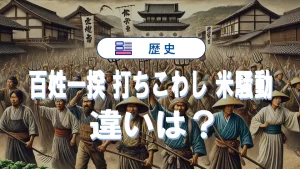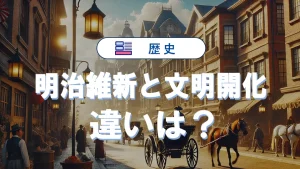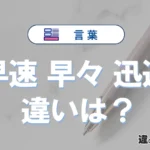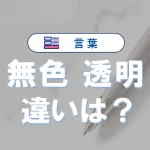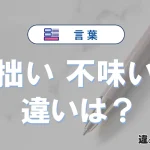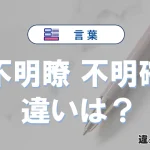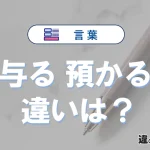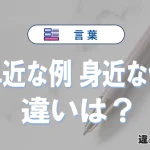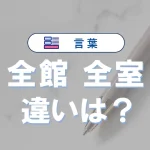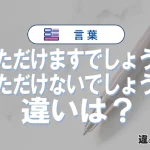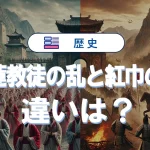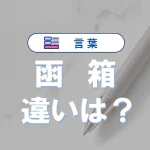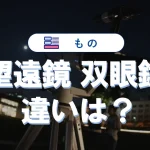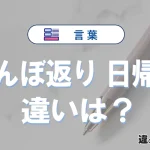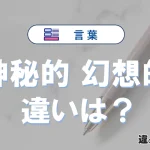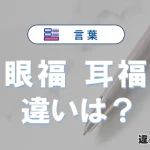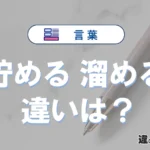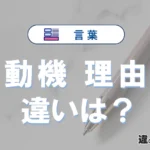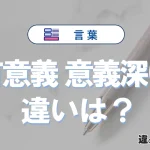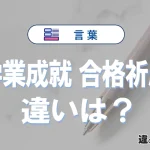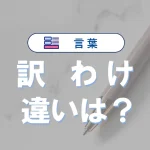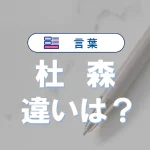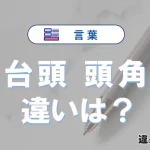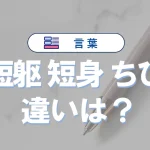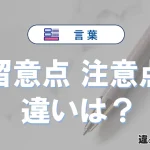「治外法権」という言葉を聞いたことがあると思います。歴史の授業やニュースで登場しますが、具体的な意味を理解している人は意外と少ないようです。この制度は、外国人や特定の施設に対してその国の法律が適用されない仕組みのことを指します。例えば、日本にある外国の大使館は、日本の警察が自由に立ち入ることができず、まるで「別の国」のように扱われます。これが治外法権のわかりやすい例ですね。
かつて日本では、外国人が日本の法律ではなく自国の法律で裁かれる「領事裁判権」も認められていました。しかし、これは不平等な制度として批判され、明治時代に撤廃されています。現在、日本において治外法権が認められているのは、大使館や国際機関の施設などに限られているのです。
この記事では、治外法権の意味や使い方をわかりやすく簡単に解説し、領事裁判権との違いや現在の日本の状況についても詳しく説明しますね。
- 治外法権とは何か、その具体的な意味や使い方
- 領事裁判権との違いと、その歴史的背景
- 日本における治外法権の現在の状況と適用範囲
- 治外法権が撤廃された理由とその影響
目次
治外法権をわかりやすく簡単に解説

治外法権とはどんな意味?
治外法権とは、ある特定の外国人や場所について、その国の法律を適用できないという制度のことです。簡単に言うと「自分の国の法律が通じない場所や人」を意味します。主に外国の大使館や領事館がその対象です。
この制度がある理由は、外交官や外国の施設が任務を自由に行えるようにするためです。ただし、治外法権を利用して法律の目を逃れようとするケースが起こり得る点が問題視されることもあります。
身近な例えで理解しよう

例えば、東京にあるアメリカ大使館は日本国内にありながらも、日本の警察や法律が自由に及ばない「アメリカの領土」のように扱われています。もし、大使館の中でトラブルが起きても、日本の警察が勝手に入って取り締まることはできません。
このように、大使館は「小さな外国」のような存在であり、これがまさに治外法権の分かりやすい例と言えるでしょう。ただし、だからといって大使館であれば何でも許されるわけではなく、国際的なルールに従う必要があります。
治外法権の使い方を解説
治外法権という言葉は日常会話で頻繁に使われることはありませんが、外交問題を説明するときや、海外ニュースを解説するときによく使われます。例えば、「大使館内は治外法権が認められているため、警察は自由に立ち入れない」という表現が一般的です。
治外法権は本来、外交を円滑に進めるためのものであって、悪用されることは許されません。使う際は、このような目的を正確に理解し、誤解を招かないよう注意が必要です。
「認める」とは具体的に何か

治外法権において「認める」とは、ある国や国際社会が特定の施設や人に対し、自国内の法律を適用しないことを公式に許可することです。この許可は主に条約や国際協定によって行われます。
例えば、日本がアメリカ大使館に治外法権を認めるということは、日本政府が公式に「アメリカ大使館内では日本の法律を適用しない」と約束することを指します。ただし、治外法権の対象が法律違反や犯罪行為を行った場合には、外交上のトラブルに発展する恐れがある点を認識しておきましょう。
領事裁判権との違いは?
治外法権とよく混同されるのが「領事裁判権」です。この二つの違いは明確で、治外法権が「特定の場所や施設に法律が及ばない」ことを指すのに対し、領事裁判権は「自国民が外国で起こした事件を、その国の法律ではなく自国の法律で裁判できる権利」のことです。
例えば、かつて日本で外国人が犯罪を起こした際、日本の法律ではなく外国の領事が裁判を行った歴史があります。現在、日本には領事裁判権は存在しませんが、治外法権は外国大使館などに対して引き続き認められています。
日本の現在から治外法権をわかりやすく

日本はいつ撤廃したのか?理由は?
日本が治外法権(領事裁判権)を撤廃したのは1894年の日英通商航海条約締結のときです。日本は明治初期、外国と結んだ不平等条約により治外法権を認めざるを得ませんでしたが、明治政府は近代化を進め、国力を高めることで条約改正を目指しました。
その努力が実り、日本が自国で公平に裁判を行えることを諸外国が認めたため、治外法権は廃止されました。ただし、撤廃には数十年もの外交努力が必要だったことは、覚えておくべきでしょう。
現在の日本に治外法権はある?

現在、日本国内に治外法権が完全に無いわけではありません。実際、日本にある外国の大使館や領事館には治外法権が適用されており、日本の警察や裁判所が自由に介入することはできません。
ただし、これには外交上の安全を保つ目的があり、各国がお互いに同じルールを守っているためです。一方、大使館以外の日常生活で治外法権が認められる場所は存在しないため、一般の生活にはほとんど影響がありません。
治外法権が認められるのはどこ?
治外法権が認められている場所は主に各国の大使館や領事館、国際機関の本部、軍事基地などです。日本で言えばアメリカ大使館や各国の領事館などが具体例となります。また、国際連合(国連)の本部があるニューヨークでは、国連敷地内にアメリカの法律が及ばず、治外法権が認められています。
ただし、治外法権が認められているからといって無法地帯になるわけではなく、国際法や条約による一定のルールに基づいて運用されています。
世界での治外法権の例え

世界の治外法権の例として分かりやすいのが、イタリアのローマにあるバチカン市国です。バチカン市国は世界最小の国家ですが、ローマ市内に位置しているにもかかわらず、イタリア政府の法律や権力が及ばない独立国家です。
これは、バチカンが国として国際的に認められているからこそ可能なことで、治外法権が国家レベルで適用されている特別な例です。このように、治外法権の考え方は単なる施設や人に限らず、独立した国家間でも存在します。
治外法権が残る国や地域は?
現在も治外法権が問題となる地域としては、中東やアフリカの一部の地域が挙げられます。これらの地域では、外国の軍事基地や国際的な組織の施設に治外法権が認められています。
例えば、中東諸国に駐留するアメリカ軍基地では、基地内においては現地の法律ではなくアメリカの法律が適用されます。ただし、治外法権の存在は地元住民との摩擦や外交上の緊張を生むこともあるため、運用には慎重さが求められるという点に注意が必要です。
治外法権をわかりやすく簡単に解説|Q&A

Q1. 治外法権と領事裁判権が撤廃されたのはいつか?
日本は1894年に日英通商航海条約を結び、治外法権(領事裁判権)を撤廃した。この条約により、外国人が日本国内で日本の法律に従うことが正式に決定した。完全実施は1899年である。
Q2. 治外法権を無くした人は誰ですか?
治外法権の撤廃を実現したのは、当時の外務大臣・陸奥宗光である。彼は1894年に日英通商航海条約を締結し、日本の法制度の独立を確立した。その後、他国とも条約を改正し撤廃を進めた。
Q3. 外交特権とはなんですか?
外交特権とは、外交官が滞在国で特定の法的制約を受けず、公務を円滑に遂行できる権利である。例えば、外交官の逮捕や訴追を免除し、大使館が治外法権の対象となることが含まれる。
Q4. 陸奥宗光は投獄されたのですか?
陸奥宗光は明治政府初期、自由民権運動に関与し、1878年に政府転覆計画の疑いで投獄された。その後、出獄して外務大臣となり、不平等条約改正に尽力し、日本の外交独立に貢献した。
Q5. 不平等条約を結んだのは誰ですか?
不平等条約は、江戸幕府の井伊直弼が1858年にアメリカと結んだ日米修好通商条約が最初である。その後、イギリス・フランスなどとも同様の条約を締結し、日本は治外法権を認めさせられた。
治外法権をわかりやすく簡単に解説|まとめ
- 治外法権とは外国人や施設に自国の法律が適用されない制度
- 外国の大使館や領事館が主な対象
- 外交活動を円滑に進めるために認められている
- 東京のアメリカ大使館がその具体的な例
- 大使館内で事件が起きても日本の警察は自由に介入できない
- 治外法権が認められる場所は「小さな外国」と例えられる
- 日本国内でも現在、大使館などに治外法権が認められている
- 治外法権の許可は国際条約に基づいている
- 悪用すれば外交問題になるリスクがある
- 領事裁判権は「自国の法律で裁判を行う権利」で治外法権とは異なる
- 日本の治外法権(領事裁判権)は1894年に撤廃された
- 治外法権撤廃は日本の近代化と外交努力の結果である
- 世界的な例ではバチカン市国が治外法権の代表例である
- 中東の米軍基地にも治外法権が認められている
- 治外法権は外交安全を守る一方、摩擦や問題も起こりうる