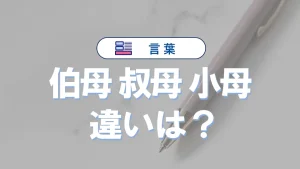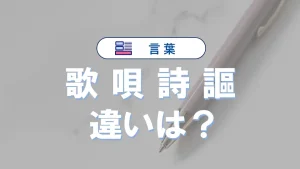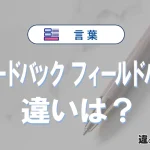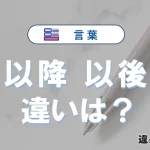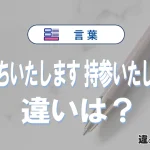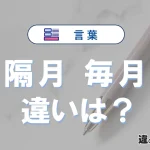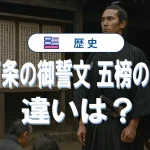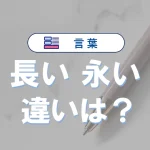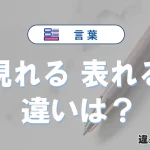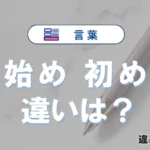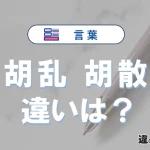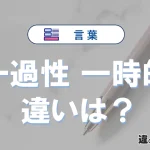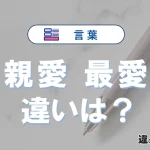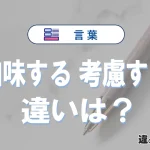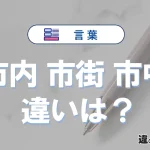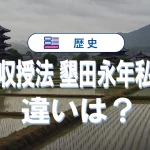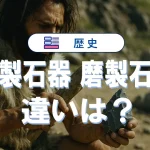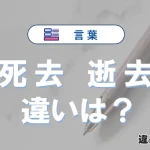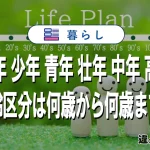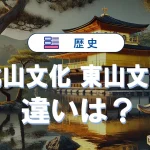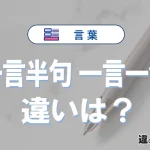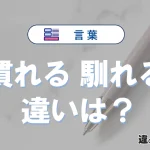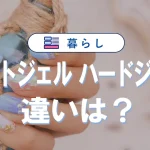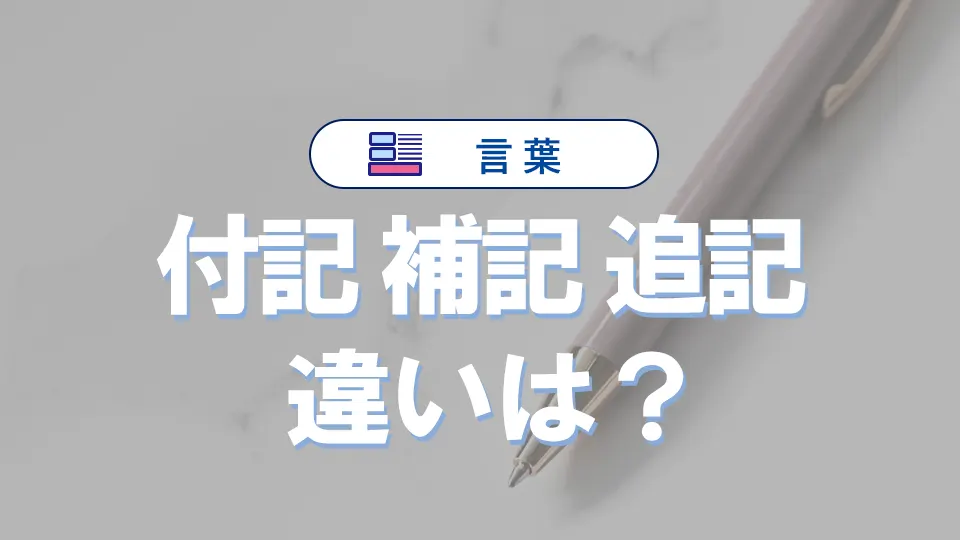
「付記」「補記」「追記」の違いを正しく理解し、意味・語源・類義語・対義語・言い換え・使い方・例文を押さえることは、書類やメール・報告書・ブログ記事など、ビジネス/日常の文章表現でとても有用です。日本語には「本文を書いたあとに何かを加える」というシーンで似たような言葉が複数あり、「付記」「補記」「追記」の使い分けで迷う方も少なくありません。例えば「この仕様書には補記があります」「報告書に付記を付しました」「メールに追記があります」といった具合です。
本記事では、各語が持つ微妙なニュアンスの違いや適切な使用場面を「意味」「語源」「使い分け」「例文」で整理しますので、文章表現力・日本語運用力を高めたい方には必読です。
この記事を読んでわかること
- 付記・補記・追記それぞれの意味・語源・使い方が理解できる
- 付記・補記・追記の違いや使い分けが明確になる
- 各語に対する適切な英語表現や言い換えがわかる
- 例文を通して、正しい使い方・間違いやすい表現が身につく
目次
付記と補記と追記の違い

結論:付記と補記と追記の意味の違い
まず結論として、以下のように整理できます。
| 用語 | 概要 | 主なニュアンス |
|---|---|---|
| 付記 | 本文に付け加えて書き記すこと。内容が本文と直接関連しているかどうかを問わない。 | 補助的・添付的な書き足し |
| 補記 | 本文で不足しているところを補って書き記すこと。本文の内容に対して「補う」目的。 | 不足を埋める・補強する書き足し |
| 追記 | あらかじめ本文を書き終えた後、後から付け加えて書き足すこと。漏れや後出の記述を含む。 | 後付け・追加・書き漏れのフォロー |
このように「付記」「補記」「追記」は重なりつつも、使われる文脈・ニュアンスが異なります。「付記」は比較的汎用で「付け加えた」感、「補記」は「補う」ニュアンス、「追記」は「後から付け足す」の感に重点があります。
付記と補記と追記の使い分けの違い
使い分ける際のポイントを整理します。
- 付記:本文の補足・参考・添付情報として用いるとき。「参考資料を付記しました」「注記を付記しておきます」など、本文とは別に添える感覚。
- 補記:本文に書き切れなかった、または不足していた部分を補うために用いるとき。「契約書に補記事項を設ける」「報告書に注意事項を補記する」など、文章の十分性を担保する目的。
- 追記:本文を書き終えたあとで、漏れ・付け足し・補足を行いたいとき。「メールの最後に追記があります」「前回掲載記事に追記しました」など、時間的な「あとから」要素が強い。
また、場面によってはフォーマル度や相手との関係も影響します。たとえばビジネスメールで「追記:」という表記はややカジュアル・軽めに見えるため、目上の相手やフォーマルな書類では「補記」「付記」の方が無難、という指摘もあります。
付記と補記と追記の英語表現の違い
英語表現も場面に応じて使い分けられます。
- 付記(fuki/adding additional note) → “append”, “add note”, “addendum”など。
- 補記(hoki/supplementing missing part) → “supplement”, “add supplementary note”, “supplementary entry”など。
- 追記(tsuiki/post-script or afterthought) → “postscript (P.S.)”, “additional note”, “add later”など。実際「P.S.」という形で「追伸」「追記」の英語語が紹介されることもあります。
例えば、「追記:」「P.S.」はまさに「本文後に付け加える」というニュアンスが英語圏でも近いです。
付記の意味
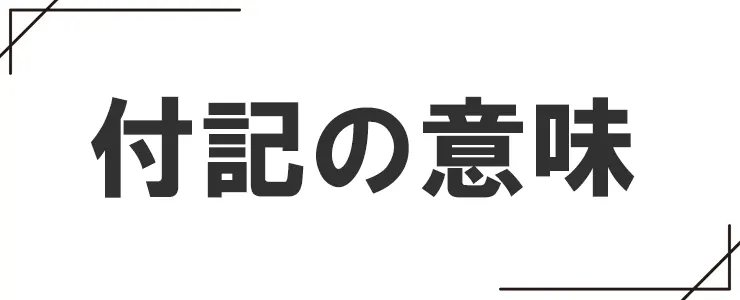
付記とは何か?
「付記」(ふき・附記)は、「本文に付け加えて書き記すこと。また、その書き加えた部分」を意味します。
つまり、本文とは別枠で「付け加えた情報」「補足した内容」「参考として添えた記述」を「付記」と称します。例えば報告書末尾に「付記:本件の参考資料として〇〇を添付します」といった形です。
付記はどんな時に使用する?
使用場面として、次のようなケースがあります。
- 本文の主たる内容は完結しているが、補助的に情報を付加したいとき。
- 資料・報告書・論文などで、本文に含めなかったが知っておいてほしい注釈・補足を書き添えるとき。
- 書籍や巻末資料で、本文とは別に「付記」として追加したものを設けるとき。
たとえば、「この論文では触れなかった関連文献を付記しておく」「別紙資料を付記する」「付記登記を行う」などです。 「付記」には、必ずしも本文と厳密に主題連動している必要はなく、関連する情報を添えるというゆるやかな役割があります。
付記の語源は?
「付記」は「付(つ)け加える」「記(しるす)」の漢字から構成されており、「本文に“付”けて“記”す(書き記す)」という意味合いです。古くは「附記」とも書かれ、「付」の「附(つ)く」という意も含まれています。国語辞典には「本文または主たる事項につけ加えて書くこと」 と記されています。
語源的には「記録する文章に対して補助的に付け足す」という文書運用上の動詞・名詞変化と捉えられます。
付記の類義語と対義語は?
類義語としては、例えば次があります。
- 補記(ほき) — 不足部分を補って書き足すこと。本文に対して補助的・補足的書き足し。
- 追記(ついき) — 本文を終えてから付け加えること。
- 添記、付載、書き添える、付言 など
対義語としては、書き足す・付け加えるという動作に対して「削除」「省略」「省く」「省略する」などが挙げられます。例えば「付記事項はありません」という記述は、本来書き足すものがないことを示します。
補記の意味
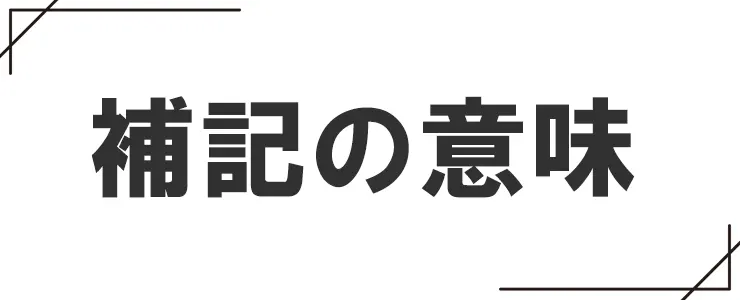
補記とは何か?
「補記」(ほき)は、「不足しているところを補って書き記すこと」あるいは「その書き足した記述」を指します。
つまり、本文だけでは情報的に足りなかった、説明が不十分だった、補足が必要だったという場合に、追記的・補足的に書き加えるものを「補記」と言います。
補記はどんな時に使用する?
典型的な使用場面は以下の通りです。
- 報告書や論文で、本文中には記載できなかったが読者に知っておいてほしい補助的説明や注意事項を追記したいとき。
- 契約書・議事録・会議記録などで、後から判明した重要事項を「補記事項」として記載する場合。
- 書誌記述(図書・目録作成)において、資料に表示されていないが補記すべき事項(出版社所在地、発行年補記など)を付け加える場面。
補記は「本文を補う」役割であり、単なる添え物ではなく「あるべき説明を補完する」意味合いが濃いのが特徴です。
補記の語源は?
「補記」は「補(おぎなう・補う)」「記(しるす)」から構成されており、「記録(記)を補(おぎな)って書き記す」ことを意味します。つまり、「正本文だけでは十分ではないから、補って記す」という動作を表す語です。学術・書誌的な文脈では「補記事項」という形で用いられることが多く、目録作成の用語としても定義があります。
補記の類義語と対義語は?
類義語:
- 付記 — 本文に付け加えるという意味では共通。しかし「補記」に比べると「補う」ニュアンスが弱め。
- 追記 — 後からの追加という点で似るが、必ずしも「補う」意味ではない。
- 補足 — 「説明を補う」という意味で近接。
対義語:
- 省略、削除、欠記(けっき)など「書き足さない・記述を省く」方向。
文脈によっては「省記」「省略記」などが使われることもあります。
追記の意味
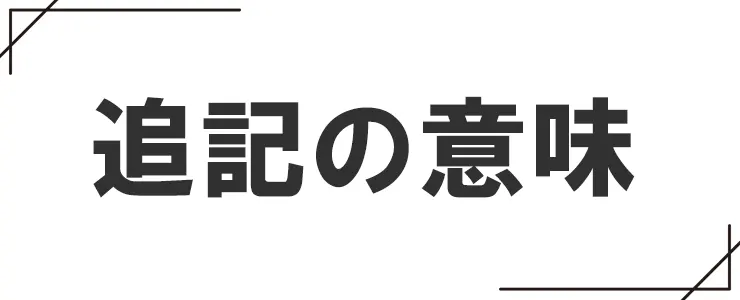
追記とは何か?
「追記」(ついき)は、「後から付け加えて書くこと」あるいは「その書き足したもの」を指します。
つまり、文章を一度完結させたうえで、「あとからさらに書き足す」行為が「追記」です。例として「メール本文の最後に追記:〜」という使い方が挙げられます。
追記はどんな時に使用する?
次のような場面が典型です。
- 書き出した内容に漏れがあった、あるいは新たな情報が入ったため、本文後に追加したいとき。
- メール・手紙・ブログ記事などで「先ほど送った内容に補足があります」という意味で使うとき。
- 書類の末尾に「追記事項:…」と記載し、先に記載した内容に対して追加で情報提供するとき。
ただし、ビジネス文書では目上の人向けには避けた方が良い表現という指摘もあります。
追記の語源は?
「追記」は「追(おって・つい)」「記(しるす)」の語から成り、「後から記す」意味を直接含みます。書き終えた文章に対して「追って記す」という動作をそのまま反映した語です。英語の「postscript (P.S.)」も同様に「post-script=書いた後に加える文」という語源を持ちます。
追記の類義語と対義語は?
類義語
- 付記 — 書き足すという点では同様だが、時間的な「あとから」という強調が薄い。
- 補記 — 本文を「補う」というニュアンスが強いため、時間的な「あとから」という作用を必ず含まない。
- 追伸 — 手紙での「P.S.」的用法。文章中の追記とほぼ重なるが、形式や文脈(手紙)に特化。
対義語
- 先記、予記、前記、前文など「あとからではなく先に記す」状態。
- 削除、取り下げ、欠記など「追記しない」「書き足さない」方向の言葉。
付記の正しい使い方・例文
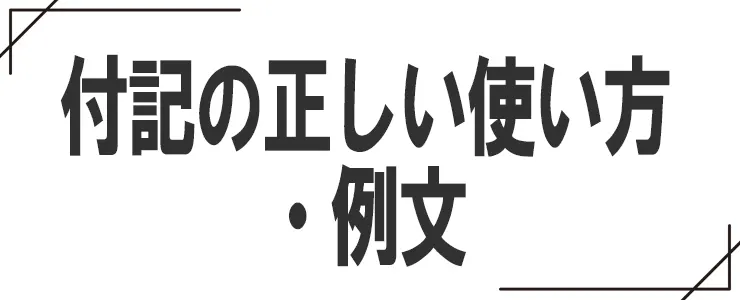
付記の例文
使用頻度が高く、汎用性のある例文を5つ掲載します。
- 本報告書の内容に関しては、別紙資料を付記しておりますので、ご確認ください。
- プロジェクト完了後のフォローアップとして、関連案件の進捗状況を付記しました。
- 商品仕様書末尾に、サンプルデータを付記しておきます。
- 論文の参考資料として、過去の研究を付記しておきます。
- 契約書において、付則事項を付記した上で押印をお願い申し上げます。
付記の言い換え可能なフレーズ
- 「追記」
- 「添記」
- 「付載」
- 「書き添える」
- 「加え記す」
ただし、この中にはニュアンスが微妙に異なるものもあるため、文脈によって適切な語を選ぶことが大切です。
付記の正しい使い方のポイント
- 本文が主たる内容をきちんと伝えており、かつ「補足」「添付」「参考」などの目的で書き加えるとき「付記」が適しています。
- 書き加える内容が本文の主題と大きくずれていても、「添付・付加」目的であれば許容されます。
- フォーマルな文書・報告書などでは、末尾に「付記:」や「付記事項:」と見出しを付けると分かりやすいです。
- 書き加えの内容が「後から発生した新情報」や「書き漏れ」などの場合は、「追記」に切り替えた方がニュアンスが適切です。
付記の間違いやすい表現
- 「本文を書き終えた後だが、書き漏れなので付記しました」→この場合「追記」が適切。
- 「不十分だったので書き足した」→この場合「補記」が適切。
- ビジネスメールで「付記:」とだけ書き添えるとやや形式張り過ぎに感じられる場合あり。相手や文章の格に応じて言葉遣いを調整しましょう。
補記の正しい使い方・例文
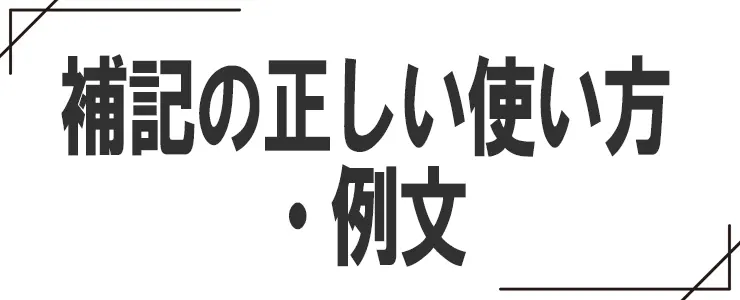
補記の例文
以下、実用的な例文を5つ掲載します。
- 契約書第3条に記載漏れがあったため、補記として別紙を添付いたします。
- 議事録本文には記載できなかった決議事項を、末尾に補記しました。
- 出版目録作成時、発行年が未記載だったので発行地を補記しました。
- 報告書の注記欄に、リスク管理項目を補記しております。
- プロジェクト仕様書にて説明が不十分だった部分を、補足資料として補記しました。
補記の言い換え可能なフレーズ
- 「追記」
- 「付記」
- 「補足記載」
- 「加記」
- 「追補」
※ただし、「追記」や「付記」とのニュアンスの違いを意識して選びましょう。
補記の正しい使い方のポイント
- 本文の記述だけでは情報が不足している・説明が足りないと判断される場合、「補記」を用いて補完的な記述を行います。
- 内容の漏れや説明未到達といった否定的な前提がある場合、「補記」が最適です。
- フォーマルな契約・報告・目録作成等の場面では「補記事項」という見出しで使われることが多いです。
- 「追記」と混同されがちですが、時間的な「後から付ける」というニュアンスよりも「補う・補完する」という目的を意識してください。
補記の間違いやすい表現
- 「本文を書き終えて、あとで思いついたので補記しました」→この場合「追記」が適切。
- 「本文に書いたが少し加筆しました」→この場合「加筆」が適切。
- 「参考資料を別紙にしました」だけでは「付記」か「補記」か区別しにくいため、目的(添付か補足か)を明確にすることが重要です。
追記の正しい使い方・例文
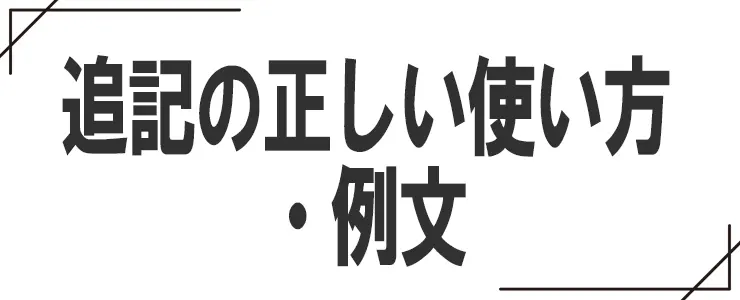
追記の例文
使用頻度が比較的高い例文を5つ示します。
- メール本文の最後に追記:会場には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。
- 前回の記事に追記として、新たに判明したデータを加えました。
- 書類を送付した後、別途追記がありますのでご確認ください。
- 報告書に掲載漏れがあり、末尾に追記事項を記載しました。
- ご検討ありがとうございます。追記:お見積りは9月末まで有効です。
追記の言い換え可能なフレーズ
- 「P.S.」
- 「加記」
- 「後記」
- 「補足記」
- 「追補」
ただし、「P.S.」はメール・手紙の文脈、「後記」は書籍・論文の末尾という文脈での使用が多いため、用途に応じて使い分けを。
追記の正しい使い方のポイント
- 本文を書いたあと「追加」「修正」「訂正」などを行いたい場合、「追記」を使うと適切です。
- メール・手紙・ブログ記事など、時間的・順序的に「あとから加える」場面で活躍します。
- ビジネスシーンでは、件名に「追記あり」や「追記:」と入れることで受け手に「追記がある」という認識を促せます。
- ただし、目上の方に対して「追記」だけで締めると「手間を省いた=失礼」と捉えられることがあるため、フォーマルな場では文末に丁寧な挨拶を付けるなど配慮が必要です。
追記の間違いやすい表現
- 本文を書き始める前に補足情報を先に書いて「追記」と題する → 「追記」の文脈(後から)に合わない。
- 本文の説明が不十分だったため補完した → 「補記」が適切。
- 本文を修正・書き直した → 「加筆」「修正」が適切。
- 手紙末尾で「追記:」と書いたが、内容が本文と関係なく雑談的だった →「追伸」の方がニュアンスに合う。
まとめ:付記と補記と追記の違いと意味・使い方の例文
本記事のまとめとして、以下のように整理できます。
- 付記:本文に付け加えて書き記す。「添付・参考・補助的」な書き足し。
- 補記:本文で不足・説明不足だったところを補って書き記す。「補足・補完」の書き足し。
- 追記:本文を書き終えた後、後から付け加えて書き足す。「あとから」の書き足し。
それぞれ語源・ニュアンス・用途が微妙に異なりますので、文章を書く際には「何を」「どの順で」「どの目的で」書き足すのかを意識して言葉を選ぶと、より洗練された表現になります。
例文を通じて、実際の運用イメージもつかんでいただけたと思います。書類・メール・報告書・ブログ記事などで、適切に「付記/補記/追記」を使い分けましょう。