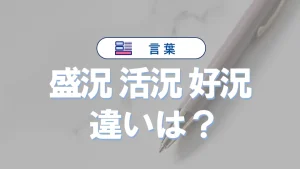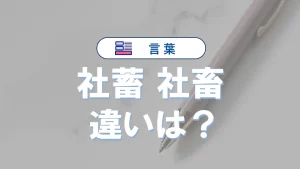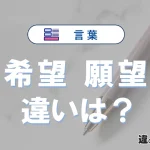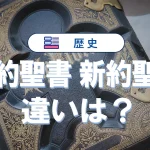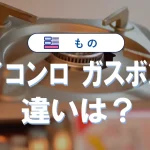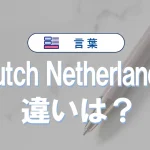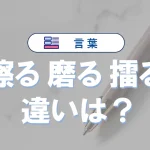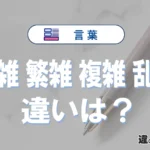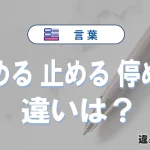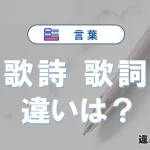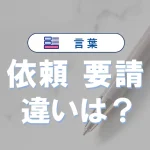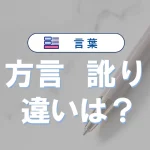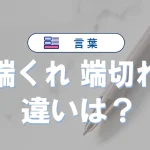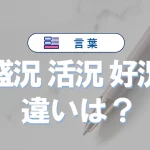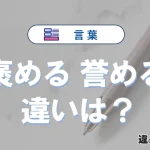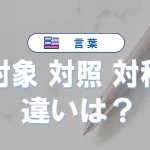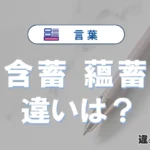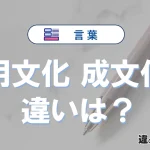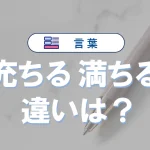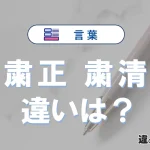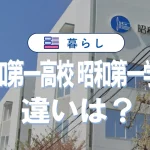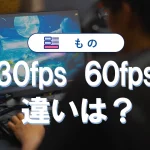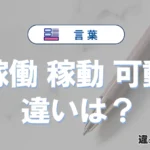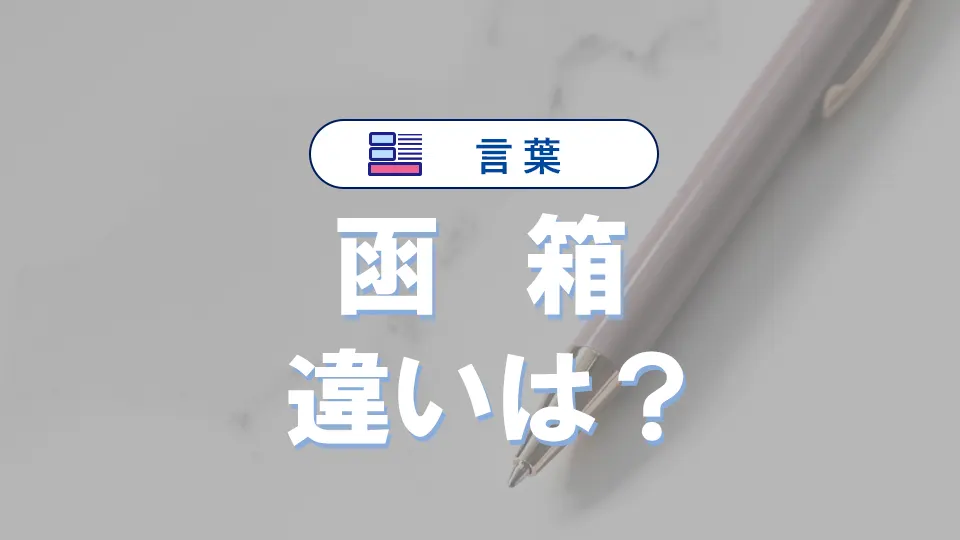
「箱」と「函」はどちらも「はこ」と読み、物を入れる容器を指す漢字ですが、日常ではほとんど「箱」が使われ、「函」は限定された語彙や地名、専門分野で見られる漢字です。本記事では、「箱」と「函」の違いを明確にしつつ、意味・歴史・使い分け・語源や例文を包括的に解説します。結論をあらかじめ述べると、「箱」は一般的な容器として広く使われ、「函」は格式性・書簡性・限定的用途を帯びた「はこ」を表す語と考えるのが妥当です。
本記事では、以下の構成で深掘りしていきます。
- 「箱」と「函」の基本的な違い
- 「函」の意味と用途
- 「函」の歴史と変化
- 発展的な用語・関連語
- 「箱館」と「函館」の漢字表記とその背景
目次
「箱」と「函」の基本的な違い
「箱」とは?
「箱(はこ)」は、一般に物を収めたり保管したりするための容器を指す基本語です。材質を問わず、木・紙・プラスチック・金属など様々な素材で作られた蓋付き・蓋なし・引き出し型など形状も多様です。
- 容器・入れ物としての汎用性が高い
- 日常語彙で圧倒的使用頻度
- 「空き箱」「箱詰め」「箱入り娘」などの熟語が豊富
- 蓋が別体(胴体とは別の蓋をかぶせる形)が多い
「箱」は、基本的に「蓋が独立していて被せるタイプ」「四角形に近い形」などを想起させ、広く一般物品の入れ物として使われます。
「函」とは?
「函(かん/はこ)」は、「箱」に比べてより限定された意味や用途を持つ漢字です。主に以下のような意味を含みます。
- はこ。物を収める入れ物。
- 手紙や文書を入れる文箱(ふばこ)。
- いれる、つつむなどの動詞的意味。
- 甲冑・武具を納める箱(古義)。
- 地名・熟語の構成要素。
また、「函」の文字形は、古代には矢を納める入れ物を象った象形文字とされ、蓋と胴体が一体になっているような設計を想像させるとも言われています。
「箱」と「函」の表記の違い
表記上、日常では「箱」のほうが圧倒的に多く用いられます。戦後の国語政策や常用漢字・当用漢字の影響で、「はこ」を表す漢字としては「箱」が標準化されてきたためです。
しかし、印刷・製本・出版業界、書籍保護用パッケージ分野では、「箱」と「函」を区別して使うケースがあります。例えば、差し込み式・被せ蓋形式の設計により、「函(差し込み式ケース)」と「箱(蓋を被せる形式)」を区別する業界慣行が見られます。
| 観点 | 「箱」の傾向 | 「函」の傾向 |
|---|---|---|
| 蓋の構造 | 胴体+別蓋(被せる形式) | 胴体と蓋が一体または差し込み式が多い |
| 用途の広さ | 日用品・商業用途全般 | 文書・書籍・限定用途 |
| 文字使用頻度 | 圧倒的優勢 | 限定的・専門語彙で使われる |
| 印象・格式 | 汎用・一般 | 格式高・文書性・専門的イメージ |
「函」の意味や用途
「函」の意味を辞書で確認する
辞書的には、以下のような意味が記されます。
- はこ。物を収める入れ物。
- 手紙や文書を入れる文箱(ふばこ)。
- いれる、包むなどの動詞的意味。
- 甲冑・武具を納める箱(古義)。
- 地名・熟語の構成要素。
また、字形・読み・異体字についても、次のような特徴があります。
- 画数:8画
- 部首:凵部
- 訓読み:はこ・いれる・よろい
- 音読み:カン
- 異体字に「凾」などがある(俗字)
「函」の一般的な用途とは
「函」が用いられる典型的用途を以下に挙げます。
- 書簡・郵便・文書関係
– 「投函」「封函」「私書函」「函送」など語彙で用いられる。
– 書類を入れる書函・文函のような用途。 - 出版・製本・書籍パッケージ
– 書籍を保護するハードケース(差し込み式ケース)を「函」と呼ぶことがある。
– 印刷業界で「函式箱(サック式函)」という用語がある。 - 地名・固有名詞
– 「函館」「函南」「銭函」など地名。
– 「函谷関」など歴史名字。 - 専門技術・工学用語
– 「潜函(せんかん)」など、基礎工法・構造用語。 - 典礼・贈答用具
– 宝物や貴重品を収める格式箱としての「函」。
「函」の歴史とその変化
「函」の歴史的背景
「函」の字は古代中国に由来し、甲骨文字・金文段階から、矢を納める器を象った字形が確認されるとの説があります。この意味が転じて「入れるもの」や「箱」に拡張されてきたと見られます。
日本でも、古代・中世には「箱」「函」「匣」「篋」など複数の漢字が併存しており、漢字文化圏で語彙との対応が変化するなか、「箱」が主流化し、「函」は限定用途に収斂してきた流れがあります。
江戸〜明治期以降、書簡文化や公文書制度の発展とともに「函」が郵便・通信・文書語彙で用いられるようになりました。さらに、戦後の漢字政策により「箱」が標準化され、「函」は限定語彙に残る傾向が強まりました。
また、手書き漢字では「函」が略字化して「了型」のような形で書かれることがあります。これは書写慣習の一環で、特に地名・看板などで見られる例です。
「函」にまつわる地域と地名
「函」を用いた地名・語彙の例は次の通りです。
- 函館(はこだて):北海道南部の都市。「箱館」とも旧表記されていた。
- 函南(かんなみ):静岡県東部の地名。
- 銭函(ぜにばこ):北海道・小樽近郊の地名。
- 函谷関(かんこくかん):中国古代の関所。
これら地名は、「箱/函」の字義・語感・時代性を反映して表記されてきたと考えられます。
「函」の変化と現代における役割
現代では、「函」は一般語としての使用頻度は低下していますが、次のような役割を保持しています。
- 出版・印刷・パッケージ分野で「函」を使った用語が残る。
- 地名・固有表記として「函館」などが残存する。
- 郵便・通信語彙で「投函」などが日常語として使われる。
- 古典書物や版元で伝統的表記として「函」が用いられることがある。
- 漢字文化論・比較論の題材として扱われる。
発展的な用語と関連情報
「通函」とは?
「通函(つうかん)」は、郵便・書簡を授受・回送するための箱・容器を指す語です。鉄道郵便時代には郵便物を輸送する入れ物として「通函」が用いられ、また企業内で文書を回す「通い函」という形式もあります。「通函」は「函」が伝統的に採用された代表例です。
「函」の書き方と正しい使い方
「函」を正しく書く・使うための注意点を以下に示します。
- 筆順・書き順:8画。正しい筆順を漢字辞典で確認する。
- 異体字・俗字「凾」など:正字は「函」。俗字「凾」は注意。
- 字体の簡略化(了型など):手書きでは略字化されやすい。
- 用途に応じた使い分け:日常物品=箱、文書・専門用途=函。
- 誤用注意:「函入れ」「函詰め」などは文脈判断を要する。
以下に、「箱」「函」の使い分けを示す例文を改めて掲載します。
「箱」を使った例文
- プレゼントは素敵な箱に包んで渡した。
- 段ボール箱を開けると中に本がいっぱい詰まっていた。
- 店先に空き箱を積み上げて、処分を待っている。
- このワインはオリジナルの木製箱に入っているから高級感がある。
- 子供が積み木で遊んで、箱を倒して中身が散らばった。
「函」を使った例文
- 書類をこの函に入れて郵便局へ持っていく。
- 古書は特別な布張りの函に収められて保存されていた。
- 君の手紙を投函したから、明日届くはずだ。
- この図録は差し込み式の函入りで、開閉がしやすい。
- 「函館」はもともと「箱館」とも表記された歴史を持つ地名である。
「箱館」と「函館」の関係
「箱館」の歴史的な役割
「箱館(はこだて)」という地名表記は、江戸時代から使われてきた旧表記です。松前藩時代から「箱館奉行所」など公的施設名にも用いられ、港町・交易拠点として発展しました。歴史的な古地図や文献には「箱館」の表記が多数見られます。
「箱館戦争」など明治維新期の事件名にもこの表記が用いられており、地名として「箱館」が標準であった時代が長く続きました。
「函館」の地名の由来
明治新政府の下で、地名整理・行政制度整備が進められた際、「箱館」表記から「函館」に改称されたとされます。歴史的背景として次のような論点があります。
- 「函」の字は公的・格式的な印象をもたらすため、地名としてふさわしいとの判断。
- 漢字表記の近代化・標準化政策により、旧来の表記を刷新する動きがあった。
- 「箱館」から「函館」への切り替えは、1869 年(明治 2 年)前後に行われたとの説。
ただし一部には「箱館」の表記も観光的用途や看板などで残されている場合もあります。現在は「函館」が正式な表記として使われています。
まとめ:「箱」と「函」の違い|意味や使い分け、語源や例文
本記事では、「箱」と「函」の違いを以下の観点から総括しました。
- 意味と語感:箱=汎用入れ物、函=文書性・限定性を帯びる語感
- 表記頻度と使い分け:箱が圧倒的使用、函は専門領域で残存
- 歴史と変遷:函は古代に起源し、書簡文化に結びつき、日本では箱が標準化された流れ
- 地名・固有表記:函館など、歴史・地域性を反映した表記
- 例文比較:箱・函の使用例で語感の違いを確認
総じて、「箱」は日常・汎用のはこ、「函」は格式・文書性・限定用途を帯びたはこ、と覚えておくと、誤用を避けつつ適切に選べます。