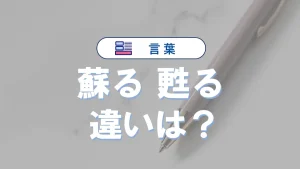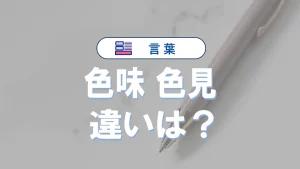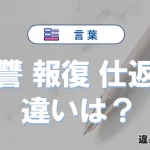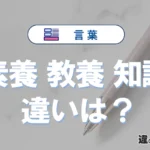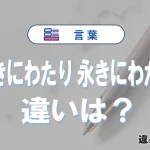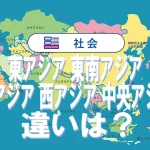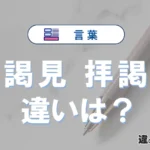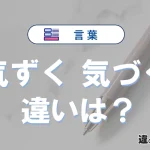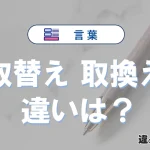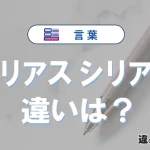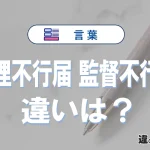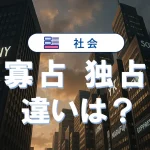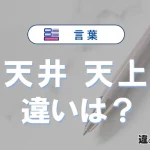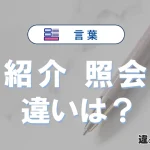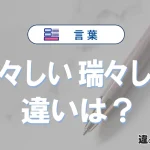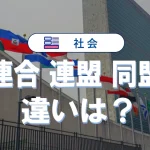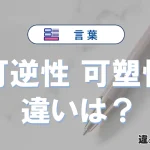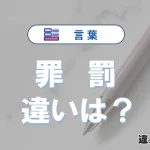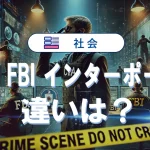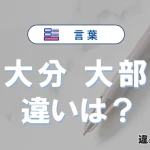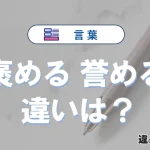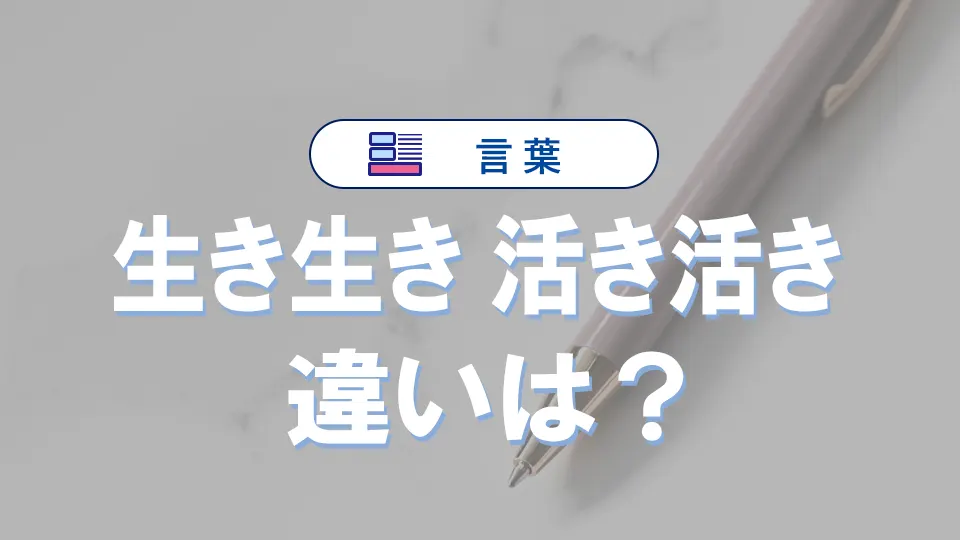
「生き生き」と「活き活き」という言葉は、どちらも「元気である」「活力にあふれている」といった意味を持ち、日常的にもよく使われる表現です。しかし、「生き生き」と「活き活き」の違い・意味・語源・類義語・対義語・言い換え・使い方・例文を整理してみると、使われる場面や漢字表記の背景に微妙な違いがあることがわかります。この記事では、生き生きと活き活きの違いや使い分け、英語表現まで詳しく解説していきます。
この記事を読んでわかること
- 「生き生き」と「活き活き」の意味と違いが理解できる
- それぞれの語源・類義語・対義語が整理できる
- 両者の正しい使い方・例文・言い換えフレーズが身につく
- 英語表現など、グローバルな視点での理解も深まる
生き生きと活き活きの違い
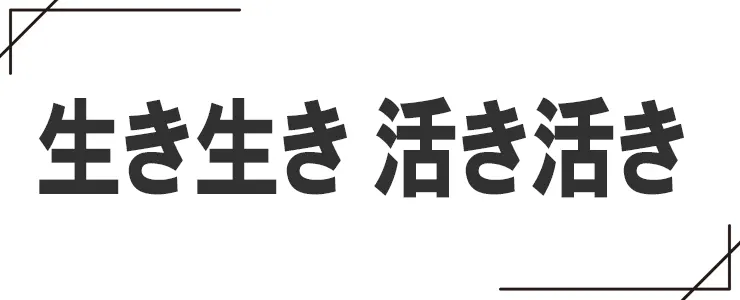
結論:生き生きと活き活きの意味の違い
まず結論から申し上げると、「生き生き」と「活き活き」の意味そのものに大きな違いはありません。どちらも「元気で、勢いよく、生命力や活力にあふれている様子」を表す言葉です。ただし、漢字表記の背景(「生き/活き」)や使用される場面、印象として微妙なニュアンスの違いが指摘されています。例えば、一般的には「生き生き」の方が常用漢字を使っており、文書やメディアで使われる機会が多いという点。また、語源やニュアンスから「生き生き=生命力・若々しさ」「活き活き=活動的・勢い」という整理もなされています。
生き生きと活き活きの使い分けの違い
具体的な使い分けのポイントは以下の通りです。
- 「生き生き」:生命の息吹や若々しさを感じさせる場面、「命がある」「存在感がある」「みずみずしい」などの意味が前面に出る場合に用いられます。
- 「活き活き」:活動・動き・エネルギー・勢いという意味合いをやや強めて用いる場合に使われることがあります。「動いて活躍している」「活動中である」などのニュアンス。
- ただし、現実にはこの使い分けが厳密に守られているわけではなく、両者を同じ意味合いで用いるケースも多々あります。
また、公用文・報道文などでは「生き生き」が用いられる傾向が強いです。これは「生き」が常用漢字である一方、「活き」が常用漢字外であるためです。
生き生きと活き活きの英語表現の違い
英語表現においては、「生き生き」「活き活き」をそれぞれ完全に区別して訳すというよりも、文脈に応じて “lively”, “vivid”, “energetic”, “vigorous”, “full of life” などの語が使われます。例えば:
- She looked lively and engaged in her work.(彼女は生き生きと仕事に取り組んでいた。)
- The fish were swimming vigorously.(魚が活き活きと泳いでいた。)
なお、「生き生き」= “lively/vivid/energetic”、「活き活き」= “vigorous/full of life” のような区別を紹介している記事もあります。つまり、英語では両者をあえて明確に分ける必要は少ないものの、ニュアンスに応じて使い分けることが可能です。
生き生きの意味
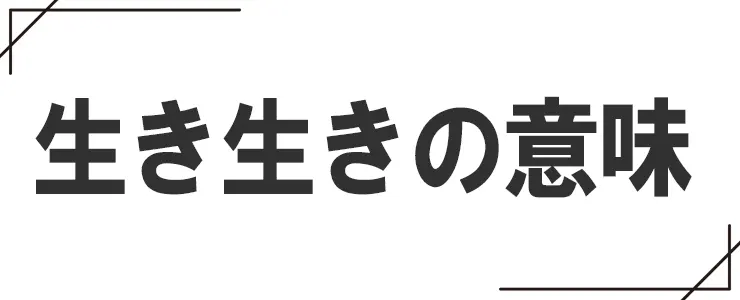
生き生きとは何か?
「生き生き」は副詞あるいは形容動詞として使われ、「生気があふれていて勢いのよいさま」「活気にみちたさま」「新鮮なさま」を意味します。 漢字「生」は、「草や木が地上に生じてきた」という象形から、「はえる・いきる」を意味する字として成立しています。よって「生き生き」という語は「生きること/存在することがみずみずしく、力強く、元気にある状態」を表す言葉といえます。
生き生きはどんな時に使用する?
以下のようなシーンで「生き生き」は使われます。
- 人の表情や態度が元気で活気にあふれているとき:「彼は生き生きとプレゼンしていた」など。
- 植物・草花・自然などが生命力を感じさせるとき:「庭の草木が生き生きとしている」など。
- 描写・文章・絵画などが鮮明で生命感を感じさせるとき:「生き生きとした描写」など。
このように、「存在している」「命がある」「活動している」というよりも、「元気・活気・若々しさ・生命力」を含んだイメージが強いのが特徴です。
生き生きの語源は?
「生き生き」という表現を漢字で書く際、「生き=生きる」の「生き」に「生き」を重ねた形です。国語辞典では「いき-いき【生生/活活】」という形で説明されており、明治期以降の文献にも登場します。特に、「生き生き」の「生」が示す「存在・生命・成長」の意味が根底にあります。さらに、「生き生き」という語が慣用化された際、同じ読み「いきいき」の漢字を変えて「活き活き」も併用されるようになりました。 語源という観点から見れば、「生き生き=生命力/みずみずしさ」「活き活き=活動力・勢い」という意味の違いを漢字の「生」・「活」の字が暗示している、という整理がなされています。
生き生きの類義語と対義語は?
まず「生き生き」の類義語・対義語を見ておきましょう。
| 語 | 意味・解説 |
|---|---|
| 類義語 | 「みずみずしい」「活気ある」「生気あふれる」「元気いっぱい」など。「生き生き」のニュアンスと近い言葉です。 |
| 対義語 | 「ぱっとしない」「生気がない」「いきいきしていない」「沈んでいる」など、元気・活気・生命力が見られない状態を表します。 |
また、「活き活き」との関係で整理すると、「活き活き」がほぼ類義的関係にあるものの、漢字の違いや使用場面において“微差”があります。つまり、対義語としては「活き活きしていない」「生命力・活動力が感じられない」といった表現が該当します。
活き活きの意味
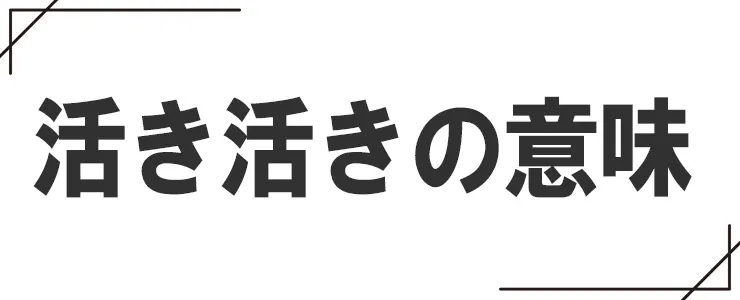
活き活きとは何か?
「活き活き」は「元気で活動的・勢いがある様子」「生き生きとして動いているさま」を意味します。辞書的には「活動的・活発な元気さ」というニュアンスが強いとされています。漢字「活」は「流れる水」「つぶれた目・口」などを象形として、「勢いよく動く」「いきる」を意味する字です。
活き活きはどんな時に使用する?
以下のようなシーンで「活き活き」は使われることがあります。
- 人が元気に活動している様子や、動き・活躍・勢いを感じる場面:「彼女は新しい職場で活き活きと働いている」など。
- 生き物・植物・自然などが“動き”や“勢い”を感じさせるとき:「水中の魚が活き活きと泳いでいる」など。
このように、「活き活き」は「ただ存在している」のではなく「活動している」「勢いよく振る舞っている」「動的である」というイメージを持つことができます。
活き活きの語源は?
「活き活き」という語を漢字で書く際、「活き=活きる(いきる)」という書き方が用いられ、「活」の字が示す「動く・勢いある・流れる」などの意味が根底にあります。このため、語源的には「活き活き=活動力・勢い・動的な生命力」というニュアンスが成り立ちます。また、前述の通り「活き」が常用漢字外であるという漢字使用上の背景も、「活き活き」が日常的な文書でやや使われにくい理由となっています。
活き活きの類義語と対義語は?
「活き活き」の類義語・対義語を整理します。
| 語 | 意味・解説 |
|---|---|
| 類義語 | 「生き生き」「活発」「元気いっぱい」「エネルギッシュ」など。 |
| 対義語 | 「活気がない」「だらだらしている」「勢いがない」「停滞している」など。 |
「活き活き」は「活動的・勢いある元気さ」という面で「生き生き」と重なる部分が多いため、類義語として互換的に使われることもありますが、漢字の違いやニュアンスの違いを踏まえると上のような整理が可能です。
生き生きの正しい使い方・例文
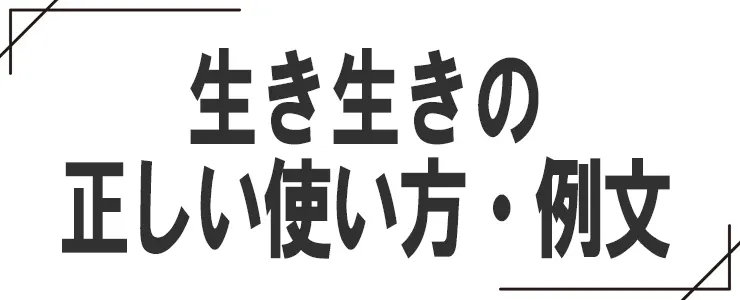
生き生きの例文
「生き生き」を使った例文
- 子どもたちは公園で生き生きと遊んでいた。
- 彼女は生き生きと表情を変えながら話をしていた。
- 春の庭の草木が生き生きと芽吹いている。
- その写真には生き生きとした笑顔が写っていた。
- 新しいプロジェクトのおかげでチームが生き生きとしてきた。
生き生きの言い換え可能なフレーズ
「生き生き」を別の言い回しに言い換え
- 「みずみずしく輝いている」
- 「活気に満ちている」
- 「元気いっぱいだ」
- 「生気あふれる」
- 「若々しくて勢いがある」
生き生きの正しい使い方のポイント
「生き生き」を使う際のポイント
- 「生き生きと~する」「生き生きとした~」といった形で副詞・連用修飾語として使うことが多いです。
- 「命がある」「活動している」「元気がある」というニュアンスを含んでいるため、ただ“存在している”だけではなく“活気がある”という意味合いがある場面で使うと自然です。
- 公用文・報道・公式文書などでは「生き生き」が表記上安心で、漢字の使用上も適切です。
- ただし、「活き活き」の方が適切だと感じる“活動・勢い・動き”を強調する場面では、あえて「活き活き」を選ぶ余地もあります。
生き生きの間違いやすい表現
「生き生き」の使用で注意すべき誤り・曖昧な使われ方
- 「生き生きと暮らしている魚」…魚など“命ある動物・生物”に使っても間違いではありませんが、魚が「活動的に泳ぎ回っている」という意味を強めたいなら「活き活き」の方が適切とする考え方もあります。
- 「活き活きとしている人」を「生き生きとしている人」と言いかえても大きな問題はありませんが、「活き活き」の方が“活動・勢い”を強調します。
- 漢字を混在させて「生き活きと」「活き生きと」という使い方は避けるべきです。また、「生き生きとしていたが、今は…」と文末を締める場合、文脈が「元気だったが今は…」という意味になるため、文脈を明確にしておきましょう。
活き活きの正しい使い方・例文
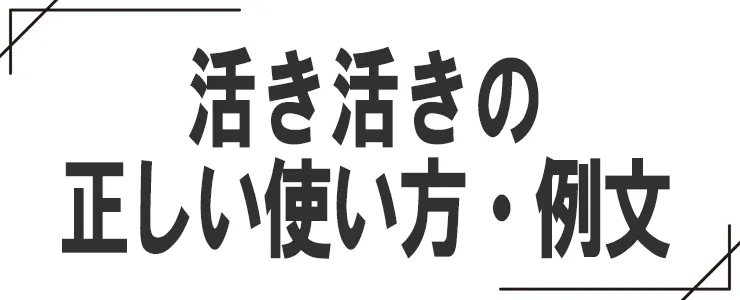
活き活きの例文
「活き活き」を使った例文
- 新しい職場で彼女は活き活きと働いている。
- 水槽の中の魚が活き活きと泳いでいた。
- 休暇を取って戻った彼は、活き活きとした表情を取り戻した。
- 子どもたちは活き活きとゲームに興じていた。
- 企画会議で彼のアイデアが活き活きと形になっていった。
活き活きの言い換え可能なフレーズ
「活き活き」を別の言い回しに言い換え
- 「エネルギーに満ちあふれている」
- 「勢いよく動いている」
- 「活動的である」
- 「パワフルに振る舞っている」
- 「生き生きとしている(ただし「生き生き」の語感と若干異なる)」
活き活きの正しい使い方のポイント
「活き活き」を使う際のポイント
- 「活き活きと~する」「活き活きとした~」という形で使うことが多く、特に“動き・活動・勢い”を伴う表現に適しています。
- 生物・人・活動など「活発に動いている」「力を発揮している」場面で使うとニュアンスが自然に伝わります。
- 公式文書・報道文などでは「活き活き」の使用が少なめです。漢字の選択・文体に注意が必要です。
- あえて「活き活き」を使うことで、単なる“元気”ではなく“活動的・鮮烈な動き”という印象を与えられることがあります。
活き活きの間違いやすい表現
「活き活き」の使用で注意すべき誤り・曖昧な使われ方
- 「活き活きとした草木」…植物・草花にも使えなくはありませんが、「若々しさ・みずみずしさ」を伝えたいなら「生き生き」の方が一般的とされます。
- 「活き活きとした静かな風景」…“静かで落ち着いた”という意味合いなら「活き活き」より「生き生き」や別の表現の方が適切です。
- 「活き活き」はあくまで漢字「活き」を使った書き方なので、文書の漢字使用基準(常用漢字等)を意識して“公式性”を求められる文では慎重に選択すべきです。
まとめ:生き生きと活き活きの違いと意味・使い方の例文
本記事では、「生き生き」と「活き活き」の違い・意味・語源・類義語・対義語・使い方・例文について詳しく解説しました。
ポイントを改めて整理します
- 「生き生き」も「活き活き」も、基本的には「元気で活気がある」「生命力・活力にあふれている」といった意味を持ちます。
- 漢字の違いから、語源・ニュアンスに「生命力・若々しさ(生き生き)」対「活動的・勢い(活き活き)」という整理がなされることがあります。
- 実際にはどちらを使っても大きな誤りではありませんが、公式な場面・文書・報道では「生き生き」が優勢です。また、活動・動き・勢いを強く表現したい場合は「活き活き」を選ぶことで微妙なニュアンスを強調できます。
- 例文とともに言い換えフレーズ、使い方のポイント・間違いやすい表現も把握しておくことで、適切な場面で自然に使い分けることができます。
言葉を丁寧に使い分けることで、読み手に伝わる印象や表現力がより豊かになります。あなたが「生き生き」「活き活き」という言葉を使う時に、少し立ち止まって漢字・意味・場面を意識してみるだけで、その言葉の持つ力がグッと際立つことでしょう。