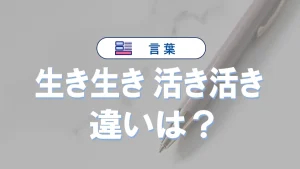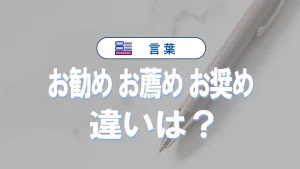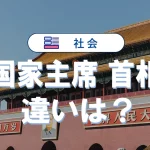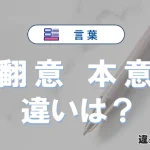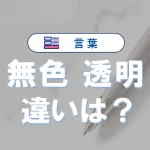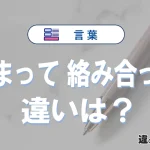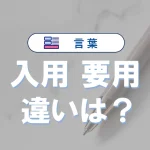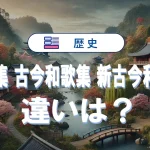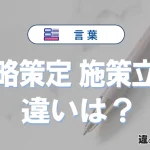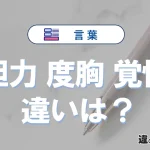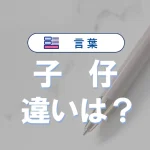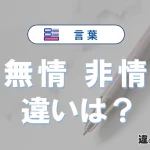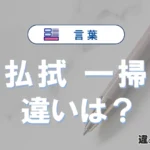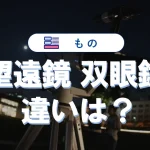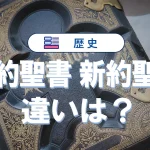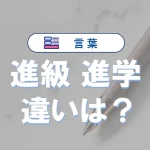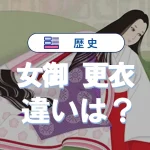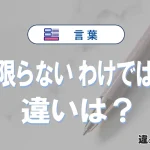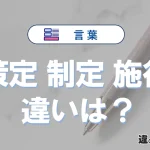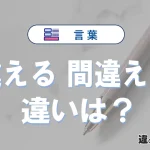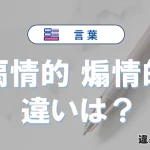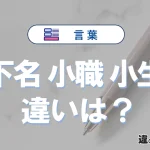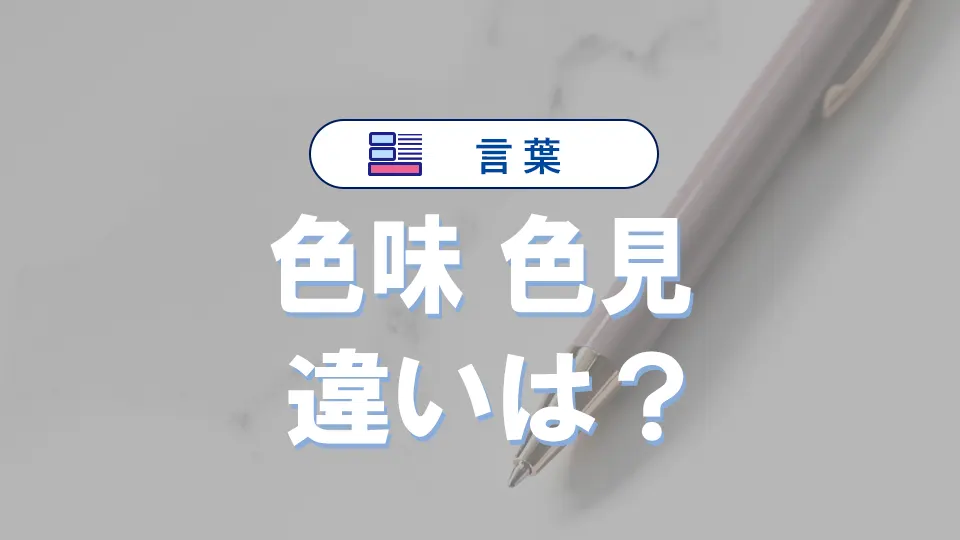
色味と色見――この二つの言葉、似ているようで実はニュアンスや使われ方に微妙な違いがあります。この記事では、「色味」と「色見」の違い・意味・語源・類義語・対義語・言い換え・使い方・例文などを、しっかり詳しく解説します。
この記事を読んでわかること
- 色味と色見、それぞれの意味と語源
- 色味と色見の違い・使い分け・英語表現の違い
- 色味の正しい使い方、例文と言い換え、間違いやすい表現
- 色見の正しい使い方、例文と言い換え、間違いやすい表現
色味と色見の違い

結論:色味と色見の意味の違い
「色味」は、色そのものの特性・色合い・トーンや濃淡・微妙なニュアンスを指す言葉です。また、「色見」は、視覚的に「色がどのように見えるか」「色の見え方・印象・ずれ・差異」を指すことが多く、印刷・製造・インテリアなど実務的な場面で用いられます。つまり、色味=色の持つ“味わいや色合い”、色見=“見え方・色の見え状態・色の印象”という違いがあります。
色味と色見の使い分けの違い
使い分けとして覚えておくと便利なのは、以下の通りです。
- 色味:日常語/感覚的な色のニュアンスを語るときに自然。「この赤の色味が好きだ」「色味を少し明るくする」など。
- 色見:専門的・実務的な場面/印刷・建築・素材の見え方を考えるとき。「素材によって色見が変わる」「色見をチェックする」など。
例えば、美術・デザイン・ファッションの話で「この布の色味」「そのペンキの色味」という言い方は普通ですが、「色見」の場合は「印刷仕上がりの色見」「板の色見合わせ」というような使い方をされることが多いです。
色味と色見の英語表現の違い
英語で表現するならば、以下のような違いが考えられます。
- 「色味」→ “hue nuance”, “tonal quality of a color”, “shade/tint of a color” など。
- 「色見」→ “visual appearance of color”, “how a color appears (under this lighting)”, “color appearance” など。
要するに、「色味=色の性質・味わい」「色見=見え方・印象」の英語的区分がそのまま表現できるでしょう。
色味の意味
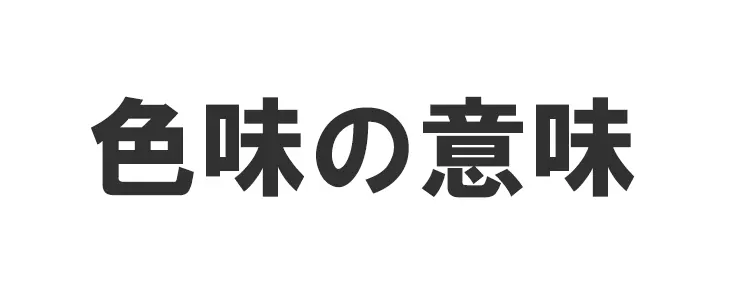
色味とは何か?
「色味(いろみ)」とは、「(微妙な)色の濃淡やずれの具合。色合い。色加減。」という意味があります。例えば「鏡で頬紅の色味を確かめる」「色味を足す」などの用例があります。また、印刷や映像の分野では「色味=微細な色合い」を指す語として扱われており、媒体や条件によって違って見える色合いを指して「色味が違う」と言われることもあります。
色味はどんな時に使用する?
色味は、次のような場面でよく使われます。
- デザイン・ファッション・インテリアで「このカラーの色味が良い/悪い」というような感覚的表現。
- 写真・映像・印刷物で「色味を調整する」「色味のズレがある」というような技術的表現。
- 日常会話でも「服の色味が少し暗め」「壁紙の色味が暖かい/寒い」など、色の印象を語るとき。
このように、「色味」は視覚が捉える“色のニュアンス”から、質的な色表現に使われます。
色味の語源は?
「色味」は「色+味(み)」という組み合わせです。辞書によれば、「み」は接尾語、「味」は当て字で、「〜味(〜み)」が「〜の感じ・〜の具合」を表す語です。つまり、「色味=色の“味わい・具合”」という語感があります。また、「色相(しきそう)」「明度」「彩度」というカラー理論でも、「色味=色相」のことを指す場合が紹介されています。
色味の類義語と対義語は?
類義語としては、以下が挙げられます。
- 色合い(いろあい)
- 色調(しきちょう)
- トーン(tone)
- 色相(しきそう)
- 彩り(いろどり)
対義語という観点では、「色味」が色の“ニュアンス・味わい”を指すのに対して、「色見」など“見え方・印象”を示す語が対となり得ます。つまり、「色見=見え方のズレ・差異」という点で対比できます。加えて、「無彩色」「単色」「無味(味わいがない色)」などを“味わいがない”という意味で対義的に捉えることも可能です。
色見の意味
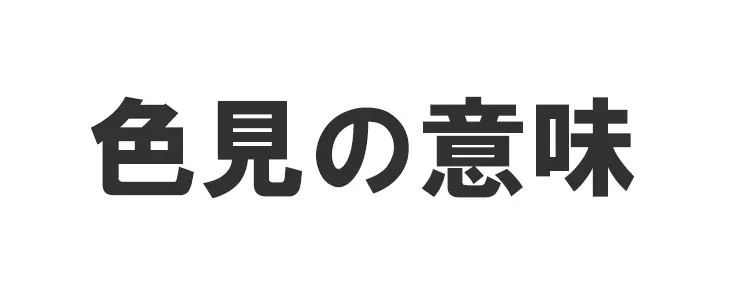
色見とは何か?
「色見(いろみ/いろみえ)」とは、「色が見える様子」「視覚的に捉えられる色の印象」「印刷・製造などの場で色のズレ・差異を確認すること」などを指す言葉です。ただし、辞書によっては「色見」が一般的な語として十分に掲載されていない場合もあり、やや実務的・専門的に使われるニュアンスがあります。
色見はどんな時に使用する?
色見という言葉は、以下のような場面で使われます。
- 印刷・製造・建築・インテリアなど、材料・光源・表面条件によって「同じ色でも見え方が変わる」ことを語るとき。
- 色見本や色見合わせ、色見チェックというような用語として、色差や見え方のズレを管理する現場で。
- デザイン・写真・映像では、「この素材での色見」「この光源下の色見合わせ」というような表現。
つまり、色見は色そのものよりも“その色が見える/どう見えるか”という“見え方”を重視します。
色見の語源は?
「色見」という語も「色+見(み/みえ)」から成ります。「見」は“見る・見える”を意味し、「色見=色が見える具合・見え方”という語感を持ちます。言葉としては、実務で色の見え方を表現する専門語の側面があります。語源資料としては明確な古典的出典は乏しいものの、印刷・製造分野で使われる語として定着しています。
色見の類義語と対義語は?
類義語としては、以下が挙げられます。
- 見え色(みえいろ)
- 色の見え方
- 色見合わせ
- カラーマッチング(色見本の一致確認)
- 視覚上の色差
対義語としては、「色味」が先ほど紹介したように“色そのものの味わい”を指す言葉です。また、「見えない色」「色が曖昧な見え方」「色差がない」という意味で“色見のズレがない”ことを対応的に捉えることもできます。
色味の正しい使い方・例文
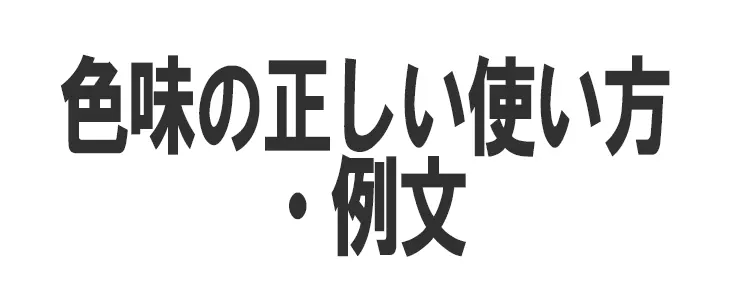
色味の例文
使用頻度の高い「色味」を使った例文
- このジャケットは深いネイビーで、色味が落ち着いていて秋冬にぴったりだ。
- 壁紙の色味が想像より暗かったので、部屋全体が重い印象になってしまった。
- 写真撮影では、光源によって色味が変わるためホワイトバランスを調整する必要がある。
- このリップはピンクが強めですが、色味を少し落とせば大人っぽく使えそうだ。
- 印刷物で「色味のチェック」が入っており、指定より少し赤みが強かったので再校正となった。
色味の言い換え可能なフレーズ
色味=色合い/トーン/風合いのある色(ニュアンスカラー)/微妙な色のずれ/色のニュアンス
色味の正しい使い方のポイント
・「色味を変える/色味が合わない/色味を足す」など、色のニュアンスや具合を話すときに自然。
・「色味が暗い/明るい/くすんでいる/鮮やか」など、形容詞+色味で使いやすい。
・光源・素材・隣接色によって色味が変化することを認識し、「色味に差が出る」といった表現も可能。
・一方で、「色味=見え方そのもの」という意味合いで使うと違和感が生じる場合があるため、「見え方」を語るなら「色見」の方が適切。
色味の間違いやすい表現
・「色味が見える」:誤用として「色見が見える/色見える色」などと混同しやすく、「色味」は“味わい”なので「見える/見えにくい」という表現は少し違和感あり。
・「色味を確認する=見え方を確認する」:確認する対象が“見え方・ズレ・差”なら「色見を確認する」がより適切。
・「色味サンプル」:使われてはいますが、“見え方”を重視したいときには「色見サンプル/色見本」の方が分かりやすい。
・「色味が合う/合わない」:色合いや雰囲気を語る分には問題ないが、素材や製造で“色見差”を論じるなら「色見が合う/合わない」という言い方を使う方が正確。
色見の正しい使い方・例文
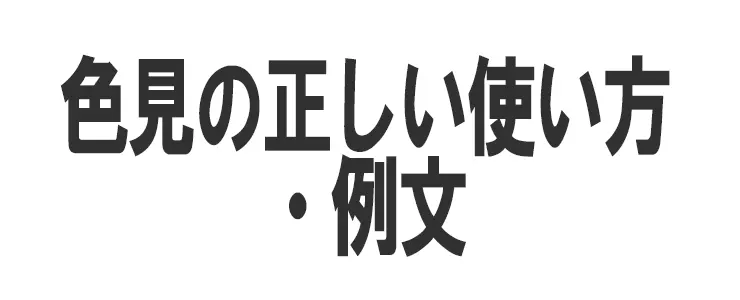
色見の例文
使用頻度の高い「色見」を使った例文
- 印刷工程で「色見のズレ」が発覚し、色校正をやり直すことになった。
- 同じ塗料でも壁の材質や光源によって「色見」が変わるため注意が必要だ。
- 色見本を何種類か試して、家具の色見を確認してから購入を決めた。
- 撮影スタジオではライトを変えて「色見をチェック」し、素材の色が正しく出ているか確認する。
- ウェブサイトのデザインでは、モニターによって「色見」が変わるため、複数の環境で確認した。
色見の言い換え可能なフレーズ
色見=色の見え方/視覚上の色差/色見合わせ/カラーマッチング(色見本の一致確認)/見え色(みえいろ)
色見の正しい使い方のポイント
・「色見が異なる/色見がズレている/色見を確認する」というように、“見え方・差”に言及する際に使う。
・素材・光源・印刷・モニターなど環境の変化が色の見え方に影響を及ぼす場面で使うと適切。
・日常会話で「この色の見え方」という意味で用いても構いませんが、専門領域では「色見」として認識されることが多い。
・「色味」と混同されやすいため、“味わい”として語るなら「色味」、“見え方・色差・チェック”として語るなら「色見」という線引きを意識する。
色見の間違いやすい表現
・「色見を感じる」:違和感がある表現。色見は“見え方・チェック対象”なので、「色見を感じる」ではなく「色見を確認する/見る・チェックする」が自然。
・「色見がいい/悪い」:文脈によっては「色味がいい/悪い」が本来の意図かもしれません。色のニュアンスを語りたいなら「色味」が適当。
・「色見が鮮やか」:鮮やかさを語るなら「色味が鮮やか」が一般的。「色見が鮮やか」というと“見え方の鮮やかさ”という少し異なる意味合いとなる。
・「色見を作る」:通常「色味を作る・調整する」「色見を作る」という表現は専門的で、日常語としては少し硬く感じられる。
まとめ:色味と色見の違いと意味・使い方の例文
本記事では、「色味」と「色見」の違い・意味・語源・類義語・対義語・言い換え・使い方・例文について、広く深く解説しました。
ポイントを改めて整理します
・色味 = 色そのもののニュアンス・トーン・味わい。日常的にも使いやすい。
・色見 = 色の見え方・視覚的印象・環境によるズレ。専門・実務的な場面で使われることが多い。
・語源的には、色味は「色+味(み)」=“色の味わい”、色見は「色+見(み/みえ)」=“色の見え方”。
・使い分けとしては、感覚的・イメージ的に語るなら「色味」、見え方・色差・チェックを語るなら「色見」が適切。
・例文を活用して、日常・ビジネス・専門いずれの場面でも正しく使えるようにしましょう。