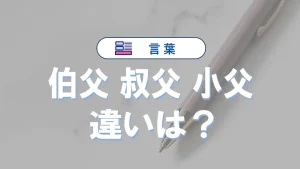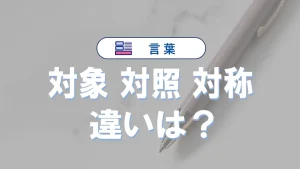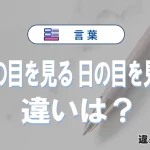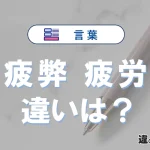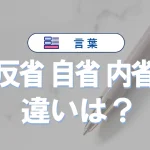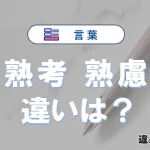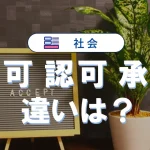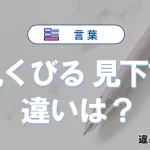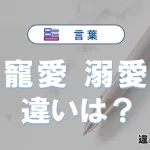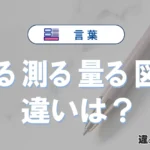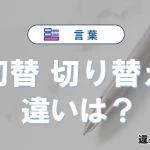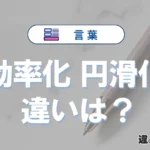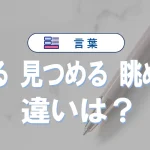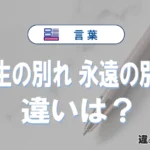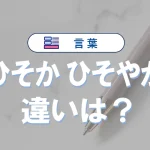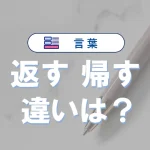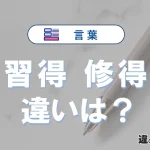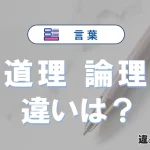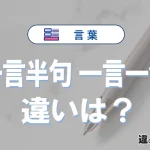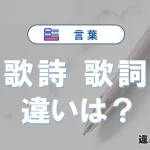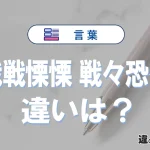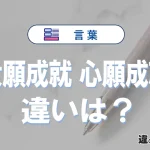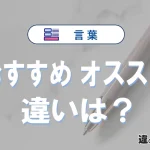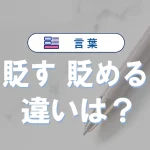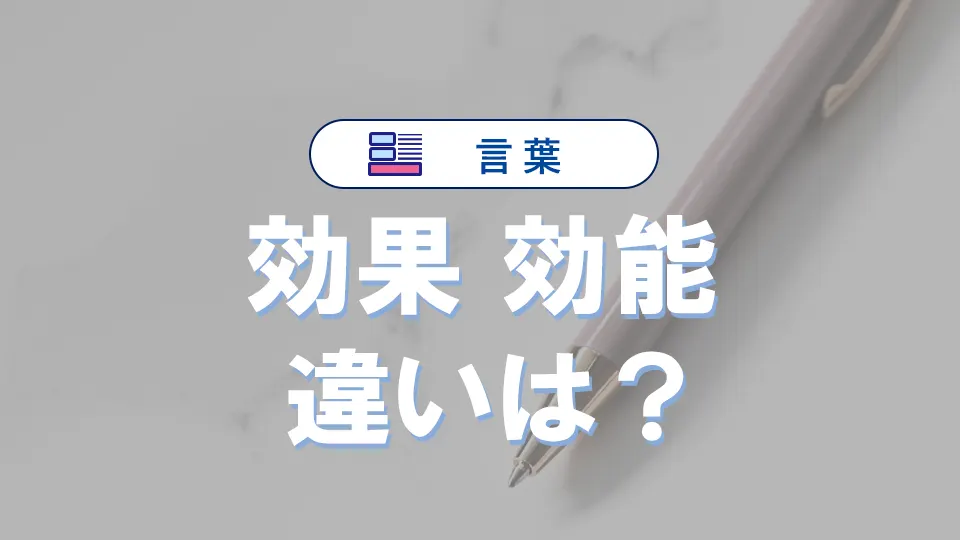
「効果」と「効能」という言葉は、日常会話からビジネス、医療、健康食品、さらには法律用語にまで幅広く登場します。しかし、この二つの言葉の正確な違いを理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。たとえば「この薬は効果がある」と言った場合と「この薬の効能は〇〇である」と言った場合では、意味合いが大きく異なります。本記事では、「効果」と「効能」の違いを明確に整理し、それぞれの使い方や例文を詳しく解説します。また、医薬品や食品、英語表現、さらには法律・科学的な背景に至るまで徹底的に掘り下げ、読者が自信を持って正しい言葉を選べるようにガイドします。
目次
「効果」と「効能」の意味と違い
「効果」の意味とは?
「効果」とは、ある行為や手段によって得られた具体的な結果や影響を意味します。日常生活の中で非常に幅広く用いられ、「勉強の効果」「広告の効果」「薬の効果」など、心理的・社会的・身体的な結果を含みます。特徴的なのは、科学的根拠が必ずしも必要ではなく、主観的な感覚でも「効果があった」と表現できる点です。
「効能」の意味とは?
「効能」は、特に医薬品やサプリメント、食品成分などの医学的・科学的な作用に限定して使われる言葉です。効能は臨床試験や研究データに基づき、国の基準に従って定義されることが多く、「解熱作用」「鎮痛作用」「整腸作用」といった形で表現されます。したがって、効能はより専門的で厳密な表現であるといえます。
「効果効能」とは?
「効果効能」という言葉は、主に医薬品や化粧品、健康食品の広告や説明書で使われます。「効果」は実際に期待できる結果を指し、「効能」は科学的に認められた作用を表します。ただし、薬事法や景品表示法によって「効能」を誇大に表現することは規制されています。消費者が誤解しないよう、業界では厳しいルールのもとに表現が管理されています。厚生労働省のガイドラインも参照にされます。
医薬品における「効果」と「効能」の違い
医薬品においては「効能」が正式に承認され、パッケージや添付文書に記載されます。たとえば「鎮痛作用」「解熱作用」などです。一方で「効果」は、効能を受けた個人が実際に感じた変化や結果を意味します。つまり、「薬の効能は解熱作用」であり、「その効果として熱が下がった」と表現するのが正確です。
「効果」と「効能」の具体的な違いと例文
「効果」を使用した例文
- この薬を飲んだら頭痛に効果があった。
- 笑顔は人間関係を良好にする効果がある。
- 禁煙には健康維持に大きな効果が期待できる。
- 運動にはストレス解消の効果がある。
- プレゼンで視覚資料を使うと説得力が増す効果がある。
「効能」を使用した例文
- この漢方薬には胃腸を整える効能がある。
- ビタミンCには抗酸化作用という効能が認められている。
- 緑茶のカテキンは抗菌作用の効能で注目されている。
- 漢方薬の効能は体質改善に重きを置いている。
- この温泉には神経痛に効能があるとされる。
「効果」と「効能」の比較:具体例で見る
| 項目 | 効果 | 効能 |
|---|---|---|
| 使う場面 | 日常会話、教育、ビジネス | 医薬品、食品、科学研究 |
| 意味 | 結果や影響(広義) | 科学的に認められた作用(狭義) |
| 例 | 「勉強の効果が出た」 | 「解熱の効能がある」 |
| 科学的根拠 | 必ずしも必要ではない | 臨床試験・研究が必要 |
英語での「効果」と「効能」の違い
「効果」の英語訳と使い方
「効果」は英語でeffectやresultと訳されます。日常的に「何かの影響で生じた結果」を意味する表現です。
- The medicine had a good effect on his headache.
- Exercise has a positive effect on mental health.
- The campaign produced a strong effect on sales.
- Music has a calming effect.
- The speech had a great effect on the audience.
「効能」の英語訳と文脈
「効能」はefficacyやbenefitと訳されます。特に医薬品やサプリメントの有効性を示す文脈で用いられます。
- The efficacy of the vaccine has been proven in clinical trials.
- This herb has benefits for digestion.
- The drug’s efficacy was demonstrated through research.
- Scientists are testing the efficacy of the new treatment.
- Green tea is known for its health benefits.
翻訳によるニュアンスの違い
「効果」は幅広い「結果」を意味するため *effect* が一般的ですが、「効能」は科学的有効性を指すため *efficacy* の方が正確です。この違いを理解することで、英語での表現精度が高まります。
日常生活における「効果」と「効能」の違いと使い方
食品における「効果」と「効能」
食品は「効果がある」と日常的に表現されることがあります。しかし「効能」として表示するには法的制約があります。例えば「トマトは美肌に効果がある」と言えますが、「効能」と表現することは薬事法上認められていません。
サプリメントの「効能効果」を理解する
サプリメントは医薬品ではないため「効能」として広告できません。多くは「効果が期待できる」という表現にとどめられます。消費者はその違いを理解して選択する必要があります。国立健康・栄養研究所も、健康食品の過大評価に注意するよう呼びかけています。
健康管理における役割とその影響
健康食品やサプリメントの「効果」を信じて摂取することは可能ですが、科学的に「効能」が認められるのは医薬品に限られます。この違いを理解して正しく使い分けることが、健全な健康管理に直結します。
「効果」と「効能」を言い換えると何か?
それぞれの言い換え例:効用や作用
- 効果 → 結果、成果、影響、作用、メリット
- 効能 → 効用、薬効、特性、適応、働き
適切な言い換えがもたらすメリット
「効果」と「効能」を混同すると、誤解や誇大広告につながる恐れがあります。正確に言い換えることで、信頼性の高い情報発信が可能になり、社会的信用の維持にもつながります。
場面に応じた言葉の選択
ビジネス文書では「効果」を用い、医療関連の説明書では「効能」を用いるなど、文脈に応じた選択が重要です。言葉の使い分けによって、文章の説得力や正確性が大きく変わります。
「効果」と「効能」の法的・科学的背景の違い
日本の薬事法に基づく定義
薬事法では、医薬品や医薬部外品に関して「効能・効果」の記載を義務付けています。食品やサプリメントはこの対象外であり、「効能」を表示することはできません。これは消費者保護の観点からの規制です。
効果と効能を示すための基準
効能は臨床試験や研究データに基づき、再現性が確認されて初めて承認されます。一方、効果は必ずしも科学的データに基づかず、経験や実感によって語られることが多い点で異なります。
科学的根拠に基づく評価
効能を認めるには科学的データが不可欠です。医薬品医療機器総合機構(PMDA)が審査・評価を行い、その裏付けが確認されることで効能表示が可能になります。この厳密なプロセスが「効果」と「効能」の根本的な違いを作っています。
まとめ:「効果」と「効能」の違い
理解を深めるためのキーポイント
- 効果=結果や影響(幅広い場面で使用)
- 効能=科学的に認められた作用(医薬品・成分に限定)
日常生活への応用とその利点
両者を理解することで、広告や説明文を正しく解釈し、健康やビジネスの場で適切に言葉を選べるようになります。これは健康リテラシー向上にもつながります。
今後の医療・健康分野での展望
今後は、消費者自身が「効果」と「効能」を区別し、正しい判断を下す力がますます求められるでしょう。特にサプリメント市場の拡大に伴い、この知識は必須のスキルとなるはずです。