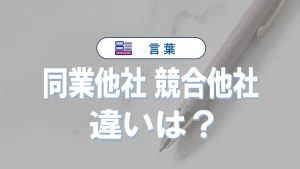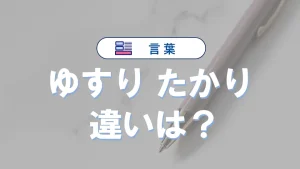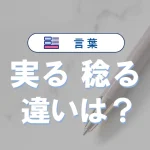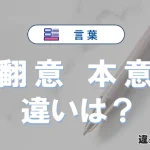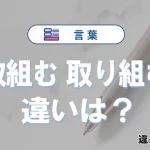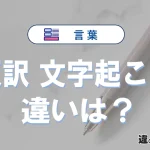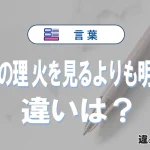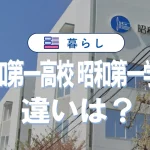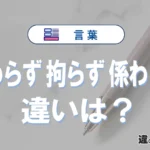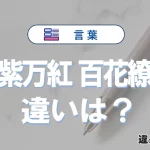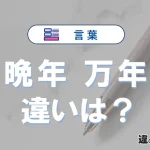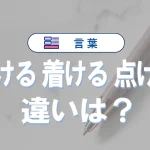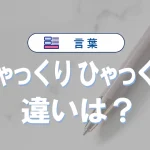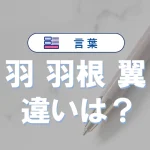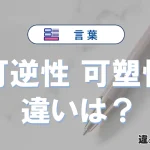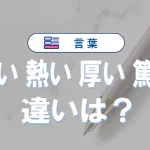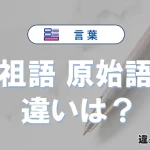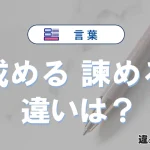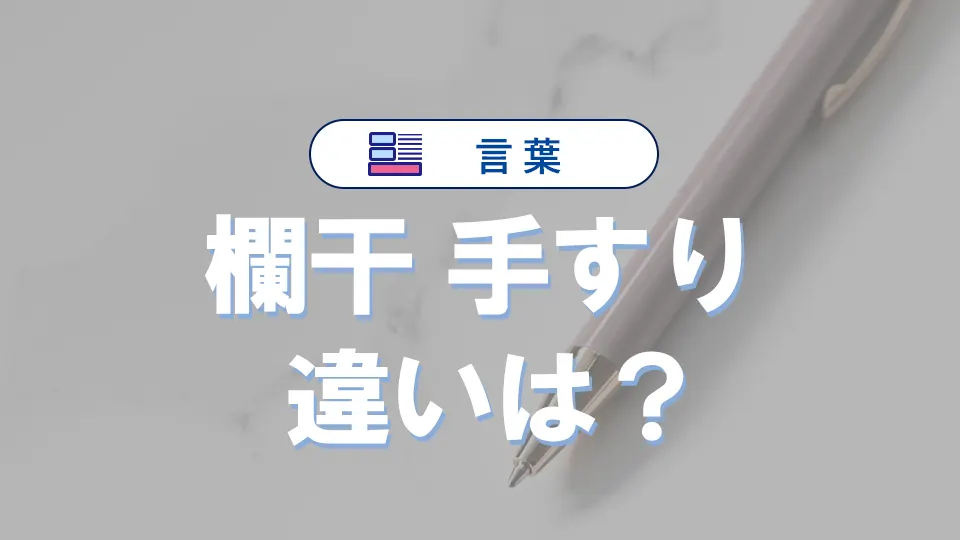
「欄干(らんかん)」と「手すり(てすり)」は、一見すると似た機能を持つ建築構造物ですが、用途・設計意図・呼称の使い分けに明確な違いがあります。本記事では、「欄干」と「手すり」の違いを結論から簡潔に示すとともに、意味・使用場面・例文・英語表現などを丁寧に解説します。
結論:「欄干」は主として高所や開口部での転落防止を目的とした柵・手すり構造を指し、「手すり」は人が手をかけて体を支えたり移動を補助したりする装置や部材を指します。すなわち、「欄干」は手すりのうち特に安全性・柵的役割を強く意図するもの、という使い分けが一般的です。
目次
「欄干」と「手すり」の意味と使用場面
「欄干」とは何か?
「欄干(らんかん)」は、もともと建築・造作の用語で、高所の縁や開口部(橋・ベランダ・展望デッキなど)で、人が誤って落ちないように設置される柵構造を意味します。「欄」は“囲い・手すりを付ける構造”の意味を含み、「干」は木材を渡す意を含む語源的要素があります。 古典的な欄干には、擬宝珠(ぎぼし)・柱・透かし彫り・笠木(かさぎ)などの意匠要素が含まれることも多く、美観性が重視されることもあります。
辞書的には、広義には手すり構造も「欄干」の仲間として扱われることもあります(例:コトバンクで「欄干」を「高欄」として扱う記述)
「手すり」とは何か?
「手すり(てすり)」は、人が手をかけて身体を支える・補助する目的で設置される部材・構造を指します。階段・廊下・スロープ・トイレや浴室などで、手すりを掴む・伝わせることで移動や動作の補助、安全性向上を図ります。 建築用語集などによれば、手すりには「転倒防止・歩行補助」「転落防止(柵的役割)」の両方の役割を持つものが含まれます。
手すりは、使用者が実際に手をかけることが想定されるため、太さ・形状・材質・高さなどを考慮して設計されます。たとえば建築基準法上、バルコニーや屋上の手すりは高さ 1.1 m 以上を要求されるケースがあります 。
「欄干」と「手すり」の共通点と相違点
以下の表に、両者の共通点と主な違いを整理します。
| 項目 | 共通点 | 違い・注意点 |
|---|---|---|
| 目的・機能 | 転落・転倒事故防止、安全性の向上 | 欄干:主に高所・開口部の転落防止用途。 手すり:歩行補助・動作補助が主目的になることが多い。 |
| 設置場所 | 橋・ベランダ・階段・通路・展望デッキ等 | 欄干という呼称が使われるのは高所・屋外開口部が多い。階段・室内などの補助用途では「手すり」が一般的。 |
| 構造・形状 | 柱・横桟・手掛かり部分を含む構成 | 欄干には意匠性(透かし・彫刻)が入りやすい。手すりは握りやすさ・継続性・人体工学が重視。 |
| 呼称の範囲 | 重なる部分あり | すべての手すりが欄干と呼ばれるわけではない。階段用手すりを「階段の欄干」とは呼ばない例も多い 。 |
このように、「欄干」と「手すり」は用途や文脈に応じて使い分けられます。実務や日常では「高所での柵=欄干」「階段・介助補助用途=手すり」と意識することが多いでしょう。
「欄干」と「手すり」が必要な理由
建築における役割と重要性
建築構造の観点から、開口部・高所部分・段差部分などには、安全対策として柵や手すりを設けることが不可欠です。これにより、事故や転落リスクを低減し、人命や物件の安全性を確保できます。
特に公共建築や不特定多数が利用する建物には、建築基準法などの法規制が適用されます。例として、屋上や2階以上のバルコニーなどには高さ 1.1 m 以上の手すり壁・柵を求める規定があります。
また、設計上の配慮として、手すり子(縦材)の間隔(児童の頭が通り抜けないよう 11 cm 以下など)や、手すりの耐荷重、コーナー端部の処理、意匠性との折り合いなども検討されます。
階段やバルコニーでの安全性確保
階段や廊下における手すりは、特に移動時の体重移動やバランスを支える補助装置としての意味が強いです。階段には法律的にも手すり設置義務があるケースがあり、少なくとも片側に設置しなければならないことがあります 。
バルコニー・屋上・吹き抜け部分などには、転落防止の柵や欄干(または手すり構造)が不可欠です。例えば東京都では、子供の転落事故例が過去に報告されており、設計段階から乗り越え防止や足掛かり対策などを考慮する必要性が指摘されています。
防止対策としての機能
手すり/欄干構造は、単に「転落を防ぐ」だけでなく、以下のような防止・抑止的機能も果たします
- 心理的な区画意識:境界を視覚的に示し、近づきすぎないよう誘導する。
- 転倒時のブレーキ機能:手すりを掴んで体勢を立て直す可能性を与える。
- 動線誘導:移動方向をガイドし、手を沿わせながら進行方向を安心させる。
- 装飾性・意匠性:欄干には意匠が付されることが多く、安全性と美観の両立が図られる。
これらの理由により、手すり・欄干の設計・設置は建築設計上重要な要素です。
「欄干」と「手すり」の英語表現と例文
「欄干」の例文と英文翻訳
まず、「欄干」に相当する英語は “balustrade,” “parapet,” “railing” などがあり、文脈によって適切な語を選びます。
例文を5つ挙げ、それぞれ英訳を示します:
- 展望デッキの欄干に寄りかかって景色を眺めた。 → I leaned against the balustrade of the observation deck and gazed out at the view.
- 橋の欄干が風雨で腐食して、交換工事が必要になった。 → The bridge’s railing had corroded due to wind and rain, requiring replacement work.
- 古い庭園の石造の欄干は風格がある。 → The stone parapet in the old garden exudes a stately elegance.
- 高層ビルの屋上には安全のための欄干が設置されている。 → A protective parapet is installed on the rooftop of the skyscraper for safety.
- 温泉旅館の露天風呂には木製の欄干が配されている。 → The open-air bath at the ryokan is bordered by a wooden balustrade.
「手すり」の例文と英文翻訳
「手すり」に対応する英語には “handrail,” “handrail support,” “grab rail,” “banister” などがあります。
例文を5つと英訳を示します:
- 階段の手すりをしっかり持って上りましょう。 → Be sure to hold onto the handrail firmly when climbing the stairs.
- トイレに手すりを付けると高齢者も安心して使える。 → Installing grab rails in the restroom allows elderly people to use it with confidence.
- 廊下に沿って手すりを設けて歩行補助とした。 → We installed a handrail along the corridor to assist walking.
- 浴室の壁に手すりを取り付けて立ち上がりを支えた。 → A wall-mounted grab bar was installed in the bathroom to support standing up.
- スロープの両側に手すりがあれば安全性が高まる。 → Having handrails on both sides of a ramp increases safety.
まとめ:「欄干」と「手すり」の違い
本記事では、「欄干」と「手すり」の意味・使用場面・相違点・英語表現・例文まで詳しく解説しました。再度、その違いを整理します:
- 「欄干」は、高所や開口部での転落防止を強く意図した柵的構造を指すことが多い。
- 「手すり」は、手をかけて身体を支えたり移動を補助したりする部材であり、階段・廊下・浴室など広い用途を持つ。
- 用途や文脈によって呼称が使い分けられ、必ずしも完全に別物というわけではない。
- 英語では、balustrade/parapet/railing といった語が欄干に、handrail/grab rail/banister といった語が手すりに対応することが多い。
用途や設計意図を踏まえた使い分けを意識すれば、読み手にも明快に伝わる表現が可能になります。