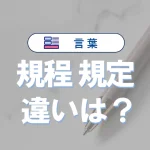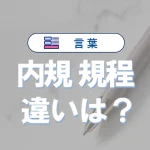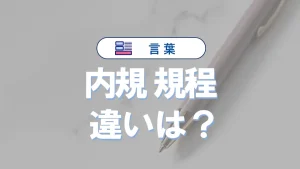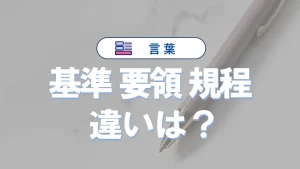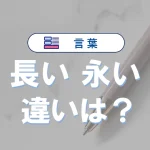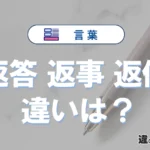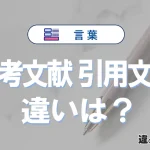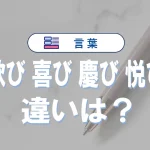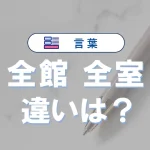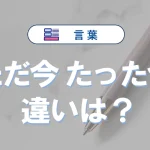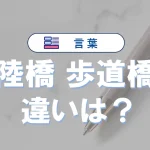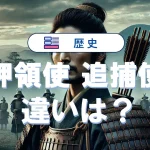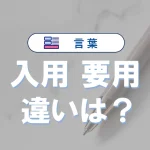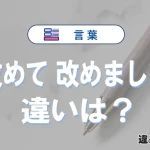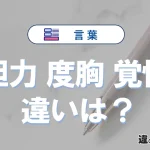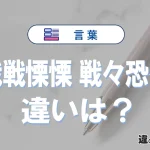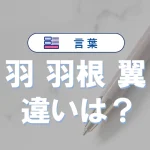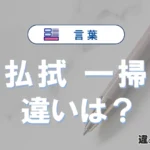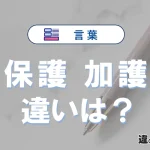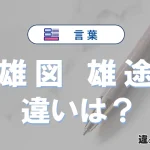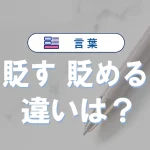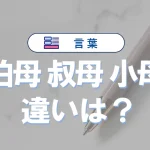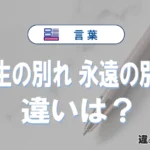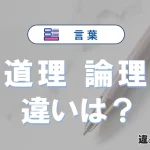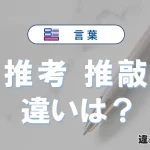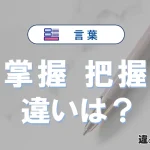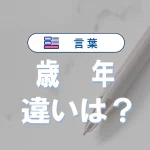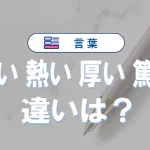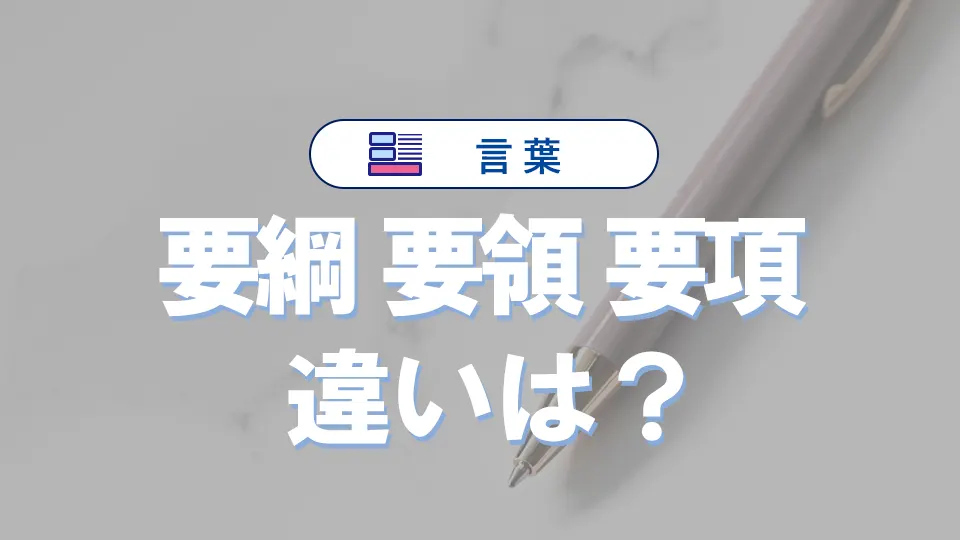
「要綱」「要領」「要項」という熟語、ビジネス文書や行政文書で目にすることが多いですが、「なんとなく似ているから使っている」「どれを使えばいいか迷う」と感じる方も多いでしょう。本記事では、「要綱」「要領」「要項」の意味・語源・類義語・対義語・言い換え・使い方・例文まで、体系的に整理し、「要綱・要領・要項の違い」を明確にします。特に、言い換え可能なフレーズや、使い分けのポイント・間違いやすい表現も丁寧に解説しますので、ビジネス・行政文書だけでなく、日常の言葉遣いにも活かせます。
この記事を読んでわかること
- 「要綱」「要領」「要項」のそれぞれの意味と語源
- 「要綱」「要領」「要項」の違い・使い分け方
- 「要綱」「要領」「要項」の正しい使い方と例文(各5例ずつ)
- 「要綱」「要領」「要項」の言い換え可能なフレーズと、よくある誤用
目次
要綱と要領と要項の違い
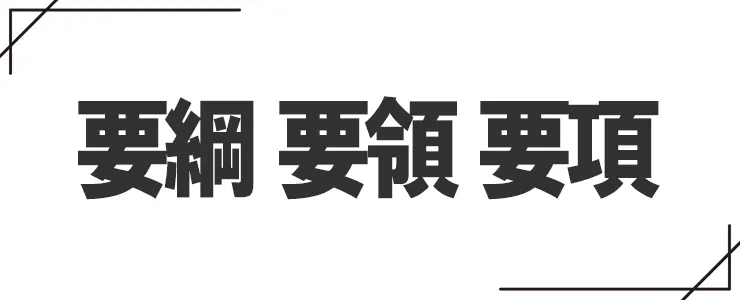
結論:要綱と要領と要項の意味の違い
要綱と要領と要項の意味の違いを以下の表に整理しました。
| 語 | 意味の要点 |
|---|---|
| 要綱 | 物事の<根本的な大枠・大綱>を示したもの。重要な基本方針。 |
| 要項 | 物事を実行するにあたっての<具体的な必要事項・項目>。文書化されたものも多い。 |
| 要領 | ①物事の最も大切な点・要点 ②物事をうまく処理する手段・コツ・手際。 |
したがって、簡単に言えば「要綱」がもっとも大きな枠組み、「要項」がその枠の中の必要事項、「要領」が「それをどう処理するか」という手段・コツという順にイメージできます。実務では多少重なって使われることもありますが、この構造を押さえておけば言葉を正しく使う手助けになります。
要綱と要領と要項の使い分けの違い
使い分けの観点から、以下を押さえておきましょう。
- 要綱:政策・事業・計画の「基本方針・大枠」を示す文書タイトル等に用いられることが多い。
- 要項:入試・募集・大会などの「必要条件・実施項目」を列挙した文書。「募集要項」「入試要項」などが典型。
- 要領:何かを実際に処理・実行する際の「コツ・手際」や「要点」を指す。文章や話で「要領を得る」「要領が悪い」などの表現も多い。
以下のような観点でも比較できます。
| 指標 | 要綱 | 要項 | 要領 |
|---|---|---|---|
| 抽象度 | 高(大枠・根本) | 中(具体的な項目) | 低〜中(実行・手法) |
| 書かれる文書 | 基本方針・指針系 | 実施条件・項目表 | コツ・手順・やり方説明系 |
| 使われる場面例 | 政策、組織の方針 | 募集、試験、イベント | 日常業務、説明、実務処理 |
このように整理しておくと、「○○要綱」「○○要項」「○○要領」といった見出しを見たときに「これは大枠だな」「これは実施条件だな」「これは手順・コツだな」と瞬時に判断できます。
要綱と要領と要項の英語表現の違い
英語表現も押さえておくと、書類の翻訳や英語での説明時に役立ちます。
- 要綱: basic framework, outline of policy, general guidelines
- 要項: requirements, detailed items, application guidelines
- 要領: key points, essentials, method/knack, how-to
例えば、募集要項=“application requirements”、「要領を得る」=“to grasp the key points”などの訳が使われます。
要綱の意味
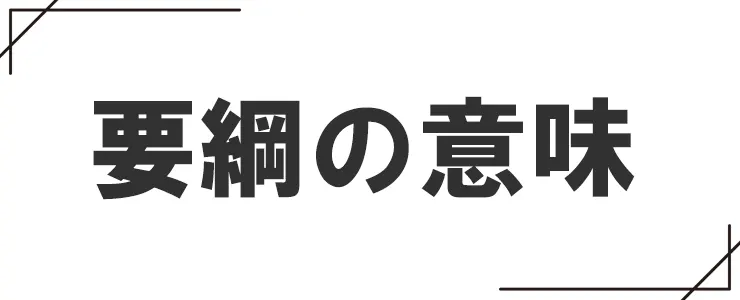
要綱とは何か?
「要綱(ようこう)」とは、簡潔に言えば「物事の重要な大枠・基本となる大綱」を意味する語です。辞書的には「要約した大綱。基本となる重要な事柄。また、それをまとめ記したもの。」とあります。
行政文書では、法律・条例等のような法的拘束力のあるルールとは別に、内部指針・処理基準として要綱が定められることがあります。
つまり、「何を目的に」「どのような大方針で」という“枠”を提示する言葉と文書の役割を担います。
要綱はどんな時に使用する?
要綱は次のような場面で使用されます。
- 組織・行政・政策等の基本方針・大枠を示す文書表題として(例:「指導要綱」「運動方針要綱」)
- 何らかの事業やプロジェクトの根本的な枠組み・骨格を示す説明文として
- ビジネス文書・報告書において、細部ではなく“まずは大枠を押さえる”という意味合いで使われる場合
たとえば、ある地域行政機関が「○○事業の実施にあたっては、別途『実施要綱』を制定する」というような形で使われています。
このように、細部の手続きよりも「この事業はこういう方針で進める」という枠組み提示に用いられます。
要綱の語源は?
語源・由来を見てみると、以下のような理解ができます。
・「要」=「かなめ」「大切なところ」を意味し、根本・中心という意味合いがあります。
・「綱」=本来は「太い綱」「つな」を意味し、転じて「大もと」「根本を貫くもの」を示す漢字。
このことから「要綱」は、事柄の根幹・大枠を示す語として成り立っていると解釈できます。
行政用語としての「要綱」は、法律・条例・規則といった法形式ではないものの、内部処理・指針として“統一的処理を行う上での枠”として位置づけられています。
要綱の類義語と対義語は?
「要綱」の類義語と対義語
類義語としては、「綱要」「大綱」「基本方針」「指針」「骨子」「枠組み」などが挙げられます。
対義語的な語は、厳密には定まっていませんが、「詳細」「細目」「具体的項目」「細則」など、“大枠ではなく細部を指す”語が対照的です。例えば、「要綱」が大枠・骨格、「要項」が細部・必要事項、という構造から、「要綱」に対して「要項」が対比語として機能するケースもあります。
要領の意味
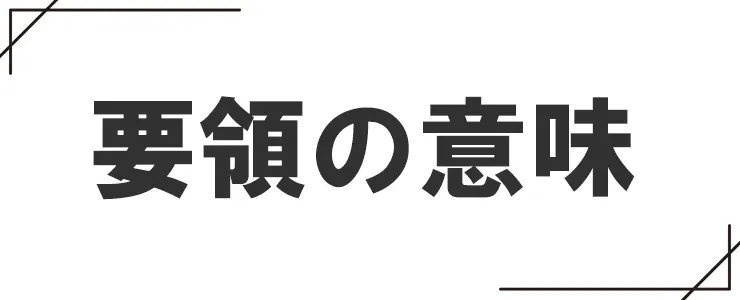
要領とは何か?
「要領(ようりょう)」とは、主に次の二つの意味を持つ語です。
- 物事の最も大事な点・要点。
- 物事をうまく処理する手段・コツ・手際。
つまり、「要領を得る」「要領がいい・悪い」という言い方をするときの「要領」は、「要点をつかむ」「処理の手際がよい」という意味合いを含みます。
要領はどんな時に使用する?
要領は、以下のような場面で多く使われます。
- 会議・説明・報告などで、「話の要領を得る」「要領を押さえる」という使い方。→「要点を掴む」意味。
- 実務・作業・処理において、「要領がいい」「要領よく進める」という使い方。→「手際よく・コツを知る」意味。
- 説明書・指示書などでも、「“この要領で”進めてください」という形で「手順・やり方」を示す場面。
また、「要領を得ない」という否定的表現もよく使われ、「話の筋が通っていない」「要点が掴めていない」という意味になります。
要領の語源は?
語源的には、以下のように説明されています。
- 「要」=「腰」「かなめ」等、物事の中心・重要なところ。
- 「領」=「襟」「えり」など、衣服を扱う際に重要な部分。転じて「領る(おさめる)」「掌る(つかさどる)」などの意、そして「領域」などの語でも使われる。
語源説明では、「衣服の丁寧な着付けでは必ず腰(要)と襟(領)を抑える必要がある」という比喩から、「物事を扱う際の要点」を意味するようになったという説があります。
このように「要領」には、「物事を適切・効率的に処理するための要点・コツを抑えること」というニュアンスが語源的にも裏付けられています。
要領の類義語と対義語は?
「要領」の類義語と対義語
類義語としては、「要点」「肝(きも)」「勘所」「コツ」「手際」「ポイント」「秘訣」などが挙げられます。
対義語としては、「要領を得ない(=要点を掴めない)」「手順が滞る・手際が悪い」などの表現から、「粗雑」「効率悪い」「無駄が多い」などが反意的に使われます。また、「細則重視」「冗長」といった語が対立軸になります。
要項の意味
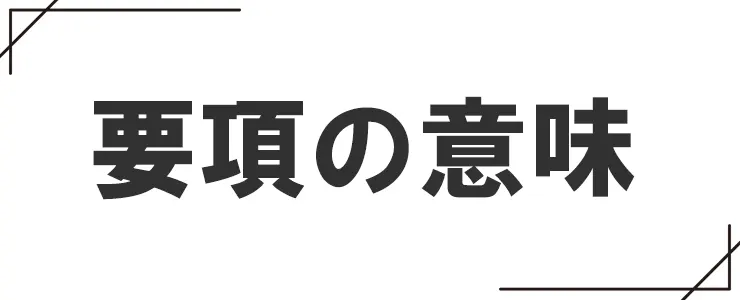
要項とは何か?
「要項(ようこう)」は、「大切な事柄・必要な事項。また、それを書き記したもの」という意味を持つ熟語です。辞書では「必要な事項。大切な事柄。また、それを書き表わしたもの。」と定義されています。
実務的には、入試・募集・大会・プロジェクトなど、特定の実施・応募にあたって提示される条件や項目を列挙した文書のタイトルとして使われることが多いです。
要項はどんな時に使用する?
要項は、以下のような場面で多く使われます。
- 高校・大学の「入学要項」、企業の「募集要項」、イベントの「参加要項」など、応募・参加・実施にあたっての条件・手続き項目を示す文書。
- プロジェクトや活動の「実施要項」「開催要項」など、実行に必要な項目・スケジュール・条件を提示するとき。
- ビジネス・行政文書において、実務を行うために“確認すべき項目”として使われる場合。
つまり、「要綱」が大枠を示し、「要項」がその大枠を実現するための“必要項目”を示す、という使い分けができます。
要項の語源は?
語源的には、以下のように説明されています。
- 「要」=「大切なところ・かなめ」などの意味。
- 「項」=「小分けされた一つ一つの事柄・区分」。辞書的には「細かく分けた一つ一つ」などと説明があります。
このことから、「要項」は「大切な事柄を“項目”ごとに整理したもの・必要な項目を記したもの」という意味として成り立っています。
要項の類義語と対義語は?
「要項」類義語と対義語
類義語としては、「条件」「実施項目」「必要事項」「募集概要」「仕様書」などが挙げられます。
対義語としては、「大枠」「基本方針」「骨子」「指針」など、“細項目ではなく大きな枠”を意味する語が対比となります。「要綱」がその役割を果たす例もあります。
要綱の正しい使い方・例文
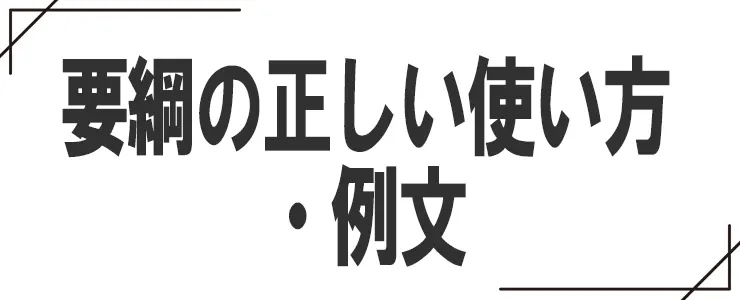
要綱の例文
使用頻度の高い「要綱」の例文
- 新しい経営戦略の要綱を明文化し、社内に周知した。
- 地方自治体が策定した地域振興計画要綱に基づいて、事業を進める。
- 教育委員会が公表した指導要綱を参照して、新カリキュラムを設計した。
- 環境保護に関する基本要綱を策定し、関係団体に向けて説明会を開催した。
- 本プロジェクトの設置要綱には、目的・対象・手段が簡潔にまとめられている。
要綱の言い換え可能なフレーズ
「要綱」の言い換え可能な表現
- 基本方針
- 骨子
- 枠組み
- 大綱
- 指針
要綱の正しい使い方のポイント
正しい使い方のポイント
- 文書タイトルや見出しとして使う場合、「○○要綱」という形で、政策・計画・組織の大枠を示す場面に用いるのが適切です。
- 「細かな実施条件・項目」を表す場面では「要項」の方がふさわしいため、使い分けを意識しましょう。
- 「要綱」の中に細かい手順・方法が羅列されていると、語感的にずれてしまう可能性があるため、手順・方法を示したい場合は「要領」「要項」など別語を検討すると良いです.
- 行政文書やビジネス文書において「要綱で定める」など使われることが多く、やや堅い語感であるため、カジュアルな文脈では「基本方針」などを使うほうが自然なこともあります。
要綱の間違いやすい表現
間違いやすい表現
- 「募集要綱」と「募集要項」を混同して使ってしまう。実務的にはどちらも使われることがありますが、「募集要綱」は大枠、「募集要項」は具体条件という意識があると使い分けしやすいです。
- 「要綱を掴む」「要綱が悪い」というように、「要綱」を「要点を掴む」「手際よく進める」という意味で用いるのは「要領」の意味になってしまうため、語のニュアンスがずれてしまいます。
- 「要綱に沿って細かく手順を記す」といった使い方で、実際には「要項」の趣旨を超えてしまっているケース。要綱は大枠提示が主なので、細目を入れるなら「要項」或いは「要領」を検討するべきです。
要領の正しい使い方・例文
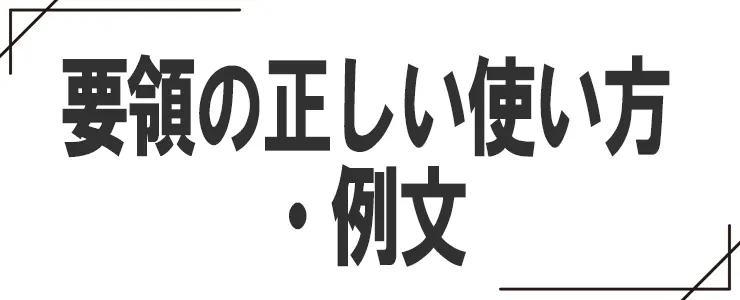
要領の例文
よく使われる「要領」の例文
- 会議資料を見ただけでは、要領を得ないまま午後の会議が始まってしまった。
- 彼女は作業の要領が良く、いつも短時間で仕上げてしまう。
- 初めての作業でも、手順を確認してから要領よく進めればミスが少ない。
- 上司から「この書類は今日中に仕上げろ」と言われ、要領を掴むまで少し時間がかかった。
- 説明が長すぎて要領を失い、参加者から「結局何をすれば良いの?」という声が出た。
要領の言い換え可能なフレーズ
「要領」の言い換えとして適切な表現
- 要点を押さえる
- コツを掴む
- 手際よく進める
- ポイントを理解する
- 鍵となるところ
要領の正しい使い方のポイント
正しい使い方のポイント
- 「要領を得ない」「要領がいい/悪い」「要領を掴む」など、動詞とセットでよく使われる語です。語感として「手際・コツ・処理の仕方」に焦点があります。
- 実務や説明・指導の場面で「要領よく対応する」「要領を伝える」「この要領で進めてください」などと使われることが多いです。
- 「要領=手順」ではなく、「手順を含むが、それをうまく処理する“方法”も含む」という点がポイントです。
- 「要領を押さえる」という表現では、「要点をつかむ」という意味合いなので、説明・報告・処理の準備段階にも使えます。
要領の間違いやすい表現
間違いやすい表現
- 「要領=項目一覧」という意味で使ってしまうと、「要項」の意味とずれてしまいます。「要領を列挙する」という使い方は誤用となりがちです。
- 「要領がいい人=手続き書類を読み込んでいる人」という理解だけだと、「手際よさ」「効率の良さ」というニュアンスが抜けてしまいます。「要領がいい」は「効率的・機転が利く」「無駄なく立ち回る」という意味が含まれます。
- 「要領を得た」ではなく、「要領を得る」など、“得る”動詞が使われるのが正しいですが、「要領を掴む」などの別表現も使われます。「要領を失う」などの否定形も多用されます
要項の正しい使い方・例文
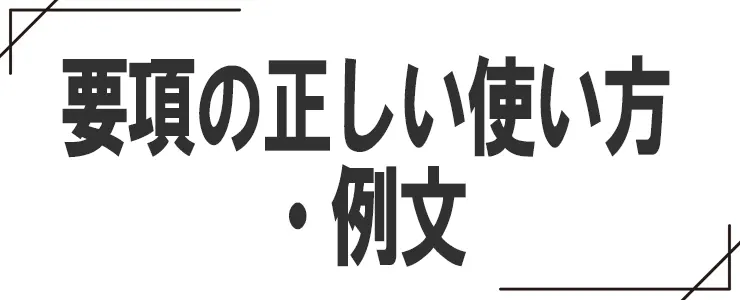
要項の例文
「要項」を使った例文
- 入学要項をしっかり確認してから願書を提出してください。
- 募集要項に記載された応募条件を満たしているかどうか、自己チェックを行った。
- 実施要項によれば、申込期間や参加費、会場が明記されている。
- 参加要項に沿って手続きを進めたが、必要書類が一部不足していた。
- 大会要項に従って、選手登録と会場受付を行った。
要項の言い換え可能なフレーズ
「要項」を別の表現に置き換えると
- 応募条件一覧
- 実施条件
- 必要事項表
- 参加規程
- 実行項目
要項の正しい使い方のポイント
正しい使い方のポイント
文書のタイトルや案内文で「○○要項」という形式で使われることが多く、「何をすべきか・いつ・どこで・どのように」という実務的な項目が列挙されています。「要綱」「要領」との違いを念頭に、「この場面では具体的条件を示す“要項”が相応しいか」「大枠なら“要綱”」「処理のコツなら“要領”」という判断ができます。
要項の間違いやすい表現
間違いやすい表現
- 「○○要項に沿って大方針を定めた」というように、実は大枠を示す場面で「要項」を使ってしまうのは語感的にずれています。その場合は「要綱」が適切です。
- 「要項を掴む」「要項が悪い」など、「要領」の意味合いを含む表現と混同して使われやすいです。例えば「要項を掴む」は「要点を掴む」という意味では「要領」の方が近い用法です。
- 「要項」と「要綱」を無意識に混在させてしまうケースが多いため、「この文書は大枠か/具体条件か」を判断して使い分けることが大切です。
まとめ:要綱と要領と要項の違いと意味・使い方の例文
ここまで、「要綱」「要領」「要項」の意味・語源・類義語・対義語・使い方・例文を詳しく解説しました。改めて整理します。
- 「要綱」=物事の根本的大枠・大綱。基本方針や骨子を示す文書。
- 「要項」=その枠を実現するための具体的な必要事項・項目。文書形式で提示されることが多い。
- 「要領」=物事を進める際の要点・コツ・手際。実務・処理・説明の場面で重視される。
正しく使い分けることで、書類のタイトル・報告書・日常会話において、伝えたいニュアンスを誤らずに表現できます。例えば、行政の「補助金公募要領」、入試の「入学要項」など、語の使い分けが明確になります。ぜひ、今後「要綱」「要領」「要項」のいずれかを使う際には、「大枠か」「具体条件か」「処理のコツか」を意識して選んでみてください。
参考文献・引用