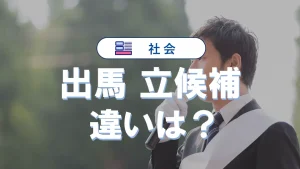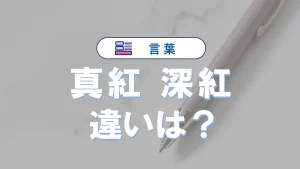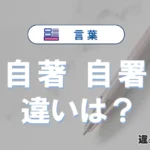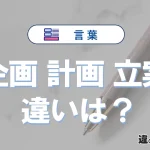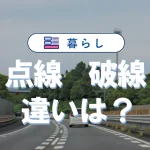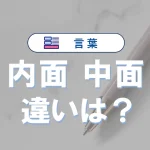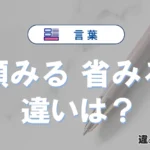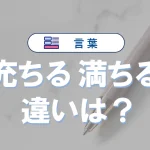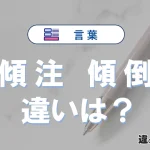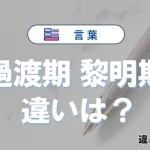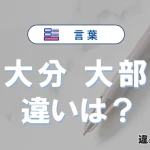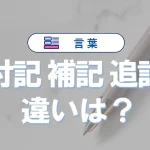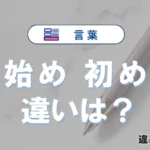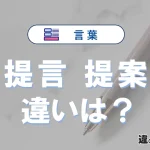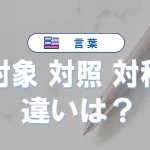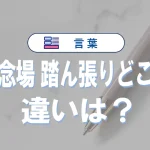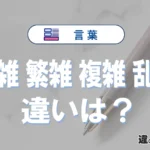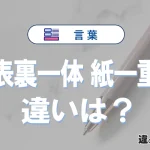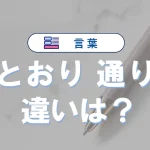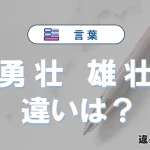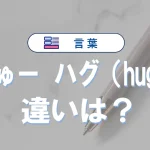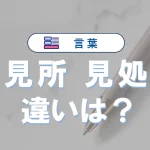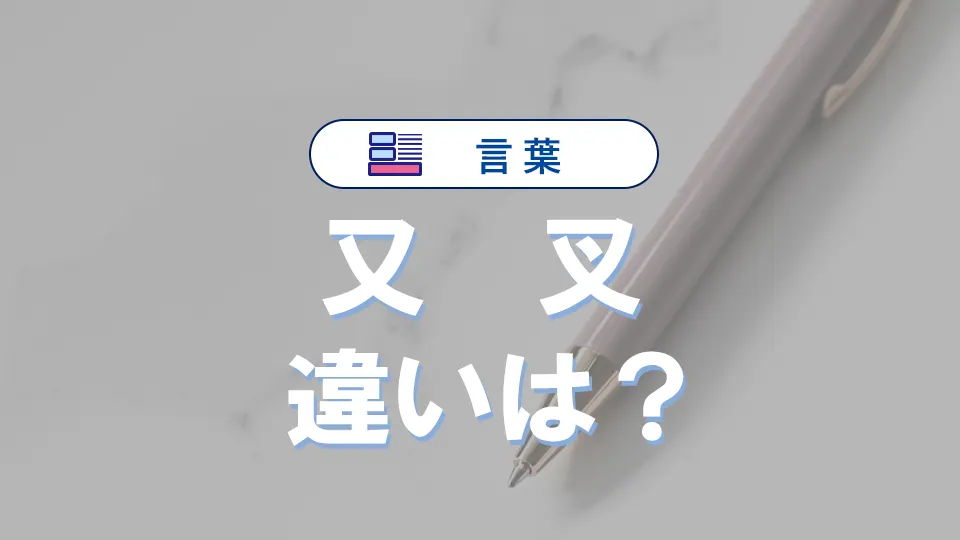
「また」と読む漢字には「又」と「叉」があります。字形はよく似ており、つい同じ感覚で使ってしまいがちですが、実は語源・意味の核・使われる文脈が異なります。誤用すると、文意が変わったり、硬すぎる印象を与えたり、専門語としての慣習表記に反してしまうことも。
本記事では、「又」は時間・論理の“再び/付加”、「叉」は形・構造の“分岐/交差”というコアを軸に、読み方・辞書的定義・専門用語(医学・工学・料理)・字源・頻出例文まで徹底解説します。表や実例を豊富に交え、ビジネス文書や学術文書での注意点も掘り下げます。
目次
「又」と「叉」の意味と違いを理解
「又」と「叉」の意味の違い
両者の違いをまずは俯瞰しましょう。意味の“向き”が異なるため、適切な字を選ぶと文が引き締まります。
| 漢字 | 中核的な意味 | 主な用法・現れる領域 | 例 |
|---|---|---|---|
| 又 | 再び/もう一度/その上(付加) | 接続(また)、副詞用法、選択(A又はB)など一般文体 | 「また来た」「優秀で、又、努力家」「A又はB」 |
| 叉 | 二股・分岐・交差・叉状 | 専門語(交叉・三叉・音叉・叉手・叉焼)/形態・構造の描写 | 「交叉点」「三叉神経」「音叉」「叉焼」 |
要点は、「又」は出来事の時間的反復・論理的付加、「叉」は対象の形態・関係の分岐や交差にフォーカスすること。したがって「又来た(再来)」は“又”、道路の「三叉路」は“叉”が自然です。
参考:三叉神経(Wikipedia)/叉焼(Wikipedia)
「又」の読み方と使い方
「又」は現代日本語で最も自然に使える漢字表記のひとつで、基本読みはまた。副詞・接続詞の働きが中心で、文語調のフォーマル文でも違和感がありません。選択を示す法令・規程の定型表現「A又はB」もよく見られます。
- 再び・反復:ある出来事が繰り返される(例:「また会う」「また起きた」)。
- 付加・順接:情報を積み増す(例:「彼は有能で、又、誠実だ」)。
- 並列・選択:論理接続(例:「A又はB」「C、又はD」)。
- 慣用強調:「またまた」「またぞろ」など反復のニュアンスを増幅。
用字のポイントは読みやすさと目的適合性。ビジネスメールでは「さらに/再度」へ言い換えると平明になりやすく、規程文では「又は」を保つのが一般的です。
「叉」の読み方と使い方
「叉」は基本読みがまたですが、現代一般文ではほとんど用いません。むしろ専門語や名詞語彙で威力を発揮し、分岐・交差・二股という形態的特徴を表す語に現れます。派生読みとして「さ」「しゃ」「さす」「さすまた(叉手)」などがあります。
- 交差・分岐の描写:交叉・三叉・分岐構造・叉状。
- 道具・器具名:音叉(調律用具)、叉手(さすまた/二股の武具・捕具)。
- 料理名:叉焼(広東語発の料理名。中国語「叉燒/叉烧」由来)。
現代の標準表記では道路標識や一般記事で「交差」の方が通行しますが、学術・技術文では「交叉」も根強く使われます。
「叉焼」と「交叉」の関連性
一見無関係の「叉焼」と「交叉」ですが、どちらにも“叉=二股/交差形”という共通モチーフがあります。広東語の「叉燒」は、叉(フォーク状・串状)で刺して焼く調理法に由来し、字形・語源の観点からも「分岐・叉状」のイメージが核にあります。
「又」と「叉」それぞれの漢字の成り立ち
字源を知るとコアイメージが定着します。字形=意味の縮図という観点から確認します。
- 又:甲骨文・金文では手(右手)の象形に由来し、「握る/取る」から「持つ」「再び(繰り返し)」へと意味が抽象化したと解されます。
叉:「又(手)」に「八(分かれる形象)」が結びつき、枝分かれ・交差の象る形。ゆえに「交叉」「三叉」「叉状」など形態語に広がりました。
「又」と「叉」の使い分けと実際の例文
「又」を使った実際の例文
使用頻度が高く、汎用性のあるものを中心に挙げます。
- また会いましょう。
- 彼は優秀であり、又、誠実でもある。
- それは又別の話だ。
- またまたトラブルが発生した。
- 本件は又後日ご連絡いたします。
「叉」を使った実際の例文
専門語・名詞中心で、実際に遭遇しやすい語を選定しました。
- 音叉を用いてピッチを確認する。
- この交叉点は見通しが悪い。
- 三叉神経痛の症状が再燃した。
- 道が叉つ(ふたまた)になっている。
- 昼は叉焼麺を注文した。
「又」と「叉」を入れた医療用語の使い方
医療・生体領域では「叉」の語が多く、形態・経路の分岐を表すのに適しています。
| 用語 | 領域 | 意味・ポイント | 補足 |
|---|---|---|---|
| 三叉神経 | 神経解剖 | 三方向に分岐する第Ⅴ脳神経 | |
| 交叉(神経交叉) | 神経生理 | 神経線維・経路の交差 | 一般には「交差」表記も流通 |
| 叉状枝(分岐構造) | 形態学 | 枝分かれ状の形態記述 | 「叉状」は形容語として頻用 |
| 交叉性反応 | 神経学 | 一側刺激が対側へ及ぶ現象 | 文脈で「交差性」も使用 |
| 叉骨(ウィッシュボーン) | 比較解剖 | 鳥の胸骨の一部で分岐形状 | 形態に「叉」の意が反映 |
語源的に「叉=分岐・交差」を担うため、医療・生体の命名は“叉”寄りになりがちです。
参考:医学用語語源対話(千葉大学OPAC)
「又」と「叉」の日常的な使われ方
日常会話における「又」と「叉」
日常会話・一般向け文章では圧倒的に「又(また)」が自然です。「叉」は古風・専門的な印象を与えやすいため、日常文に無理に持ち込む必要はありません。会話文で「また」はひらがな表記でも可読性が高く馴染みます。
ビジネスシーンでの使い分け
- 平易が最優先:「また」「さらに」「再度」などの日本語言い換えが有効。
- 規程・契約では定型:「A又はB」は法令調の定式として定着。
- 専門語は慣習を尊重:「交叉神経」は分野により「交差神経」表記へ揃える場合あり。
「読みやすさ>装飾性」。読み手の専門度に応じて、漢字・かな・言い換えのバランスを調整しましょう。
文書作成における注意点
- 意味を先に決める:再来・付加→「又」、分岐・交差→「叉」。
- 慣習表記を確認:分野固有の表記(例:「交叉/交差」)を統一。
- 可読性を担保:一般読者向けは「また」をひらがなで。
- 誤変換に注意:IMEで「叉」が出ても、意味が合わなければ「又」に直す。
学問的視点から見る「又」と「叉」
言語学的な観点からの分析
語彙意味論的には、両語は上位ノード「また」に連なるが、核義は異なります。「又」=時間的・論理的な反復・付加、「叉」=形態的・関係的な分岐・交差。統語的にも、「又」は副詞・接続的機能が強く命題全体の関係を規定、「叉」は名詞・形容語基盤で対象の構造記述を担うため、文中の役割が本質的にずれるのがポイントです。
日本語の表現豊かさと「又」「叉」の役割
同音異字がニュアンスを分担するのは日本語の強みです。
「又」で論理を滑らかに接続し、「叉」で構造を精密に描く——この機能分担を意識すると、文章の情報設計が洗練されます。技術文書や学術論においては、形態・関係の描写力を上げるために「叉」を的確に使い分けると、読み手に専門的な安心感を与えられます。
「又」と「叉」に関するFAQ
「叉」の他の使い道は?
- 叉焼:広東料理の焼豚。「叉=フォーク状・串状」の意に由来。
- 音叉:調律・音響学の基本器具。
- 叉手(さすまた):二股の捕具・武具。
- 三叉路:道路の分岐。形態命名。
- 交叉:学術・技術分野での“交わり”。一般向けには「交差」も広く使用。
「又」と「叉」の違いに関するよくある質問
- Q. 「叉」は「また(再び)」の意味で使えますか?
A. 古い文体や一部の表記では見られますが、現代一般文ではほぼ使いません。反復は「又(また)」が原則。 - Q. 「交叉」と「交差」は違いますか?
A. 意味はほぼ同じですが、一般文では「交差」、学術・技術文で「交叉」の用字が残っています。 - Q. 料理の「叉焼」はなぜ“叉”?
A. 叉状(串状)に刺して焼く調理法に由来するため。 - Q. 「A又はB」と「AまたはB」はどちらが正しい?
A. 法令・契約などの定式では「又は」が多い一方、一般文では「または」ひらがなが読みやすいです。
みんなが知っている漢字「叉」の例
- 交叉(こうさ)
- 三叉(さんさ)/三叉路
- 音叉(おんさ)
- 叉焼(チャーシュー)
- 夜叉(やしゃ)
まとめ:「又」と「叉」の違い、意味・使い分け・例文
結論:「又」は出来事・情報の再来/付加、「叉」は対象・関係の分岐/交差。このコアを押さえ、文書の目的と読者層に合わせて用字を選びましょう。
- 一般文・会話:「また」or「又」。
- 規程・契約:「A又はB」など定式を踏襲。
- 学術・技術:形態・構造は「叉」を基準に(交叉・三叉・音叉等)。
- 料理・器具名:慣習表記(叉焼・叉手)を尊重。
最後に迷ったら、伝えたい意味が“時間・論理”か、“形・構造”かを自問し、その軸で「又」と「叉」を選べば、誤用はほぼ避けられます。