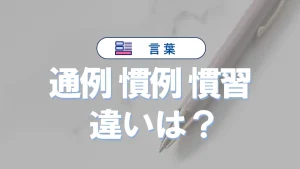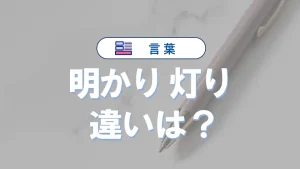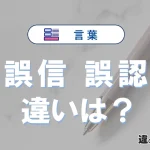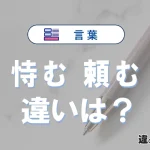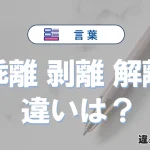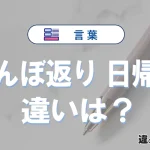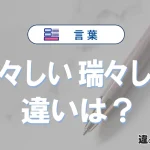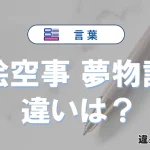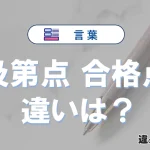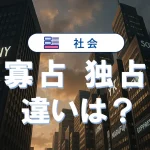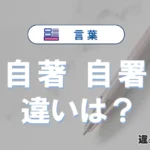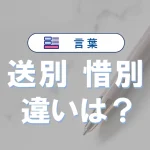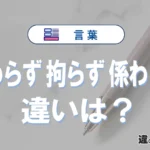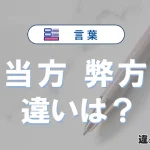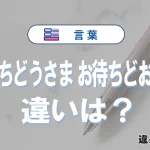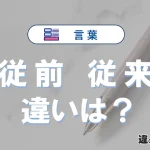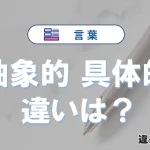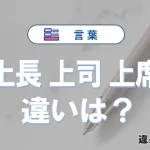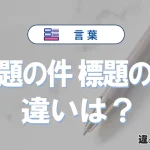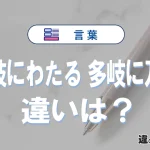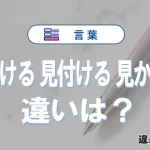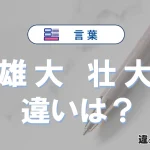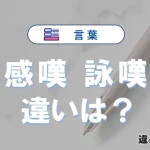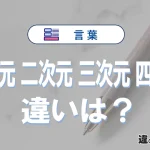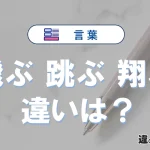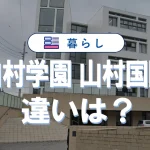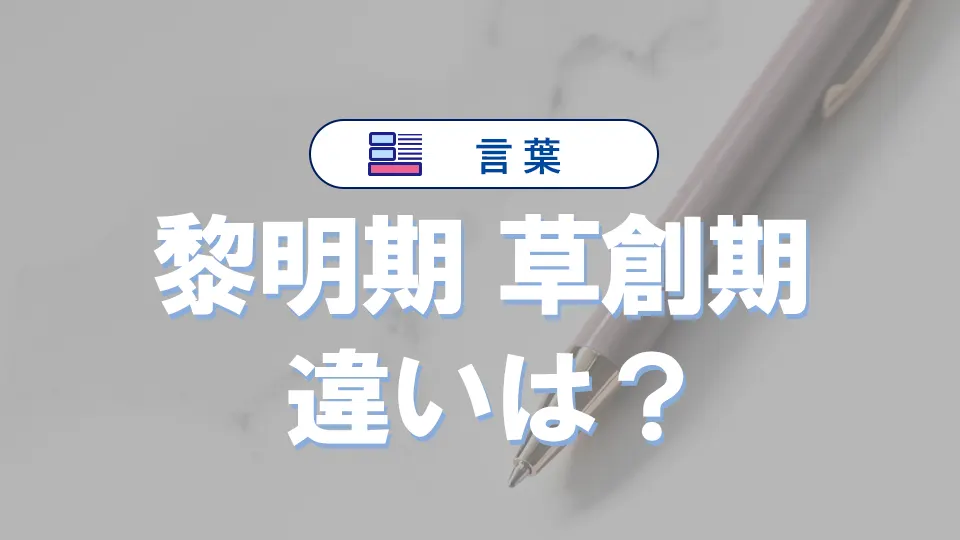
「黎明期」と「草創期」、どちらも物事の「はじまり」の時期を指す言葉として使われますが、ニュアンスや用法には微妙な違いがあります。本記事では、 「黎明期」と「草創期」の違いを明確に示したうえで、読み方・意味・使い分け・歴史例・類語・時系列的関係 まで丁寧に解説します。 結論を先に言えば、「黎明期」は “夜明けのようにこれから明るさが訪れる段階” を強調する語感があり、「草創期」は “物事を創り始めたばかりの段階/創業的な初期” をより現実的・実務的なニュアンスで表す語感があります。どちらも初期を表しますが、強調点と使われる文脈が異なるのです。
「黎明期」と「草創期」の基本的な意味
「黎明期」の読み方と意味
読み方:れいめいき(「そうめいき」などの読み方は誤りです)
意味:
「黎明」はもともと「夜明け」「明ける直前の薄明」を指す語で、それを比喩的に用いて「物事がまだ暗闇にある中で、明けようとする、始まりつつある時期」を意味します。辞書的には「夜明けにあたる時期。新しい時代・文化などが始まろうとする時期」などとされます。 語源的には「黎(暗い)+明(明るい)+期(時期)」という構成で、「暗→明へ移行する段階」のニュアンスを伴います。
「黎明期」に関する例文
- インターネット黎明期には、多くの試行錯誤があった。
- 人工知能技術は今まさに黎明期を迎えている。
- この分野の黎明期を間近で見られるのは貴重な経験だ。
- かつて日本のテレビゲームは黎明期から世界に広がった。
- 宇宙探査が黎明期にあった時代を振り返る。
「草創期」の読み方と意味
読み方:そうそうき(またはサウサウキ)
意味:
「草創」は「草(粗略、初歩的)」「創(創始)」という漢字を含み、「物事を創り始めること」「物事の始まり」「創業・創始」を指します。したがって「草創期」はその「創始・創業」の初期段階を示す言葉です。語源的には “なにもない土地から草が生えるように物事が始まる” というイメージも語られます。
「草創期」に関する例文
- その企業も創業当初は草創期だった。
- 日本プロ野球は草創期に多くの苦難を乗り越えた。
- 当社の草創期には、社員は数名に過ぎなかった。
- 草創期の研究成果が後の発展を支えた。
- この町の観光産業は草創期を迎えている。
黎明期と草創期の使い方の違い
ここまで意味を見てきましたが、実際に文章で使うときのニュアンス・使われやすさには違いがあります。以下に比較表を示します。
| 観点 | 黎明期 | 草創期 |
|---|---|---|
| 語感・比喩性 | 詩的・象徴的。「夜明け」「暗→明」などの比喩性を含む | より実務的・創始的。「始めた」「創業」の現場感が強い |
| 使用場面 | 新技術・新時代・文化変化など、変革性のある領域 | 企業・事業・組織・制度の創立初期段階 |
| 強調点 | これから光(発展・成長)が来る期待・可能性 | 初動期の苦労・創り始めている状態 |
| 使われやすさ | 未来志向・理想的・宣言的な文脈 | 歴史記述・事実記録・ビジネス報告など現実性重視の文脈 |
このように、「黎明期」は未来方向へ開ける期待感・比喩感があり、「草創期」は実際の創始フェーズ・現場感を伴う語感となります。
歴史における「黎明期」と「草創期」の例
「黎明期」の歴史的背景と具体例
「黎明期」が使われる代表的な歴史的文脈を紹介します。
- 明治維新・近代化期:封建社会から近代国家へ移行しつつあった段階を、近代化黎明期と語る文脈がある。
- 電気・鉄道の黎明期:19世紀後半〜20世紀初頭、電力網・鉄道網が拡大を始めた時代。
- インターネット黎明期:1990年代後半~2000年代初頭、Web 技術や通信基盤が発展し始めた段階。
- 学問・技術分野:量子力学黎明期、航空宇宙黎明期、人工知能黎明期など。
「草創期」の歴史的背景と具体例
「草創期」が使われる具体的歴史例を挙げます。
- 日本プロ野球の草創期:制度やチーム編成が未発達の段階を指して「草創期」とされる。
- 企業の草創期:有名企業も必ず草創期を経ており、その時期は創業者や初期社員の苦労譚として語られることが多い。
- 制度・団体・協会の草創期:学会・協会・公共制度の創立初期を指して言われる。
- 産業の草創期:特定産業(例:自動車・通信・IT産業)が制度整備や基盤構築を始めた最初期段階。
黎明期と草創期における代表的な企業・事例比較
| 分野/会社 | 黎明期として語られる例 | 草創期として語られる例 |
|---|---|---|
| インターネット・Webサービス | Web 技術全体の黎明期(技術基盤が整い始めた段階) | Web ベンチャー企業の創業初期(草創期) |
| 自動車産業 | 自動車産業黎明期(技術転換・普及期の発端) | 自動車メーカー設立初期(草創期) |
| 電気・電力事業 | 電灯・電力網黎明期(電力供給の萌芽期) | 電力会社創業初期(草創期) |
| AI / 機械学習 | AI研究黎明期(技術基盤の模索段階) | AI企業・スタートアップの創業初期(草創期) |
| スタートアップ | 技術分野全体の黎明期 | 個別スタートアップ企業が創業した草創期段階 |
類語と対義語についての解説
黎明期の類語とそれぞれの違い
- 萌芽期(ほうがき)/萌芽段階:物事が芽を出し始める段階。黎明期よりさらに初期感が強い。
- 端緒(たんしょ):始まりのきっかけや入口段階を指す語。
- 初期/初期段階:始まりという意味で中立的・一般的な語。
- 草創期:創始・創業に重きを置く初期段階を表す語(本記事の対象語)。
- 創成期:物事が成立し始めた段階を指す語。黎明期よりやや進行した開始後段階を含むニュアンスになることがある。
草創期の類語とそれぞれの違い
- 創業期:企業・団体を始めた時期に限定して使われることが多い。
- 創成期:制度や組織が成立し始めた段階を指すことがある。
- 立ち上げ期:プロジェクト・組織を立ち上げる時期を指す口語的表現。
- 初期:中立語で創始性を強調しない。
- 萌芽期:芽を出す段階を強調する語で、草創期よりさらに初期感が強い。
黎明期・草創期の対義語
- 成熟期(じゅくせいき):物事が落ち着き、安定している時期。
- 成長期(せいちょうき):発展・拡大が活発な時期。
- 盛期/全盛期:最も勢いがある時期。
- 衰退期(すいたいき):勢いが衰えていく時期。
- 終焉期/衰弱期:終わりに近づく、力を失う段階。
黎明期と草創期の時系列
物事の発展における黎明期の位置づけ
物事が生まれ、成長し、成熟するまでには多段階のプロセスがあります。黎明期はその最も初期に近いフェーズであり、以下のような時間軸の流れに位置づけられることが多いです。
- 萌芽期/端緒期 → 黎明期 → 草創期 → 成長期 → 成熟期/全盛期 → 衰退期 など
黎明期は形が定まっておらず、変化と可能性が混在する段階と見なされます。
草創期の後に続く成長期と成熟期
草創期が過ぎると、通常 成長期(拡大期) に移行します。組織や事業の拡張、需要拡大、効率化などが中心課題になります。そして成長期を経て 成熟期 に至り、成長速度は鈍化し、安定・維持・改善が主眼となります。
過渡期と全盛期の関連性
成長期から成熟期・衰退期に移行する間の段階を 過渡期 と呼ぶことがあります。こうして時間軸を捉えると、黎明期 → 草創期 → 成長期 → 過渡期 → 成熟期/全盛期 → 衰退期 といった発展モデルが見えてきます。
まとめ:「黎明期」と「草創期」の違い・読み方や意味
本記事では、「黎明期」と「草創期」の違いを、読み方・意味・使い分け・歴史例・類語・時系列などさまざまな観点から詳しく解説しました。
- 読み方:黎明期=れいめいき、草創期=そうそうき/サウサウキ
- 意味・ニュアンスの違い:黎明期は変化・可能性を含む始まり、草創期は創始・創業の初期段階
- 用法の違い:黎明期は未来志向・変革文脈、草創期は企業・組織の創立初期などに適用されやすい
- 歴史例:黎明期は社会変動レベル、草創期は事業・組織レベルで使われる例が多い
- 類語・対義語との関係:萌芽期・創成期・成長期・成熟期・衰退期などを対比して使い分けが理解できる
- 時系列モデル:黎明期 → 草創期 → 成長期 → 成熟期 → 衰退期、という流れで語感を考えると使い分けが明確になる
日本語の言葉を丁寧に使い分けたい方にとって、「黎明期」と「草創期」の違いを押さえておくことは非常に有用です。文章を書く際には、単に “始まり” とせず、文脈や意図を踏まえて適切な語を選ぶようにしましょう。